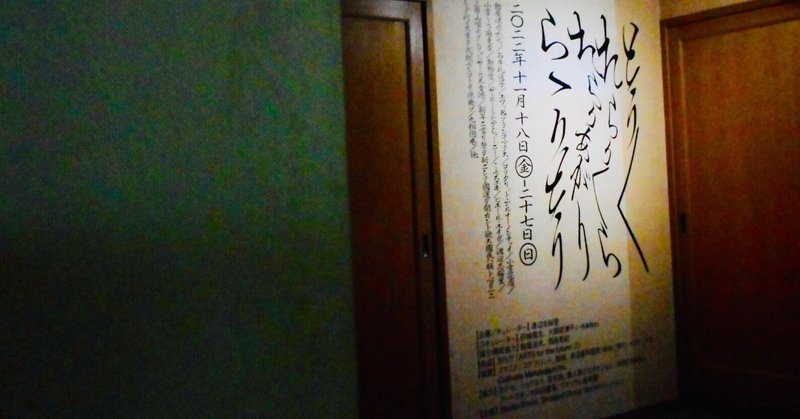
『とうとうたらりたらりらたらりあがりららりとう』------「凄いけれど、分からないことを、形にしようとした展覧会」。
ツイッターで、この情報を知った。それから数日後、会期が10日間しかない展覧会に行けた。アートによって、日常的でないことを考えられたから、それだけで、有意義だったと思う。
能楽
どうやら、この展覧会は、能楽が関係あるらしいが、能楽は、気がついたら10年以上、年に1〜2回程度とはいえ観てきたから、個人的には少し馴染みがあるけれど、恥ずかしながら、能楽に「翁」という演目があるのを知らなかった。
そのことをテーマにしているというのだけど、なんだか新しい、みたいなことだけが語られていて、かえって興味が持てた。
個人的には辛い時も、20年以上、ただの観客として、特に現代美術には、作品に触れることで支えられてきたから、「新しい」が出た時は、やっぱり行きたくなる。
ただ、持病のこともあるから、コロナ禍になってからは、極力外出は控える生活が続いていて、だから、アートを見に行く機会はすごく減ってしまったし、今も、感染状況を見ながら、出かけるのを決めている。
『とうとうたらりたらりらたらりあがりららりとう』
「とうとうたらりたらりらたらりあがりららりとう」と何かが流れてくるような言祝ぎで始まる能の演目「翁」は、あちらとこちらの世界をつなげる存在である。
「翁」は、胎児や温泉、火山や天皇、「まれびと」まで、様々な存在として、⼦宮を通したあの世との交信、宇宙的な世界観、⽣殖の神秘、⽣と死の連続した運動など、神性を体現する。また、演目としては、芸能全ての根底に脈々と流れるドメスティックな⾃然観、宗教観、思想、天皇制などにまつわる国家観を体現するものとして受け継がれている。
このプロジェクトでは、その「翁」に着想を得て、民俗学、文学、絵画、芸能または歴史から、人類を生物、無生物といった自然と同等に扱い、精霊や生物、無機物、言葉、所作をつなぐ<生態系を紐解き、この先のエコロジーの可能性と、それが根付く古層の可視化を試みる。
「翁」については、多分、能楽として見たことがないけれど、この「プロジェクトについて」は、話が大きすぎ、抽象的で、正直、雲をつかむような話だった。
でも、この「分からない感じ」は、「新しさ」と関係あるかもしれず、とても気になったし、意欲は感じたので、やっぱり行くことにした。平日の昼間だったら、新宿歌舞伎町といっても、それほど人がいないだろうし、展覧会も、人がぎっしり来ないと思って、チケットも購入した。
本展では、国内外のアーティストに限らず、食やインターネット、文筆家や演出家、動物の販売店や花屋など、多様な分野の表現者らの作品が、人間の歴史、環境、自然にまつわるファクトと結びつくことで、独自の世界観を提示する。
見に行くまで分からなそうだった、というよりも、見に行っても分からないかもしれない。
歌舞伎町
地下鉄の駅を降りて、長い地下の通路を歩いて、表へ出たら、花園神社がある。そのそばにはゴールデン街があり、歌舞伎町もある。いろいろな意味で、個人が語りきれないほど、重力が重い場所のように思う。
本当に久しぶりに新宿に来たから、人がそれほど歩いていなくても熱量は高く、そして、新宿眼科画廊には行ったことがあるから、その少し先だと把握していたことで、勝手な安心感を得ようとしていた。
『新宿眼科画廊』
https://www.gankagarou.com
だけど、そばまで来ているはずなのに、展覧会場が、分からない。
確かにワシントンプラザに来たのに、お店しかない。だから、階段を降りて、隣のマンションの入り口から建物に入って、そこの管理人さんに聞いていたら、掃除のスタッフの女性が声をかけてくれる。
展覧会場である能舞台の場所を案内してもらいながら、何やっているの?何を売っているの?と繰り返し聞かれ、アートの展覧会です。と答えても、物はなに?と尋ねられ、物はなくて、展示なんですが、と言えるだけだった。お礼を言って、階段を登る。
よく見たら、外側に大きい「能舞台」という看板があったのに気がつかなかった。
第一会場
入り口前の階段の受付で、自分の足のサイズに合わせて、足袋を選ぶ。
本当ならば、裸足で履いた方がいいのだけど、会場の入り口から入って、長椅子に座って、靴下を履いたまま足を入れた。足袋の二本指が空のままだった。
会場の中は暗く、そして、どこへ入ったらいいのか分からなかったけれど、スライドで変わる映像があって、顕微鏡がらみの作品があって、そして、スクリーンで映像作品が流れている。しばらく座って、見る。
それから廊下を歩いて、そこにも作品があり、さらに、ドアを開けると、そこが能舞台だった。
このために足袋を履いている。
初めて、能舞台という場所に立つ。
そこは、振動スピーカーを使って、舞台自体をスピーカーのようにしていて、その振動が伝わるし、能での足拍子の再現のようにも思え、新鮮だった。
その舞台を降りると、座布団が敷いてあって、その前に映像があったり、暖炉のようなものがあったり、壁に文章が書かれてあったり、大きいQRコードがあったり、何があるのか、分からず、どこから考えていいのか。なんだか途方に暮れる気持ちになった。
いわゆる展覧会のようなところで、こんな気持ちになるのは初めてだった。
それは、「新しい」ということなのかもしれない。
説明
ただ、あまりにも暗中模索な感じで、このままだと何も感じないで、帰ってしまうかもと思い、たまたま、そばに、キュレーターの渡辺志桜里氏がいたので、聞いてもいいですか?と声をかけたら、話をしてくれた。
自分にとって、とっかかりがなくて、といったことを話し、そうしたら、渡辺氏は、何か統一的なテーマがあるというのはでなくて、「翁」という大きすぎるものがあって、といった話から始まって、こちらの無知な質問に対しても丁寧に答えてくれるうちに、少しぼんやりとわかってきた。
自分の細胞を、向かいのラブホテルの一室で培養しているアーティストは、新宿の街中のビジョンにその映像を映したりしているらしい。それは自分の細胞というプライバシーを、公共に見せるということをしている。
他にも、いろいろな話をしているうちに、少しだけわかった気がしたのは、「翁」という概念は、昔から存在したのだけど、それは、現代の視点から考えても「新しく」しかも、「巨大」らしい。
だから、それは命とか、個人とか、自然とか、存在とか、そういったことについてアーティストがそれぞれ考えるから、展覧会としても、統一感があるわけでもなく、複雑な感じがして、だから、観客としても、どこに手をかけたらいいのか分からない。そんな状態になるのは、分かった気がした。
こんな乱暴な話に付き合ってくれて、それは、とてもありがたいことだった。
第2会場
荷物を手に持って、それがかさばって、ガサガサしていて、だから、見かねて、会場のスタッフの人が、こちらに置くのはどうですか?と言ってもらったり、親切にしてもらった上に、話を聞いた後だと、それぞれのアーティストが、それぞれの方法で、何か困難なことをしようとしているのは、分かった気がして、だけど、それは分かりやすさとは関係がないのは、分かったように思う。
こんなふうに混乱した表現になるくらい分かっていなかったのだけど、最初は、ただつるんとしたものを触っていたのが、少し手にひっかかるものができてきたような感触はあった。
そこから、また次の会場に歩く。
第2会場は、さっきの能舞台の足拍子が続いているように思えた。
それから、さらに、普段は行かないような場所での展示があって、その風景も含めて、作品のようだったし、そこに設置されてあった作品が、複雑な意味を投げかけてくれて、日常的でないことを、考えようとすることはできた。
それは、そこにも現場のスタッフの方がいて、こちらの素朴な疑問に丁寧に答えてくれたから、できたことだった。ありがたい。
ずっと日常的なことを考えて、それで、前日も悩んでいたりもしたのだけど、今回の展覧会は、今ある「世界」を、大げさにいえば、その外側からの視点について考えるようなことなのかもしれない、などと思えたから、やっぱり来て良かったのだと思う。
日常的ではない視点
電車で帰る途中にステートメントを改めて読む。
人類は、約700万年前に登場し、いずれ絶滅する、地球や宇宙の生の中のほんの一瞬にだけ繁栄する種であるが、後にも先にもその歴史には、いわゆる「翁的なトポロジー」が(人類とは関係なく)存在する。
「翁」への考察は古くは金春禅竹の『明宿集』がある。そこでは「翁」は人間が感知し得ない存在全ての「あらわれ」として、壮大な宇宙観の中で記されている。「物事の区別以前の混沌」であり、その前には二項対立的なものですら、対立せずに成立してしまう。停滞した日常に揺さぶりをかけるその存在は、私たちの生命力を呼び覚ます。
展覧会に行く前は、自分とはとても遠いところで、見えもしなかったこの文章が表すことが、展覧会に行った後は、なんとなく、こういうことを見せてくれようとしたのでないか。日常とは違うというよりも、日常からも、こういう世界が感じられるはず、とオカルト的なものとは違う「非日常的な視点」を示そうとしていたのかもしれない、などと思うようになった。
世界の外側。
普段なら恥ずかしくて書けないような表現だし、「翁」的な概念とも違うかもしれないし、的外れかもしれないけど、そんなことを想像するような刺激は受けたような気がする。そういう視点がないと、生き物も無生物も物体も全てが一緒、というようなことはイメージしにくいのではないか。
これは、展覧会を実際に観に行かないと思わなかったはずだ。
最古の能の演目『翁』をベースにした本展は、「存在そのもの全て」だとされる「翁」、そして人間以外の存在「人外」が語る能に着目することで、独自の視点からの新たな自然観を探るもの。出展作家は、飴屋法水たち、石牟礼道子、エヴァ&フランコ・マテス、コラクリット・アルナーノンチャイ、小宮花店、小宮りさ麻吏奈、ザ・ルートビアジャーニー、動物堂、ピエール・ユイグ、ミセスユキ、渡辺志桜里。
本展では、国内外のアーティストに限らず、食やインターネット、文筆家や演出家、動物の販売店や花屋など、多様な分野の表現者らの作品が、人間の歴史、環境、自然にまつわるファクトと結びつくことで、独自の世界観を提示する。
こうした、専門誌のサイト↑の文章を読んだら、とても分かりやすく感じた。(「動物の販売店や花屋」という表現は、確かにそうなのだけど、それをアーティストが運営しているから、微妙にニュアンスが違うかもしれないとは思うけれど)。
「翁」が、「存在そのもの全て」という表現が正確だとすれば、そんなものを作品化しようとすることは、普通は最初から諦めそうだけど、家に帰って、ハンドアウトを読み返し、会場の光景を思い起こすと、そのことに対して、参加しているアーティストたちは、少なくとも正面から真面目に取り組もうとしていたような気がした。
そして、それぞれのアーティストの作品は、ある意味で、別々に点として存在していて、それを鑑賞者が、意識の中でつなぐことで、もしかしたら、その「存在そのもの全て」を考えるきっかけになるのかもしれないと思い、金春禅竹という名前は教えてもらったので、「明宿集」だけは読もうと思った。
金春禅竹が、能楽の金春流の開祖だと、恥ずかしながら初めて知った。
(他にも、いろいろと書いています↓。よろしかったら、読んでもらえたら、うれしいです)。
#最近の学び #イベントレポ #現代美術 #現代アート
#展覧会 #とうとうたらりたらりらたらりあがりららりとう
#能楽 #翁 #金春禅竹 #渡辺志桜里 #アート
#キュレーション #存在そのもの全て #毎日投稿
記事を読んでいただき、ありがとうございました。もし、面白かったり、役に立ったのであれば、サポートをお願いできたら、有り難く思います。より良い文章を書こうとする試みを、続けるための力になります。
