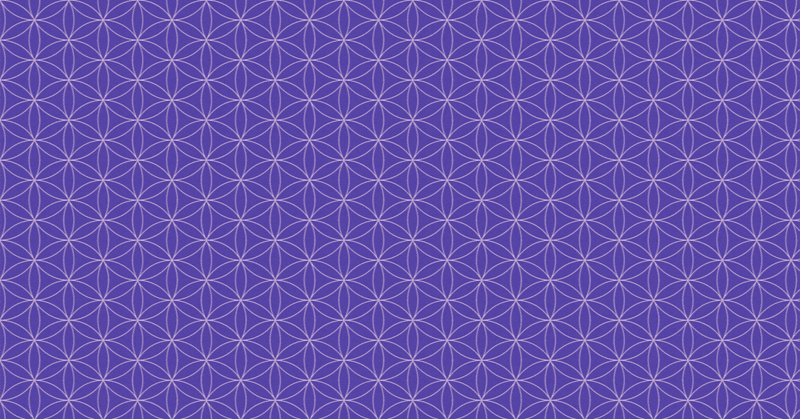
【短編小説】”あちら”から来た男
「過去帳改めに来た。邪魔するぞ」
雪のちらつく、とある山深い集落。
男はその中でもひときわ古い一軒の玄関を開けると、そう告げた。
すぐに返事があって、ひとりの老婆が出てきた。老婆はきっちりと結い上げた長い白髪と同じ色の割烹着姿で、男の前で膝を折って正座すると、深々と頭を下げてこう言った。
「お待ちしておりました。遠いところ、ご苦労さまでございます。さ、上がってくださいな。今日はたいそう冷えますから」
そして、皺だらけの顔に人の良さそうな笑みを浮かべ、男を家の中へ招き入れた。
「ああ、翼をぶつけないようにお気をつけください」
その言葉で、男は広げたままだった背中の翼を身幅にまで折りたたんだ。ついでに羽織の肩口に積もった雪を手で払う。
翼の生えた和装の男がそうする様を、老婆は笑顔のまま見守っていた。
男が通されたのはその家の仏間だった。
朝からストーブを焚いていたのか、載せられたやかんからは湯気がうっすらと立ち上っている。部屋にはこまめに磨かれているとおぼしき仏壇が壁の一面に埋め込まれるように設えられ、それを取り囲むように埃ひとつ付いていない額縁に収められた先祖たちの遺影が飾られていた。
物珍しそうに部屋の中を見回す男をよそに、老婆は仏壇の引き出しから朱色の金襴張りの帳面を一冊取り出すと、傍らに置いた白木の三方に載せた。そして、すっと姿勢を正すとその三方を両手で捧げ持って男の前まで歩き、
「こちらが、我が家の過去帳でございます」
と、差し出した。
男が三方から過去帳を取ると、老婆はそのまますっと後ずさり、仏壇を背にして正座した。
「それでは、改めさせてもらう」
老婆の視線を感じながら、男は過去帳に書かれたこの家の故人の名前や没年を一人ひとり確認していく。もし去年から増えていたならば、その者の生前の様子を聞き、記録しなければならない。
それがこの辺一帯で昔から続いている『過去帳改め』、そしてこの男の仕事だった。
男は過去帳をめくっていくと、最後に記された名前に目を留めた。そこには去年までの記録になかった名前が書かれている。
「一人、増えたか」
男がその名前を指でそっと撫でながらそう言うと、老婆が身を乗り出してその名前を覗き込んだ。そして、深い溜め息をひとつしてから体を戻すと、絞り出すようにこう言った。
「ええ、そうなんです。夫がね」
男が過去帳から顔を上げると、老婆は仏間の掃き出し窓の向こうに広がる雪景色を見つめながら言葉を続けた。
「桜が満開の、それはそれはきれいな日でした。長いこと患って、ようやく家に帰ってこられたのに、その次の日にはもう。せっかちな人でしたけど、最後くらいはゆっくりしてくれてもよかったのに」
老婆はそこまで話すと、一度振り返って仏壇を見やった。それから男の方に向き直ると、真剣な眼差しで畳に手をつき、頭を下げた。
「”あちら”でどうぞ、夫に良くしてやってください。せっかちではありましたが、頭の回転が早くて、いつも人の先を行って私を引っ張ってくれる人でした。”あちら”でも、きっと何かのお役に立てるはずです」
「ああ。安心してくれ」
男がうなずいてみせると、老婆は安心したようにふっと頬をゆるめた。
「まあ、せっかちなだけにおっちょこちょいなところもありますから、あなた様のように、過去帳改めのような誇らしいお役目をいただけるかは……あら、いけない。こんなこと言ったら夫に怒られてしまう」
そこまで言うと、老婆はふふふ、と声を上げて笑った。その瞳はまるでいたずらをする子供のようだった。
「詳しいな」
「はい。この辺りの者は、誰かが亡くなった折に必ず教えられておりますから」
老婆は男の言葉を褒められたと取ったのか、嬉しそうに応えた。
「亡くなった者の名を過去帳に記すというのは、その者が人の世界ではない”あちら”に移り住み、新しく籍を作ること。だから、”あちら”からいらしたお役人様にどれだけ素晴らしい人だったかを申し送りしてあげれば、”あちら”でもお役人になって幸せに暮らせる、と」
「そうなのか」
「ええ。私は爺さまの時に教わりまして……あら、いけない」
話しながら視線をストーブに移すと、老婆はそこではっと何かに気づいたように話を止めた。
「私ったら、せっかく来ていただいたお役人様にお茶もお出ししないなんて。今お持ちします」
老婆は素早く立ち上がってストーブの上のやかんを手に取ると、仏間を出ていった。
遠くの方でしばらくがちゃがちゃとにぎやかな音をさせた後、再び戻ってきた老婆は黒漆で塗られた大きな盆を両手で重そうに持っていた。盆の上には急須に湯呑み、そして大きな皿に山盛りにされたぼた餅が載っている。
「不調法な真似をして申し訳ありませんでした。さあ、こちらもよろしかったらどうぞ。私が作ったぼた餅です」
盆を仏間に置かれた座卓に置くと、老婆は笑顔でそう言ってぼた餅の皿を男の前に置いた。続いて、籐の弦つきの大きな急須から茶を注ぐ。急須と揃いの白い椿の花が描かれた玉湯呑みに、なみなみと緑茶が注がれていく。
「遠慮せずに、たんと召し上がってください。もう食べてくれる人もいないのを忘れて、山のように作ってしまったんです」
「他には誰もいないのか」
男は前に置かれた湯呑みを取り、皿からぼた餅をひとつ手にしてかじるとそう問いかけた。
「ええ。ほら、ここ」
老婆は座卓の上に置かれたままになっていた過去帳を失礼します、と言ってから手に取ると、最後の頁を開き、ある名前を指した。先程夫だと言った名前のひとつ前だった。
「これは息子の名前なんです。まだ十歳そこらで、事故に遭ってしまって。今は隣町にいい病院ができましたけど、あの頃は医者を探すのもひと苦労で。間に合いませんでした」
老婆の顔に悲しみと、諦めのような表情が浮かぶ。
それを見た男の動きがぴたりと止まった。
「他の者は」
「子供はこの子ひとりきりでした。長い間望んで、ようやく授かった一人息子だったんです。良くしてくださったご近所や親戚連中は、ほとんど村を出てしまいました。皆、よく顔を見せに来てはくれますが、今はこの集落にいるのは私くらいです」
「そうか」
老婆はじっと過去帳に記された息子の名前を見つめ、黙ってしまった。
男はそれを見つめていたが、やがて耐えきれなくなったように手にしたぼた餅をかじりだし、さらに二つ食べてから茶で洗い流すようにそれを飲み込む。そして、しばらくしてから口を開いた。
「その……書いたのか。息子の、過去帳を」
「ええ。親としてしてやれる最後のことですから。あの時の過去帳改めでは、私ら夫婦だけでなく、まだ元気だったあの子の祖父母に親戚連中、ご近所の皆さんやあの子の学校の先生やお友達まで来てくださって。ほとんど村の者総出でもってあの子のことをお願いしました。せめて、”あちら”では幸せに、どうか、どうか幸せに過ごしてほしい。きっと、そうしていると信じております。あ、あの子だけは……すみません」
話すうち、老婆は泣き出していた。割烹着のポケットを探り、白いガーゼのハンカチを取り出すと、男から顔を背けて涙を拭った。
「いや、すまない……こちらこそ」
男も老婆から顔を背けてそう言うと、ぬるくなった茶を一口すすった。
「だけど、私ももうすぐ”あちら”で息子に会えるでしょう」
まだ涙声の老婆がそう言うのが聞こえると、男は音がしそうなほど勢いよくそちらに顔を向けた。
老婆は涙を拭いたハンカチをポケットにしまうと、両手を拳の形にして膝の上に置き、すっかり赤くなった目で何かを覚悟したかのように男を見つめる。それから、夫のことを話した時のように畳に手をついて頭を下げた。
「私のことを過去帳に記してくれる人はもうおりませんが、”あちら”に行けた折にはどうぞよろしくお願いいたします」
「まだいい」
間髪入れずに強い口調で男がそう答える。
「え?」
予想していない答えだったのか、老婆は驚いた様子で顔を上げた。
「俺はあんたのぼた餅が気に入った。来年もまた食べに来る。だから、まだこちらにいろ」
そう言うと、男はさらにもう一つぼた餅を手に取り、口に運んだ。そして、老婆が呆気にとられながらも淹れ直した茶を一気に飲み干すとこう言った。
「あんたまでせっかちになることはない。もう少し、ゆっくりしていってもいいだろう」
男の顔を見た老婆の表情がいくぶん明るくなった。
男はそれを見て満足そうにうなずくと、湯呑みを戻し、開いたままの過去帳を閉じて老婆の膝の上にそっと置いた。
「これにて、過去帳改めは以上とする」
そう言って立ち上がると、まだ皿の上にずいぶん残っているぼた餅を指さす。
「ところで、これをもらっていっても構わないか。オカシラへの土産にしたい」
「はい……はい! 今包みますから、ちょっと待ってくださいね」
今度こそ笑顔になった老婆が、皿を持って一礼してから仏間を出ていく。
男はその少し曲がった小さな背中を、泣き笑いのような顔でじっと見つめていた。
老婆は、七宝文様が入った藍色の大きな風呂敷包みを抱えて戻ってきた。
その姿を見ると、男は仏間を出て玄関へと歩いていく。雪駄に足を入れ振り返ると、老婆が風呂敷包みを差し出してきた。それを受け取ると、少し考えてからできる限りの優しい口調でこう言った。
「あんたの旦那のことも、いつかやってくるあんたのことも、必ず俺がオカシラへ伝える。心配なんてしなくていい。約束……するからさ、」
男はまた泣き笑いのような顔になると、左手を顔の横まで上げて、小さくひらひらと振った。
その瞬間、老婆の小さな瞳がこれ以上ないくらいに大きく見開かれた。ふるふると唇を震わせたかと思うと、小さな、小さな声でつぶやく。
「ヨウイチ……?」
男はそのつぶやきが聞こえないふりをして、老婆に背を向けた。
「かあちゃん」。男は最後のその一言をすんでのところで飲み込んだ。玄関から一歩踏み出して家の外に出ると、背中に畳んでいた翼を広げる。
その一言は、決して口にしてはいけないのだ。
『決して、母には息子だと告げぬこと』
それを条件にようやく掴んだこの役目を、失うわけにはいかないのだから。
ずっしりと重い風呂敷包みを両手でしっかり抱え、雪のちらつく冬空の奥の奥、人の世を超えた遥かな”あちら”へと男は飛び立った。
母が自分の名を呼ぶその声を、その身と翼いっぱいに受けながら。
powered by
三題噺スイッチ改訂版 | どこまでも、まよいみち https://mayoi.tokyo/switch/switch2.html
読んでいただき、誠にありがとうございました。 サポートいただけますと、中の人がスタバのラテにワンショット追加できるかもしれません。
