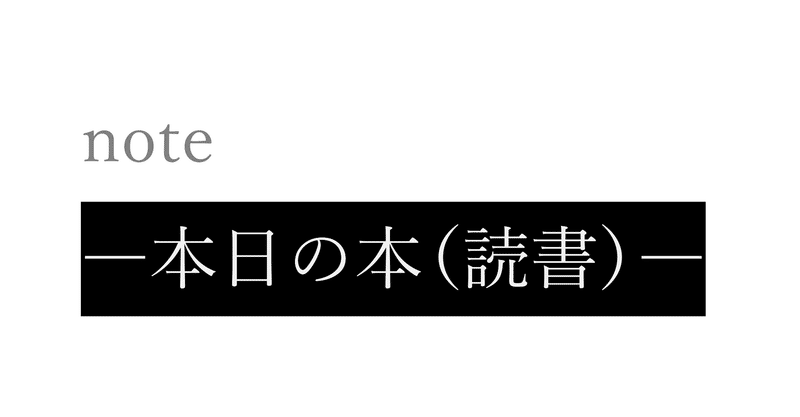
『大江健三郎自選短編』(岩波文庫、2014年)の感想
いま短編小説の総体からある数を選んだ(そのようにして残すものより除外するものが思っていたより多くなりました)、この場合にも私は必要に思う書き直しはして、最終的な定本作りをこころがけました。
本作p811「生きることの習慣――あとがきとして」
大江健三郎氏の最後の新作長編『晩年様式集』のあとに発表された自選作品集。Ⅰ初期短編、Ⅱ中期短編、Ⅲ後期短編に分けられてノーベル賞文学者の短編が総覧できる作品集だが、とりわけ中期短編が強烈で、大江健三郎渾身の「最新作」と評したくなる迫力が感じられる。
まず、Ⅰ初期短編の紹介を。
犬を大量死させるアルバイトに参加する「奇妙な仕事」、同じくアルバイトで検体を移動させる「死者の奢り」、サナトリウムの虚無に左翼学生の希望が悲劇をもたらす「他人の足」、村に敵国の兵士がきた「飼育」、バス車内での米兵の暴力行為の余波を克明に描く「人間の羊」、外国兵と通訳が村にきた「不意の唖」、劣等感にさいなまれる男子学生が右傾化する「セブンティーン」、作曲家Dを空から訪れる幻想にバイト君がつきそう「空の怪物アグイー」の八篇。サルトル直系タブー感のある鮮烈なイマジネーションで現代を活写する切れ味の有名短編のセレクト。「アグイー」の他人のイマジネーションが転移するがただの心的な事象に収斂しないラストが印象的。
そして、Ⅱ中期短編を。
世界的文学者のエッセイのようでブニュエルの映画のような奇妙さに突入していく「頭のいい「雨の木」」、「雨の木」の象徴性をメタに語りながら旧友高安氏のふるまいが衝撃的な「「雨の木」を聴く女たち」、その衝撃的なふるまいの意味がさらにややこしくなる「さかさまに立つ「雨の木」」、作家の障害をもつ長男の鬱屈の想像「無垢の歌、経験の歌」、彼の心中の死と再生を描く「怒りの大気に冷たい嬰児が立ちあがって」、2人のスイミング話に「組織」活動が挿入されていく「落ちる、落ちる、叫びながら……」、みだらなエピソードと聖性が同時に描かれる「新しい人よ眼ざめよ」、両親が海外に行き、作家の子どもたちの生活が娘の視線で描かれる「静かな生活」、タルコフスキーの映画『ストーカー』が生活に心象をもたらす「案内人」、内ゲバに関わった青年と作家の交流の物語「河馬に噛まれる」、そこに若い娘さんも加わり不思議な三角関係の「「河馬の勇士」と愛らしいラベオ」の全11篇。
はじめに衝撃を受けたのは、これらが全て連作短編の抜粋である点だ。
『「雨の木」を聴く女たち』の1, 2, 4
『新しい人よ眼ざめよ』の1, 2, 3, 7
『静かな生活』の1, 3
『河馬に噛まれる』の1, 2
「最終的な定本」な作品が抜粋であること。特に『新しい人よ眼ざめよ』は一冊のダイジェストのような趣さえ出てしまっている。この作家以外のアンソロジストがやったら非難ゴウゴウになると想像にかたくない作品の再編集=「書き直し」を大江健三郎なぜしたのか。それはきっと「連作短編」同士のイメージの運動をいま新たに提示せんとする野心があるからだ。
きみのヴィジョンの「雨の木」は進化せず展開もしない。ついに死の時をむかえるまで、しだいに古びてゆく「雨の木」のメタファーを、きみは護符のように持ちつづけるつもりなのか?(略)僕はこの批判について沈黙しているほかなかった。そのうち僕は小説に書かなかった、もうひとつの「雨の木」に思いがゆくのを感じることがあった。実在する「雨の木」。
本作p580「新しい人よ眼ざめよ」、「レイン・ツリー」のルビを略した
こう書きながら大江健三郎はメタファーを進化させている。これまで「小説に書かなかった」ことを新たに書き足して。その証拠に本作のラストでは「生命の樹」のイメージと新たにむすびついて「雨の木」は更新する。それは同時に「雨の木」のかつての調和を破壊する「書き直し」である。
「雨の木」をとおりぬけて、「雨の木」の彼方へと、すでにひとつに合体したものでありながら、個としてもっとも自由である者として、帰還するのだ。
本作p635-636「新しい人よ眼ざめよ」
もしも本当にこの境地を人間が生きられるとしたらと考えてみよう。きっとそれは「個」によって認識が激変するものになることはまちがいないだろう。「静かな生活」「河馬に噛まれる」のテキストも、作家の私生活の書き直し以上に、この境地に対する認識のちがいがモチーフにある感じがする。
私の体をつらぬいて光が放射されるように、続けて起こって来るのはあきらかに邪悪な強い歓喜で――私はこの世界の人間のうちもう兄と自分自身のことしか考えなかった
本作p693「案内人」、題「ストーカー」のルビおよび「邪悪な」の傍点略
青年と自分の情動を綯いあわせるようにして、勇ましい河馬の光景を思ったのだが、それは自分の発した声援が、コダマのように戻ってくるのへ耳をかたむけようとねがったのでもあっただろう
本作p744「「河馬の勇士」と愛らしいラベオ」
他人と結びつく力の邪悪さや、内むきのかげを大江健三郎はフェアに執拗に記述する。それはひとが本当に「合体」を生きることができるのかを問う格闘といえるだろう。Ⅱ中期短編は全部まとめて大江健三郎がひたむきに凶暴なまでにテーマの「書き直し」を刻んだドキュメントとして受け取れる。
最後に、それに続くⅢ後期短編を。
いまだ作品化していなかった四国の森のイメージを記す「「涙を流す人」の楡」、ダンテと不倫がセットになって大江節が健在すぎる「ベラックヮの十年」、マリアと「救い」と死の物語「マルゴ公妃のかくしつきスカート」、ウグイスと「私」を超えて大きく包み込む魂の小論「火をめぐらす鳥」の4篇。より形式的に自由な印象と、中期と同様の迫力とを感じます。
最後の最後に「あとがき」の引用を。全的な力を小説にになわせるための「書き直し」という方法にたどりついた自負が強烈。このパワーこそが本作を大江健三郎の最新作と呼びたくなる所以です。ぶ厚いのもおすすめです。
小説を書くことは、全人格が参加する行為であり、芸術は人間の全体に根をおとしている習慣である。(略)私は若い年に始めてしまった、小説家として生きることに、本質的な困難を感じつづけてきました。そしてそれを自分の書いたものを書き直す習慣によって乗り越えることができた、といまになって考えます。
本作p838「生きることの習慣――あとがきとして」
(付記として:中期は本作で読むと鮮烈なテーマの展開に瞠目しますが、それぞれの作品を通しで読んでも別の気迫がたたえられていてそっちもおすすめ。特に『「雨の木」~』の残念すぎるラストの「泳ぐ男」、『新しい人よ眼ざめよ』で冒頭2ページでのテーマの提出がえぐいくらい強い「蚤の幽霊」、『静かな生活』の大江全小説のなかでも(プールで事件おおすぎと思うけど)本当に素敵なラストの「家としての日記」、『河馬に噛まれる』の中最も長く内省的に他者を描く「死に先だつ苦痛について」は必読といえます。ただし繰り返しになりますが、本作で連作を読む鮮烈さは貴重です!)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
