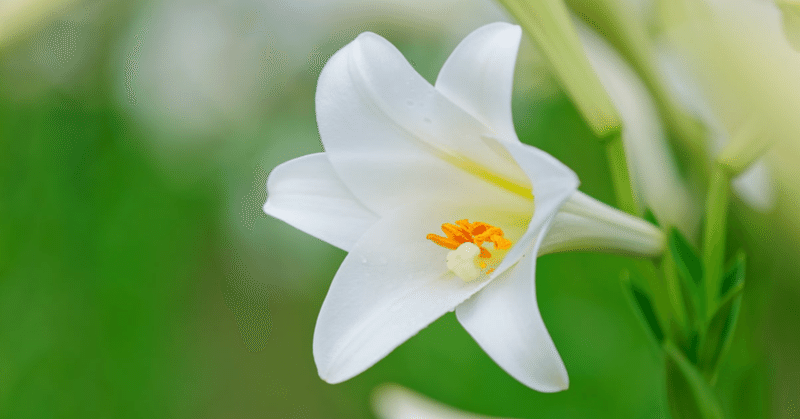
【エッセイ】花の声 ――あるユリの最期の言葉
植物に心はあるのだろうか。
そんな問いに、科学的根拠を示して明確に答えられる人は、まだいないだろう。
今回の記事は、私が植物の心について考えさせられた、少し不思議な話だ。
最近の病院では、複数人一緒の相部屋であっても、それぞれが1日中自分のベッド回りにカーテンを引いていて、相部屋の中に仕切られた個人的な空間が複数ある状態で、同室患者との交流もほとんどないものだ(ただし、病状の重い患者は、看護や介護のしやすさを優先してカーテンを開けたままの場合もある)。
昔と比べて1つの相部屋に同室する患者数は減り、患者1人当たりのスペースも広がった。入院患者の過ごしやすさやプライバシー保持を重視された結果なのだろう。
昔の病院では、起床後消灯まで仕切りのカーテンは開けておくのが当たり前で、6人が同室する大部屋もよく見かけ、あまりプライバシーがない反面、同室患者とは自然と親密な交流が生まれたものだった。
毎日顔を合わせ、声をかけ合い、世間話をする。お互い差し支えない程度に病状を聞き合い、気遣い合い、励まし合う中で友情も生まれる。
これはそんな昔の、27年前の病院での出来事だ。
私はある持病で、4月末から8月中旬までの約3ヶ月半の間、入院していた。
たいして重病ではなく、安静にしている必要はなかったので、いつの間にか、6人部屋である同室患者の世話や手伝いをすることが日課になっていた。
中でも花の世話は私の担当だった。
最近の病院ではあまりお見舞いの花を見かけない。
最近は基本的に付き添いを断っている病院が多いと思われるが、そういう状態で患者が日々花の世話をするのは療養の負担になるし、病院のスタッフもそこまでは手が回らないために、お見舞いの花を断っているのだろう。
しかし当時は、入院患者がお見舞いの花をもらうのは当たり前だった。私が入院していた病院の病棟には予備の花瓶があって、必要な人は貸し出してもらえた。
そうは言っても、付き添いがいる患者はともかく、そうでない、中でも病が重い患者にとっては、花の世話は一仕事であり面倒なものだ。
花瓶に活けられている花は、水を替えないまま数日そのままにしておくと、水につけている茎の部分が腐って水が濁ってくる。
フローラルフォームと呼ばれる緑色の堅目のスポンジに花を差してあるアレンジメントもあるが、これも、花瓶の花より持ちはいいものの、数日放っておけば水分が花に吸収されてスポンジが乾いてきてしまうし、スポンジに差している部分は弱って腐ってくる。
そもそも切り花にした時点で、花は次第に腐って行く運命にあるのだ。
しかし、その速度を緩めることはできる。
毎日花瓶の水を新しいものに取り替え、腐ってしまった茎の先の部分を切り落として活け直せば、きれいな姿を長く保てるわけだ。
アレンジメントも同様だ。2日おきくらいに差している茎の状態を確認し、弱ってしまった部分は切り落として、スポンジに水を含ませればいい。
そして、花瓶の花もアレンジメントも、枯れたり駄目になった部分を取り除き、きれいな部分だけを残して整えるのだ。
私は、当初は自分の花の世話だけしていたのだが、なかなか世話がされないまま弱って行く同室の他の花を見てかわいそうになり、世話を買って出るようになった。
しかも生き返ったようにきれいになる花を見て喜ばれるので、それが嬉しくもあった。
やがて、1人の同室患者の花の世話をするようになれば、その人の花だけを特別に、というのも何だか変な感じに思い、気がつけば同室患者の花は全部私が世話をするようになっていたのだ。
きれいに活け直された花を見て、同室患者には、花屋に勤めていたのか?と必ず聞かれたものだ。そういうわけではないが、当時勤めていた仕事で生花に携わることもあったので、その時に基本的なことを学んだのだ。
仕事で習得した技術が予想外の場所で活かされていることが、我ながら少しおかしかった。
入院していると、後から入院して来た人が先に退院することもある。
急性に発症した短期入院の人は、お見舞いにもらった花が、入院中最初で最後の花になることもある。
部屋では、「この花が散る前に退院できるだろうか?」という言葉がよく聞かれた。
私は毎日花の世話をしながら、無意識の内に、できるだけ長持ちしてくれ、と花に念じたものだ。
白いユリも、そんな花の1つだった。時は6月で、丁度ユリのきれいな頃だ。
ユリは香りが強くてお見舞いの花には向かない、とも言われるが、このユリの持ち主は喜んで愛でていたし、私を含め他の同室患者も不快に思うことはなく、楽しませてもらっていた。
私は持ち主の退院日までの日数を数えて、あと○日持ってくれ、と祈りながら花の世話を続けた。
たくさん咲いていた花も1輪散り、2輪散り、やがて最後の1輪の花も、6枚の花弁(正確には3枚の花弁と3枚のがく)の内、2枚を残すのみになった。
そしてついに、ユリの持ち主の退院日を迎えた。持ち主の同室患者は、何とか2枚花弁を残していたユリに、「退院するまで残っていてくれてよかった。ありがとう」と礼を言っていた。
退院した同室患者から後を託された私は、洗い場に花瓶のユリを運んで水を替えながら、「○○さんが退院するまで頑張ってくれてありがとう」と、心の中でユリに礼を言った。
その時だった。
突然、「ああ……私は満足だ……」と言うユリの声を、確かに私は聞いた。それは、男性の声とも女性の声とも言い難い、あえて言うなら中性的な、そして直接頭に響くテレパシーのような声だった。
そしてその瞬間、ユリに残っていた2枚の白い花弁が、ハラリと散った。私の手には、茎だけになったユリが残された。
ユリの、花としての命は終わったのだ。
まさにもう死ぬという、ユリの最期の瞬間の声を私は聞いたのだ。
ユリは、わかってくれていたのだ。私の思いを。持ち主である同室患者の思いを。
そして本当に、持ち主のために、長持ちするように頑張ってくれていたのだ。
どれほどの人が、誰かのために精一杯命を燃やして、死に際に「満足だった」と言える生き方ができるだろうか。
それは、決してたやすくはないはずだ。
そう思えばこそ、ユリの思いの尊さがひしひしと感じさせられて、私は誰もいない洗い場で1人、震える心のままに涙を流していた。
植物に心があると言う人もいれば、ないと言う人もいる。
以下のように、植物の心について研究された記事もある。
しかし植物に心があるかどうかは、まだ科学で明確に解明されてはいない。
私が花の声を聞いたのも、この出来事が最初で最後だ。
病院という、社会や日常から隔絶された場所で、祈りと共に行う利他的な行為は、修行僧や修道士の行いに似ていたのかもしれない。
純化された感性があったからこそ、奇跡的に、花の声が届いたのかもしれない。
花の声を聞いたと言えば、多くの人は「空耳だ」と言って笑い飛ばすだろう。
これを読んだあなたがそう思うのなら、それでもいい。笑い飛ばしてくれて構わない。
それでも、この出来事は私にとって、まぎれもない真実であり、心に刻まれた貴重で大切な経験なのだ。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
よかったら「スキ」→「フォロー」していただけると嬉しいです。
コメントにて感想をいただけたらとても喜びます。
サポートしていただけたら嬉しいです。いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます。
