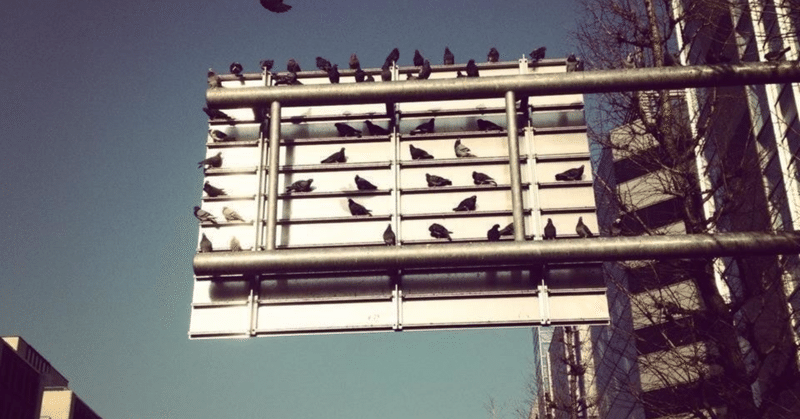
李龍徳「報われない人間は永遠に報われない」
作者は2014年「死にたくなったら電話して」で第51回文藝賞でデビューした方。何の予備知識もなく題名に惹かれて手に取った。
クレジットカード会社での、深夜帯コールセンター業務に従事する派遣社員の二人の話。語り手の近藤と、諸見映子という、これまで他人とは距離を置いて過ごし続けてきた二人がひょんなことからくっつく。恋愛に至る前に、それまで抑圧されてきた言葉が、破裂するように二人の間で交わされる。
僕たちは言葉が止まらなかった。ちょっと押せば彼女は、映子は、よく喋る。僕もまた、こまめにメールをしたためたものだった。なぜといって、こうして格好の話し相手を見つける以前の僕たちというのは、益体もない言葉の泡に埋もれていた。暇な人間とはそうである。人生の埒外に置かれた人間とはそうだ。自分自身しか対話者がいないから言葉の泡が身辺に吹き溜まり、僕らはそれを宝珠であるかのように天高く撒こうとするのだが、重みなく、輝きなく、産業廃棄物のそれのように汚らわしく身体にまとわりついて結局はその場に山となり、僕らはそこに埋もれる。あるべき言葉とは、真の知性とは、そういうものではないだろう。もっと重みがあって光沢があって、もっと風通しのよい健全なものであるはずだ。
半同棲を始めても二人の関係性はいつまでも人に慣れないままのようで、「報われない人間は永遠に報われない」という作中の映子の言葉のように、「変われない人間は永遠に変われない」かのようだ。もどかしくもありながら、ここでどちらかが積極的に前向きになって明るい人生を歩き始めたら、興醒めしてしまうことだろう。
もっとも私に響いたのは、「後日談」と題された最後の文章だ。映子と別れた近藤が、もはや伝えられない言葉を映子に向けて語っている。既に若くなく、昔の映子を笑える状況でなくなっている彼の言葉は、真摯で実直で心に響く。最初からこうであれば、誰も不幸にはならなかったはずなのに、そうはいかないのだから、小説は生まれる。5ページに満たないその「後日談」を私は何度も読み返している。
入院費用にあてさせていただきます。
