
ちいさなトライを重ねること。
こんにちは。
フリーのバリスタとして活動を始めてから1年、
店舗時代にできなかったやってみたかったこと、こうだったらいいのではないかと感じていたことをたくさん試すことができました。
そのひとつが、今年に入ってからはじめた、既存の店舗に間借りする形の《Guerrilla Coffee》。
ゲリラ部隊のゲリラです。
ゲリラ(スペイン語: guerrilla)は、ゲリラ戦(遊撃戦)と呼ばれる不正規戦闘を行う民兵またはその組織のこと。 ゲリラ戦とは、予め攻撃する敵を定めず、戦線外において小規模な部隊を運用して、臨機応変に奇襲、待ち伏せ、後方支援の破壊といった、攪乱や攻撃を行う戦法
今日はこの《Guerrilla Coffee》とそれ以外の活動について、なぜこういったスタイルを選ぶのか、何を目指しているのかということを少しお伝えしたいとおもいます。
やってみてわかったことを受けて、今、こう考えています、というお話です。個人的なことですが、よければお付き合いください☺︎

みんなちがう、という原点
コーヒーショップで働き始めた頃、クレマがしっかり張ったエスプレッソに、甘みの出る温度帯で仕上げたスチームドミルクを合わせるカフェラテを作るのが好きでした。
毎朝エスプレッソ調整の作業をし、どうしたらどうなる、というのを実際の抽出をとおして知っていくことも、
技術がついてきて、狙った味に仕上げられるようになっていくのも、すごく楽しかったんですね。
なかでもいちばん楽しかったのは、
基本的には決まったレシピがあるけれど、お客さんから
「こういうのできる?」「これ、こうならないかな?」という要望があって、それに応えたり、試行錯誤することで、
だんだんとその人に合わせたラテやカプチーノを作るようになりました。
ひとりひとりに合わせてつくる、というのは、すごく手間がかかることのように感じられるかもしれませんがそんなことはありません。
理由は、基本的なことは変えないからです。
お店の味、という条件がある上で、変えていいポイントは《ちょっとだけの手間》で《お客さんにとっての価値が高くなる》ところ。
状況によりこのバランスの見極めが必要ではありますが、
ラテやカプチーノの温度調整などは自分にとってこの代表格です。
仕上がりは57度を基準として、たとえば熱め、という指定があった場合、ミルクのスチーミング(冷たい牛乳にマシンで蒸気を入れ込み、温めていく作業)で調整が可能です。
これはマシンにもよりますが、スチーミングの時間を1-2秒長めにする、という対処になります。
この手間ってほぼゼロですが、それだけで、時間をかけても最後まで美味しく飲める(最後がぬるくない)ラテに仕上がります。
甘味を感じやすい温度帯から外れることで、ミルクの甘さは感じにくくなるものの、その日によってゆっくり飲みたいほうが優先度が高いとしたらこっちが正解になるわけです。
これはお客さん自身が選べるほうがいいよね。
というのが今も基本的に変わらない自分の考えです。
お店では毎日同じ時間に来て、同じものを飲む人のほうが断然多かったものの、
メニューにないオーダーであれ、できるかぎり対応したい、そして自分はそれを楽しんでいるという空気は伝えられていたかなとおもいます。

実際、それまで知らなかった飲みかたを知るのはたのしく、特にエスプレッソが広く、そして長く飲まれているヨーロッパ圏出身の常連さんたちには、いろんなことを教えてもらいました。
「この人にこれをオーダーされなかったら、この飲みかたは知らないままだっただろうな」というものもたくさんあって、
「それのどこがどうしておいしいの?」という超、超、超ーードライな(液体が少ない)ほぼ泡でできたカプチーノとか、千利休もびっくりの(熱くてカップを)触れないラテとか。笑
でもその人には、それを求める理由があるんです。
何かはわからないけど、何かしらの、それじゃないといけない理由が。
だとしたら、やっぱりそれを提供したいなとおもう。
そしてこちらは、「それをつくったことがある」という経験を得ることができます。
そういった《自分自身のたのしさ》と《お客さんが喜んでくれる》という結果の組み合わせで自分を伸ばしていけるというのは本当にありがたく、
ひとりひとり好みが違って、状態も毎日違う、という前提に立って、その日のその人に合わせるようなやりかたが、標準に設定されていきました。
(その基準がのちの自分にとっても大きな財産になりました)
このたのしさは、やっぱりお客さんに教えてもらったことで、
自分の飲みかたや好みを知っていて、それぞれのスタイルで楽しむ人がどういう人たちで、
その人たちが作ってくれる店の空気がどういうものになり、それがどんなお客さんを呼ぶのか
毎日、目の前で見せてもらうことができたんです。
お店って、スタッフよりもお客さんのほうが(物理的に)数がおおい状態の時間が圧倒的に長いわけですから、場所の空気をつくっているのはお客さんなんですよね。
(スタッフの役割は、おおきな意味でその場所の治安維持に尽きるとおもいます)
理屈ではなく、毎日その場にいて体験として受け取ることができたからこそ、腑に落ちてきた部分があり、自分が目指したいとおもえるものが少しずつ見えていったような気がします。
今の自分が、うまくいかずに何を目指したらいいのか迷うときに、
「いろんな意見はあるけど、自分はこっちかな」
と最終的に判断できる部分は、この景色を見せてもらったことで強化されていったようにおもいます。
「相手が受け取ることになるものの価値は、あくまでも相手が主体で決まるべき」という考えかたや、
そこへの関与のしかた、ありかたを学んだのはこの時期かもしれない、とおもうんですね。
どんなふうに、こちらの意図を伝え提案をするのか、お互い得られるものがおおきくなる関係とはどういうものか、ということ。
お客さんどうしも、スタッフも含めて、こういう関係性のなかにいたいな、という景色の中に自分がいることができたことで、
パブロフの犬のように、毎日それを体験から学習させられて、笑
きっとそれがあるから今も、こういう人たちに向いていきたい、という判断がある程度できるのかな、と。
自分が何かを提供する立場になったとき、
もう半歩だけ相手に寄せた何かしらの貢献ができることに素直に喜びを感じられるのは、
店舗時代のお客さんに育てられた部分がおおきいです。

表現を喜ばれるという体験
もともと朝食とエスプレッソのお店がやりたかったので、両方を並行して技術の獲得に努めていたものの、いつ開業するのか、というのは最後まで決めることができませんでした。
店舗を持つ、ということが自分にとって最適解と言い切れない、これは技術や経験に対する自信のなさというよりは、
その選択がベストか?という疑問への自信のなさです。
いろんなところに行って、新しいことや、めずらしいものに驚く、知らないことを知ることが何よりもたのしくて、それを誰かに伝えられるのが嬉しい。
そういう自分が、お店ではない場所でできることがどのくらいあって、そのうちのどのくらいが成立するのだろう。
そう考えるようになって、少しずつ店舗での時間を減らし、個人でワークショップやイベントをするようになって少しした頃、感染症の流行がはじまりました。
それをきっかけに、考えていたことをいろいろ試してみると、
より一層、店舗という答え以外の選択肢に可能性を感じるようになっていきました。
《すきま》というとざっくりしてしまいますが、
店舗に立つバリスタが担えない範囲というのが意外とあるように私からは見えて、
そこの詳細を探れたら、今後の指針を決めるための信頼できる情報になるような気がしました。
おおきくいって、
なにが求められているか。(お客さんの視点)
今後、なにを伝えていくべきか。(業界が伸びるための視点)
自分という1人のバリスタ を挟んで存在する双方に何かしらの貢献をできるポイントで、どんな動きができるか、ということなのですが、
そんなふうに考えると、店舗に属さずフレキシブルに試せる1人ゲリラ部隊はある意味でベストの形だとおもいました。
機動力を保って、ちいさなトライを持続できるからです。
その価値の高さが、自分が店舗を持つことに最後まで抵抗があったことの種明かしなのかもしれない。
自分の中で解けかかった謎にひとり納得しながら、根底に変わらずあったのは、
「こうあるべき、ということは一旦おいて、お客さんにはそれぞれの好みのものを楽しんでほしい」
という想いでした。
その基礎には
「自分で納得して選んでいる満足感があるお客さんだからこそ、こちらのことも尊重してくれるし、こちらの表現を楽しんで受け取ってくれる。」
という、店舗時代のお客さんから受け取った価値観というか、マッチングの鍵があって、
「こっちを目指せばいいんだ」という羅針盤みたいな感覚があったようにおもいます。

ダメでも、得ることができる価値
一見だれも求めていないように見えるけれども、本当に求める人がいない、とはっきりわかるまでは諦めきれないこと。
そういうことって誰しもあるとおもうんです。
バリスタとめぐる「コーヒーショップ分解」ツアー
や
が、自分にとってはそれで、店舗を持たずに独立する形を探り、試して、ダメならまた考えようという、おおきく諦めてちいさく試し検証する、というスタンスをとることで《はじめる》ことができました。
もしかしたら全然見当違いで、見向きもされないかもしれないけど、それならそれでいいから、ダメならダメという結果を見たい。
「ちがうんだな」という結果がでることも前進と捉えなければ、何かをはじめるなんて恐くてできない。
だけどどっちみち《次の情報》が得られないと、良くなっていけない。そういう気持ちです。
この形が最適かはわからないけれども、今の自分がとれる選択肢の中ではかなりベストに近い、そういう自分なりのコンテンツ。
この1年は、そういったことをやってみて、結果を自分に見せる、ということの繰り返しだったようにおもいます。
こういうのはどうだろう、というアイディアのもととなる疑問を持ち、
実行してみられるだけの専門性が育っていたことと、試せる場所があったことは幸運でした。
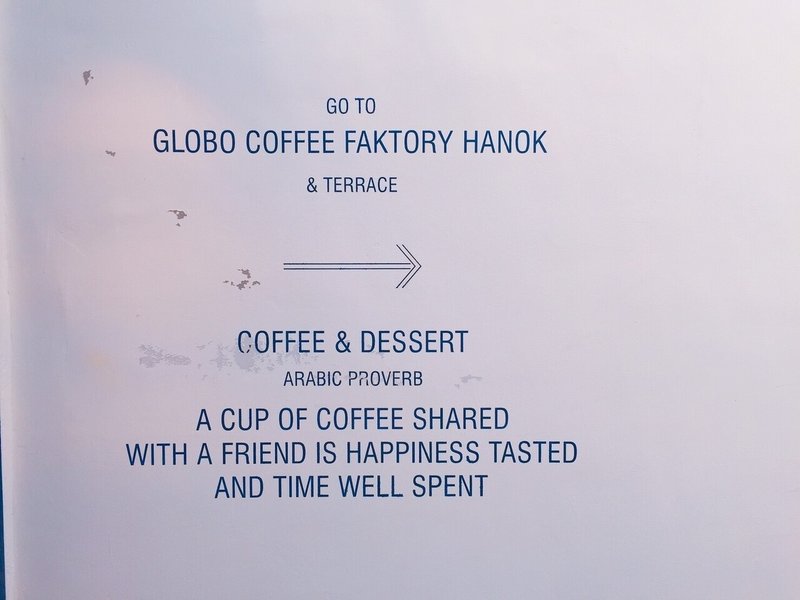
おおきなハコを借り、立派な設備を整えて、多くの人に最上のものを提供する。
そういったサービスはできないけれど、目の前の人に向き、
「もうちょっとだけいろいろあるとしたら、本当にはどういうのがいいですかね?」
というやりとりをしたい。
これはわりと積極的にしたい。
「自分がそんなふうにおもうんだ」という驚きとともに、そういう希望がみえてきました。
そのモチベーションのベースにあったのは、オーストラリアをはじめ、主に異国で見てきた個人のたのしさが尊重されている景色や、店舗時代のお客さんが示してくれた自分はこうする、というスタイルへの憧れでした。
そして、コーチングの現場で「やりたいことがわからない」「何かしたいけど、それが何かわからない」と悩む人をたくさん見ていたのも大きかったとおもいます。
(自分で選ぶ体験が不足すると、判断の主体が自分から離れてしまい、どうするのが自分らしいかという視点より他人からみた自分がどうか、という視点が強くなっていく、という仮説をもっていたため)
誰にも迷惑をかけないところで自分を制限してしまう
これは特に外国の人と比べて日本人の判断基準で顕著な部分だとおもいます。
自分自身が外国で暮らした経験からも、
初めは「日本人は控えめで気遣いができる」と言ってくれる外国人も、だんだんぶっちゃけてくると、
「自分で決めない人が多いよね」「自分のことなのに他人に判断を任せるのはchildishだよね」といった本音を聞く機会もあり、
ちいさなことでも、自分で選ぶ機会を減らすようなことに加担をしたくないな、という気持ちが自分の中で強くありました。

素材の自由度を取りもどす
ここで少しだけコーヒーそのものについてお伝えしたいのですが、
よく知られていることですが、コーヒー豆というのはコーヒーチェリーという果実の種なんですね。
素材まで戻り、チェリーという食材の一部と捉えることで発想が広がる部分は確実にあって、
今は特に、素材の特性を活かした焙煎をした《浅煎り》のコーヒーをどう知ってもらっていくかという部分が自分の課題です。
単に浅煎りを飲んでもらいたいということではなく、価値を知られずに食わず嫌いされている側面にどうアプローチをかけ選択肢を増やすか、ということ。
選択肢について、もう少しだけ詳しくお伝えしますね。笑
たとえば「酸味のあるコーヒーが苦手」という声をお客さんからよく聞きます。
どの酸味についてお話しているのか?という視点を持ちつつ、逆に、その方にとって好きなコーヒーはどんなものか?と考えます。
よく聞くと、これまで主流だった深煎りのコーヒーがお好きで、その方にとっては苦味がしっかりしたコーヒー感があるものが「コーヒーである」という認識であることが多い。
そういった認識のある人に、浅煎りのフルーティーなコーヒー(素材の特徴を活かしチェリー感が強く酸味がややボールド、苦味ほとんどなし)が
情報のないまま《コーヒーとして》提供されることで、おもっていたものと違った=満足できないという状況がうまれ
お客さんの中で酸っぱい味(これまでのコーヒーと最も違う点が酸味)のインパクトと《コーヒー》というワードが刻まれてしまうことで、
「酸味のあるコーヒーが苦手」という変換がされてしまう。
重要なのはそれが、この素材(浅煎りの豆)自体を嫌だ、と感じる体験になってしまっている、ということなんですね。
この誤解を解きたい、という希望があります。
たとえば、ごく浅い焙煎のコーヒーを、「コーヒーチェリーティーです」と言って提供されたら、ハイビスカスやローズヒップなどと同じように、「こういう味のフルーツティーなんだ」と認識するとおもうのですが(酸味も受け入れることができる)
「(コーヒーという食品だから)コーヒーです」という提供のしかたをすることでギャップをうむ。
これまで広く飲まれてきたもの(深煎りのコーヒー)と味が大きく変わっていることに対して、理解をされないまま飲まれているから、満足してもらえず、リピートされないのでは。
という仮説を長いこともっていて、そのミスマッチについてはこちらの記事にまとめています。↓
↑こちらでは、見逃されている価値を市場に出してみることで、それが好きな人がいないかを探す、ということも書いていますが、この
「見えていなかった選択肢に、求めているものがあるとしたら?」
という可能性を照らしたい欲求が自分はすごく強いようで、
知らない(というだけで)=選べない、という状況のアンフェアさのようなものに、なぜだか全然納得ができないんです。
浅煎りの豆と、深煎りの豆を比べて良し悪しを論じるような飲みかたではなく、違う良さを知って、選んでほしい、
「比べない、という選択肢」があることを知ってほしい。
それにはそれぞれのことを伝える場をつくる必要がある。
そんな考えのもと、今もいろんなアプローチを試しています。
浅煎りの豆に深煎りの良さを求めるミスマッチを減らし、浅煎りだからこそたのしめる方法を伝えたり、いっしょに考えたりしてもらいたいな、とおもうんです。
ゲリラコーヒーの場で実際に提供した《ダブルファンタジー》という創作ドリンクがあります。(ネーミングセンスはともかく味は美味しいです)
構成は
生姜シロップ 1に対し
浅煎り〜中煎りのアイスのコーヒーが3
ソーダが5
という割合です。
これはフルーティーなコーヒーだからこそ可能になる飲みかたなんですね。
甘いけど辛い自家製の生姜シロップに、酸味と甘味とコーヒー感のバランスが絶妙なアイスコーヒー(コーヒーが主張しすぎずもしっかり感じられるのがポイント)を
ソーダでまとめた爽快感が絶妙と考えてつくったものですが、従来のコーヒー感が強い深煎りのコーヒーではできない飲みかただとおもいます。
そんなふうに《使い分け》をしてみせることで、
お客さんに「同じ(素材)だけど、(こんなにも)違う」という一見矛盾するロジックを《体験から伝えたい》
実際に、「おもしろい」「こんな飲みかたあるんだ」という感想をいただくのはすごく嬉しいですし、
考えてきたことを試して、伝えたいことが伝わった瞬間の喜びは格別です。
提供するモノは変わっていないけれど、調理を変える、切り口を変えることで、また
実際に飲んでみてもらう味の体験と、論理という説明を並行することで、伝わりやすくなります。
飲み慣れていない味を、《説明せずにそのまま出す》のか、
《説明をして、飲みやすくして、まずは飲み始めてもらうのか》
これは、こちらが選ぶことができる行動なのかなと。

どんなバリスタで 「いたい」 のか。
なにを訊かれてもいいように理論武装をしようと考えるのでなく、
「今、自分はコーヒーについてこういうふうに考えていて、こんなことをやっていきたい、理由はこれです。」
というようなことを言わずとも「もっている」のが大事なのかな、と以前よりも感じるようになりました。
感覚の話で恐縮ですが、それが「求められている」ように感じます。
君はどう考えるの?
というところを、お客さんが楽しんで、興味を持って聞いてくれるようになった。
技術の進歩とともに正解が変わっていく素材や、
判断が人に依存する部分がおおきい《おいしさ》という要素を扱う以上、
「非の打ち所がない答え」がないという状態で自分はどうするかを決めるほうが大事なのかなとおもうんですね。
知識をコンプリートしても使えなければ意味がなくて、いろいろ知ることの価値は、自分や目の前の誰かの役に立てられるかどうか、であり、相手にとって何が役に立つのか知るためには、やりとりが必要。
自分の場合はどうするのかと考えたとき、
私は、お客さんが自分で興味を深めたり、長くコーヒーと付き合っていけるようなスタイルをもてるお手伝いをしたい、とおもっています。
自分がいるお店や場所で会えなくなったとしても、お客さん自身が自分の飲みかたをもって、自由にコーヒーを扱えること。
そのほうが、状況に左右されずいつもおいしいコーヒーがある生活を送れるとおもうからです。
興味が持続するような関わりをしてほしいから、そのひとが知りたいことから始めてほしい。
そのため伝えすぎないこと、体験を大事にすること、に気をつけています。
「訊かれたことに答える」という寄り添いすぎないスタンスを標準設定にするのは、
自分がもっている知識や経験をどの程度お渡しするか、その答えは相手がもっている、という考えかたで、今のところはやっていきたい。
出し惜しみしているのではなく、あくまでも相手の興味が主導権をもった状態に保ちたい。
大事なのは相手が「知りたい」とおもってくれたタイミングでこちらに《用意があること》なんです。
「コーヒーってこんなに自由でいいんだ」
というのを感じてもらいたいし、正しさよりもおもしろさを知ってもらいたい。
物理的な正解は一応あるかもしれないけれども、自分の正解は自分のなかにあったりするし、それはどんどん変わっていいもの。
そういう、伝えたいことがきちんと伝わる構図をつくることが大事なんだ、とひしひしと感じています。
今日は、この1年ほどフリーのバリスタとしてやってみたことをもとに、わかったことについて書きました。
読んでいただきありがとうございます。
バリスタ、調理師で、コーチングのコーチもやるというスタイルは、まだまだ一般的ではないかもしれないし、
どれが本業?という印象も、今後も与えていってしまうとおもいます。
それでも自分はこれを、こういう理由で選んでいます、と言えるかどうか、これは、理解をしてもらうためというよりは自分が納得している、と自覚しているために必要なことなので、整理ができてよかったです。
自分が迷っている状態では人に伝えることは困難で、伝わらなければ協力や応援をしてもらうこともむずかしいと考えているので
現時点では、こう、という結論を出さないまでも、方向としてどの方位を向くかはなんとなく持っておくこと。
そういう状態を大事にして試しつづけ、
そして、過程も楽しんでいたい。(これはマスト)
そんなふうに考えています。

お仕事に関するお問い合わせはこちらに。
chieoikawa5@gmail.com
よろしくお願いいたします☺︎
いただいたサポートは、新しい体験をしたり、応援したい方のサポートに使いたいと考えています☺︎普段の活動はこちらです💁 https://www.instagram.com/changeisgoodccc/
