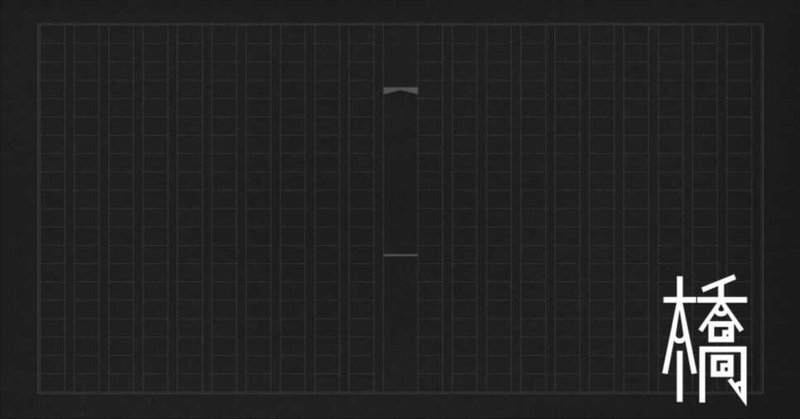
『橋』
私は旅人だった。
夏のひんやり冷たい夕方のことだ。風の吹き荒れる深い谷を目前に、今、此岸から彼岸へ、橋を渡ろうとしていた。一体何処から来て何処へ行くのか、私は杖を片手にただ旅をしていた。そうして私は、地図にもまだ記されていないその橋にたどり着いたのだ。
橋は人間だった。こちらの端につま先を、向こうの端に両手を突き立てて、ぼろぼろ崩れていく土にしがみついていた。風は彼の裾をはためかせ、下ではマスの棲む渓流がとどろいていた。
手すりもなく、ただひとりの人間がつくるこの橋を渡るのはひどく頼りない。だが、渡るのだ。それは私のためであり、また彼のためでもあるのだ。橋としての彼の役割を、今こそ全うさせるのだ。
――さあ、おまえ、準備しろ。ひどく頼りないから気をつけろ。もしも私がつまずいたら間髪入れず、山の神よろしく向こう岸まで放ってくれ。
私は橋を歩み始めた。一足先を確かめるように、杖の先っぽの鉄の尖りで彼をつっついた。よしよし。その杖で彼の上衣の裾を撫でつけた。さらに彼のさんばら髪に杖を突き立て、キョロキョロあたりを見廻しているフリをして、その間ずっと突き立てたまま放置していた。
私は山や谷のことなど考えもしなかった。ただ彼が何者なのかを考えていたのだ。彼はじっと黙りこくって橋の務めを果たしていた。
私はヒョイと両足で、彼の体のまん中に跳びのった。
お前は誰だ?
大人か、死体か、落ちこぼれか、成功者か、罪人か、作家か?
私は知りたかった。
だが、彼はそこで寝返りを打った。――なんと、橋が寝返りを打つ! 私はぐらついた彼を踏み越えて、一気に向こう岸まで渡り切った。彼は落下し、一瞬のうちにバラバラになり、渓流の中からのどかに角を突き出している岩の尖りに刺しつらぬかれた。
私は彼の最期に嘲笑をくれてやり、旅を進めた。
――――フランツ・カフカ『橋』へ敬意を表して。
2016年作
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
