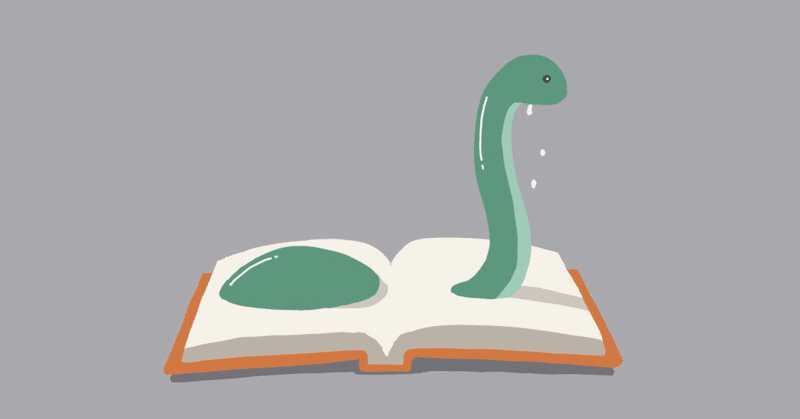
哲学に触れて-世界と自己と死-
最近仕事が忙しくなって、休日に予定もあって、図書館で借りた本を1週間で読みきれないのがストレスになってきた。私の住んでいる市の図書館は貸出期間の延長が1回だけできて、通常は2週間のところ、申請した日からさらに2週間の延長ができるので、最長約1ヶ月借りることができる。
そんなこんなで3週間かけてやっと読み終わったのが『1日で学び直す哲学-常識を打ち破る思考力をつける-』(光文社新書 著・甲田純生)である。
自分の中でのまとめと、考えたことを書きたいと思う。
(哲学素人、ただの一般人の感想なので、間違いがあるかと思いますが、どうかご容赦ください。)
本について
この本は「哲学のエッセンスとその面白さ、醍醐味を伝えるもの」として書かれている。
哲学全てを掘り下げるとあまりに難しすぎるし、哲学史として全ての哲学者を紹介するとあまりにも薄い。その塩梅を考え、哲学初心者に分かりやすく、しかし哲学の面白さを伝えるためにかなり苦慮されたようだ。
本の内容は厳選した哲学者「ピタゴラス」「ミレトス学派(タレス、アナクシマンドロス、アナクシメネス)」「ソクラテス」「プラトン」「アリストテレス」「デカルト」「ベルクソン」「バタイユ」「カント」「ヘーゲル」「ハイデガー」を本筋で紹介し、コラムでその他の哲学者について補足している。さらに「自然(ピュシス)をめぐる思考」と「時間の概念と死」についての「哲学における捉え方の歴史」を軸としてまとめられている。途中「わけわからん」状態になってしまったが、最後はうまくまとめられていて、自分の中で体系化できたと思う。
ピタゴラス(紀元前570年頃)
「ピタゴラスの定理(三平方の定理)」でお馴染みのピタゴラス。実は、ピタゴラス自身はピタゴラス教団の教祖で、三平方の定理を見つけたのはその教団だったらしい!とってもびっくり。
その教団は「魂の不死と輪廻転生」を教義とし、本来清い「魂」が穢れた「肉体」に閉じ込められており、魂の浄化のために禁欲的戒律と「数学」を親しむことが求められたという。数学的秩序が絶対的に正しく、その数学に触れることができるのは魂(理性)だけであるとの考えで、なるほど、わからなくはない。
ピタゴラスがのちの哲学に残した思想は「数学的思考(学問は論理的に証明されるべきもの)」「宗教的思考(神の存在)」「魂の不死(魂と肉体の二元論)」「感覚世界と超感覚世界の価値の逆転(肉体が感じる世界ではなく、魂が見るべき理想の世界が正しいものである)」の4つとのこと。
(√2の逸話がかなり面白いので是非読んでほしい!)
ミレトス学派(紀元前6世紀頃)
古代ギリシャの最初の哲学が発生したのが、ここらへんのようだ。ミレトス学派が追い求めた「万物のアルケー(起源、根源、成り立ち)は何か」は今日の哲学にも脈々と受け継がれているテーマだ。現代の私たちであれば、原子からできていると考えるだろうか。それも一種の哲学であると思う。
ミレトス学派の人たちはもちろん原子の概念など知らない。そのため、自然(ピュシス・そこにあるもの全体)の中に生命が生まれ出る何かしらのエネルギー(根源物質)があると考えた。この「生命やある存在が生まれ出る根源についての思考」が今日の哲学に息づいている。
ソクラテス(紀元前470年頃)
ソクラテスは著作を残していないため、明確に「哲学者」とは言えないらしい。ソクラテスの思想については主にプラトンの著作から学ぶことができる。(本書を読んで、プラトンが熱狂的なソクラテスのファンであると思った。)
ソクラテスは自分より賢い人がいるかどうかを各地の賢人と呼ばれる人を訪ね歩いて調べ、「みんな自分に知らないことがあることを知らないから、それを知っている私が一番賢いかも(無知の知)」という結論に達したらしい。論破だけしに来るやつは嫌ですね。
ソクラテスは裁判(人心に国家の思想じゃないものを植えつけた罪、実際は嫉妬や中傷の類であったよう)にかけられ、処刑される運命になってしまう。その際、実際は逃亡することもできたが、ソクラテス自身が服毒自殺を選ぶ。そのことがプラトンに大変な衝撃を与え、哲学者プラトンが誕生した。
「ソクラテスの死」と「キリストの死」に見られる共有事項が興味深い。二人の言動はその当時の人にとってとても過激で大変ビビらせるものであった。そのことが二人の死を招いてしまった。二人とも、その死から逃げることができたが、あえて死を受け入れた。そして、その死は後継者たちにとっては理不尽で受け入れられないものであった。
「キリストの死」がキリスト教を生み出し、「ソクラテスの死」がのちの「哲学」の礎となった。
プラトン(紀元前427年頃)
ソクラテスやプラトンは「魂の不死」を「テオーリア(永遠なるものを見ること)」のために必要なこととして捉えた。そこには「現実への軽蔑」が含まれる。ソクラテスを死へ追いやった現実への憤りと、肉体が消滅することによってしか見ることのできない「真なるもの」が正しい存在で、肉体が感じている現実世界は正しいものではないという考え方だ。その「現実世界への懐疑」がのちの哲学の骨子となっていく。
プラトンの「イデア論」は私たちが世界を認識するとき、「五感が世界から受け取った情報」を魂だけがかつて見ていた「イデア(ものの定義、概念、観念)」と照らし合わせて認識している、ということかな?と私は理解した。例えば2冊の違う本があったときに、どちらも同じ「本」であると認識できるのは、魂が知っている「等しさのイデア」によって現実世界の有象無象のただの2次元の映像から「本」という輪郭を作り上げて認識していると言える、ということ?
プラトンは「真なるもの(イデア)は不変なものである」と捉えた。魂はもともと、完璧な存在であるイデアの世界にいるが、人間が生まれたときには魂は肉体という牢獄に閉じ込められ、イデアを思い出すこと(アナムネーシス)しかできなくなっている。哲学の中では「言葉の語源」を研究することが多いが、それも「真理」を思い出すこと(アナムネーシス)になるようだ。
アリストテレス(紀元前384年頃)
「知の巨人」と呼ばれるアリストテレスはプラトンの教え子。父親が医者であったため、幼いときから医学や生物学に親しんでいたようだ。
アリストテレスは哲学者というより「自然の探求者」の側面が強い。論理学、形而上学、自然学(動物論、天文論、気象論)、政治学、経済学、弁論術、芸術論と森羅万象に対して興味があったようだ。
「どんなものにも驚くべきことがある」と考えたアリストテレスの考え方に私はとても共感した。どんなに小さな動物や事象の中にも、私たちには計り知れない自然の摂理が存在している。
プラトンの「イデア論」では、真なるものは不変なものだが、アリストテレスは自然が常に変化するものだと捉えていたため、新たな考え方「形相(エイドス)と質量(ヒュレー)」「カテゴリー論」を生み出した。形相は質量と一体となって存在するもので、形相はそのものの性質を決定するもの。カテゴリーとは「ある主語に対してどんな述語を与えるか」ということでその述語の分類分けを行った。アリストテレスのカテゴリー論の中でも一番大事な分類が「実体」のカテゴリーで、例えば「Aは30歳です」というカテゴリーの場合はAに対する述語は1年後は変化するが、「Aは人間です」というカテゴリー(実体)の場合は変化することはない。この「実体」については不変なものとしてイデア的考え方を継承している。
不変なものである「実体」は「変化」を説明することができない。例えば、卵がニワトリになるのか、ワニになるのか、のような「生体変化」を説明しようとしたのが「四原因説」と「可能態と現実態」である。そのものが存在している原因は形相因(そのものの設計図のようなもの・魂)と目的因(そのものを生み出す理由)、動因(そのものを作り上げた動き)、質量因(そのものの材料)に分けられ、さらに目的因と動因は形相因に含まれるものと考えられ、ものが存在している原因は「形相因」と「質量因」の大きく二つであると考えられた。また、ニワトリの卵はニワトリになる「可能態」でニワトリは「現実態」となる。卵はニワトリ(形相)になるため(目的因)に成長し(動因)、やがてニワトリ(現実態)となる。
アリストテレスの形相という考え方は、生命が成長していく不思議さをどうにかして説明しようとしたのかな。
デカルト(1600年頃)
時代は進み、近代フランスのデカルトに。この時代はガリレオの地動説が発表され、宗教裁判で有罪になってしまった時代だ。
デカルトで有名なのは「我思う、ゆえに我あり」だ。これがのちの「哲学の第一原理」となる。私たちが感じている世界は本当の現実世界をそのまま感じているのではない、というのは以前も書いたことがある「テニスのボールは数秒先のボールがあると思われる場所を脳が見せているもの」として周知のものである。自分が感じているものは脳が作り出した世界なのだ。だが、そう考えている「私」だけは少なくとも本当に存在していると考えられる。デカルトの「精神の領域」と「物質の領域」を分けたこの考え方はピタゴラスから続く「魂と肉体の二元論」と同一だと考えられる。
ベルクソン(1860年頃)
ベルクソンはパリで生まれ、晩年は第二次世界大戦中に亡くなっている。19世紀末に発表されたダーウィンの進化論に影響を受けて「自然科学への理解」と「言語化するのが難しいものの理解」、「空間化を許さない物への理解」を目指した。
時間やメロディーなどはそのものの一瞬を切り取っただけでは意味をなさず、一瞬一瞬をただ寄せ集めただけでも意味をなさない。そういうものは「持続」であると定義した。時間は実際は今このときしかなく、過去も未来も存在していない。それがあたかも過去も未来も「ある」ように錯覚しているのは、時間を川の流れのような空間的なものとして無理やり捉えているためであるという。また、ベルクソンは「生命」についても持続とし、次の瞬間にどうなるかわからないもの(未決定性)として「表情」を上げている。精神が物質を変化させているが、ときには精神の制御ができず、人間の物質感を感じる時もある。(精神に対する物質の反乱)
バタイユ(1900年頃)
フランス中部のビヨンで生まれたバタイユは、幼少期に梅毒を患って精神的、肉体的に衰弱していく父親を見て育ち、精神的に不安定な青年時代を過ごしたようだ。
ニーチェやフロイト、ヘーゲル哲学の影響を受け、バタイユの思索は「人間存在のアルケー(原理、起源)の解明」に向かっていった。人間と猿を分かつものがなんであるかを突き詰めた結果、「そこにあるものはAであると同時にBであると考えられること」と、死体を見て、それが自分を死へと誘うように感じ、死に対する恐怖を得たこと、つまり「死を意識して理解したこと」で猿から人間になったとしている。
カント(1724年頃)
ドイツ観念論の先駆者のカントはルソー(社会契約論)から大きな影響を受けている。最初は自然科学の研究者であり、太陽系の起源について有名な星雲説を出しているそう。その後『純粋理性批判』を皮切りに多くの哲学書を出し、『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』が三批判書と呼ばれ、カント哲学の中核となるようだ。
カントもカテゴリー論を展開している。アリストテレスとの違いは「時間」と「場所」についてのカテゴリーがないこと。アリストテレスのカテゴリー論は「存在のカテゴリー」でカントのカテゴリー論は「認識のカテゴリー」とされる。カントはそのものの存在を認識するには、自分の感覚(五感の情報を脳が解釈すること)というフィルターを通してしか認識することができないとして、私たちが認識している世界を「現象界」と呼び、物質そのものとは区別した。五感それぞれから得た情報を「私」が一つにまとめ上げ、そのものを理解している。そこにはデカルトの考えた哲学の第一原理が受け継がれている。また、何かを認識するためには「時間と空間の均質化」が必要になる。人間は数を数える能力を得たことで、時間という本来空間化できないものも1分、2分と数えることによって均質なものとして捉えることに成功した。時間が均質化したことによって、自分の「近くのもの(すぐに行く事ができるところ)」と「遠くのもの(そこに行くまで時間がかかるところ)」の認識が生まれ、空間が均質化された。空間が均質化されたことによって、宇宙空間のような世界の広がり、本来見る事ができないものの存在も認識できるようになった。
ヘーゲル(1770年頃)
ヨーロッパの激動の時代を生きた哲学者のヘーゲルはドイツ観念論の大御所でナポレオンの1年後に生まれた。1789年には「自由・平等・友愛」を掲げたフランス革命があり、その後ナポレオンのヨーロッパ統一(ナポレオン戦争)があった。ヘーゲルもアリストテレス同様に研究対象は多岐にわたっていたが、主な関心は歴史、社会的事象であった。
ヘーゲル哲学の中核をなす思想は「存在はすべてそのうちに爆弾を抱えている」である。存在はその内部にある爆弾が爆発すると消滅し、別のものになる。生き物の死は予め決定されているという考え方はその一端であると言えるかな?『鹿の王』という上橋菜穂子先生の小説にも同様の考えが書かれていたことを思い出した。
ヘーゲルの考えた「私」の理解は「人間だけが宗教を持つこと」つまり、人間だけが神的視点、世界を俯瞰する超越した視点を持つ事ができ、それによって自分を外から見る事ができ「自己認識」ができること。そして「私」は私だけでなく、他者も自己のことを「私」と認識していることを私は知っていること。私は他者からの承認を得ることで初めて「私」として成立する。それは「私」という哲学の第一原理ですら、他者からの承認がなければ消滅してしまう可能性があることを示唆している。ヘーゲルは「真なるものは不変なものだ」と考えられてきた哲学に「存在はすべて爆弾を抱えているため、不変なものなどない」と一石を投じたことになる。ヘーゲルは「存在はすべていろんなものの相互関係の上で成り立っている」とした。
ハイデガー(1890年頃)
20世紀最大の哲学者と言われるハイデガーは哲学史の中でかなりの衝撃を与えた一方、ナチスへの入党により世間からは批判の的となってしまった人物だ。
ハイデガーは「人間の存在=時間」であるとし、人間は保持した記憶の前後関係を認識できることで「過去」の時間を認識し、死を見つめることで「未来」の時間を認識できる。ベルクソンの「持続」を本来的時間、カントの「均質化された時間」を非本来的時間として、日常的な人間の考え方(現在の時間を生きていること、死を直視していない時)を非本来的時間の人間の在り方と考えた。さらに人生のリミット(死)を意識したときには、未来の時間は均質化されてただ過ぎ去るものではなく、濃厚なものにしなければいけないと考える時の人間の考え方を本来的時間の人間の在り方とした。
哲学について思うこと
ハイデガーについて
実は、この本を読む前にハイデガーの著書『存在と時間』をNHKの「100分de名著」で予習していた。(全4回のうち、第2回だけ予約失敗で見れていない)番組でも深掘りされていた、ハイデガーのナチス入党について、思うところがあるので書いてみたい。
ハイデガーの『存在と時間』では、日常生活で人間は周りに合わせてしまうことが多いが、それは非本来的時間を意識した行動で、本来的時間を意識(死を実感)することで本来人間としてあるべき行動をとることができる、としている。そうは言っていたハイデガーであるが、ナチスという「全体主義」を支援する形になってしまっているのは矛盾しているじゃないか、というのが第二次世界大戦終戦後からハイデガーが亡くなった今日にも続く論争だという。ハイデガー自身は自分がナチスに入党したことについて、亡くなるまで後悔を言うことはなかったという。
その話を聞いて、自身が導き出した「存在」に関する哲学もハイデガーにとっては真実で、第一次世界大戦後のドイツという場でハイデガー自身が思った祖国に対する自身の在り方に対する考え方もハイデガーの真実であったと私は捉えた。いわば、理想論と現実論とでもいうか、現実問題、お金を稼いで生きていかなければならないわけで、本来はストレスなく生きていけるのが理想だが、そうも言ってられないのが現実だ。ハイデガーをそういう現実に向き合わせてしまった社会が悪いのでは、と私は思う。
あと、NHKでは取り上げていなかったと思うのが、戦後のハイデガーを批判したというアレントとの関係。のちに政治哲学者として有名になるユダヤ人学者のアレントはハイデガーの教え子であるが、一時期既婚者のハイデガーと不倫関係にあったらしい。そういう愛憎も批判の裏にあったのでは、と思えてならない。
「私」とは何か
前に2chのスレまとめでとても興味深い思考実験のスレがあったことを思い出した。
ここで書かれていることが正しいとすると、今言語を考えて思考している「私」は「左脳の私」であると言える。「右脳の私」はどこにいるのか?そもそも脳は肉体であって、思考しているのも肉体であると言える。「私」とはただ肉体が生命活動を維持する機能にすぎない?
ここから哲学を深められそうな気がしてくる。
死を意識すること
最近、会社の制作チームのスケジュール管理をしていて思うのが、「スケジュールを考えること=本来的時間を意識すること」なのではということだ。作業スケジュールを考えなくても、漫然と作業をする事ができる。だが、締め切りを意識することによって、焦りやスケジュール通りに行っていると逆に安心する事ができる。この締め切りを意識したスケジュールを考えることが死を意識した人生の過ごし方になるのかもしれないと思った。
哲学って案外同じテーマを扱っているものなのだと知り、案外読めるかもと思いました。ここに取り上げられていない哲学者についても興味が出たので、また図書館で借りてみようかなと思います。
長々とお付き合いいただき、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
