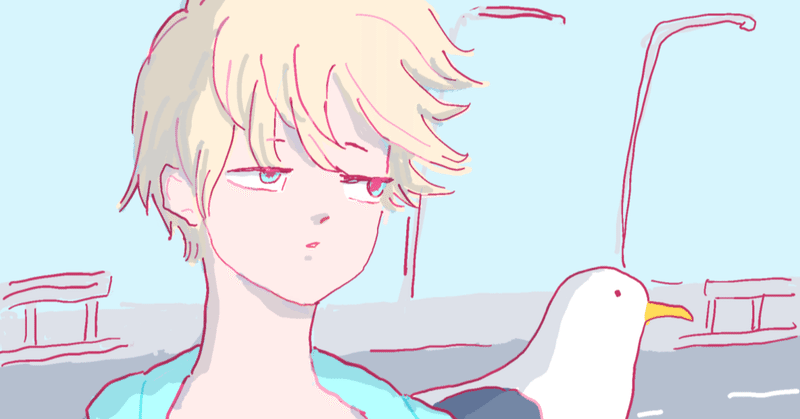
あの春、変質者に出会い僕は逆ダーツをはじめた
春になると変質者が現れるというのは、どうやら本当らしい。僕が出会ったのは卑猥なタイプではなく、頭がおかしいタイプの変質者だった。不審者と言ったほうが正しいかもしれない。
三月末の夕方、住宅街を歩いていると、ある民家から「キエエエエエエ」という雄叫びが聞こえた。男の声だった。それだけでも十分事件だ。ここは閑静な住宅街である。そのあとすぐに『ドーン』と、でかい物音がした。どこかに何かをぶつけるような音だった。急な大音に体がすくみ、体温が上がるのを感じた。
民家はボーボーに生えた庭木で囲まれていて、中で何が起きていたのか確認できなかった。もちろん向こう側からも見えないので、近くに僕がいることを相手は知らない。それがせめてもの救いだった。頭のおかしい奴に襲われたりしたら最悪だ。せっかく志望校に合格し、春休みが終わったら晴れて高校に入学するというのに。何かあって入学できないことになったら取り返しがつかない。
再び僕が歩き出すと、さらにもう一度大声が聞こえた。「ウオオオオ」のようなセリフだったと思う。僕は走って逃げ出した。頭の湧いた輩に会ったら、逃げるのが一番だ。
◇
もういちど声を聞いたのは、それから二日後だった。
一部始終を早川さんに喋ったら「おもしろそう! 私も聞きたい!」と言い出したのだ。喋るんじゃなかった。この女、何を考えてるんだ。そう思ったけれど、目を煌めかせている彼女には何も言えなかった。「見に行こうよ」と言われ、カッコつけたい手前、断ることもできず、僕らは住宅街に足を踏み入れた。二人だと言う安心感もあったんだと思う。それに早川さんの家はこの住宅街のどこかにあると知っていたから、いざとなったら逃げ込む場所も確保できていた。
早川さんとは中3の最後の方に仲良くなった。同じクラスの中心グループにいた彼女は、その中でも一目置かれていた。リーダー的な存在ではないけれど、それは誰とも群れたがらないからリーダーではないだけで、早川さんが意見を言えば通ってしまうようなカリスマ性を持っていた。いちおう表の面でのリーダーはサヤカだったが、最終的に早川さんの顔色を伺っていたのは、雰囲気でわかる。
早川さんは周りが寄ってくるからグループでいたけれど、本当は一人でも平気なのだと思う。中学生ながら、精神的に自立してそうな強さを感じるのだ。それにグループで一人だけ頭が良く、そういう意味でも浮いていた。
仲良くなったのはなんでもない、席替えで隣になったからだ。彼女がやたらと真面目にノートをとっていたので、ちらりと見ると、書かれていたのは漫画だった。左利きなのも、なんだか彼女っぽい。そのタッチが少年漫画っぽく、見とれていると目が合ってしまい、小さい声で「変態〜!」と言われた。僕はすぐに顔が赤くなり、早川さんはそれを見てケラケラ笑っていた。そのとき先生に注意され、一緒に掃除をするハメになり、それ以来、喋るようになったのだ。
クラスのヒエラルキーでは真ん中くらい(のはず)の僕、いわゆる“普通”の僕となぜそんなに喋ってくれるのかわからないけれど、早川さんとの会話は楽しかった。「全員坊主にしたら、どの先生が一番ハンサムか」とか「山に捨てられるか、テトラポッドから海に落とされるか、どっちがいいか」とか、なんだか男子と喋ってるみたいだった。
◇
「ここだよ」
僕らは例の家の庭木の前に到着した。早川さんはその隙間から様子を覗いた。
「普通の家じゃん。変質者さんも私たちと同じような家に住むんだね」
「どんな家だと思ったの?」
「そりゃあカラフルだったり、天守閣があったり、ね?」
ね? と言われても共感できない。やっぱり変わっている。
「しばらく待ってみる?」
「私なんか飲み物、買って来るよ。変質者さんにいつ会えるか分からないんだし」
彼女はそう言って一人で行こうとしたので、僕は慌てて手を掴んだ。早川さんに触れたのは、この時が初めてだった。いつか握りたかったその手に初めて触れるときの感情が、まさか“恐怖”だとは思わなかった。しかしそんなこと言ってられない。一人にするなよ。
結局「見張っておかないとすぐに出てきたら困るから」という理由で、僕が一人で買いに行くことになった。意気地のない僕は、ひとり残って待つことを選べなかった。早川さんのこういう場面での勇気というか、肝の座った感は敬服に値する。
僕たちは二人でラムネを飲みながら、民家の向かいのバス停に腰を下ろして待った。ときおり彼女は僕の目を盗んで、走って庭木まで行き「お〜い」だの「変質者さ〜ん」だの、声を出した。僕はすぐに追いかけ、彼女の口を塞いでバス停まで連れ戻した。彼女は焦る僕をみてキャッキャと笑っていた。もはや僕を困らせるのが目的だったのではないかと思う。
変化が起きたのは、待ち始めて2時間が経過したころだった。庭木の前まで行った彼女が隙間から庭を覗いたあと、こちらに向けて手招きしたのだ。僕が小さい声で「見つかった?」と聞くと、「シー」と人差し指を口に当て、早く来るように呼んだ。どうやら動きがあったらしい。慌てて彼女の隣へ駆け、彼女から3mほど離れた位置で、庭木の隙間から中を覗いた。すると玄関の前に、上裸の男が見えた。この人が声の主なのだろうか? 野太い声からおじさんとばかり思っていたが、肌の感じからして、歳は僕より少し上くらいだろう。顔は凛々しく、ヒゲを蓄えている。筋肉は隆々で、武術か何かで鍛えてるんだろうなとすぐにわかった。だがカッコいいボクサーのような締まった体というよりは、ただただ大きく、全体的に四角だった。
さらに驚いたのは、庭の真ん中に自動販売機が置かれていたことだった。彼よりもっと四角かった。見た感じかなり年季が入っていて、『DyDo』の文字が色あせていた。三段に分かれたジュース入れはどこも空で、サンプルをホールドするための金属がむき出しだった。もちろんガラスは割れている。完全に役目を終えた自動販売機。なぜそんなものが庭に置かれているのか全く理解できなかった。
しゃがみ込んで眺めていると、男はスクワットをしたり、庭の端にある鉄棒で懸垂をしたり、入念なトレーニングを始めた。呼吸はいっさい乱れておらず、ひとつひとつのメニューが終わるごとにタオルで汗を拭き、優しく筋肉をほぐしていた。その清々しい姿は、変質者だとか、頭の狂った奴だとかからは程遠かった。
「この人じゃないんじゃない? まともな人に見えるもの」
「さあ。僕も声を聞いただけだから」
「本当にこの家であってるの?」
「それは間違いないよ。早川さんこそ、家近いんじゃないの? あの男、見たことない?」
僕がそう聞いたとき、バンッと聞こえた。それは男が玄関の前に停車している車のトランクを閉める音で、中からダンベルを取り出していた。車の奥に表札があるのはわかるけれど、ちょうど死角で文字までは見えなかった。
彼は庭の中央に戻って、腕を鍛え始めた。屈強な男が辛そうな表情をしているので、かなり重たいのだろう。彼がもし奇声の主で、頭のおかしい変質者だとしたら、この前逃げたのは正解だった。僕がどうあがいても、勝てる相手ではない。
「いつまでトレーニングするのかな。もう随分やってるけど」
「さあ……」
「……話しかけてみる?」
これが早川さんだ。物怖じしない。度胸がある。それは僕にはないものだ。
「なんて話しかけるの?」
「頭のおかしい人ですか? って」
「そんな失礼なこと言えるわけないだろ。こっちが頭おかしいよ」
「だって、拓海くんが言ったんじゃん。奇声を発する奴がいたって。この目で見たいの、聞きたいの、私は」
訂正する。彼女は物怖じしないというより、頭のネジが一本外れている。自分の欲を満たすために、知らない民家の庭に立ち入ろうと笑いながら言っているのだ。どちらにしろ、僕が持っていないものに変わりはない。
「大丈夫だよ。今朝の占い、一位だったから」
早川さんはそう言って立ち上がった。そのとき、はずみで横に置いていたラムネの瓶が転げた。注意しろよ。こちらから物音を立てるのはマズいだろ。
早川さんもさすがに焦ったのか、慌てて瓶を止めた。そして僕に向けて手を合わせ、謝るジェスチャーをしてきた。僕は「シー」と返し、再び庭木の隙間から男を覗いた。彼も物音には気が付いたのか、筋トレをやめてキョロキョロしていた。とりあえず僕らの存在に気付いていないようで安心した。早川さんは小さく僕の名前を呼び「セーフ」と言って、笑っていた。
奇声を聞いたのはその瞬間だった。
「キエエエエエエ」と、先日と同じ声が聞こえ、『ドーン』と物音がした。僕と早川さんはパチンと目が合い、その場に固まった。そしてお互い「そっちが覗いてよ」と言わんばかりに、ここに来た責任のようなものを押し付けあった。そうこうしてるうちに今度は「ウオオオオ」と声がした。どうやら「キエエエエエエ」と「ウオオオオ」はセットらしい。
僕らは「せーのっ」とささやき、庭を覗いた。そこに見えたのは、自動販売機を起こしている男だった。
まさか、倒したのか……?
あんなの100kgを超えているぞ。もしかしたら200kg、いや300あるかもしれない。信じられない。しばらく眺めていると、男はジャンプをしたり、肩を回したりしたあと、息を吐きながら精神統一のようなものを始めた。そして右手で自動販売機の後ろの角を掴んだ。その瞬間だった。大きく息を吸い、吐いたあと、「キエエエエエエ」の声とともに自動販売機を薙ぎ倒した。あまりの怪力に、見ているだけで腰が抜けそうだった。
男はそのあと、やはり「ウオオオオ」と吠えて自販機を起こし、数十秒のインターバルのあと、ふたたび雄叫びを上げて自販機を倒した。一体、何をしているのだろう……。倒したり起こしたり、何かのためのトレーニングか、それとも自己満足か、検討もつかない。
尻に痛みが走ったのは、そのときだった。
振り返ると、早川さんが笑いながら立っていた。彼女の両手は握られていて、人差し指だけが伸びていた。
カ、カンチョー……?
女子ってカンチョーするのか……?
「早く、行くよ」
唐突な出来事に戸惑っていると、早川さんはそう言って僕の手を取った。間違いなく、男に話しかける気だ。僕は我に返り、その手を振り払った。
「行ってどうするの?」
「どうするって、何してるか聞くに決まってるじゃん。気にならないの?」
「気にはなるけど……」
「もういい、私一人で行くから」
早川さんは僕を押しのけて、玄関へと続く道の入り口まで走った。
「失礼します!! 私、北原中学の早川みさきと申します」
彼女はそう身分を明かし、庭へズカズカ入っていった。何か作戦があるのだろうか。僕は物怖じしながら、その様子を覗いていた。
「本日は学級新聞の『街で見かけたステキなひと』というコーナーで、取材をさせていただきたく、ここへ来ました!」
なるほど。パッと思いつく中ではベストな戦術だ。男はそんな早川さんのセリフを聴きながら、ニヤニヤ笑っていた。
「すぐに取材も終わりますし、質問にお答えしてください!」
緊張しているのか、セリフが変だ。それに、たぶん僕に聞こえるよう、大声で喋っている。男はあいかわらず笑って彼女を眺めていた。
「今、お時間はあるでしょうか?」
「はい、お時間はあります!」
男は思ったよりノリが良く、彼女ばりの大声で質問に大声で答えた。
「取材と写真撮影、どちらが先が良いでしょうか?」
「トレーニング中の写真が撮りたいなら、写真でお願いします!」
「はい! かしこまりました!」
彼女はそう言って、スマホを構えた。
「取材は一人ですか?」
「いえ。二人できましたが、一人逃げました! 意気地なしです」
やめろよ、そんなこと言うの。
「なんなら彼に誘われて来たのですが、逃げてしまいました」
「それは、意気地なしですね」
「はい! とても嫌いになりました」
さすがに早川さんに嫌いと言われるのは、グサリと刺さった。
わかったよ、出て行くよ……。
僕はゆっくりと立ち上がり、玄関へと続く道の入り口まで歩いた。
「お兄さん、あいつです!」
早川さんが指差すと、男は僕に向かって手招きした。僕はしぶしぶ、二人の方へ歩いた。
「なぜ、彼女を一人にしたんだ? え?」
「それは、人の家の庭に勝手に入るなんて普通しないし……」
「でも彼女は、勇気を出して入ってきた。お前はそんな彼女を一人にしたんだぞ」
「まあ、はい、それは……」
「それにお前から誘ったらしいじゃないか」
「はい……」
「なんと言って誘ったんだ?」
「住宅街に変質者がいると言ってました〜」
すかさず早川さんがそう答えた。何を考えてるんだ、こいつは。
「なんだと? 俺のどこが変質者なんだ! 答えろ!」
男はそう言って僕を睨みつけた。
僕はビビって何も言えず、黙っていた。
「たくさん奇声をあげていると言ってました〜」
また早川さんが答えた。こいつはどっちの味方なんだろう……。
「じゃあなんでお前たちは、変質者の俺なんかを学級新聞に載せたいんだ? おかしいだろそんなの! それに奇声ってなんだよ。俺は庭でトレーニングしているだけだろうが!」
男はからかわれてると思ったのか、怒りのボルテージがどんどん上がっていく。
「俺だって自分を追い込んで、必死に頑張ってるんだ! お前らのネタにされてたまるかってんだ! 取材お断りお断りお断りお断りお断り、キエエエエエエエエ〜」
男は喋りながら自販機に手を伸ばし、怒りに任せてなぎ倒した。あまりの怪力と勢いに、自販機が地面でワンバウンドしたかのように感じた。すぐさま地面から埃っぽい風が立ち、ふわっと顔を襲った。
僕は気がついたら早川さんの手をとり、全力で走っていた。
「あはは、はは、ははは」
早川さんは、何がおかしいのかずっと笑っていた。
家の敷地を出るとき「ウオオオオ」と聞こえた。男が自販機を起こしたのだろう。
そこで早川さんはピタッと止まった。
「だめ、もうダメだ」
「何が? 早く逃げないと!」
「ううん、もう十分」
早川さんは笑いながらそう言って、家の方に振り返った。すると男がこっちに向かって叫んだ。
「みさき〜、もう大丈夫か〜?」
「ありがとうー!」
は?
どういうことだ!?
男は早川さんに向かって親指を立て、こちらに歩いて来た。
「拓海くん、ごめんね。あれ、兄ちゃんなの」
「は? うそ?」
「騙すつもりはなかったんだけど、なんか楽しくなっちゃって」
早川さんはそう言って、ペロッと舌を出した。
奥に見えた表札には『早川』と書かれていた。
◇
「壮大なコント見せられた気分ですよ」
「はは、みさきが楽しそうに話すから、つい協力したくなってな。クラスイチのビビリが、こんど兄ちゃんのこと偵察に行くって」
ク、クラスイチのビビリと思われてたのか……。
「でも君と仲良くなってから学校が楽しいって、嬉しそうにしてたぞ」
「え?」
「なんか、波長というか、相性合うかもしれないってさ」
そんなこと急に言われたら、照れてしまう。僕も同じように思っているから。
そこへ早川さんが麦茶を持って現れた。
「みさき、拓海くんに決めたのか?」
「うん。高校も同じだし」
「え、決めたって、え?」
「拓海くん、私と、その……」
まじかよ。そんなの返事は決まっている。
それにしてもすごい季節だ、春は。
変質者も出るし、恋も始まる。
「ペアになってください!」
ぺ。ペア?
恋人同士やカップルのことを、ペアなんて言い方するのだろうか……。
まあ、そんなことは今はどうでもいい。
「こちらこそお願いします」
僕はそう言って、手を差し出した。
早川さんといられるなら何でもいい、そんな一心で軽率に返事をしてしまった。
早川さんは僕の手を取り「決まりね!」と言った。
入学はまだだけれど、この日から高校生活が始まったと言っても過言ではない。
◇◇
あのとき、誰が想像しただろうか。早川さんとペアを組み、『逆ダーツ』の選手になることを。
僕は今、県大会の決勝ラウンドに挑んでいる。
見慣れたダーツマシン。その右側に立ち、壁に固定されたダーツの矢を見つめている。もちろん左側に立っているのは、早川さんだ。
笛が鳴った。
僕は早川さんとお互いの拳をチョンと合わせたあと、壁を睨みつけた。
必ず、必ずブルに刺すんだ。全国へ行くんだ。
そう誓い、僕らは台車に乗せたダーツ台をゆっくりと押し始めた。
あと10歩、5歩、4、3、2、1……。
行け!!
僕らは、踏み切り線から足が出ないよう注意しながら、絶妙なタイミングで手を離した。ダーツ台を乗せた台車は、程よい速度で5m先の壁に向けて走ってゆく。
止まるな、届け、届け、届け……。
プシュウン。
願いが通じた! 台車は見事に壁の手前数センチで止まり、ブルに刺さった音を立てた。
力任せに台車を離して壁にぶつけると、ダーツは折れてしまい、得点にならない。また僕と早川さんのパワーバランスに差があると、左右どちらかにズレて、ブルから外れてしまう。それが『逆ダーツ・壁』の難しいところだ。
僕らはそれから5m、10m、15m、20mに挑戦し、20回のアタックで8回のブルを叩き出した。まさに阿吽の呼吸。一気にランキング2位に躍り出た。
そしてもうすぐ、『逆ダーツ・床』が始まる。
早川さんの兄ちゃんは『自動販売機倒し』で鍛えぬいた肉体を使い、『個人・床』で全国制覇を果たした。そして今は逆ダーツ推薦で本場エジプトの大学に進学し、個人トレーナーをつけて練習している。メキメキと上達しているだろうから、もしかしたら次のオリンピックでは日本代表に選ばれるかもしれない。
ダーツはイギリスが発祥で、19世紀末に今の形になった。
一方で逆ダーツは、当時イギリスの植民地であったエジプトで、支配へのアンチテーゼとして生み出された。いわばプロテスト・スポーツだ。イギリスにスエズ運河を買収されたり、自国で好き勝手されて我慢できなかった民衆たちが、ダーツを楽しむイギリス兵をからかうために始めたとされている。
始めは壁に固定したダーツの矢に、マトを投げる遊びだった。いわばそれは、近代逆ダーツだ。それが1980年代、エレクトリックダーツマシンの発明を受けて、こんにちの『モダン逆ダーツ』へと繋がっている。徐々に世界で人気を高め、オリンピック競技に選ばれたのは記憶に新しい。
僕が高一で逆ダーツ部に入ったとき、高三のキャプテンが早川・兄だった。総体で、床の矢にダーツマシンを突き刺す姿には心を奪われた。まさか変質者と思っていた人に憧れるなんて、夢にも思わなかった。それから彼に基礎を叩き込んでもらった。
僕のような非力な選手もプレイできるのが逆ダーツの良いところで、そういう者はみなペアで挑んでいる。いわば個人は『力・センス』が問われるのに対し、ペアは『バランス・センス』あたりだろう。
それに男子ペア・女子ペア・男女ペアと組み合わせは自由で、カテゴリわけはない。ジェンダーレスなのも現代スポーツとして人気を得た理由だ。ゆくゆくはノーベル・スポーツ賞も受賞するのではないかと言われている。
◇
控え室へ行くと早川さんが肩をほぐしていた。
「痛いの?」
「うん、少しね。でも、大丈夫」
「痛み止めは?」
「少し打ってもらった」
「よし。今日が終われば楽になるから、頑張ろう」
僕は早川さんが筋肉を伸ばすのを手伝った。しかし逞しくなったもんだ。高一の始めは華奢だった彼女の肩に、こんなに筋肉が付くなんて。
早川さんは活躍する兄の姿を見て、高校生になったら誰かとペアを組んで逆ダーツをしようと決めていたらしい。そこでたまたまトレーニング中の兄の奇声に出くわした僕に、白羽の矢が立ったわけだ。もちろん学校で仲が良くなっていたのもあるとは思う。
今となっては奇声を発する理由がわかる。特に台車を使わずに 100kgを超えるダーツ台を動かさないといけない『逆ダーツ・床』では、何か言葉を発さないと、気合いが入らないからだ。
僕らは互いにストレッチを手伝ったあと、最終決戦のフィールドへ向かった。
◇
笛が鳴る。
5・4・3・2・1……。GO!!
よし、イメージトレーニングは完璧だ。
僕はゆっくり目を開いた。
僕らの前のペアは同率2位につけている北沢・北沢ペアだった。彼女らは双子で、息もパワーバランスもぴったり。姉の怪我も治ったみたいだ。全国への枠は二つしかないから、どうしても彼女たちに勝たないといけない。
早川さんはダーツ台にもたれて、音楽を聞いていた。彼女なりのモチベを上げる方法なのだろう。何を聞いているかは、僕は知らない。
逆ダーツを始めたころ、相手のミスを願っていた僕と早川さんは、もうここにはいない。自分のやるべきことに集中するだけだ。
北沢ペアは5回のアタックでブルを4回出した。驚異的な勝負強さだ。プレッシャーが魔物となって、重くのしかかる。
5分の5……。
それ以外、全国への道は残されていない……。
尻に激痛が走ったのは、そのときだった。
振り返ると、早川さんが笑いながら立っていた。彼女の両手は握られていて、人差し指だけが伸びていた。
またカンチョーだ……。
何を考えてんだ、こいつは。こんな大舞台で。
しかも三年前とは違い、鍛え上げられた早川さんのカンチョーの威力は数段増していた。
僕の緊張をほぐしてくれようとしたのは分かる。しかしその光景がモニターで映し出され、会場には驚きと笑いが同時に起こってしまった。
彼女は自分のペースを乱されると怒るくせに、僕のは平気で乱してくる。それは中学の頃から、変質者に凸したあの春から変わらない。まあでも、おかげで今日もほぐれたよ。
僕らは会場から今日イチの注目を浴びながら、ダーツ台の横にスタンバイした。
そして、笛が鳴った。
5・4・3・2・1……。
カウントの間に、100kg超えのダーツマシンを少しだけ浮かせ、走り、5m先の踏み切り線まで移動させる。そして柔道のように上手く足を引っ掛け、ダーツマシンを、倒す!
GO!!
持てるパワー・二人のバランス・テクニック全てを総動員した最高のアタックになったと思う。
床には、飛び出しているダーツの矢。
プシュウン。
手応え通り、ブルに刺さった音がした。何度聞いても最高の音だ。もはやこの音を聞くために、3年間生きてきたと言っても過言ではない。早川さんも大きくガッツポーズしていた。
◇
GO!!
GO!!
GO!!
僕らはそれから3投、ブルに刺し続けた。正直、自己ベストだった。そんなこと脳ではわかっていたけれど、ふたりとも反応しなかった。それくらい集中していたのだと思う。
物言いがついたのはその後だった。最後のアタック、ダーツマシンから手が離れるのが5秒を少しオーバーしていたらしい。
VTRチェックが入る。
すると、早川さんの右手が少しマシンにかかっていた。おそらく連投の途中で、痛みが出てきたのだろう。
「ごめん……」
「大丈夫、まだある!」
僕は自分の肩を、床にうなだれた早川さん肩の下に差し込んで立たせた。
その時だった。ピキイと尻に痛みが走った。先ほどのカンチョーの箇所だ。悶絶するほどの激痛。これ、骨をやってんじゃないのか……?
僕はなんとか耐えながらも早川さんの両肩を掴み「集中!」と言って、ダーツマシンに向かった。
しかし人間の我慢にも限界がある。火事場のクソ力に期待したが、ダメだった。僕はラスト一投の5秒カウントの間、尻の痛みに我慢できずに、地面に転げてしまった。ダーツマシンを持ち上げた時の負荷に耐えられなかったのだろう。早川さんもバランスを崩し、ダーツマシンは明後日の方向へ向かって倒れていった。
「限界だね、ふたりとも」
「ごめん、強がってた」
「ううん」
僕はカンチョーのせいだけど、カンチョーのせいだとは思わなかった。
プレッシャーに弱い僕、ほぐしてくれようとした彼女。無理しているのをわかっていても、早川さんを鼓舞した僕。痛み止めを使ってでも頑張ろうとした彼女。
早川さんは僕にあまり弱みは見せないぶん、抱え込んでいたものがあるのだと思う。兄がすごいプレイヤーだというのも、重圧だったかもしれない。
ペアやコンビというのは、プレイ以上に絶妙なパワーバランスの上に成り立っているのだろう。二人の強み、弱み、過去、未来すべてを包み込んで、戦わないといけない。そこには自分を信じること、そして相手を信頼することという人類の命題のようなものが横たわっている。
◇
僕らは結局、全国に行くことができた。優勝したのは北沢・北沢ペアだったが、ランキング1位で僕らのあとにプレーした長澤・中川ペアは床を苦手としていて、ブルに一度しか刺さらなかったのだ。僕は結果を見たあと、すぐにタクシーに乗せてもらい病院へ向かった。レントゲンを撮ると、尾てい骨が疲労骨折を起こしているとわかり、大部屋のベッドで横にさせられた。
しばらくすると表彰式終わりの早川さんがメダルを持ってやって来た。僕らはパソコンでエジプトのお兄さんにテレビ電話をつなぎ、結果を報告した。するとかなり喜んだようで、野太い声で何度も「おめでとう」と言ってくれた。
場所がどこかわからなかったが、後ろには広い砂漠とラクダと、自動販売機が写っていた。おそらく僕には想像もつかないトレーニングをしているのだろう。最後にはサービスだといって「キエエエエ」の奇声と、自動販売機を倒すところをもう一度、見せてくれた。二人でクスクス笑った。このあと砂漠で、自販機を起き上がらせるのはかなりしんどいだろう。
「あのとき、拓海くんに決めてよかった」
早川さんは電話を切った瞬間、そう言った。
「まさか、一緒にメダルが獲れるなんてな」
「ヘナチョコ中学生だったのにね」
彼女はベッドに深く腰掛け、カーテンを閉めた。
「でも、もう一つ、今日決めたことあるんだ」
「え、何を?」
「拓海くん、私と、その……」
うわ。前と同じセリフだ。今度は何を言われるんだ。もう騙されないぞ。
僕が身構えた瞬間だった。
早川さんはお兄さんの真似をして「キエエエエ」と奇声を上げ、僕の唇にキスをした。
あまりに突然のことに戸惑った。
カーテンの向こうの患者たちは、庭木の向こうにいたあの日の僕と同じ気持ちかもしれない。変質者が入院して来たぞ、と。
好きのキスか、ありがとうのキスか、僕にはわからなかったけれど、心の中ではなぜか『プシュウン』と、ブルの音が鳴っていた。
面白いもの書きます!
