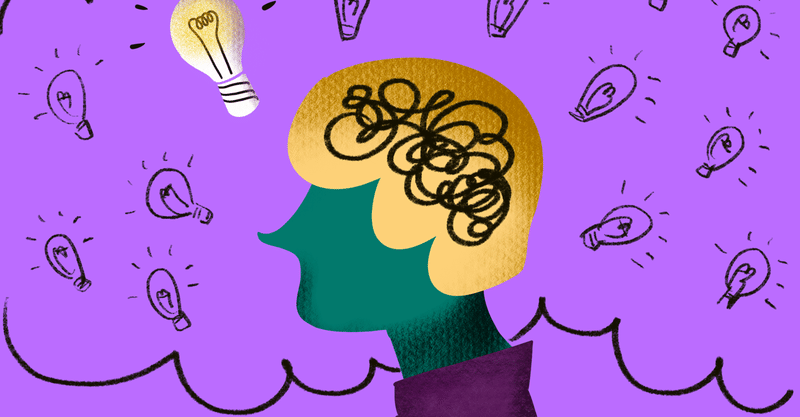
「自由」の「不自由」さ。
休校延長が決まりました。休みが長くなればなるほど、授業をしたい思いが強くなっていきます。「やってみたいことがあるのに、子どもたちが登校してくれない。」教師にとってまさに地獄のような期間が続いております。
先日、子育て世代の友達と話をしている中で、気になる発言がありました。
「いつも預けているところなんだけど、最近あんまり行きたがらなくて。自由に遊ぶ時間がつまらないんだって。」
どういうこと?と、疑問に思い、
「自由に遊ぶ時間が面白いんじゃないの?」
と聞いてみました。どうやら、
「自由時間と言われると、遊びたいことがなくて家に帰りたくなっちゃうんだよね。」
なるほど!そういう子もいるんだなぁと思い、自分自身を振り返りました。
僕の学級の子どもたちも、「自由」とか「思った通りに」、「自分の好きなように」という指示で困惑する子どもが少なからずいます。
指示する立場の僕からすれば、「この時間は、読書をします!」という宣言することに縛りを感じて、最近は隙間時間を、「自分のしたいことに使おう。」とか「自分をレベルアップできることをしよう。」などと、いくつかの言い方を試しました。まあ、簡単に言えば「自由!」と言っていると同じなのですが。
その結果、家から好きな本をもってきて読書の時間にあてたり、漢字や計算、折り紙でくす玉づくり、漫画制作など、その子なりの活動で過ごす姿が見られるようになってきました。しばらく実践していると、順調に興味・関心の幅を広げている子どもがいる反面、「したいことが見つからない。」子どもの存在が目立つようになってきました。そこで、「迷ったらこのプリントをやろう。」というように、こちらから活動を提供する支援をも取り入れてみました。
僕が子どもの立場だったら、担任の先生が、「自由に時間を使っていいよ!」と宣言したら、飛び上がって喜ぶことだろう。しかしながら、「自由だからこそ不自由」になってしまう子どもも一定数いるのです。しかも、友達の話を根拠とすると、それは、小学校就学前から続いているのです。
そのような子どもに対して、親としてできることは、その子が得意なことを言語化してあげることだと思います。「あなたは、絵がとても上手。」「ブロックでこんな素晴らしいものをつくれるなんてすごい!」というように、子どもの「良さ」を言葉にして伝えてあげることが1つの手立てとなります。
あとは、「飽きてしまってもよし。」無理して続けさせることなく、いろんなことに挑戦できる環境を整えるという覚悟を決めることも大切です。もちろん、教師の役割も重大です。ご両親の努力を途絶えさせてはいけません。決して自分の価値観で判断した言葉をかけるのではなく、挑戦している子どもの姿を認めていきましょう。
茂木健一郎さんの「#やり抜く脳の鍛え方」には、
自分の興味や関心のアンテナを鍛えるためには、「自己肯定力を高める」ことを意識する。
と書かれていました。やはり、親や教師による子どもが「自己肯定力を高められる」環境づくりが大きく影響してくるのです。
子どもたちが、1日の約半分を過ごす学校。教科学習も大切ですが、その隙間時間も「自己肯定力」をつける時間として有効に使っていきたいものです!
いただいたサポートは、地域の「居場所」へ寄付させていただきます!
