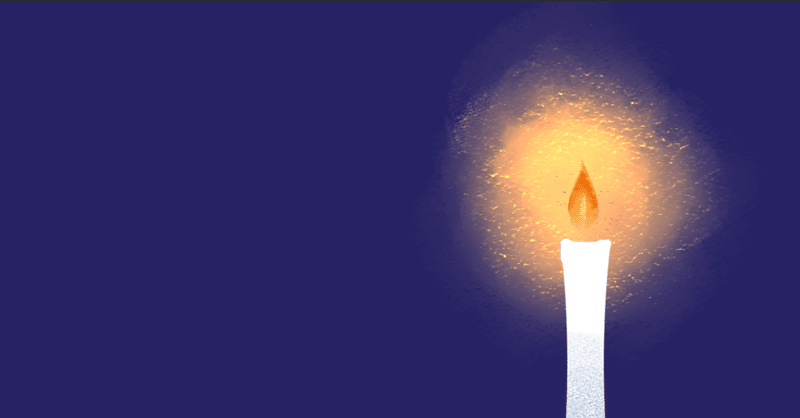
2021年、健全な怪談ブームがきている!
怪談・オカルトは僕らのそばに
怪談、オカルトのブームというものは、爆発的なヒットではなく、水面下でじわじわと息が長く続くものである。
振り返れば、1990年代はじめから2000年に入るこの約10年間は、テレビでは『恐怖の百物語』、『世にも奇妙な物語』、『特命リサーチ200X』、『奇跡体験アンビリバボー』、『USO!?ジャパン』などオカルトや怪談を取り上げた番組が毎週のように放送されていた。1999年のノストラダムスの大予言も重なって、怪談、オカルトはメディアで取り上げられる機会が多かったように思う。
映画でも『学校の怪談』や『リング』などが公開されたのが1990年代であり、その他ジャパンホラーと呼ばれる作品たちの公開も1990年代後半から2000年代前半であり、『ほんとにあった怖い話』のテレビでのレギュラー放送が開始されたのも2004年であった。
アニメでも『地獄先生ぬ~べ~』などが放送され、怪談作品のOVA作品も多数発売された。『ゲゲゲの鬼太郎』にいたっては今でも約10年ごとのペースで新作がテレビ放送され続けている。
2010年に入ってからは、怪談やオカルトというよりも、“スピリチュアル”という言葉の方が目にすることが多くなった。これはインターネットやSNSの普及によって、直接的な恐怖をあおるものは炎上につながるため懸念されたという見方もある。
テレビから消えた「怪談」
1990年代に毎週テレビで放送されていた「怪談」は、徐々にその姿を消して、2010年代に入ってからは夏の特番くらいでしかみることがなくなった。
しかし「怪談・オカルト」は、テレビで頻繁に放送されるコンテンツでなくなったというだけで、90年代を忘れない人々によって様々な形で世の中に残り続けていた。
その最も有力なものが、やはり動画サイトであり、2010年以降にyoutuberが動画の配信によって広告収入を得るというスタイルが取り沙汰されてから、様々な種類の動画が配信されるようになり、2020年のコロナ禍の中でさらにそれに拍車がかかった。
もちろん「怪談・オカルト」もこの流れに乗って、関連する動画が多く配信された。そもそもこの「怪談・オカルト」は注目を集めるネタとしてはかなり有力であり、現在でも心霊スポットに行ってみたという類の配信や怪談を語っている動画などは列挙に暇がない。
動画配信以外でも、イベントとして怪談会が催されたりと、テレビ放送以外の場で「怪談・オカルト」は人々の興味を引いてきた。
90年代で人々の記憶に残っていた部分が、テレビ以外の場で掘り起こされて、再びコンテンツとしての再起を促したと考えられるだろう。
「怪談師」の登場
怪談の語り部として、思い浮かぶのはやはり稲川淳二や桜金造、つまみ枝豆など、テレビで怪談を語っていた人々であろう。
彼らは、90年代のテレビ放送における「怪談・オカルト」ブームを先導した。彼らの体験した怪談奇談から「怪談・オカルト」というコンテンツはテレビで大きくなったと言えるだろう。
この彼らの怪談語りのイメージは、動画配信や怪談会の様相にも影響を与えた。
つまり、テレビでは再現VTRという形で放送され、視聴者に怪談の内容を訴えかけているが、それができないメディアが現在でも大半である。しかし先ほど名前を出したような怪談タレントたちが示した、その場で怪談を「語る」というスタイルはメディアを選ばず、誰でも行えるものであった。
怪談を「語る」というスタイルによって、「怪談・オカルト」はテレビのものではなくなったのだった。
そして、この「語る」というスタイルはそれを専門に行う「怪談師」という人々を生み出した。動画サイト以外にも、巷には怪談を楽しめる店なども現れて「怪談師」の活躍の場は広がっている。
この「怪談師」の背景には、「語る」というスタイルを確立させたタレントたちの存在と、90年代テレビで頻繁に放送されていた「怪談・オカルト」というコンテンツの世の中への浸透があるだろう。
共有される「実話怪談」
彼ら「怪談師」は怪談を語るために、その話のネタを集める必要がある。これは「怪談師」がタレントではなく、あくまでも「怪談を語る」という行為に特化した存在として認知されているからで、また一方で「怪談師」を「怪談師」たらしめるものとして、怪談のネタは必要であり、それらはお膳立てされて行うものではないからである。
語るための怪談のネタを集めていくと、そのネタの内容は完成されたものとは限らない。不思議な出来事や、心霊体験などの原因や最終的な結果が不明瞭な状態で終わてしまうものも現れる。Jホラーのドラマや映画のように観客にみせるためのものとして成立させるのは難しいネタも多くなるだろう。その結果「実話怪談」という言葉が生まれた。
「怪談」というものは古典の分野でも多くの作品が残っているが、それらは芸能として成立するように物語と作中での因果関係が明瞭になっている。しかし怪談師が求められているのは「怪談を語る」ということであって、怪談を芸能として成立させることではない。
この「この芸能としての怪談」とは少し趣が違う怪談、怪談師が「語りのネタ」としている不思議なお話を「実話怪談」と銘打つことで、その怪談のネタは「怪談語り」として成立する。
明確にオチや因果関係がわからない、しかしそんな体験をした人がいて、その出来事が怪談師の口から語られる。不思議な出来事や心霊体験のあらましが怪談師の語りによって、観客に伝えられていく。
怪談を「作品」としてではなく、「体験」として伝えるというのが、そもそも「実話怪談」で行われいる「語り」のなだろう。
これはつまり「怪談」は「実話怪談」というジャンルが生まれたことで、「鑑賞するもの」から「共有するもの」へと変化したと考えられるのではないだろうか。
怪談師から語られる「実話怪談」は、怪談師の集めたネタであり、さらにそれらは「作品」ではなく、誰かの「体験談」である。
そして「語り」による伝聞が成されるという点から考えても、「怪談」というものがただ怖がらせるための物語から、不思議な体験談を通した情報共有の側面が大きくなった。
このことは、現代においてインターネットやソーシャルネットワーキングに適したコンテンツに「怪談」を持ち上げた。
ただ怖がらせるだけということに比べれば、情報共有と考えられる現代の「怪談」は、それを通して誰かと誰かがつながっているのだから、コミュニケーションのツールと呼べなくもないので、いくらか健全な気がする。
いつかこのソーシャルネットワークがつながって、大きな輪を描いたとき「怪談」はおそらく、今以上の知名度と市民権を得た健全なコンテンツとなるだろう。怪しいイメージなどなくなり、「語る」ことでつながる文化になるだろう。
ただ、もしそうなったら「怪談」と呼んでいいのだろうか……
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
