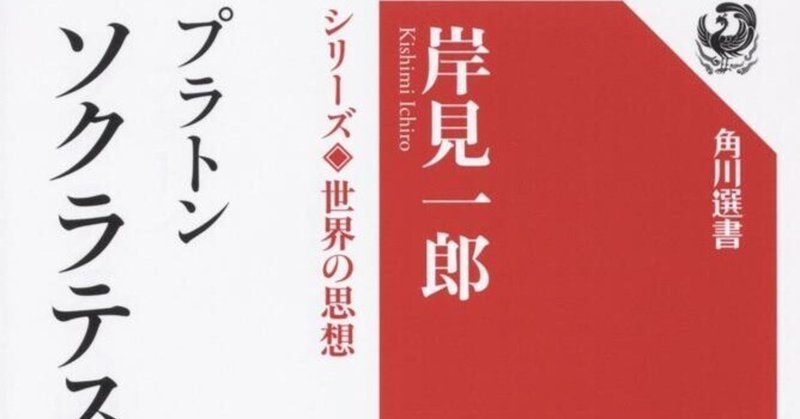
『ソクラテスの弁明』(岸見一郎)ブックレビュー
今ハマっている、『生き方』関連の本です。世の中では、“自己啓発書”とかっていうのかな?
この本は、ギリシアの哲学者ソクラテスが政治的圧力により裁判にかけられた際の言葉を、弟子のプラトン(※ソクラテス自身は弟子を持ったことはないと主張しているけども。)が書き記していたものをわかりやすく解説してくれた本。裁判では、前半で有罪or無罪が決まり、有罪となった後は死刑or罰金が決まる。ソクラテスはその場で一切の嘆願をすることはなく、その姿はまさに泰然自若、威風堂々。哲学者としての生き方を胸を張って主張し続けるソクラテスは裁判の中で言ったという。
「世にも優れた人よ、君たちは知力においても武力においても、アテナイという最も評判の高い偉大な国家の一員でありながら、お金ができる限り多く手に入ることには気を使い、そして評判や栄誉には気を使っても、知恵や真実には気を使わず、魂をできるだけ優れたものにすることにも気を使わず、心配もしないで、恥ずかしくはないのか」――
痺れました。レビューです。
第1章:ソクラテスの生涯
晩年は人間の生き方に興味を持ち、人々と対話をした。一方、時代としては国家有数の人物であるための政治的手腕や社会的能力を『徳』(アレテー)と考えられていた時期であり、知識を若者たちに教える『ソフィスト』(授業料をとって教えていた)としてソクラテスをみなす人もいた(P14)
ソクラテスは「魂が優れてあること」こそが人間としての徳(アレテー)であると考えていた。多くの人が善であると考える名誉や地位などは魂が優れ徳があれば善になり、魂が劣悪であれば悪になる付帯物に過ぎない(P17~18)
知の吟味(対話)により『知らないことを自覚する』→『絶対の知に近づいていく』ことを目指した(P21)
2~24章:第一の弁論(うち16~24章では哲学者としての生き方が語られている)
25~28章:有罪確定前の第二の弁論
29~33章:死刑確定後の第三の弁論
まずは『徳』に対する考え方が、ソクラテスはその時代の人たちを一線を画していたと。ソクラテスは「魂が優れている」ことに主眼を置き、そのためにどう生きるべきかなどを対話によって知を深めるようにしていた。一方多くの人は「政治的手腕をもつ(≒権力を持つ)」ことに主眼を置き、そのために自身が言っていることが正しいと思わせる方法論をソフィストから学んでいた、みたいなところかな。そして対話の中で無知をさらされてしまった人の中には、一定の権力者もいて、それでソクラテスは恨みを買って裁判に処されていると。
第2章:ソクラテスの弁明
1)ソクラテスを訴えたのはアミュトス一派のメレトス。説得力でなく真実で語ることを重視(P32)
4)ソフィストの弁論で勝つことありき(=正しいかどうかはどうでもいい)の能力はプラトンの言う『夢の中の必然性』(=どれほど現実的な夢でも夢から覚めればゼロになる)で無意味(P49)
6)”自称”知恵のある人と違い、ソクラテスは自身が「知らない」ということを知っている、という自覚を得た(P60)アポロン(神)の神託で「ソクラテスより知恵のある者は誰もいない」とあったのはこの意味だと分かった。“自称”知恵のある政治家にそのことを示そうとしたため憎まれるようになった(P63)
8)政治家、劇作家に続き、職人とも対話したが、やはり他のもっとも重要な事柄(=善美の事柄)に関する無知の自覚がなく、知らないことにも口出ししていた(P70)
9)人間の中で一番知恵があるのは、ソクラテスのように何も知らないということを知っている者(P76)
10)ソクラテスを中傷した中心人物はメレトス(作家)アミュトス(職人・政治家)リュコン(弁論家)。いずれもソクラテスによって無知を暴かれた(P80)
いわゆる『無知の知』ですな。同時に『知らないことを知っている』ことは自身の未熟さを謙虚に見つめ自覚することであり、学び続けるという姿勢を保つ生き方のような気がする。その点で、『無知の知』はすなわち『知ることに熱意を持ち続ける生き方』みたいな意味で素敵だと思った。
13)メレトスは「ソクラテスが故意に若者を堕落させている」と主張。しかしソクラテスは「一緒にいる人を故意に悪くすれば自身がその人から悪いことを受け取ることになる。だからたとえ実際に悪くしているとしても故意ではない(=『誰も悪を欲する人はいない』という、ソクラテスのパラドクス)。故意でないとすれば裁判ではなく個人的に諭すべき」と論破(P94)
15)ダイモーンに関わりのある事柄の存在は認めている=ダイモーンは神か神の子であり、その存在を認めている=ソクラテスは神を信じている=『不敬神』を主張したメレトスは間違い(P104)
16)自分の生き方が裁かれようとしている今、ソクラテス自身が考えるのはそれが正しいか否かのみ。死の危険は考えない(P110)
17)死がどんなものかを知らないから、死を恐れることはない。知らないものを知っているようにふるまうのは間違い。ただ生きるのではなく善く生きることが大切。善であるかを知ろうとすることが愛知者(=哲学者)の姿勢。魂をできるだけ優れたものにする(=徳を持つ)ことで、お金や他のものが全て善きものになる(P120)
18)正義に反して譲歩したことはない。誰の師にもなったことはない(=教えていたのではなく対話により共同して相手と知を探求していた)(P142)
23)ソクラテスには3人の息子がいるが、彼らを連れて嘆願するようなことは決してしなかった(P149)
→有罪280票 無罪220票(P155)
有罪か無罪かが決まる場面にもかかわらず、堂々とした、むしろ時に挑発的な弁論もするソクラテス。死に対する考え方や、哲学者としての姿勢を語った17章はマジで圧巻。
25)絶対の正義を貫くために、お涙頂戴の弁論を避けた(P158)
28)徳や他のことについての議論こそ人間最大の徳であり、それをしないものは生きるに値しない(P169)
→死刑360票 罰金刑140票(P170)
29)死を免れることは難しくない。速く走ればいい。しかし悪を避けることはもっと難しい。悪は死よりも速く走るため。(P175)
ソクラテスは最期の日、毒の盃を静かに飲み、涙を流す周囲に静かにするように諭した。最期の言葉は、「クリトンよ、アスクレピオス(医術の神)に鶏一羽の借りがある。忘れずにお返しをきっとするように」だった。(P195)
→最後の最後まで主張を誇示し続けたソクラテス。死ぬ間際の言葉さえ、なんか深みがある。
ソクラテスの論破シーンから哲学者としての生き方、人間にとっての『徳』の考え方が述べられていた『ソクラテスの弁明』。
やはりこうした本は稲盛和夫さん、渋沢栄一さん、松下幸之助さん、岩田松雄さんの本と本質的なところは共通していて、読んでいて清々しい。
迎えております、“読書の夏”。実はもう1冊、すぐに読みたい本があるのよね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
