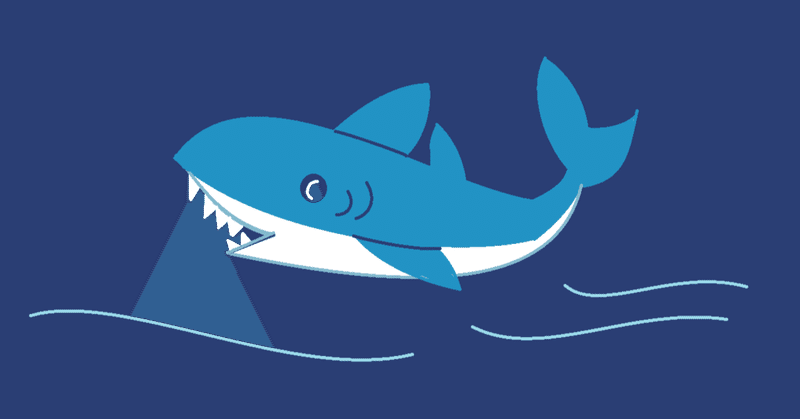
「教員の不安」を起点にした対話を
暴君の本質
「決断疲れ」を回避したいがゆえに暴君に成り果ててしまう人間の心情を、太宰治が極めて端的に表現している。
「この短刀で何をするつもりであったか。言え!」暴君ディオニスは静かに、けれども威厳を以もって問いつめた。その王の顔は蒼白で、眉間の皺は、刻み込まれたように深かった。
「市を暴君の手から救うのだ。」とメロスは悪びれずに答えた。
「おまえがか?」王は、憫笑した。「仕方の無いやつじゃ。おまえには、わしの孤独がわからぬ。」
他者に対して強く叱責したり、暴言を吐く人間がなぜそんな行動に出ざるを得ないのかといえば、他者を怖れているからに他ならない。自分とは決して同化できないものとして現前する他者、決して自分の思い通りにならない他者を怖れ、力によって自己と同一化させようとする。
小学生のころに那須正幹の『ヨースケくん』という児童文学をよく読んでいた。話の大筋は忘れてしまったが、作品の冒頭にヨースケくんを担任が叱責する場面がある。その場面で、ヨースケくんには厳しい言葉で怒っている先生の顔がどんどん小さくなるように見えた、という描写がある。小学生の当時はなぜ先生の顔が小さくなるように見えたのかよくわからなかったが、今となってはよくわかる。先生はヨースケくんが怖かったのだ。
世の中にいる暴君は、自分が孤独であり、他者を信じられなくなっているほど恐怖に苛まれているということを言語化しようとしない(もしくはできない。できないことにも様々な要因がある)。
暴君ディオニスが他の暴君と決定的に違うところは、暴君としての自分に批評的な目を向け、自らが敷いている圧政の根源がどこにあるのか、ということを見極めていることだ。そしてそれを恥ずかしげもなくメロスに対して吐露することができること。ディオニスには暴君を脱するだけの「強さ」がなぜか備わっていた。だからこそ、「おまえらの仲間の一人にしてほしい」という言葉も同じ言葉から紡ぎ出すことができた。
生徒に対して暴言を吐くのも、身体的に暴力を振るうのも、教員が生徒に「甘えている」のだと私は思う。対話を通して合意形成を図ることへのコスト、自分の思い通りにすることができなかったらという恐怖、それらを一気に回避するために「自分と同じになってくれ」と生徒に甘えを見せ、その結果教員は暴君へと成り果てる。もちろん、生徒と教員という権力勾配が形成されやすい関係性も、暴君への変身に拍車をかける。
しかし、自分の行動が「甘え」から来ていると言語化できる暴君は少ない。それどころか、自分の強い叱責が「正当な指導である」と認識し、そして「ここまで強く叱責するのは生徒のせいだ」と責任転嫁していき、「甘え」を強化していく。
教員も不安になっていい
まずは教員自身の中に巣くう、生徒に対する不安や恐怖としっかりと向き合って、時にはそれを生徒に対して吐露することも大切だ。
教員は生徒に対して、いつでも正しく、いつでも強く、いつでも気高くあらねばならないという強迫観念に駆られてしまう。権力勾配がつきやすいが故の不安。誰かの上に立たざるを得なくなるゆえの不安。そんな不安に常に追われている。
弱みを見せれば、隙を見せれば、生徒にナメられてしまう、生徒に見下されてしまうと思い込み、自分の不安を抑圧して生徒を貶めていく。しかし、生徒にナメられる最大の要因は生徒ナメることであり、生徒に見下される最大の要因は生徒を見下すことだ。自分の不安は抑圧するうちに膨張し、しかも生徒との信頼関係は崩れていく、という負のスパイラルに陥っていく。
教員だって迷うことはある。教員だって間違えることはある。教員の迷いを、ときには生徒に対して開示し、教員の不安を起点にして対話を発生させていくという手段もある。
「自分は○○が正しいと思うんだけど、みんなはどう思うのか」「私たちはどのように生きていくのが適切なのか。そもそも生き方に適切さなんてあるのか」。教員ひとりでは結論を出せない課題は世の中に溢れている。教員が答えを知らない問いを生徒に投げかけたっていい。そこで生徒とともに「答えらしきもの」を探すところに、より善い「決断」が待っているはずだ。
何かに恐怖しない人間はこの世にはいない。つまり、誰しもが暴君ディオニスになる素質を持っている。大切なのは不安になったときにどうするかだ。もちろん、生徒ではなく、周りの教員・主任と共有することも大切な手段だ。学校の管理者も、教員のもつ不安を言語化できる仕組みを構想しなければならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
