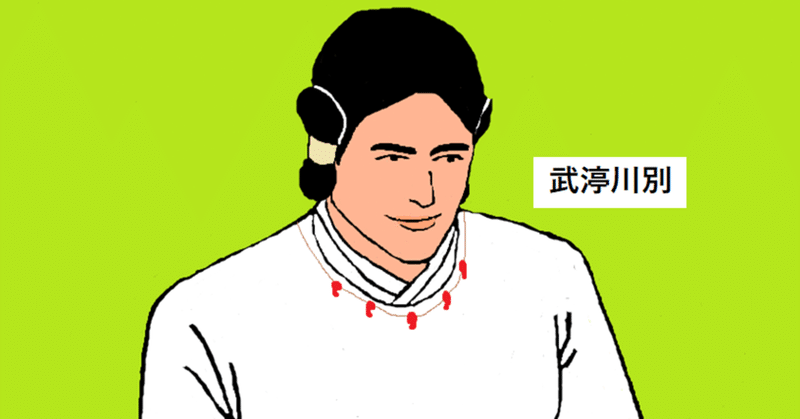
JW270 神社がいっぱい
【疫病混乱編】エピソード22 神社がいっぱい
第十代天皇、崇神天皇(すじんてんのう)の御世。
ここは三輪山(みわやま)の麓、磯城瑞籬宮(しきのみずかき・のみや)。


紀元前91年、皇紀570年(崇神天皇7)11月13日、崇神天皇こと、御間城入彦五十瓊殖尊(みまきいりひこいにえ・のみこと)(以下、ミマキ)は、天津神(あまつかみ)を祀る天社(あまつやしろ)、そして、国津神(くにつかみ)を祀る国社(くにつやしろ)の創建を宣言した。
そして、ミマキの元に、解説のため、二人の人物がやって来た。
すなわち、ミマキの従兄弟、武渟川別(たけぬなかわわけ)(以下、カーケ)と大稲腰(おおいなこし)(以下、イナコ)である。

カーケ「・・・というわけで、エピソード244以来なんだぜ。」
イナコ「・・・というわけで、早速、解説を始めますよ。淡海国(おうみ・のくに)で日吉大社(ひよしたいしゃ)が創建されました。」
ミマキ「と・・・唐突すぎるのではないか?」
イナコ「まだ五つも有るっていうのに、紙面を割き過ぎなんですよ!」
カーケ「そうだぜ。『イナコ』の申す通りなんだぜ。」
ミマキ「わ・・・分かった。し・・・して、何処(いずこ)に建てられたのじゃ?」
イナコ「滋賀県大津市坂本(おおつし・さかもと)に建てられました。」






カーケ「祭神は大山咋神(おおやまくいのかみ)だぜ。元々、日枝の山(ひえのやま)の山頂に鎮座(ちんざ)していたんだぜ。それを麓に遷座(せんざ)したんだぜ。」
ミマキ「大山咋神は、里山の神で、農耕治水の神でもあったな? されど、なにゆえ遷座を?」
イナコ「山に登るのが面倒くさかったんでしょうかねぇ?」
カーケ「これがロマンだぜ!」
ミマキ「聞いた、わしが悪かった。」
イナコ「ち・・・ちなみに、日枝の山は、のちの比叡山(ひえいざん)のことです。社名も、元々は『日吉社』と書いて『ひえしゃ』と呼んでいたんですが、第二次大戦後は『ひよし』を正式名称にしたそうです。」

カーケ「更には、大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)こと大己貴命(おおなむち・のみこと)も祀(まつ)られてるんだぜ。西本宮が大己貴命、東本宮が大山咋神だぜ。どちらも本殿が、国宝になってるぜ。」




ミマキ「左様か・・・。」
イナコ「では、次に福井県の神社を紹介しますよ。」
カーケ「大虫神社(おおむしじんじゃ)だぜ。祭神は、山幸彦(やまさちひこ)こと『ヤマピー』だぜ。それがしの御先祖様だぜ。」

ミマキ「わしの御先祖様でもあるぞ。されど、なにゆえ、福井県に『ヤマピー』の神社が? 福井県と申せば、わしらの時代では高志国(こし・のくに)ではないか? 縁もゆかりも無いような気がするが・・・。」
イナコ「縁もゆかりも有ったんですよ。かつて『ヤマピー』は、南越地方を平定、開拓したそうでして、そこで『ヤマピー』の霊を鬼ヶ嶽(おにがだけ)の山頂に祀ったのが起源とされてますね。このときは、大蒸大神(おおむしのおおかみ)と称(たた)えていたそうです。」
カーケ「ちなみに、鬼ヶ嶽は、標高533mだぜ!」
ミマキ「待て、待て。蒸すが、なにゆえ、虫になったのじゃ?」
イナコ「大王(おおきみ)の息子さん、すなわち、十一代目の時に、イナゴが大発生したそうなんですが、当社に祈願したところ、たちまちにして退散したそうなんですよ。そこで、十一代目は、大いに喜ばれ、大虫神社と改称するように命じたそうです。」
ミマキ「み・・・未来の話か・・・。まだ、十一代目は産まれておらぬぞ!」
カーケ「気にすることはないぜ。ちなみに、そのとき、山頂から麓に遷座されたんだぜ。」
ミマキ「では、二千年後は麓に有ると申すか? して、どこに鎮座しておるのじゃ?」
イナコ「福井県越前市大虫町(えちぜんし・おおむしちょう)に鎮座してますよ。」









ミマキ「して、こちらも、登るのが面倒くさかったゆえ、遷座したのか?」
カーケ「これがロマンだぜ!」
ミマキ「聞くべきではなかったな・・・。」

イナコ「どんどん行きますよ! 次は、山梨岡神社(やまなしおかじんじゃ)です!」
カーケ「祭神は、大山祇神(おおやまづみのかみ)、高龗神(たかおかみのかみ)、別雷神(わけいかずちのかみ)の三柱(さんはしら)だぜ。龗は龍の古語で、雨水を司る神とされてるぜ。」
ミマキ「む・・・難しい字じゃのう。して、何処に鎮座しておるのじゃ?」
イナコ「御室山(みむろやま)に創建されたそうです。」





ミマキ「こちらは麓に遷座しなかったのか?」
カーケ「遷座はするぜ。されど、それは十三代目の時なんで、それまで、お預けだぜ。」
ミマキ「なにゆえじゃ?」
イナコ「いろいろ有るみたいなんですよ。」
ミマキ「い・・・いろいろか・・・。」
イナコ「さくさく進めて参りますよ。次に紹介するのは、武蔵御嶽神社(むさしみたけじんじゃ)です。祭神は、櫛真智命(くしまち・のみこと)です。太占(ふとまに)を司る神ですね。」


ミマキ「太占と申せば、鹿の肩甲骨(けんこうこつ)を焼いて占うことであったな?」
イナコ「その通りです。大陸から亀卜(きぼく)が入ってくる前は、こちらが主流だったそうですね。ですから、大王が、エピソード259や264で、亀卜をしているのは、本当は、おかしな話というわけです。」
ミマキ「本来なら、太占であったということか・・・。それを『日本書紀(にほんしょき)』の編者が、改竄(かいざん)したのじゃな?」
イナコ「そういうことですね。」
カーケ「ちなみに、それがしが四道将軍(しどうしょうぐん)として赴いた際、大国主大神と少彦名命(すくなひこな・のみこと)を祀ったのが最初と伝わっているんだぜ。」
ミマキ「四道将軍?」
イナコ「ええっと・・・。いわゆる、フライングですね。もうちょっと後の話なんですが、なぜか、そうなってるというか・・・。」
唐突なフライング。
武蔵御嶽神社の解説は続くのであった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
