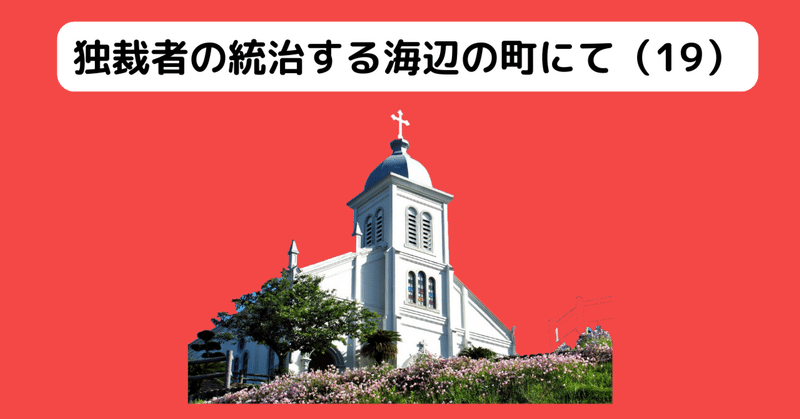
独裁者の統治する海辺の町にて(19)
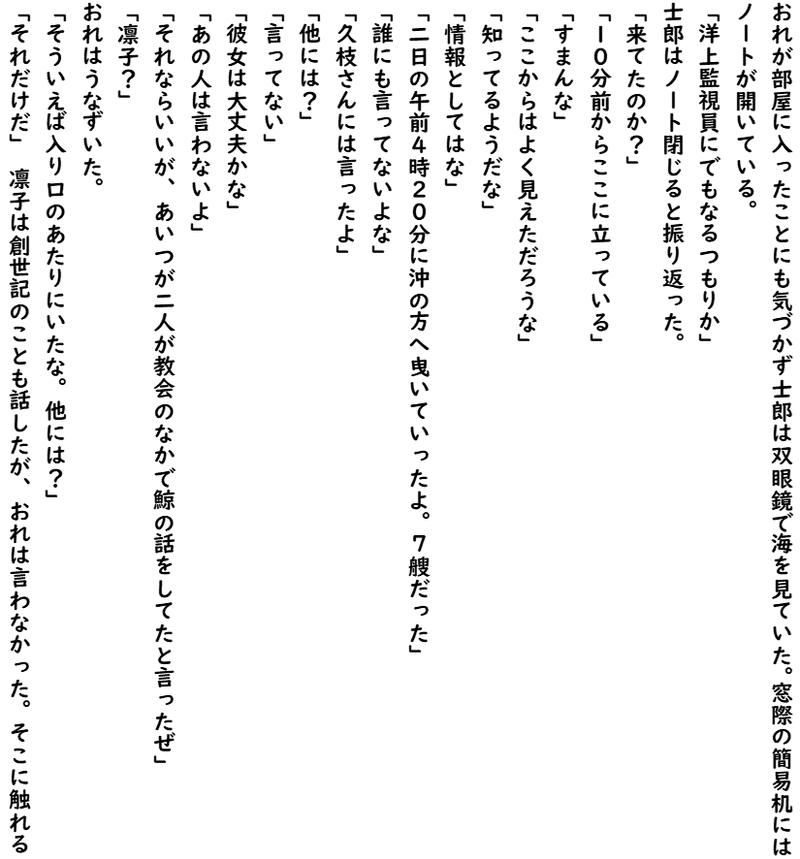
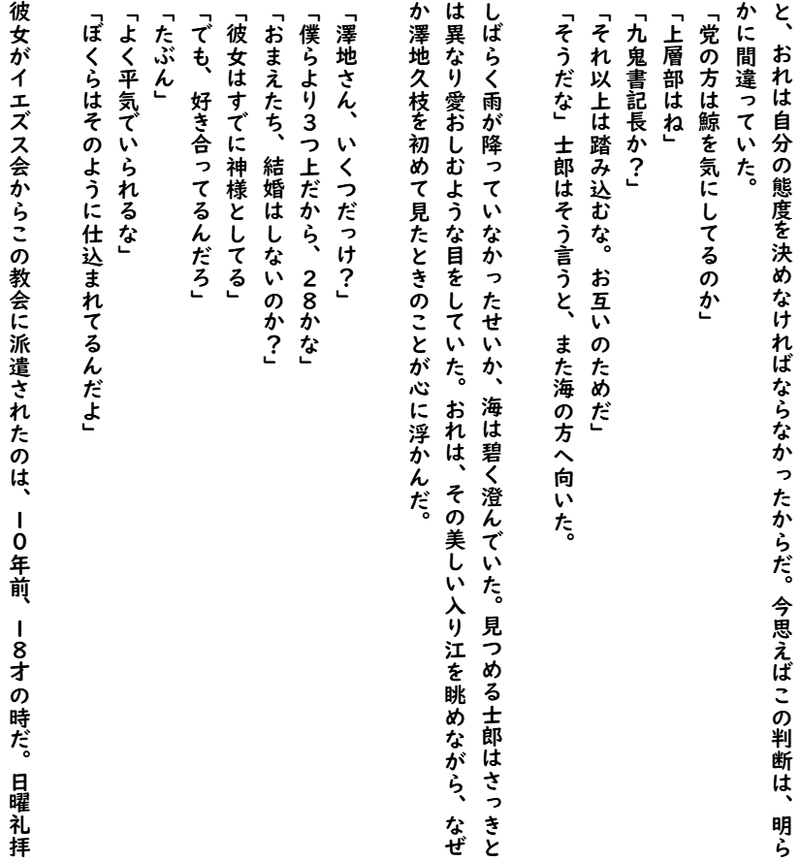
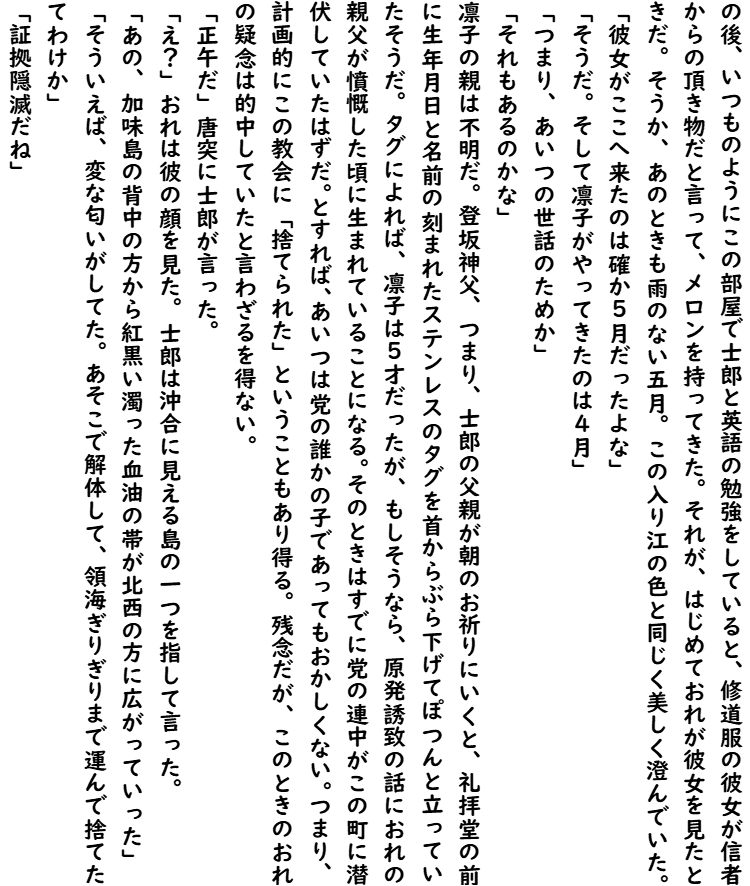
おれが部屋に入ったことにも気づかず士郎は双眼鏡で海を見ていた。窓際の簡易机にはノートが開いている。
「洋上監視員にでもなるつもりか」
士郎はノート閉じると振り返った。
「来てたのか?」
「10分前からここに立っている」
「すまんな」
「ここからはよく見えただろうな」
「知ってるようだな」
「情報としてはな」
「二日の午前4時20分に沖の方へ曳いていったよ。7艘だった」
「誰にも言ってないよな」
「久枝さんには言ったよ」
「他には?」
「言ってない」
「彼女は大丈夫かな」
「あの人は言わないよ」
「それならいいが、あいつが二人が教会のなかで鯨の話をしてたと言ったぜ」
「凛子?」
おれはうなずいた。
「そういえば入り口のあたりにいたな。他には?」
「それだけだ」 凛子は創世記のことも話したが、おれは言わなかった。そこに触れると、おれは自分の態度を決めなければならなかったからだ。今思えばこの判断は、明らかに間違っていた。
「党の方は鯨を気にしてるのか」
「上層部はね」
「九鬼書記長か?」
「それ以上は踏み込むな。お互いのためだ」
「そうだな」士郎はそう言うと、また海の方へ向いた。
しばらく雨が降っていなかったせいか、海は碧く澄んでいた。見つめる士郎はさっきとは異なり愛おしむような目をしていた。おれは、その美しい入り江を眺めながら、なぜか澤地久枝を初めて見たときのことが心に浮かんだ。
「澤地さん、いくつだっけ?」
「僕らより3つ上だから、28かな」
「おまえたち、結婚はしないのか?」
「彼女はすでに神様としてる」
「でも、好き合ってるんだろ」
「たぶん」
「よく平気でいられるな」
「ぼくらはそのように仕込まれてるんだよ」
彼女がイエズス会からこの教会に派遣されたのは、10年前、18才の時だ。日曜礼拝の後、いつものようにこの部屋で士郎と一緒に英語の勉強をしていると、修道服の彼女が信者からの頂き物だと言って、メロンを持ってきた。それが、はじめておれが彼女を見たときだ。そうか、あのときも雨のない五月。この入り江の色と同じく美しく澄んでいた。
「彼女がここへ来たのは確か5月だったよな」
「そうだ。そして凛子がやってきたのは4月」
「つまり、あいつの世話のためか」
「それもあるのかな」
凛子の親は不明だ。登坂神父、つまり、士郎の父親が朝のお祈りにいくと、礼拝堂の前に生年月日と名前の刻まれたステンレスのタグを首からぶら下げてぽつんと立っていたそうだ。タグによれば、凛子は5才だったが、もしそうなら、原発誘致の話におれの親父が憤慨した頃に生まれていることになる。そのときはすでに党の連中がこの町に潜伏していたはずだ。とすれば、あいつは党の誰かの子であってもおかしくない。つまり、計画的にこの教会に「捨てられた」ということもあり得る。残念だが、このときのおれの疑念は的中していたと言わざるを得ない。
「正午だ」唐突に士郎が言った。
「え?」おれは彼の顔を見た。士郎は沖合に見える島の一つを指して言った。
「あの、加味島の背中の方から紅黒い濁った血油の帯が北西の方に広がっていった」
「そういえば、変な匂いがしてた。あそこで解体して、領海ぎりぎりまで運んで捨てたてわけか」
「証拠隠滅だね」
(続く)
#小説 #創作 #短編小説 #連載小説 #鯨
#文学 #組織 #少女 #漫画原作 #連載小説漫画
#原発 #原子力発電
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
