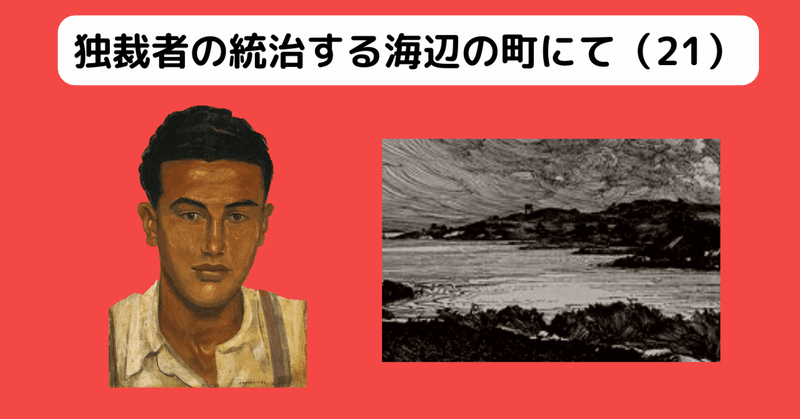
独裁者の統治する海辺の町にて(21)


百合みたいに開いた河口から鉛色の水が湾内に流れ出て漏斗状にひろがっていた。おれはバイクを飛ばし、党の本部に向かった。平良貴子(「主席」のことだ)に呼び出されていたのだ。指令を直接出すということは傍受を警戒してのことだ。彼女の九鬼書記長に対する猜疑心が深まっていることは明白だった。6月も中旬になっていた。
党の本部は2階建ての洋館だが、造りは要塞化していて、そこへ行くには長い桟橋を渡らなければならなかった。入り口の両端にはいつものように警備兵が立っていた。おれはそいつらにバイクを預け、奥の階段から上がった。二階の部屋はすべて主席の専用だった。人民服の彼女は海側に張り出したバルコニーに立っていた。午後3時だった。彼女は執務室に入ると、「もうじき雨になるな」と言いながら胸ボタンをおれにはずさせると、その人民服の上着を煩わしそうにソファーに投げ捨てた。黒いタンクトップからはみ出た上体の肉が動作とともにたわんで揺れた。
「どうやら、梅雨に入るな」
「しばらくは流れが沖に向くから鯨の心配はないでしょうね」
「ふん。だが、工事は停滞する」
「そうですね。失礼しました」
「それにしても、遅かったな」
「すいません。アパートにいなかったもんですから」
呼び出しの伝言は郵便受けに入れてあった。
「どこへ行ってた?」
「ちょっと母の顔を見に」
「悪いのか?」
知っているのに聞いているのは分かっていたが、それはこの場合どうでもいいことだった。
「いえ、たいして。ひと月に一度見舞うようにしてましたから」
「ふーん。意外と親思いだな。まあいい、ところで、あの病院から長者岬が見えるはずだが」
「それがどうかしましたか、・・・まさか、ひょとして例のやつですか」
おれはすっとぼけてみせた。
「ふん、察しがいいな、まあいい、それでちょっと内密に地盤調査をやっているんだがな」
「それが、何か」
「どうも東越電力のやつらにそれを漏らしたやつがいるみたいなんだ」
この町は西と東の端が岬になっていて、まるで蟹のはさみのように突き出している。西ヶ岬に建設予定のやつは中央電力だった。やつらは西と東で原発を建設し、二つの電力会社を支配下に置くつもりでいた。
もともと党としても東越に・・・とおれは言おうとしたがやめた。それは任務とは関係がない。粛正されないためには余計なことを言わないことが肝腎だ。
「誰なんです?」
「それが今度のお前の任務だ」
「分かりました」
雨が降り始めた。主席は部屋の外に待機していた彼女の世話係を呼び、バルコニー側の出入り口の窓とカーテンを閉めさせ、自分は奥の部屋から年代物のワインを出してきた。そして、おれのグラスに注ぎながら言った。
「酷い雨になりそうだ。バイクは奥に入れさせたが、それでよかったかな」
「はい、ありがとうございます」
世話係はいつのまにか消えていた。この雨は翌日の昼まで降り続け、湾内の海はすっかり濁った墨色になった。
おれが病院に行ったのは本当だ。しかし、母を見舞うためではない。目的は澤地久枝に会うことにあった。士郎のことを凛子が探っている。それを知らせるためだったのだが、皮肉なことに、そのとき彼女は士郎のところに行っていた。おそらく鯨と聖書について話し合うためだろう。すべてがちぐはぐだった。物事が酷い方へ向かう時はだいたいこんなものだろう。何もかもが、悔やまれるが、すべては後の祭りだ。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
