
【短編小説】最果て
※有料設定になっていますが、投げ銭方式なので全文無料で読めます。
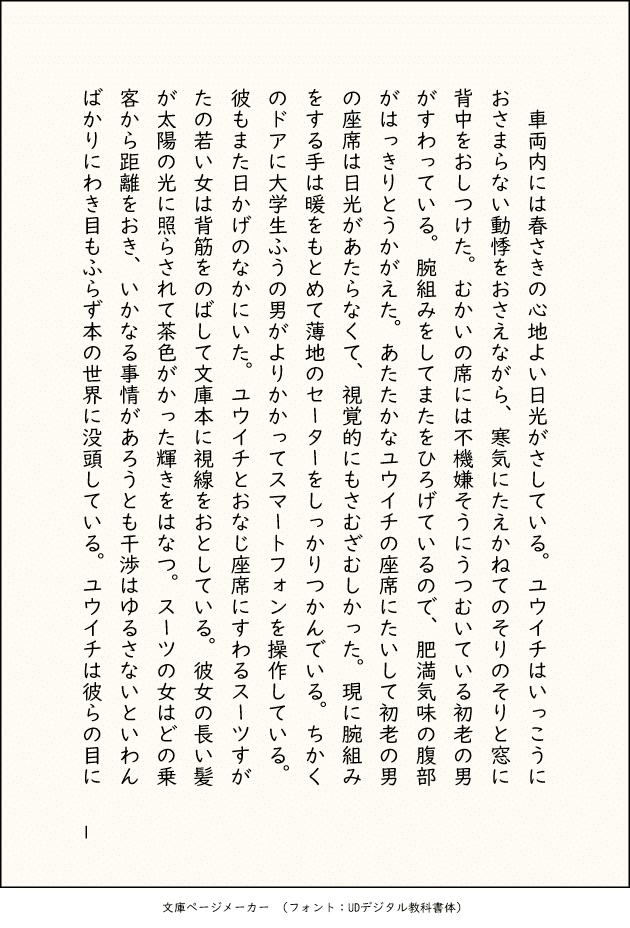
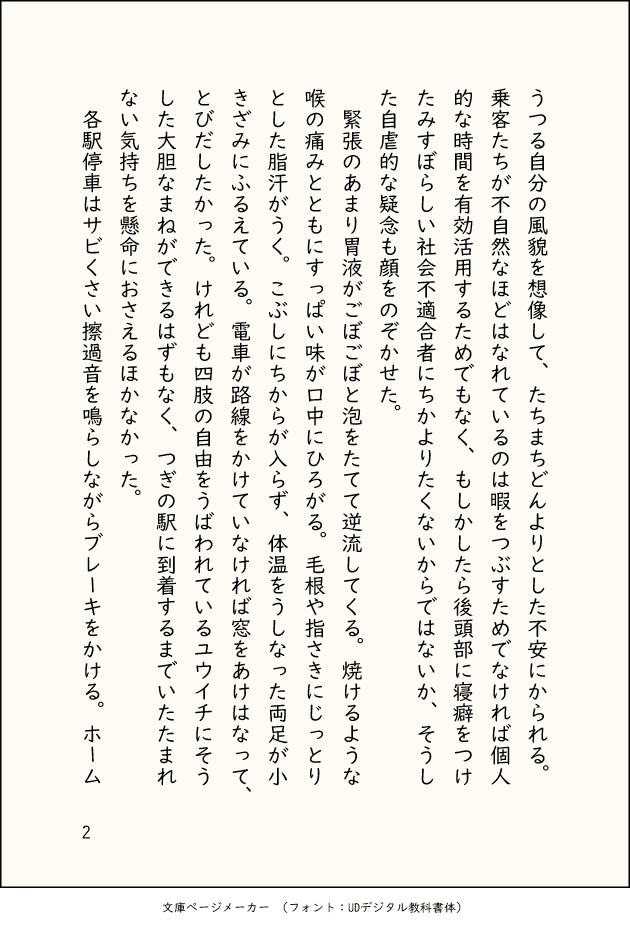

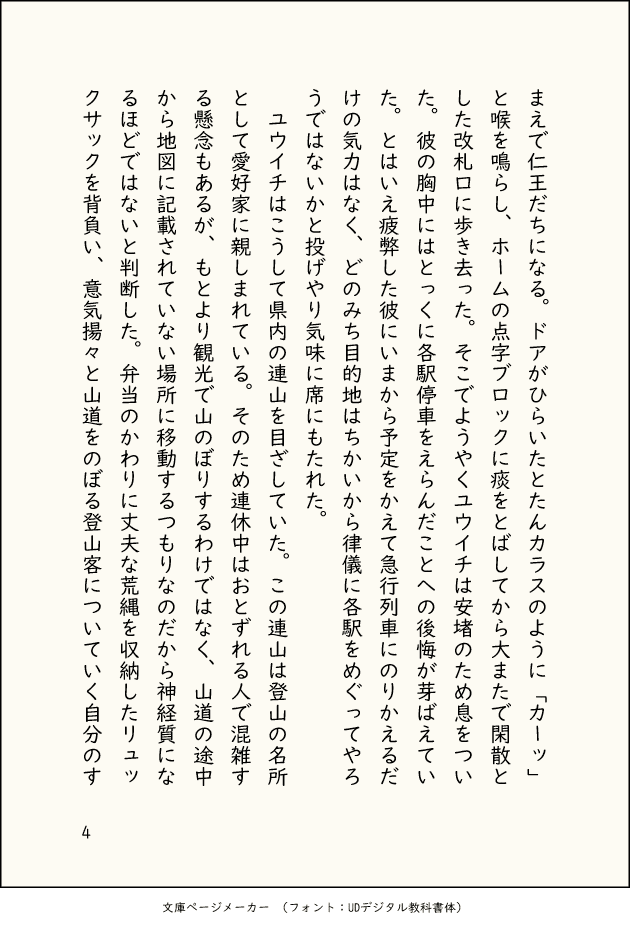
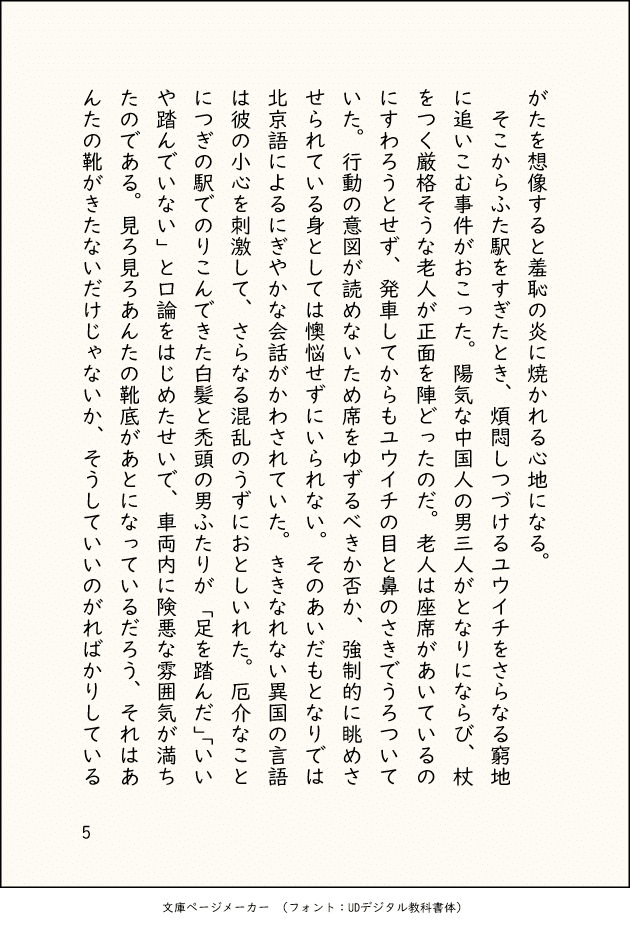
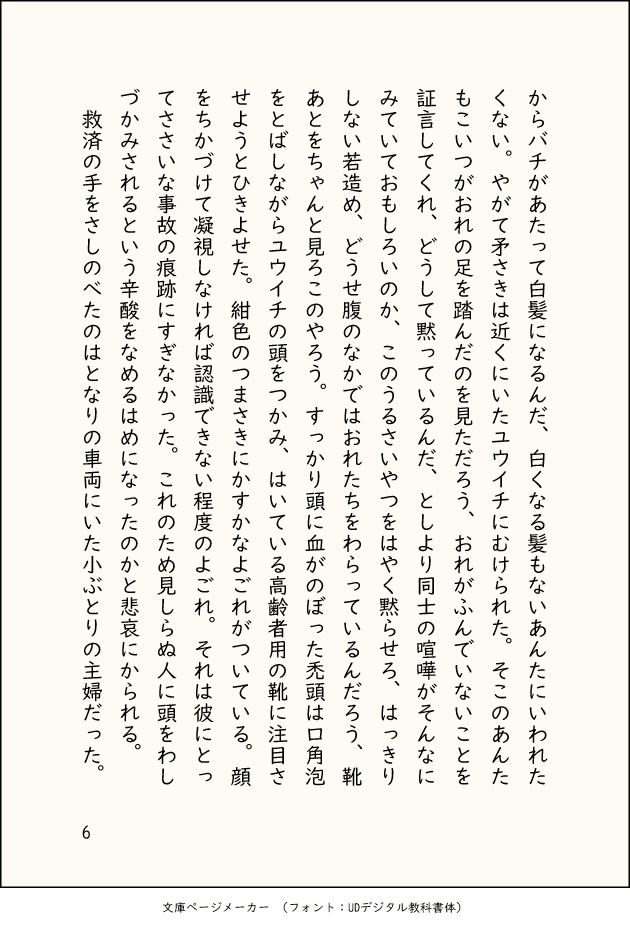

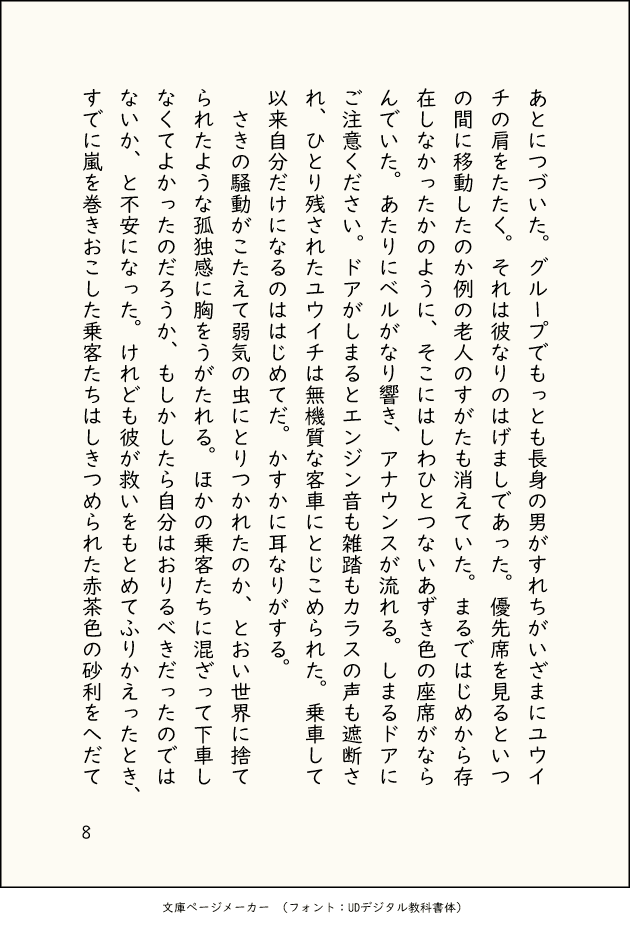
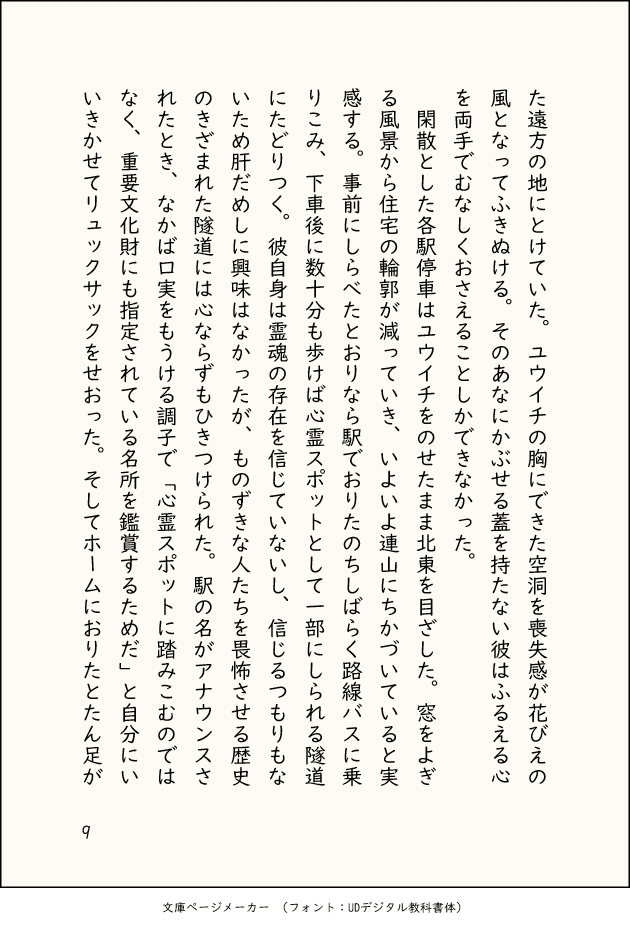
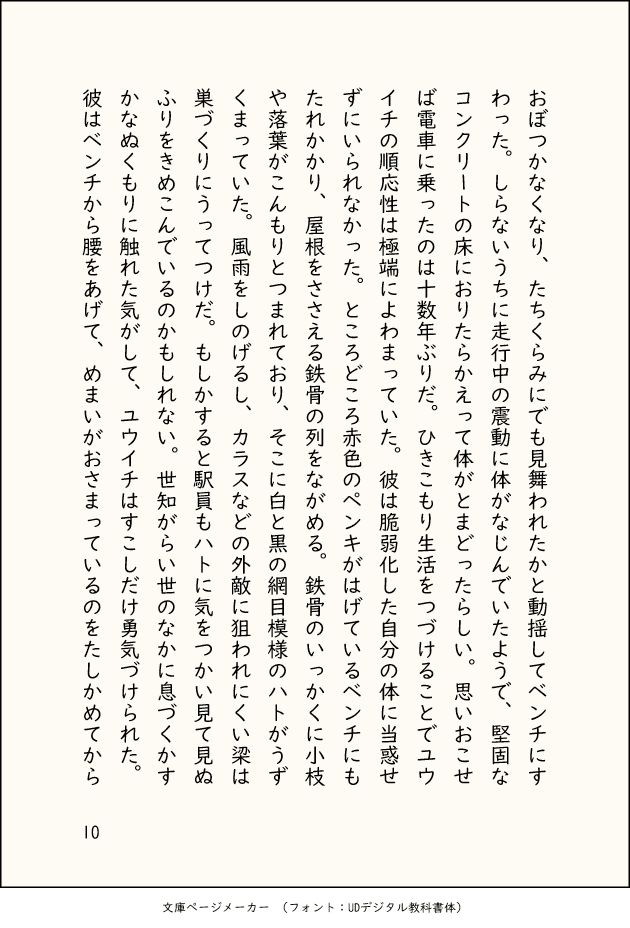
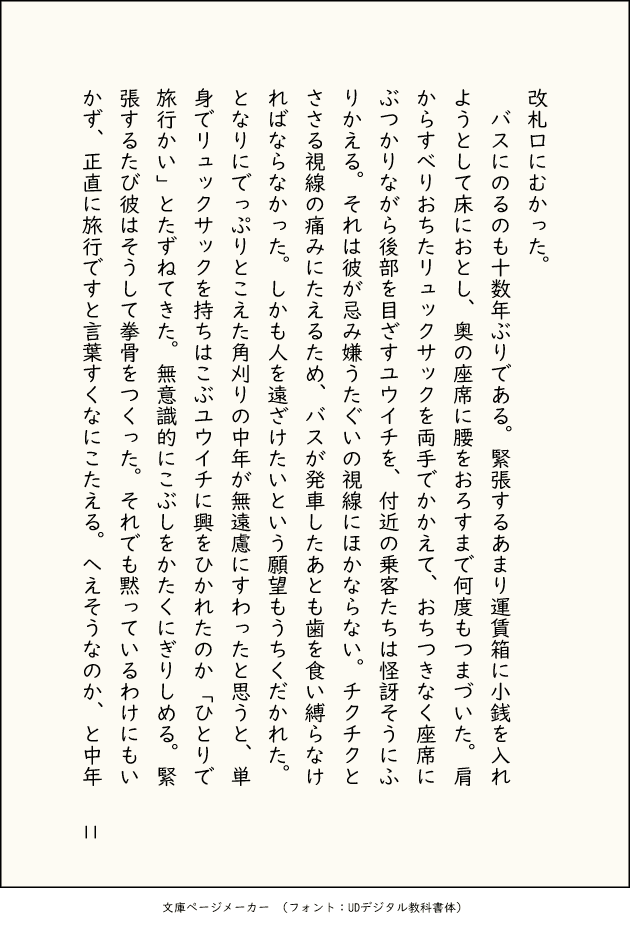


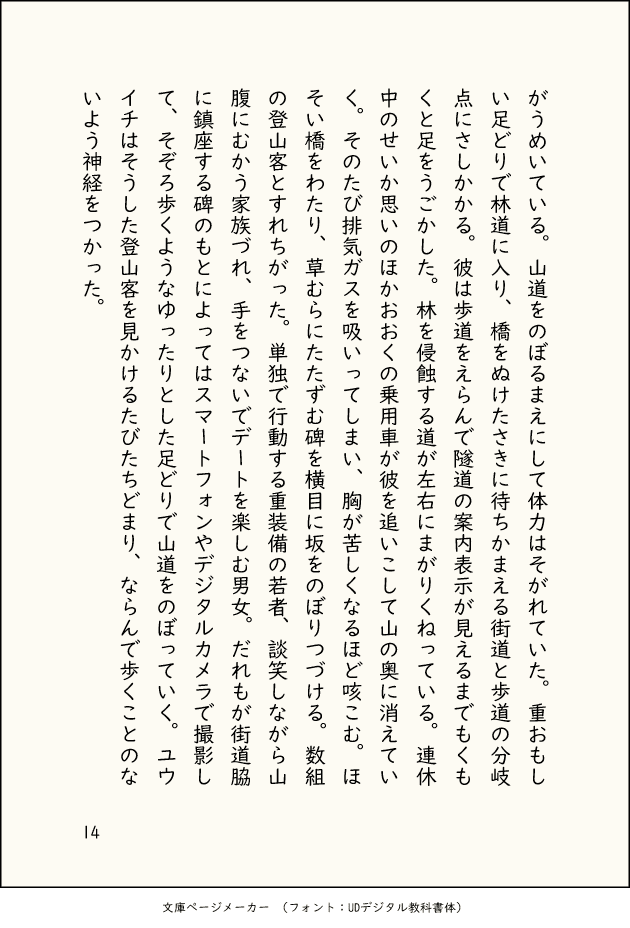
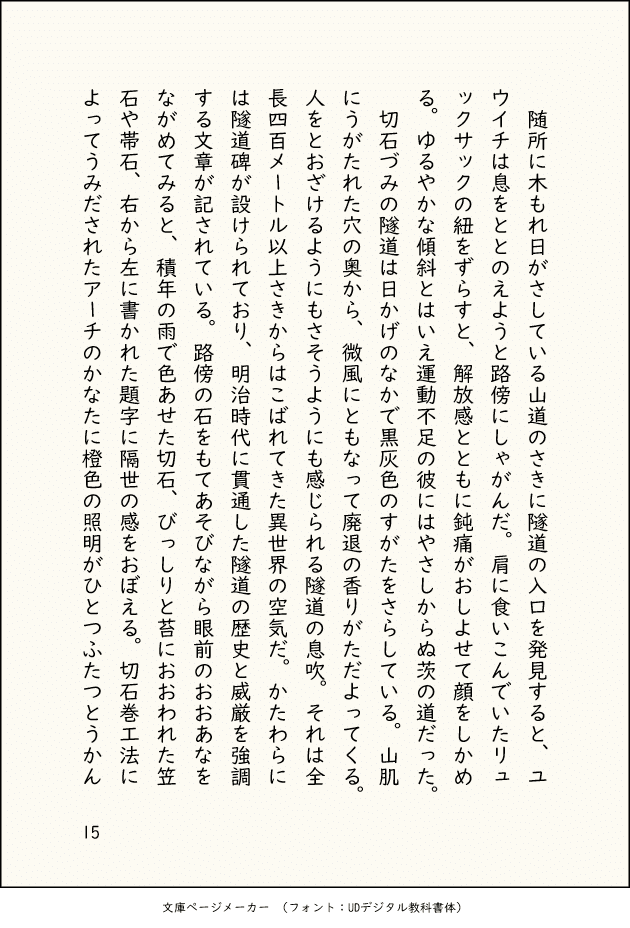
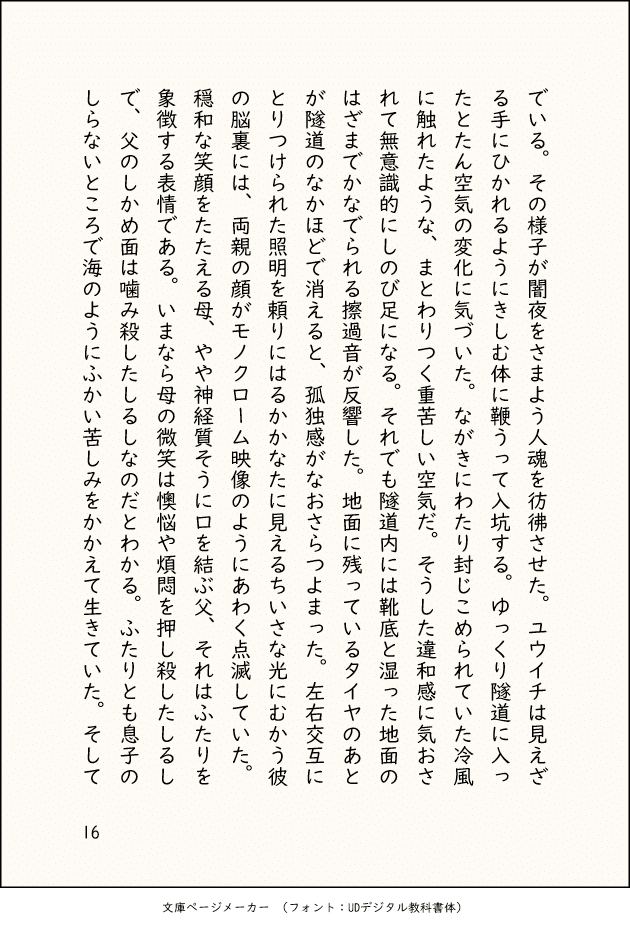
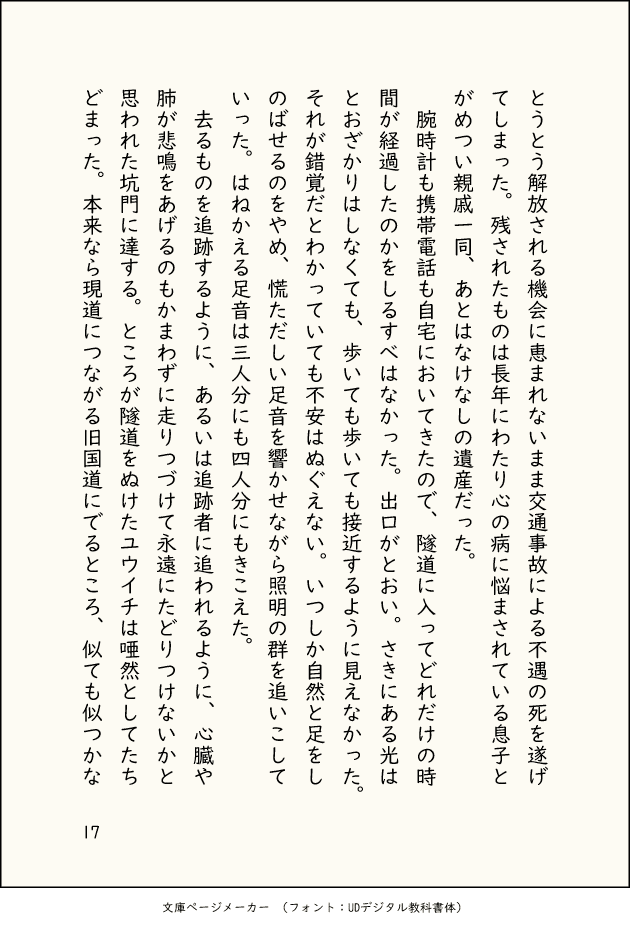

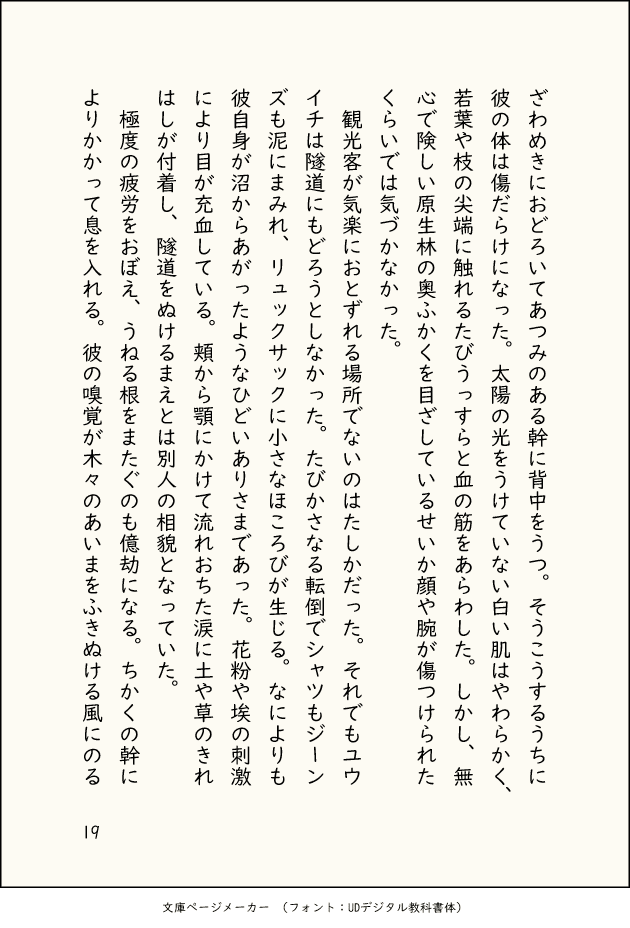
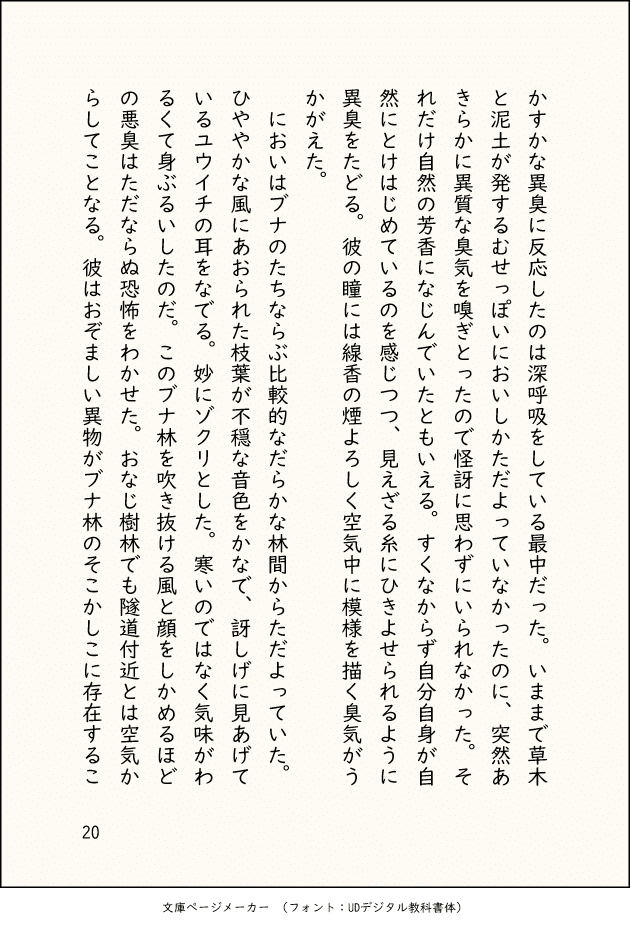
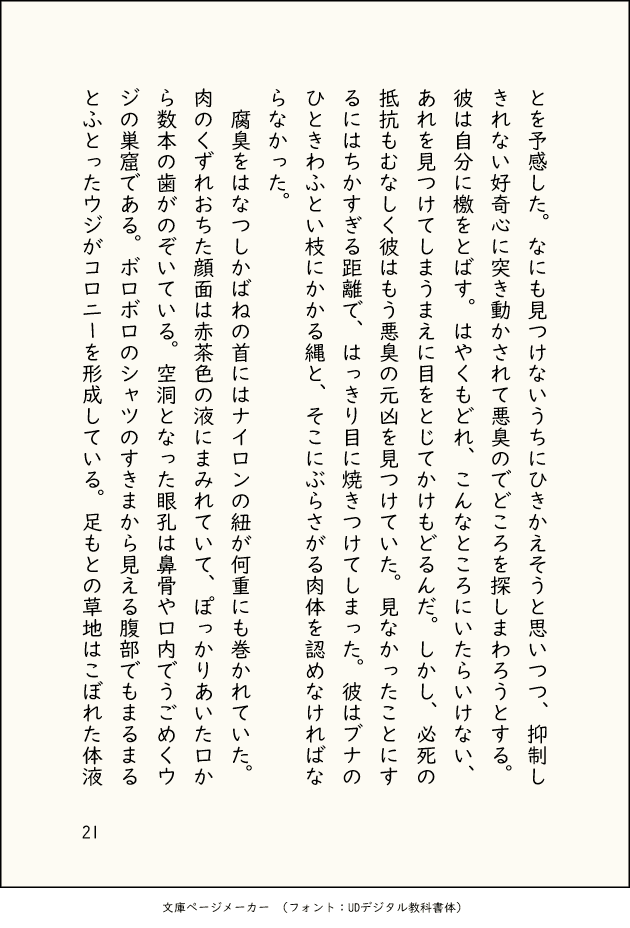
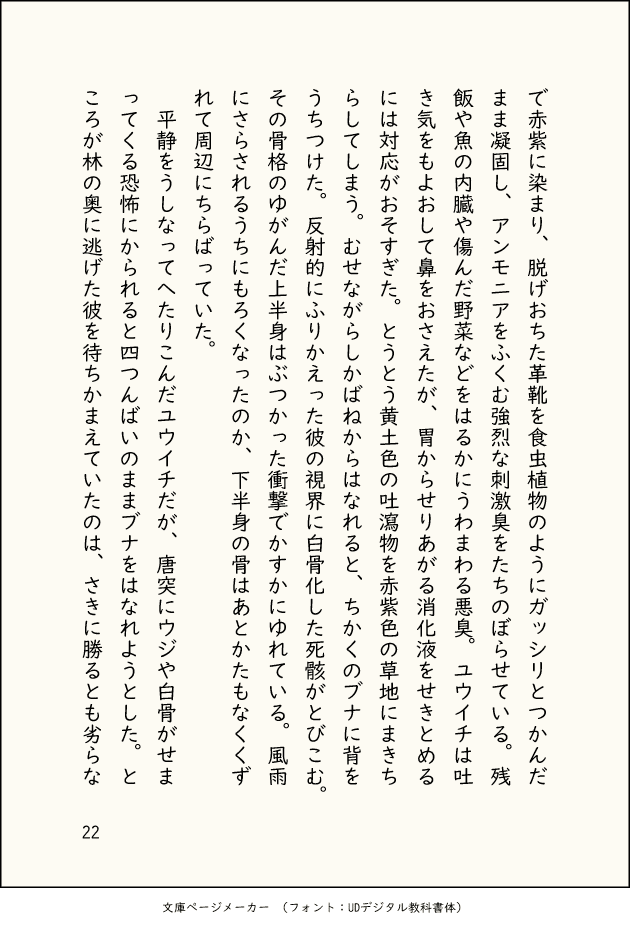
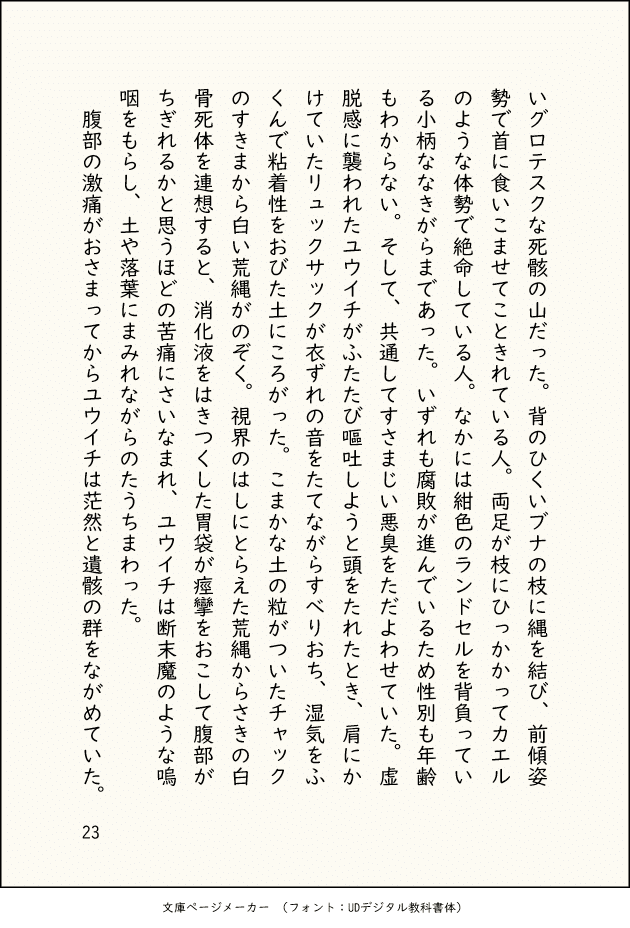
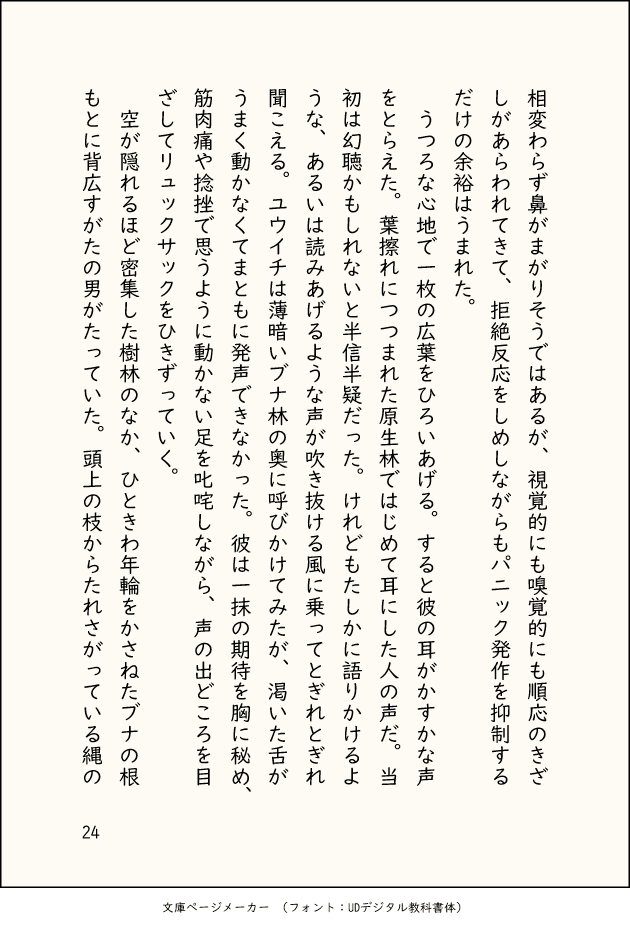
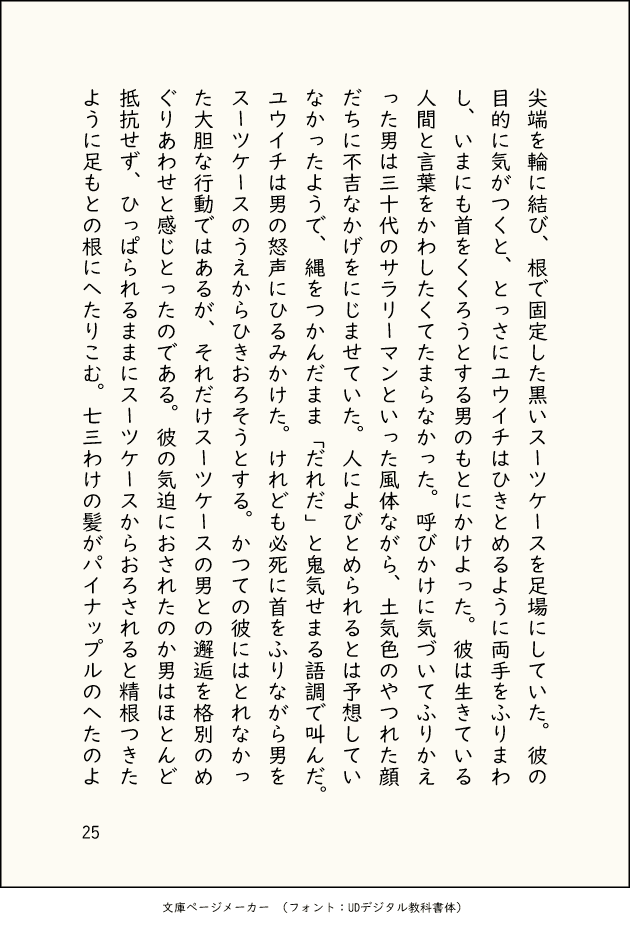
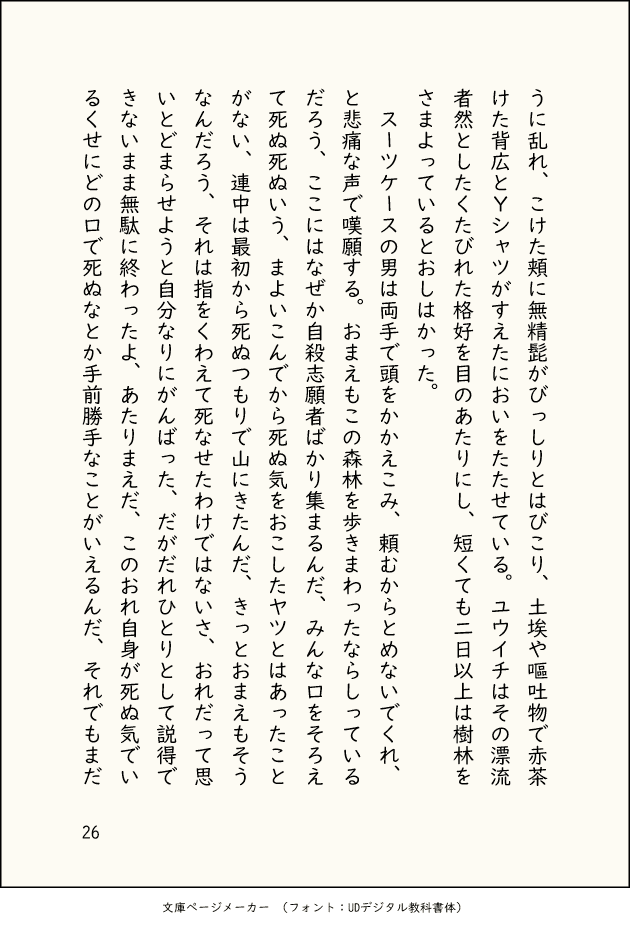
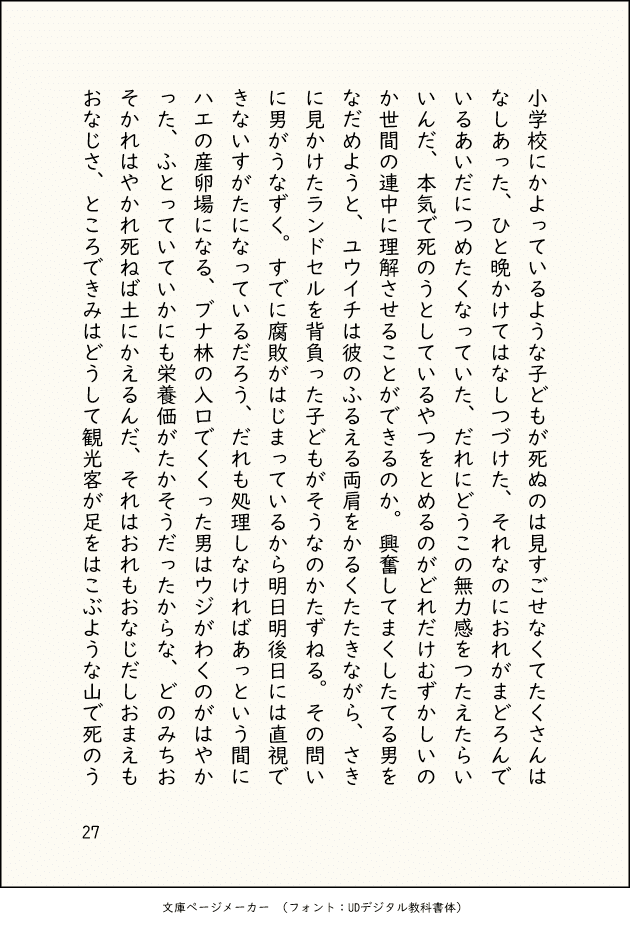
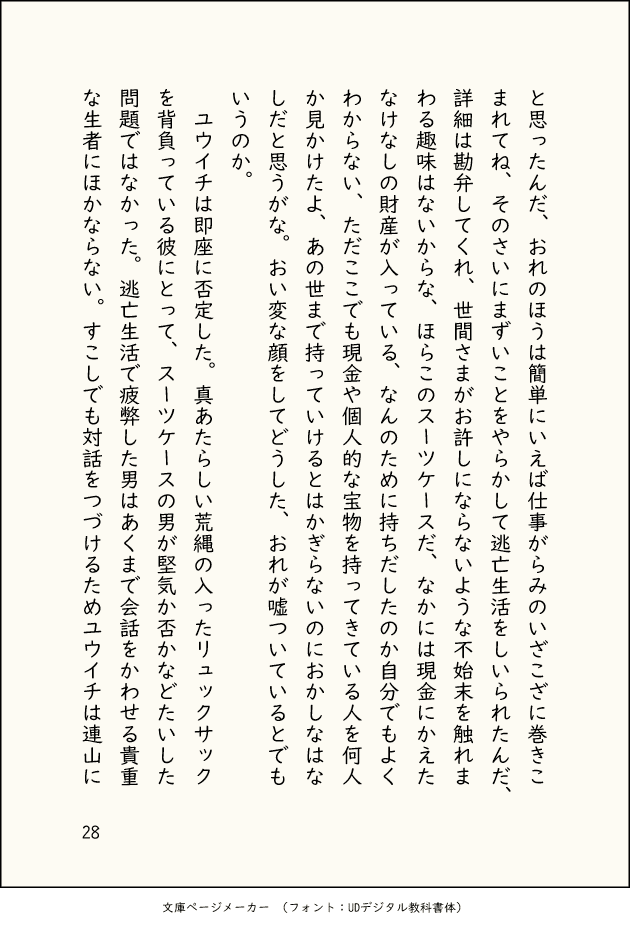
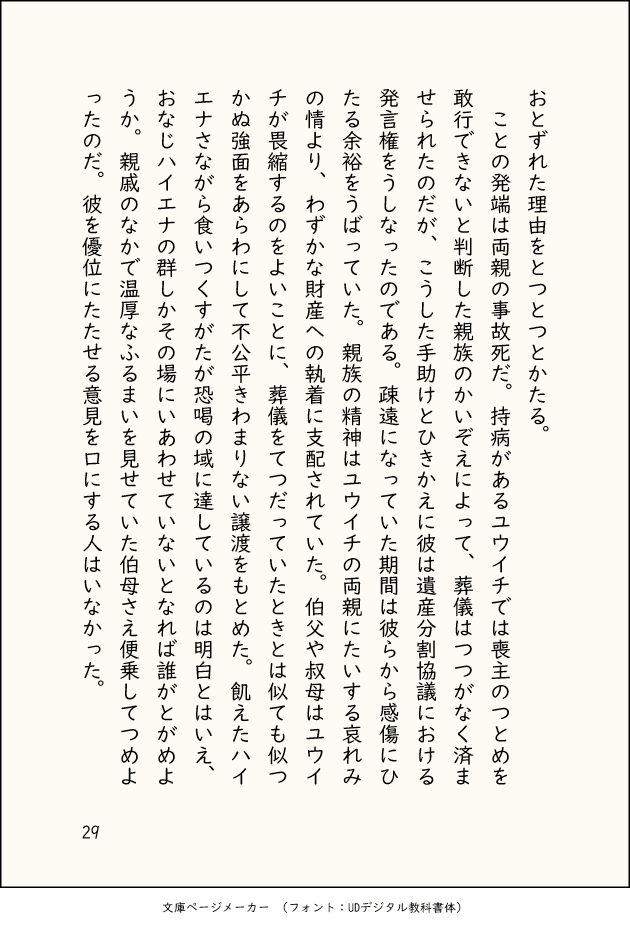
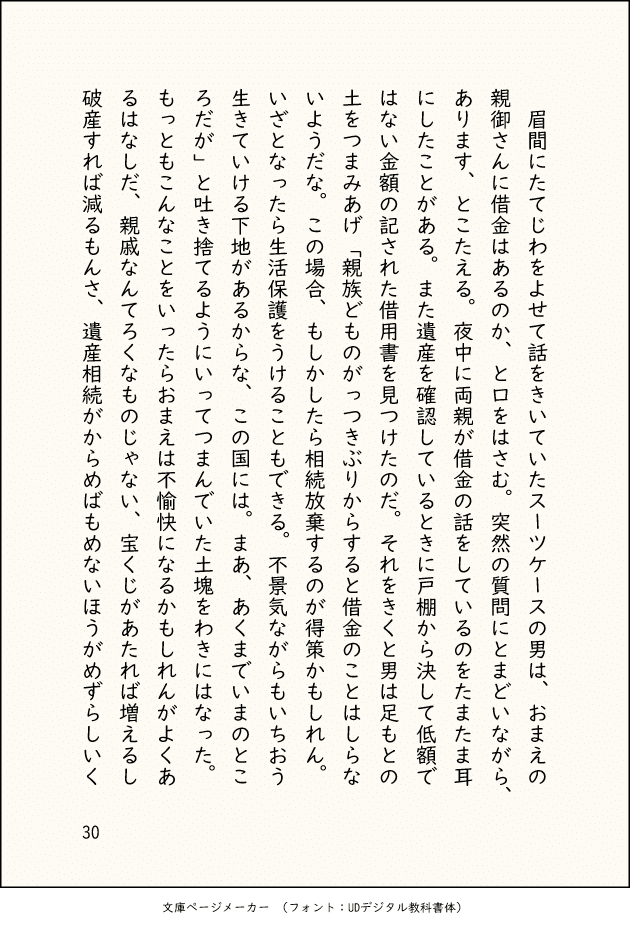
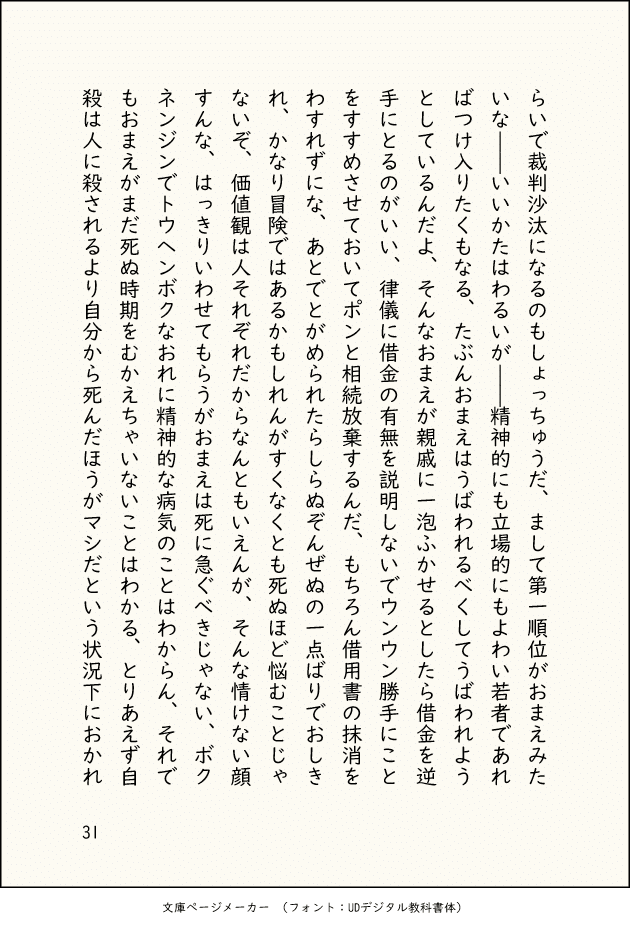
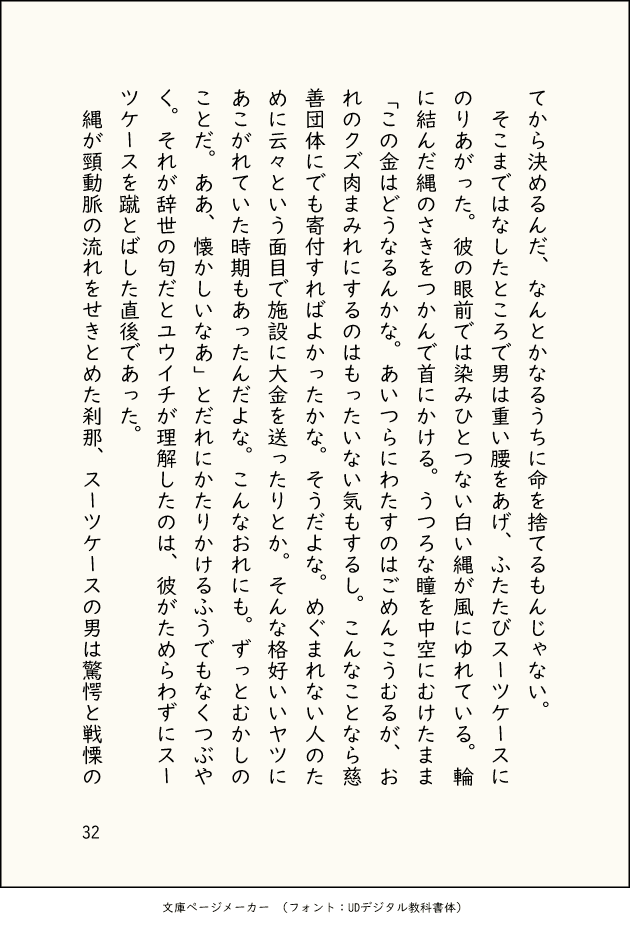
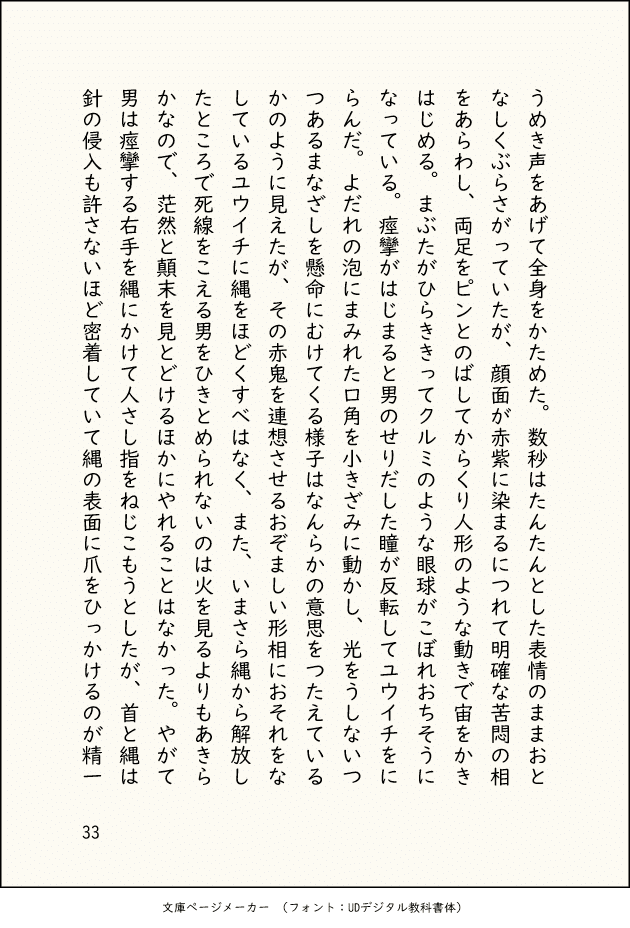
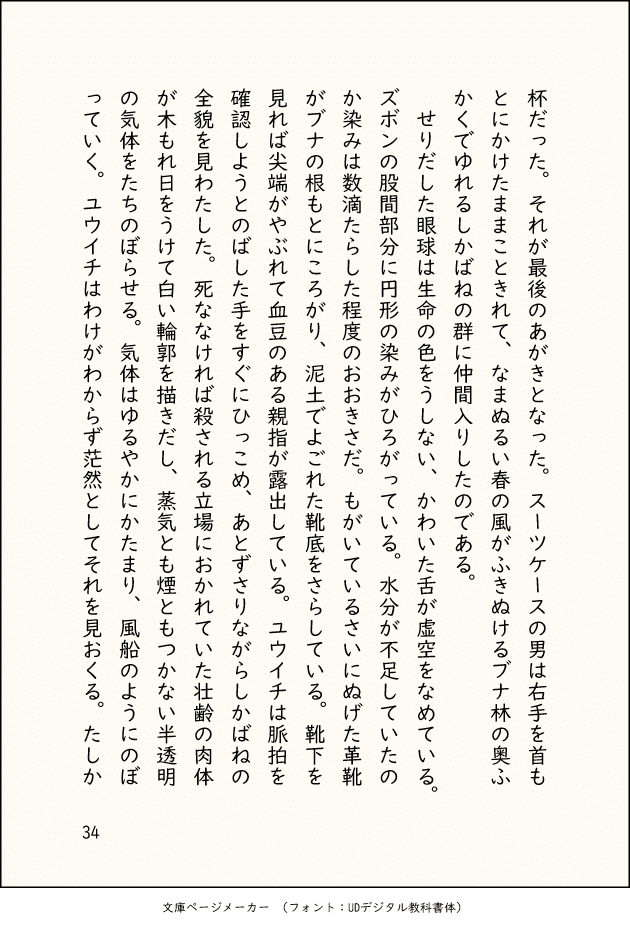
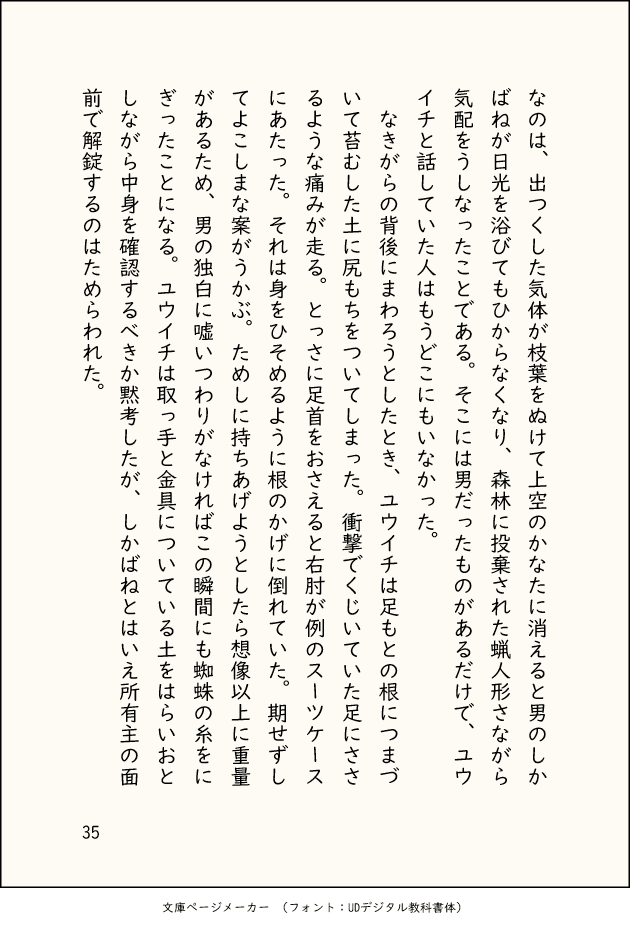

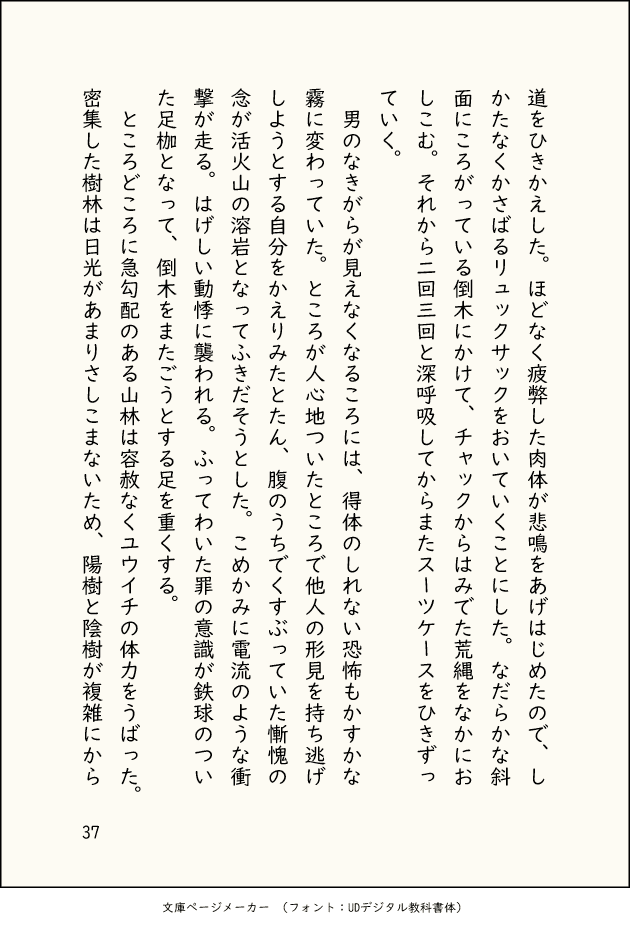
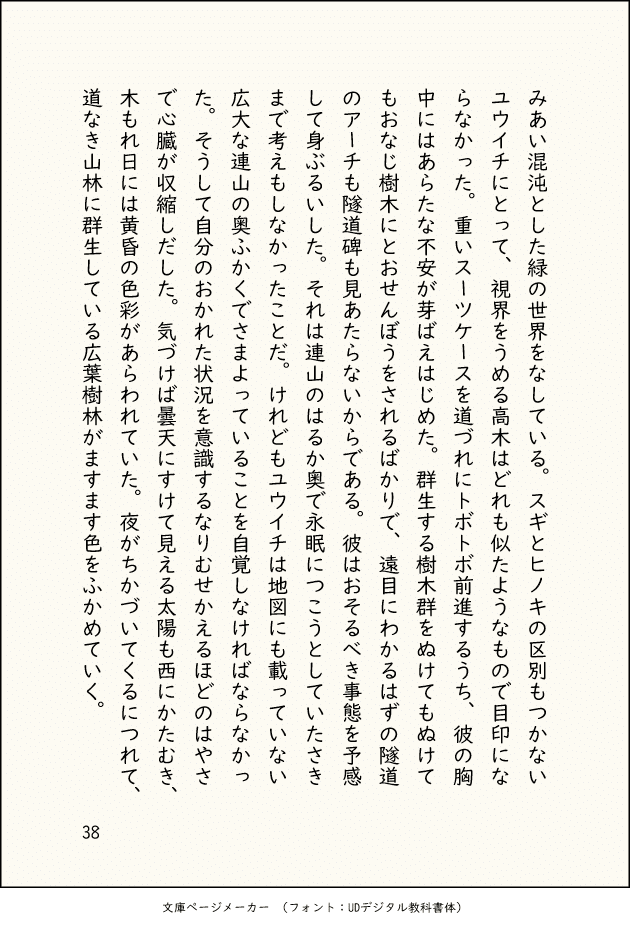
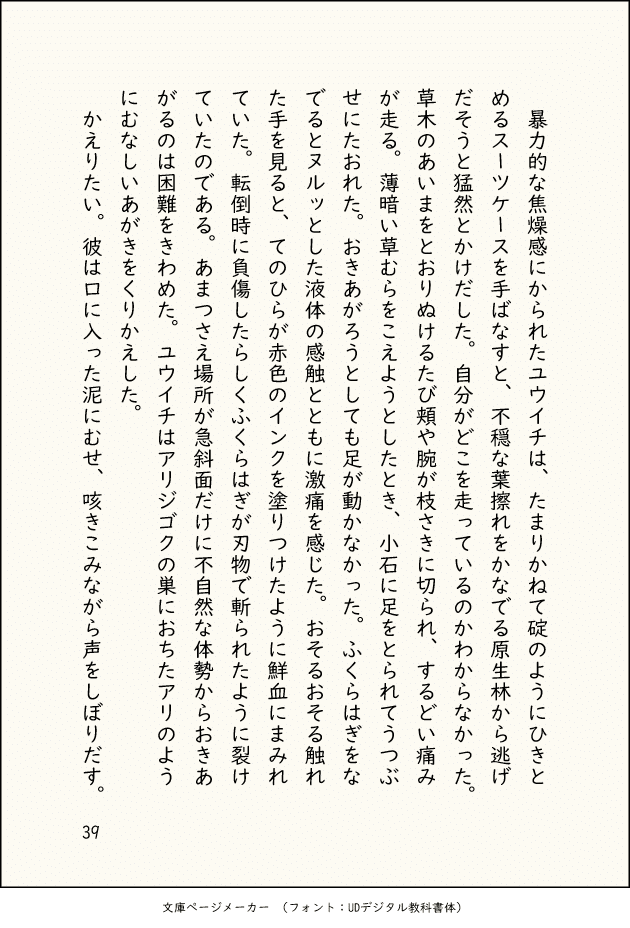
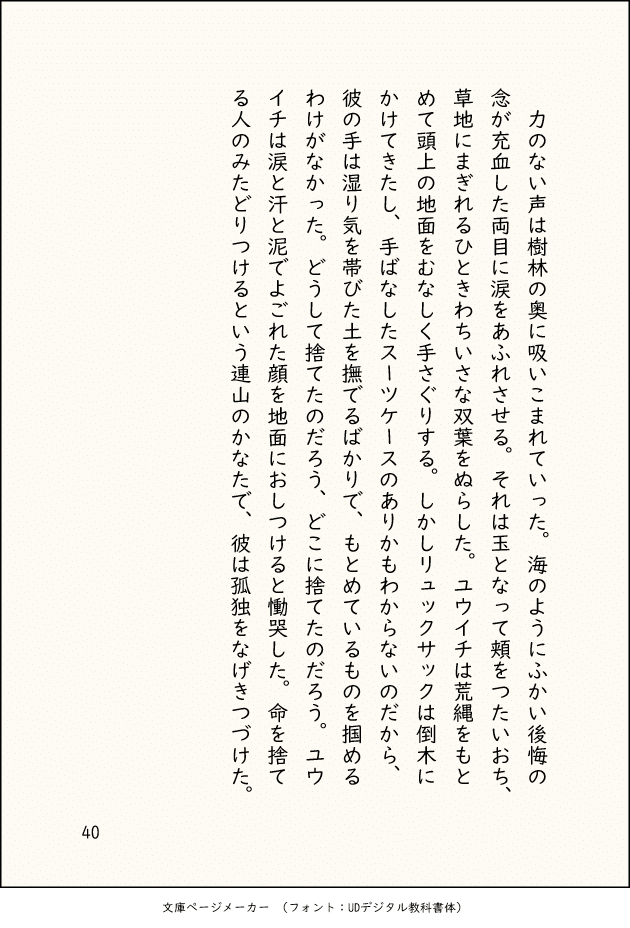
車両内には春さきの心地よい日光がさしている。ユウイチはいっこうにおさまらない動悸をおさえながら、寒気にたえかねてのそりのそりと窓に背中をおしつけた。むかいの席には不機嫌そうにうつむいている初老の男がすわっている。腕組みをしてまたをひろげているので、肥満気味の腹部がはっきりとうかがえた。あたたかなユウイチの座席にたいして初老の男の座席は日光があたらなくて、視覚的にもさむざむしかった。現に腕組みをする手は暖をもとめて薄地のセーターをしっかりつかんでいる。ちかくのドアに大学生ふうの男がよりかかってスマートフォンを操作している。彼もまた日かげのなかにいた。ユウイチとおなじ座席にすわるスーツすがたの若い女は背筋をのばして文庫本に視線をおとしている。彼女の長い髪が太陽の光に照らされて茶色がかった輝きをはなつ。スーツの女はどの乗客から距離をおき、いかなる事情があろうとも干渉はゆるさないといわんばかりにわき目もふらず本の世界に没頭している。ユウイチは彼らの目にうつる自分の風貌を想像して、たちまちどんよりとした不安にかられる。乗客たちが不自然なほどはなれているのは暇をつぶすためでなければ個人的な時間を有効活用するためでもなく、もしかしたら後頭部に寝癖をつけたみすぼらしい社会不適合者にちかよりたくないからではないか、そうした自虐的な疑念も顔をのぞかせた。
緊張のあまり胃液がごぼごぼと泡をたてて逆流してくる。焼けるような喉の痛みとともにすっぱい味が口中にひろがる。毛根や指さきにじっとりとした脂汗がうく。こぶしにちからが入らず、体温をうしなった両足が小きざみにふるえている。電車が路線をかけていなければ窓をあけはなって、とびだしたかった。けれども四肢の自由をうばわれているユウイチにそうした大胆なまねができるはずもなく、つぎの駅に到着するまでいたたまれない気持ちを懸命におさえるほかなかった。
各駅停車はサビくさい擦過音を鳴らしながらブレーキをかける。ホームにとまり、数える程度の乗客を吐きだし、あたらしい乗客を飲みこめるだけ飲みこむと、ふたたび面倒くさそうに車輪をまわしはじめる。
まよわず優先席に腰をおろしたものがいた。うしろになでつけた髪から整髪料のにおいをただよわせる柄のわるい男で、しわのよった黒色のスーツごしに筋骨隆々とした体格がうかがえた。もうひとり気のよわそうな優男が乗車していたが、彼はいかつい男のそばにいたくなかったのかドアがしまるまで車両内を見まわしていたと思うと、そそくさと隣接する車両に移動してしまった。ユウイチとしてはくさい整髪料のにおいをまきちらしている横暴な男とふたりだけですごしたくなかったが、へたに自分も車両をうつろうとして因縁をつけられたらたまったものではないので、逃げるに逃げられなくなって硬直したままつぎの駅を待たなければならなかった。そのあいだ彼はひたすら息苦しさにたえた。車内アナウンスが流れると男が優先席からたちあがり、じろりとユウイチをひとにらみしてからドアのまえで仁王だちになる。ドアがひらいたとたんカラスのように「カーッ」と喉を鳴らし、ホームの点字ブロックに痰をとばしてから大またで閑散とした改札口に歩き去った。そこでようやくユウイチは安堵のため息をついた。彼の胸中にはとっくに各駅停車をえらんだことへの後悔が芽ばえていた。とはいえ疲弊した彼にいまから予定をかえて急行列車にのりかえるだけの気力はなく、どのみち目的地はちかいから律儀に各駅をめぐってやろうではないかと投げやり気味に席にもたれた。
ユウイチはこうして県内の連山を目ざしていた。この連山は登山の名所として愛好家に親しまれている。そのため連休中はおとずれる人で混雑する懸念もあるが、もとより観光で山のぼりするわけではなく、山道の途中から地図に記載されていない場所に移動するつもりなのだから神経質になるほどではないと判断した。弁当のかわりに丈夫な荒縄を収納したリュックサックを背負い、意気揚々と山道をのぼる登山客についていく自分のすがたを想像すると羞恥の炎に焼かれる心地になる。
そこからふた駅をすぎたとき、煩悶しつづけるユウイチをさらなる窮地に追いこむ事件がおこった。陽気な中国人の男三人がとなりにならび、杖をつく厳格そうな老人が正面を陣どったのだ。老人は座席があいているのにすわろうとせず、発車してからもユウイチの目と鼻のさきでうろついていた。行動の意図が読めないため席をゆずるべきか否か、強制的に眺めさせられている身としては懊悩せずにいられない。そのあいだもとなりでは北京語によるにぎやかな会話がかわされていた。ききなれない異国の言語は彼の小心を刺激して、さらなる混乱のうずにおとしいれた。厄介なことにつぎの駅でのりこんできた白髪と禿頭の男ふたりが「足を踏んだ」「いいや踏んでいない」と口論をはじめたせいで、車両内に険悪な雰囲気が満ちたのである。見ろ見ろあんたの靴底があとになっているだろう、それはあんたの靴がきたないだけじゃないか、そうしていいのがればかりしているからバチがあたって白髪になるんだ、白くなる髪もないあんたにいわれたくない。やがて矛さきは近くにいたユウイチにむけられた。そこのあんたもこいつがおれの足を踏んだのを見ただろう、おれがふんでいないことを証言してくれ、どうして黙っているんだ、としより同士の喧嘩がそんなにみていておもしろいのか、このうるさいやつをはやく黙らせろ、はっきりしない若造め、どうせ腹のなかではおれたちをわらっているんだろう、靴あとをちゃんと見ろこのやろう。すっかり頭に血がのぼった禿頭は口角泡をとばしながらユウイチの頭をつかみ、はいている高齢者用の靴に注目させようとひきよせた。紺色のつまさきにかすかなよごれがついている。顔をちかづけて凝視しなければ認識できない程度のよごれ。それは彼にとってささいな事故の痕跡にすぎなかった。これのため見しらぬ人に頭をわしづかみされるという辛酸をなめるはめになったのかと悲哀にかられる。
救済の手をさしのべたのはとなりの車両にいた小ぶとりの主婦だった。不穏な空気を察した彼女は、まったく臆することなく対峙する両者のあいだに割って入るとにらみあうふたりをしかりつけたのである。突然の叱責に虚をつかれたふたりはようやく平静をとりもどし、気まずそうに頭をさげあうと今度は弁解をはじめた。たしかに白髪の男は足を踏んでいたのだ。ところが最初は素直に謝罪するつもりでいたのに、禿頭の男に激昂されたのが癪で抵抗したくなったという。いっぽう禿頭の男は普段ならばわらってすませられるところ、このときは虫のいどころがわるくてうっかり声を荒げてしまい、ひっこみがつかなくなったという。
「あるとも」例の杖をつく老人がつぶやく。「ん。わたしも踏んだし踏まれたもんだ」
老人は過去に踏まれた話をブツブツかたりだすと、杖で床をならしならし優先席のほうに歩き去った。束の間静寂がおとずれる。やがて電車が駅に到着して、白髪も禿頭も主婦もそろってホームにおりた。中国人たちもあとにつづいた。グループでもっとも長身の男がすれちがいざまにユウイチの肩をたたく。それは彼なりのはげましであった。優先席を見るといつの間に移動したのか例の老人のすがたも消えていた。まるではじめから存在しなかったかのように、そこにはしわひとつないあずき色の座席がならんでいた。あたりにベルがなり響き、アナウンスが流れる。しまるドアにご注意ください。ドアがしまるとエンジン音も雑踏もカラスの声も遮断され、ひとり残されたユウイチは無機質な客車にとじこめられた。乗車して以来自分だけになるのははじめてだ。かすかに耳なりがする。
さきの騒動がこたえて弱気の虫にとりつかれたのか、とおい世界に捨てられたような孤独感に胸をうがたれる。ほかの乗客たちに混ざって下車しなくてよかったのだろうか、もしかしたら自分はおりるべきだったのではないか、と不安になった。けれども彼が救いをもとめてふりかえったとき、すでに嵐を巻きおこした乗客たちはしきつめられた赤茶色の砂利をへだてた遠方の地にとけていた。ユウイチの胸にできた空洞を喪失感が花びえの風となってふきぬける。そのあなにかぶせる蓋を持たない彼はふるえる心を両手でむなしくおさえることしかできなかった。
閑散とした各駅停車はユウイチをのせたまま北東を目ざした。窓をよぎる風景から住宅の輪郭が減っていき、いよいよ連山にちかづいていると実感する。事前にしらべたとおりなら駅でおりたのちしばらく路線バスに乗りこみ、下車後に数十分も歩けば心霊スポットとして一部にしられる隧道にたどりつく。彼自身は霊魂の存在を信じていないし、信じるつもりもないため肝だめしに興味はなかったが、ものずきな人たちを畏怖させる歴史のきざまれた隧道には心ならずもひきつけられた。駅の名がアナウンスされたとき、なかば口実をもうける調子で「心霊スポットに踏みこむのではなく、重要文化財にも指定されている名所を鑑賞するためだ」と自分にいいきかせてリュックサックをせおった。そしてホームにおりたとたん足がおぼつかなくなり、たちくらみにでも見舞われたかと動揺してベンチにすわった。しらないうちに走行中の震動に体がなじんでいたようで、堅固なコンクリートの床におりたらかえって体がとまどったらしい。思いおこせば電車に乗ったのは十数年ぶりだ。ひきこもり生活をつづけることでユウイチの順応性は極端によわまっていた。彼は脆弱化した自分の体に当惑せずにいられなかった。ところどころ赤色のペンキがはげているベンチにもたれかかり、屋根をささえる鉄骨の列をながめる。鉄骨のいっかくに小枝や落葉がこんもりとつまれており、そこに白と黒の網目模様のハトがうずくまっていた。風雨をしのげるし、カラスなどの外敵に狙われにくい梁は巣づくりにうってつけだ。もしかすると駅員もハトに気をつかい見て見ぬふりをきめこんでいるのかもしれない。世知がらい世のなかに息づくかすかなぬくもりに触れた気がして、ユウイチはすこしだけ勇気づけられた。彼はベンチから腰をあげて、めまいがおさまっているのをたしかめてから改札口にむかった。
バスにのるのも十数年ぶりである。緊張するあまり運賃箱に小銭を入れようとして床におとし、奥の座席に腰をおろすまで何度もつまづいた。肩からすべりおちたリュックサックを両手でかかえて、おちつきなく座席にぶつかりながら後部を目ざすユウイチを、付近の乗客たちは怪訝そうにふりかえる。それは彼が忌み嫌うたぐいの視線にほかならない。チクチクとささる視線の痛みにたえるため、バスが発車したあとも歯を食い縛らなければならなかった。しかも人を遠ざけたいという願望もうちくだかれた。となりにでっぷりとこえた角刈りの中年が無遠慮にすわったと思うと、単身でリュックサックを持ちはこぶユウイチに興をひかれたのか「ひとりで旅行かい」とたずねてきた。無意識的にこぶしをかたくにぎりしめる。緊張するたび彼はそうして拳骨をつくった。それでも黙っているわけにもいかず、正直に旅行ですと言葉すくなにこたえる。へえそうなのか、と中年の男が感心の色をうかべる。そして今度は目的地をしりたがった。彼は顔をしかめることで干渉をこばんだが、相手は他人の顔色に無頓着でまったく察しない。そうか登山しに連山にいくところだったのか、おれも若いころはよく弁当を大量に持って挑戦したもんだ、でかいおにぎりに梅や鮭を入れたやつをいくつも用意してな、最近はとしのせいかすっかり山のぼりする体力がなくなっちまった、あんたははじめてのぼるのか、若いうちは家にこもっていないでどんどん冒険しないといけない、あそこどんな岳があるかしっているか、人の名前みたいな呼び名があるけれど、むかしそこに住んでいた天狗が由来なんだ、そうかしらなかったか、どのコースを選ぶつもりだ、おれにいわせれば東には古いトンネルがあるからおもむきを味わいたいならあちらをおすすめする、その隧道はしっているか、なんだしっているのか、あの辺は幽霊がでるといわれていておれもむかしわるい仲間をつれて肝だめしとかしたことがある、夜に自転車でとおりぬけるのは度胸がいるんだぞ、さすが歴史ある山脈というだけあるな、題名はわすれたけれど有名な小説の舞台にもなっているんだ、ひくいところにはイヌガシやカゴノキやスダジイがはえているのにたかくなるにつれてスズタケやブナやモミと木の種類が変わってくるのがまたおもしろくてな。えんえんと能書きをならびたてる中年にたいする嫌悪はふかまるばかりで、儀礼的に相手をするのもいやになったユウイチは窓のそとを向いたままはなしを聞くそぶりも見せなかった。ところが中年はかたるのみではあきたらず、はなしをひきだそうと執拗にたずねるので無視を決めこむのもむずかしかった。まさか登山についてくる気をおこさないだろうかとおそれたが、さすがに彼にも用事があるようで、バス停留所に到着してユウイチが腰をあげたさい小声で「よい旅を」と声をかけられたときは胸をなでおろした。
こうしてユウイチはバスが残した濃厚な排気ガスにむせながら隧道のあるほうへ歩きだした。足の筋肉が悲鳴をあげているし、靴のなかで指さきがうめいている。山道をのぼるまえにして体力はそがれていた。重おもしい足どりで林道に入り、橋をぬけたさきに待ちかまえる街道と歩道の分岐点にさしかかる。彼は歩道をえらんで隧道の案内表示が見えるまでもくもくと足をうごかした。林を侵蝕する道が左右にまがりくねっている。連休中のせいか思いのほかおおくの乗用車が彼を追いこして山の奥に消えていく。そのたび排気ガスを吸いってしまい、胸が苦しくなるほど咳こむ。ほそい橋をわたり、草むらにたたずむ碑を横目に坂をのぼりつづける。数組の登山客とすれちがった。単独で行動する重装備の若者、談笑しながら山腹にむかう家族づれ、手をつないでデートを楽しむ男女。だれもが街道脇に鎮座する碑のもとによってはスマートフォンやデジタルカメラで撮影して、そぞろ歩くようなゆったりとした足どりで山道をのぼっていく。ユウイチはそうした登山客を見かけるたびたちどまり、ならんで歩くことのないよう神経をつかった。
随所に木もれ日がさしている山道のさきに隧道の入口を発見すると、ユウイチは息をととのえようと路傍にしゃがんだ。肩に食いこんでいたリュックサックの紐をずらすと、解放感とともに鈍痛がおしよせて顔をしかめる。ゆるやかな傾斜とはいえ運動不足の彼にはやさしからぬ茨の道だった。
切石づみの隧道は日かげのなかで黒灰色のすがたをさらしている。山肌にうがたれた穴の奥から、微風にともなって廃退の香りがただよってくる。人をとおざけるようにもさそうようにも感じられる隧道の息吹。それは全長四百メートル以上さきからはこばれてきた異世界の空気だ。かたわらには隧道碑が設けられており、明治時代に貫通した隧道の歴史と威厳を強調する文章が記されている。路傍の石をもてあそびながら眼前のおおあなをながめてみると、積年の雨で色あせた切石、びっしりと苔におおわれた笠石や帯石、右から左に書かれた題字に隔世の感をおぼえる。切石巻工法によってうみだされたアーチのかなたに橙色の照明がひとつふたつとうかんでいる。その様子が闇夜をさまよう人魂を彷彿させた。ユウイチは見えざる手にひかれるようにきしむ体に鞭うって入坑する。ゆっくり隧道に入ったとたん空気の変化に気づいた。ながきにわたり封じこめられていた冷風に触れたような、まとわりつく重苦しい空気だ。そうした違和感に気おされて無意識的にしのび足になる。それでも隧道内には靴底と湿った地面のはざまでかなでられる擦過音が反響した。地面に残っているタイヤのあとが隧道のなかほどで消えると、孤独感がなおさらつよまった。左右交互にとりつけられた照明を頼りにはるかかなたに見えるちいさな光にむかう彼の脳裏には、両親の顔がモノクローム映像のようにあわく点滅していた。穏和な笑顔をたたえる母、やや神経質そうに口を結ぶ父、それはふたりを象徴する表情である。いまなら母の微笑は懊悩や煩悶を押し殺したしるしで、父のしかめ面は噛み殺したしるしなのだとわかる。ふたりとも息子のしらないところで海のようにふかい苦しみをかかえて生きていた。そしてとうとう解放される機会に恵まれないまま交通事故による不遇の死を遂げてしまった。残されたものは長年にわたり心の病に悩まされている息子とがめつい親戚一同、あとはなけなしの遺産だった。
腕時計も携帯電話も自宅においてきたので、隧道に入ってどれだけの時間が経過したのかをしるすべはなかった。出口がとおい。さきにある光はとおざかりはしなくても、歩いても歩いても接近するように見えなかった。それが錯覚だとわかっていても不安はぬぐえない。いつしか自然と足をしのばせるのをやめ、慌ただしい足音を響かせながら照明の群を追いこしていった。はねかえる足音は三人分にも四人分にもきこえた。
去るものを追跡するように、あるいは追跡者に追われるように、心臓や肺が悲鳴をあげるのもかまわずに走りつづけて永遠にたどりつけないかと思われた坑門に達する。ところが隧道をぬけたユウイチは唖然としてたちどまった。本来なら現道につながる旧国道にでるところ、似ても似つかない原生林のなかにでてしまったのである。おどろきのあまりアーチのしたまであとずさり、見みひらいたまなこをせわしなく動かした。大小さまざまの倒木がそこかしこにころがっていて、整地されていない凸凹の地面は絨毯をしいたように緑の雑草でおおわれている。登録有形文化財の碑もなければ隧道の歴史を記した石碑もない。隧道は一方通行なので道をまちがえることはありえない。彼はおかれた状況を把握しかねてただただうろたえた。
おそるおそる鬱蒼とした広葉樹林に踏みこんでみると、さまざまな角度にのびているクスノキ科の高木がゆく手をさえぎり、ときおり湾曲した根で彼の足をからめとる。見わたせば雑草と苔をまとったふとい根が地をはっている。道と呼べる足場がないためユウイチは高木にしがみつき、そこから隣の高木にうつるようにして樹林の奥に進んでいった。落葉と小枝の山に足をとられる。倒木をのりこえようとして苔ですべりおちる。木々のざわめきにおどろいてあつみのある幹に背中をうつ。そうこうするうちに彼の体は傷だらけになった。太陽の光をうけていない白い肌はやわらかく、若葉や枝の尖端に触れるたびうっすらと血の筋をあらわした。しかし、無心で険しい原生林の奥ふかくを目ざしているせいか顔や腕が傷つけられたくらいでは気づかなかった。
観光客が気楽におとずれる場所でないのはたしかだった。それでもユウイチは隧道にもどろうとしなかった。たびかさなる転倒でシャツもジーンズも泥にまみれ、リュックサックに小さなほころびが生じる。なによりも彼自身が沼からあがったようなひどいありさまであった。花粉や埃の刺激により目が充血している。頬から顎にかけて流れおちた涙に土や草のきれはしが付着し、隧道をぬけるまえとは別人の相貌となっていた。
極度の疲労をおぼえ、うねる根をまたぐのも億劫になる。ちかくの幹によりかかって息を入れる。彼の嗅覚が木々のあいまをふきぬける風にのるかすかな異臭に反応したのは深呼吸をしている最中だった。いままで草木と泥土が発するむせっぽいにおいしかただよっていなかったのに、突然あきらかに異質な臭気を嗅ぎとったので怪訝に思わずにいられなかった。それだけ自然の芳香になじんでいたともいえる。すくなからず自分自身が自然にとけはじめているのを感じつつ、見えざる糸にひきよせられるように異臭をたどる。彼の瞳には線香の煙よろしく空気中に模様を描く臭気がうかがえた。
においはブナのたちならぶ比較的なだらかな林間からただよっていた。ひややかな風にあおられた枝葉が不穏な音色をかなで、訝しげに見あげているユウイチの耳をなでる。妙にゾクリとした。寒いのではなく気味がわるくて身ぶるいしたのだ。このブナ林を吹き抜ける風と顔をしかめるほどの悪臭はただならぬ恐怖をわかせた。おなじ樹林でも隧道付近とは空気からしてことなる。彼はおぞましい異物がブナ林のそこかしこに存在することを予感した。なにも見つけないうちにひきかえそうと思いつつ、抑制しきれない好奇心に突き動かされて悪臭のでどころを探しまわろうとする。彼は自分に檄をとばす。はやくもどれ、こんなところにいたらいけない、あれを見つけてしまうまえに目をとじてかけもどるんだ。しかし、必死の抵抗もむなしく彼はもう悪臭の元凶を見つけていた。見なかったことにするにはちかすぎる距離で、はっきり目に焼きつけてしまった。彼はブナのひときわふとい枝にかかる縄と、そこにぶらさがる肉体を認めなければならなかった。
腐臭をはなつしかばねの首にはナイロンの紐が何重にも巻かれていた。肉のくずれおちた顔面は赤茶色の液にまみれていて、ぽっかりあいた口から数本の歯がのぞいている。空洞となった眼孔は鼻骨や口内でうごめくウジの巣窟である。ボロボロのシャツのすきまから見える腹部でもまるまるとふとったウジがコロニーを形成している。足もとの草地はこぼれた体液で赤紫に染まり、脱げおちた革靴を食虫植物のようにガッシリとつかんだまま凝固し、アンモニアをふくむ強烈な刺激臭をたちのぼらせている。残飯や魚の内臓や傷んだ野菜などをはるかにうわまわる悪臭。ユウイチは吐き気をもよおして鼻をおさえたが、胃からせりあがる消化液をせきとめるには対応がおそすぎた。とうとう黄土色の吐瀉物を赤紫色の草地にまきちらしてしまう。むせながらしかばねからはなれると、ちかくのブナに背をうちつけた。反射的にふりかえった彼の視界に白骨化した死骸がとびこむ。その骨格のゆがんだ上半身はぶつかった衝撃でかすかにゆれている。風雨にさらされるうちにもろくなったのか、下半身の骨はあとかたもなくくずれて周辺にちらばっていた。
平静をうしなってへたりこんだユウイチだが、唐突にウジや白骨がせまってくる恐怖にかられると四つんばいのままブナをはなれようとした。ところが林の奥に逃げた彼を待ちかまえていたのは、さきに勝るとも劣らないグロテスクな死骸の山だった。背のひくいブナの枝に縄を結び、前傾姿勢で首に食いこませてこときれている人。両足が枝にひっかかってカエルのような体勢で絶命している人。なかには紺色のランドセルを背負っている小柄ななきがらまであった。いずれも腐敗が進んでいるため性別も年齢もわからない。そして、共通してすさまじい悪臭をただよわせていた。虚脱感に襲われたユウイチがふたたび嘔吐しようと頭をたれたとき、肩にかけていたリュックサックが衣ずれの音をたてながらすべりおち、湿気をふくんで粘着性をおびた土にころがった。こまかな土の粒がついたチャックのすきまから白い荒縄がのぞく。視界のはしにとらえた荒縄からさきの白骨死体を連想すると、消化液をはきつくした胃袋が痙攣をおこして腹部がちぎれるかと思うほどの苦痛にさいなまれ、ユウイチは断末魔のような嗚咽をもらし、土や落葉にまみれながらのたうちまわった。
腹部の激痛がおさまってからユウイチは茫然と遺骸の群をながめていた。相変わらず鼻がまがりそうではあるが、視覚的にも嗅覚的にも順応のきざしがあらわれてきて、拒絶反応をしめしながらもパニック発作を抑制するだけの余裕はうまれた。
うつろな心地で一枚の広葉をひろいあげる。すると彼の耳がかすかな声をとらえた。葉擦れにつつまれた原生林ではじめて耳にした人の声だ。当初は幻聴かもしれないと半信半疑だった。けれどもたしかに語りかけるような、あるいは読みあげるような声が吹き抜ける風に乗ってとぎれとぎれ聞こえる。ユウイチは薄暗いブナ林の奥に呼びかけてみたが、渇いた舌がうまく動かなくてまともに発声できなかった。彼は一抹の期待を胸に秘め、筋肉痛や捻挫で思うように動かない足を叱咤しながら、声の出どころを目ざしてリュックサックをひきずっていく。
空が隠れるほど密集した樹林のなか、ひときわ年輪をかさねたブナの根もとに背広すがたの男がたっていた。頭上の枝からたれさがっている縄の尖端を輪に結び、根で固定した黒いスーツケースを足場にしていた。彼の目的に気がつくと、とっさにユウイチはひきとめるように両手をふりまわし、いまにも首をくくろうとする男のもとにかけよった。彼は生きている人間と言葉をかわしたくてたまらなかった。呼びかけに気づいてふりかえった男は三十代のサラリーマンといった風体ながら、土気色のやつれた顔だちに不吉なかげをにじませていた。人によびとめられるとは予想していなかったようで、縄をつかんだまま「だれだ」と鬼気せまる語調で叫んだ。ユウイチは男の怒声にひるみかけた。けれども必死に首をふりながら男をスーツケースのうえからひきおろそうとする。かつての彼にはとれなかった大胆な行動ではあるが、それだけスーツケースの男との邂逅を格別のめぐりあわせと感じとったのである。彼の気迫におされたのか男はほとんど抵抗せず、ひっぱられるままにスーツケースからおろされると精根つきたように足もとの根にへたりこむ。七三わけの髪がパイナップルのへたのように乱れ、こけた頬に無精髭がびっしりとはびこり、土埃や嘔吐物で赤茶けた背広とYシャツがすえたにおいをたたせている。ユウイチはその漂流者然としたくたびれた格好を目のあたりにし、短くても二日以上は樹林をさまよっているとおしはかった。
スーツケースの男は両手で頭をかかえこみ、頼むからとめないでくれ、と悲痛な声で嘆願する。おまえもこの森林を歩きまわったならしっているだろう、ここにはなぜか自殺志願者ばかり集まるんだ、みんな口をそろえて死ぬ死ぬいう、まよいこんでから死ぬ気をおこしたヤツとはあったことがない、連中は最初から死ぬつもりで山にきたんだ、きっとおまえもそうなんだろう、それは指をくわえて死なせたわけではないさ、おれだって思いとどまらせようと自分なりにがんばった、だがだれひとりとして説得できないまま無駄に終わったよ、あたりまえだ、このおれ自身が死ぬ気でいるくせにどの口で死ぬなとか手前勝手なことがいえるんだ、それでもまだ小学校にかよっているような子どもが死ぬのは見すごせなくてたくさんはなしあった、ひと晩かけてはなしつづけた、それなのにおれがまどろんでいるあいだにつめたくなっていた、だれにどうこの無力感をつたえたらいいんだ、本気で死のうとしているやつをとめるのがどれだけむずかしいのか世間の連中に理解させることができるのか。興奮してまくしたてる男をなだめようと、ユウイチは彼のふるえる両肩をかるくたたきながら、さきに見かけたランドセルを背負った子どもがそうなのかたずねる。その問いに男がうなずく。すでに腐敗がはじまっているから明日明後日には直視できないすがたになっているだろう、だれも処理しなければあっという間にハエの産卵場になる、ブナ林の入口でくくった男はウジがわくのがはやかった、ふとっていていかにも栄養価がたかそうだったからな、どのみちおそかれはやかれ死ねば土にかえるんだ、それはおれもおなじだしおまえもおなじさ、ところできみはどうして観光客が足をはこぶような山で死のうと思ったんだ、おれのほうは簡単にいえば仕事がらみのいざこざに巻きこまれてね、そのさいにまずいことをやらかして逃亡生活をしいられたんだ、詳細は勘弁してくれ、世間さまがお許しにならないような不始末を触れまわる趣味はないからな、ほらこのスーツケースだ、なかには現金にかえたなけなしの財産が入っている、なんのために持ちだしたのか自分でもよくわからない、ただここでも現金や個人的な宝物を持ってきている人を何人か見かけたよ、あの世まで持っていけるとはかぎらないのにおかしなはなしだと思うがな。おい変な顔をしてどうした、おれが嘘ついているとでもいうのか。
ユウイチは即座に否定した。真あたらしい荒縄の入ったリュックサックを背負っている彼にとって、スーツケースの男が堅気か否かなどたいした問題ではなかった。逃亡生活で疲弊した男はあくまで会話をかわせる貴重な生者にほかならない。すこしでも対話をつづけるためユウイチは連山におとずれた理由をとつとつとかたる。
ことの発端は両親の事故死だ。持病があるユウイチでは喪主のつとめを敢行できないと判断した親族のかいぞえによって、葬儀はつつがなく済ませられたのだが、こうした手助けとひきかえに彼は遺産分割協議における発言権をうしなったのである。疎遠になっていた期間は彼らから感傷にひたる余裕をうばっていた。親族の精神はユウイチの両親にたいする哀れみの情より、わずかな財産への執着に支配されていた。伯父や叔母はユウイチが畏縮するのをよいことに、葬儀をてつだっていたときとは似ても似つかぬ強面をあらわにして不公平きわまりない譲渡をもとめた。飢えたハイエナさながら食いつくすがたが恐喝の域に達しているのは明白とはいえ、おなじハイエナの群しかその場にいあわせていないとなれば誰がとがめようか。親戚のなかで温厚なふるまいを見せていた伯母さえ便乗してつめよったのだ。彼を優位にたたせる意見を口にする人はいなかった。
眉間にたてじわをよせて話をきいていたスーツケースの男は、おまえの親御さんに借金はあるのか、と口をはさむ。突然の質問にとまどいながら、あります、とこたえる。夜中に両親が借金の話をしているのをたまたま耳にしたことがある。また遺産を確認しているときに戸棚から決して低額ではない金額の記された借用書を見つけたのだ。それをきくと男は足もとの土をつまみあげ「親族どものがっつきぶりからすると借金のことはしらないようだな。この場合、もしかしたら相続放棄するのが得策かもしれん。いざとなったら生活保護をうけることもできる。不景気ながらもいちおう生きていける下地があるからな、この国には。まあ、あくまでいまのところだが」と吐き捨てるようにいってつまんでいた土塊をわきにはなった。もっともこんなことをいったらおまえは不愉快になるかもしれんがよくあるはなしだ、親戚なんてろくなものじゃない、宝くじがあたれば増えるし破産すれば減るもんさ、遺産相続がからめばもめないほうがめずらしいくらいで裁判沙汰になるのもしょっちゅうだ、まして第一順位がおまえみたいな——いいかたはわるいが——精神的にも立場的にもよわい若者であればつけ入りたくもなる、たぶんおまえはうばわれるべくしてうばわれようとしているんだよ、そんなおまえが親戚に一泡ふかせるとしたら借金を逆手にとるのがいい、律儀に借金の有無を説明しないでウンウン勝手にことをすすめさせておいてポンと相続放棄するんだ、もちろん借用書の抹消をわすれずにな、あとでとがめられたらしらぬぞんぜぬの一点ばりでおしきれ、かなり冒険ではあるかもしれんがすくなくとも死ぬほど悩むことじゃないぞ、価値観は人それぞれだからなんともいえんが、そんな情けない顔すんな、はっきりいわせてもらうがおまえは死に急ぐべきじゃない、ボクネンジンでトウヘンボクなおれに精神的な病気のことはわからん、それでもおまえがまだ死ぬ時期をむかえちゃいないことはわかる、とりあえず自殺は人に殺されるより自分から死んだほうがマシだという状況下におかれてから決めるんだ、なんとかなるうちに命を捨てるもんじゃない。
そこまではなしたところで男は重い腰をあげ、ふたたびスーツケースにのりあがった。彼の眼前では染みひとつない白い縄が風にゆれている。輪に結んだ縄のさきをつかんで首にかける。うつろな瞳を中空にむけたまま「この金はどうなるんかな。あいつらにわたすのはごめんこうむるが、おれのクズ肉まみれにするのはもったいない気もするし。こんなことなら慈善団体にでも寄付すればよかったかな。そうだよな。めぐまれない人のために云々という面目で施設に大金を送ったりとか。そんな格好いいヤツにあこがれていた時期もあったんだよな。こんなおれにも。ずっとむかしのことだ。ああ、懐かしいなあ」とだれにかたりかけるふうでもなくつぶやく。それが辞世の句だとユウイチが理解したのは、彼がためらわずにスーツケースを蹴とばした直後であった。
縄が頸動脈の流れをせきとめた刹那、スーツケースの男は驚愕と戦慄のうめき声をあげて全身をかためた。数秒はたんたんとした表情のままおとなしくぶらさがっていたが、顔面が赤紫に染まるにつれて明確な苦悶の相をあらわし、両足をピンとのばしてからくり人形のような動きで宙をかきはじめる。まぶたがひらききってクルミのような眼球がこぼれおちそうになっている。痙攣がはじまると男のせりだした瞳が反転してユウイチをにらんだ。よだれの泡にまみれた口角を小きざみに動かし、光をうしないつつあるまなざしを懸命にむけてくる様子はなんらかの意思をつたえているかのように見えたが、その赤鬼を連想させるおぞましい形相におそれをなしているユウイチに縄をほどくすべはなく、また、いまさら縄から解放したところで死線をこえる男をひきとめられないのは火を見るよりもあきらかなので、茫然と顛末を見とどけるほかにやれることはなかった。やがて男は痙攣する右手を縄にかけて人さし指をねじこもうとしたが、首と縄は針の侵入も許さないほど密着していて縄の表面に爪をひっかけるのが精一杯だった。それが最後のあがきとなった。スーツケースの男は右手を首もとにかけたままこときれて、なまぬるい春の風がふきぬけるブナ林の奥ふかくでゆれるしかばねの群に仲間入りしたのである。
せりだした眼球は生命の色をうしない、かわいた舌が虚空をなめている。ズボンの股間部分に円形の染みがひろがっている。水分が不足していたのか染みは数滴たらした程度のおおきさだ。もがいているさいにぬげた革靴がブナの根もとにころがり、泥土でよごれた靴底をさらしている。靴下を見れば尖端がやぶれて血豆のある親指が露出している。ユウイチは脈拍を確認しようとのばした手をすぐにひっこめ、あとずさりながらしかばねの全貌を見わたした。死ななければ殺される立場におかれていた壮齢の肉体が木もれ日をうけて白い輪郭を描きだし、蒸気とも煙ともつかない半透明の気体をたちのぼらせる。気体はゆるやかにかたまり、風船のようにのぼっていく。ユウイチはわけがわからず茫然としてそれを見おくる。たしかなのは、出つくした気体が枝葉をぬけて上空のかなたに消えると男のしかばねが日光を浴びてもひからなくなり、森林に投棄された蝋人形さながら気配をうしなったことである。そこには男だったものがあるだけで、ユウイチと話していた人はもうどこにもいなかった。
なきがらの背後にまわろうとしたとき、ユウイチは足もとの根につまづいて苔むした土に尻もちをついてしまった。衝撃でくじいていた足にささるような痛みが走る。とっさに足首をおさえると右肘が例のスーツケースにあたった。それは身をひそめるように根のかげに倒れていた。期せずしてよこしまな案がうかぶ。ためしに持ちあげようとしたら想像以上に重量があるため、男の独白に嘘いつわりがなければこの瞬間にも蜘蛛の糸をにぎったことになる。ユウイチは取っ手と金具についている土をはらいおとしながら中身を確認するべきか黙考したが、しかばねとはいえ所有主の面前で解錠するのはためらわれた。
ふたたびしかばねと対峙する。生きながら地獄の責め苦を味わったような表情はやわらぎ、苦痛にゆがんでいるなかにも生前の面影が認められた。だが瞳孔のひらいた漆黒のまなざしをうけていると、ふところにしのばせているわるだくみを見すかされたような気まずさがわいてきた。ばつのわるさにたえられなくて顔をそむける。そうして男とスーツケースを見くらべるあいだも、彼は男が首をくくる直前にはなった言葉を何度も思いかえしていた。
勘考の末、救世主になりたがっていた男の願望をかなえるという大義名分をたてたユウイチは、さきだつものを入手した興奮さめやらぬままずっしりとしたスーツケースをひきずりながらしかばねのもとをはなれた。はげしい擦過音をたてるたび、死者に追いかけられる予感にかられてふりかえる。けれどもたしかに生命の火がつきるところを目にしたのだと思いなおし、後方に意識をとらわれてはならないと自分を叱咤しながらもときた道をひきかえした。ほどなく疲弊した肉体が悲鳴をあげはじめたので、しかたなくかさばるリュックサックをおいていくことにした。なだらかな斜面にころがっている倒木にかけて、チャックからはみでた荒縄をなかにおしこむ。それから二回三回と深呼吸してからまたスーツケースをひきずっていく。
男のなきがらが見えなくなるころには、得体のしれない恐怖もかすかな霧に変わっていた。ところが人心地ついたところで他人の形見を持ち逃げしようとする自分をかえりみたとたん、腹のうちでくすぶっていた慚愧の念が活火山の溶岩となってふきだそうとした。こめかみに電流のような衝撃が走る。はげしい動悸に襲われる。ふってわいた罪の意識が鉄球のついた足枷となって、倒木をまたごうとする足を重くする。
ところどころに急勾配のある山林は容赦なくユウイチの体力をうばった。密集した樹林は日光があまりさしこまないため、陽樹と陰樹が複雑にからみあい混沌とした緑の世界をなしている。スギとヒノキの区別もつかないユウイチにとって、視界をうめる高木はどれも似たようなもので目印にならなかった。重いスーツケースを道づれにトボトボ前進するうち、彼の胸中にはあらたな不安が芽ばえはじめた。群生する樹木群をぬけてもぬけてもおなじ樹木にとおせんぼうをされるばかりで、遠目にわかるはずの隧道のアーチも隧道碑も見あたらないからである。彼はおそるべき事態を予感して身ぶるいした。それは連山のはるか奥で永眠につこうとしていたさきまで考えもしなかったことだ。けれどもユウイチは地図にも載っていない広大な連山の奥ふかくでさまよっていることを自覚しなければならなかった。そうして自分のおかれた状況を意識するなりむせかえるほどのはやさで心臓が収縮しだした。気づけば曇天にすけて見える太陽も西にかたむき、木もれ日には黄昏の色彩があらわれていた。夜がちかづいてくるにつれて、道なき山林に群生している広葉樹林がますます色をふかめていく。
暴力的な焦燥感にかられたユウイチは、たまりかねて碇のようにひきとめるスーツケースを手ばなすと、不穏な葉擦れをかなでる原生林から逃げだそうと猛然とかけだした。自分がどこを走っているのかわからなかった。草木のあいまをとおりぬけるたび頬や腕が枝さきに切られ、するどい痛みが走る。薄暗い草むらをこえようとしたとき、小石に足をとられてうつぶせにたおれた。おきあがろうとしても足が動かなかった。ふくらはぎをなでるとヌルッとした液体の感触とともに激痛を感じた。おそるおそる触れた手を見ると、てのひらが赤色のインクを塗りつけたように鮮血にまみれていた。転倒時に負傷したらしくふくらはぎが刃物で斬られたように裂けていたのである。あまつさえ場所が急斜面だけに不自然な体勢からおきあがるのは困難をきわめた。ユウイチはアリジゴクの巣におちたアリのようにむなしいあがきをくりかえした。
かえりたい。彼は口に入った泥にむせ、咳きこみながら声をしぼりだす。
力のない声は樹林の奥に吸いこまれていった。海のようにふかい後悔の念が充血した両目に涙をあふれさせる。それは玉となって頬をつたいおち、草地にまぎれるひときわちいさな双葉をぬらした。ユウイチは荒縄をもとめて頭上の地面をむなしく手さぐりする。しかしリュックサックは倒木にかけてきたし、手ばなしたスーツケースのありかもわからないのだから、彼の手は湿り気を帯びた土を撫でるばかりで、もとめているものを掴めるわけがなかった。どうして捨てたのだろう、どこに捨てたのだろう。ユウイチは涙と汗と泥でよごれた顔を地面におしつけると慟哭した。命を捨てる人のみたどりつけるという連山のかなたで、彼は孤独をなげきつづけた。
※2015年脱稿・2017年改稿
ここから先は
¥ 100
お読みいただき、ありがとうございます。 今後も小説を始め、さまざまな読みものを公開します。もしもお気に召したらサポートしてくださると大変助かります。サポートとはいわゆる投げ銭で、アカウントをお持ちでなくてもできます。
