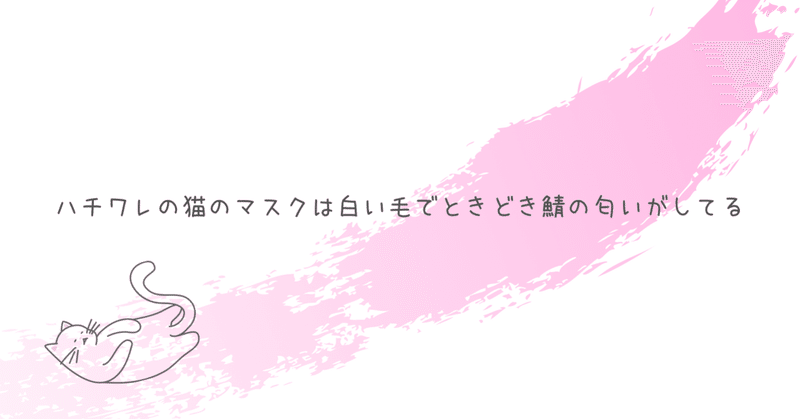
【サンプリング小説】ハチワレの猫のマスクは白い毛でときどき鯖の匂いがしてる
ハチワレの猫のマスクは白い毛でときどき鯖の匂いがしてる
引用:twitter @akiyuzu0224(春ひより 様)
町中に夕焼けこやけの歌が流れ、
子供たちは一斉に自宅へと向かい出す。
まるで牧場の羊のように、僕たちも例外では無く走り出す。
「明日も再チャレンジだからな!」
不機嫌そうに怒鳴るガキ大将のハジメの声に、隣にいた智成が小声で呟いた。
「…明日もやるの?」
背中を向け、帰宅しようとしていたハジメはその声に再び振り返り、
今度は嬉しそうに智成に近付いた。
「なんだよ、怖いのかよ」
智成はモジモジと俯いていた。
僕とハジメは目を見合わせて、肩を竦めあった。
各々背中を向いて帰路に着く。
外で遊んでいると、不思議と空が暗くなっていることに気が付かない。
もう真っ暗だったのだと気が付くのは、大体家に入った後だ。
家に入る直前、
僕は自宅の方から焼き魚の匂いがすることに気付き、思わず顔が歪んだ。
「ただいま」
僕はもう、嬉しそうに帰りの挨拶をするほど子供では無かった。
ただ決まり事を消化するだけの為に小さく呟くと、台所の方から声が返ってきた。
「おかえり!あんた、ちゃんと手洗いなさいよ!」
僕は思わず小さなため息をついた。
お母さんは、分かりきっていることを偉そうに支持する。
最近それが顕著になった気がして、余計気に食わなかった。
「ねえ、なんで魚なの」
僕は魚が嫌いだ。
だけどこの日お母さんは、文句を言った僕に対して怒ったりはしなかった。
いつもなら「好き嫌いしないの!」と言って
咎めるに違い無いのだ。
「なんでって、お父さんが帰ってくるからよ」
僕はその言葉に言い返すこともなく、小さな声でふーん、と言った。
余りに反応が薄かったのか、お母さんは呆れたような顔をした。
僕はもう、お父さんが帰って来ることを全身で喜ぶことも出来ない。
お父さんは何年も前から単身赴任をしていて、帰ってくるのは1ヶ月に1度と決まっている。
何曜日に帰ってくるかは分からない。
金曜日じゃなくても、出張の関係だかなんだかで、時々帰ってくる日があるのだ。
その日お母さんは、お父さんの好きな鯖を焼いて帰りを待つと決めている。
お父さんが帰って来ることを一番喜ぶのは、いつしか僕ではなくお母さんになった。
小さい頃、お父さんは一生帰って来ないと思いながら1ヶ月の時を過ごしていた。
その分会えた時の喜びは『ひとしお』だったというわけだ。
だけど僕も大きくなって、定期的に帰って来ることはすっかり『日常』になった。
「鯖、フースケにあげちゃ駄目よ」
お母さんは、僕がずっと前フースケに食べさせたことを、長い間根に持っている。
フースケは魚が好きなのだ。
僕は魚が嫌いなんだから、利害の一致ってやつなのに。
「もうすぐ出来るから、宿題しながら待ってなさい」
お母さんはまた、分かりきったことを
まるで今発見したかのように諭してくる。
今宿題をするのが一番得策だということは、
僕が一番よく知っている。
僕は階段を上がって部屋に戻ると、そのままベッドへ横になり、今日の出来事を思い返した。
♢
コックリさん、トイレの花子さん、テケテケ。
世の中には沢山怪談や言い伝えがあるけれど、
最近学校で流行っているのは『白いマスク』という話だ。
何でも、猫のモフモフした口周りをじーっと眺めていると
猫がニヤッと笑って、それをきっかけに
別の世界へ飛んでしまうという言い伝えだ。
クラスメイトは口を揃えて「嘘だ」「馬鹿馬鹿しい」と言っていたが、
内心興味があるのはみんな同じだった。
ただこれが、かなり長い時間見る必要があるという噂だったので、
なかなか成功者は現れなかったのである。
それが今日、クラスメイトの滝沢が成功したと言った時、
僕たちは大変盛り上がった。
滝沢は野良猫を捕まえて、30分も見つめ続けたと言うことだった。
手の傷を見せながら、その武勇伝を語っていた。
その世界は本当に素晴らしい、らしい。
おやつをどれだけ食べても怒られないし、
お父さんもお母さんも素晴らしく優しいのだそうだ。
おもちゃも沢山買いに、わざわざ店まで連れて行ってくれたと話していた。
残念ながら、元の世界にはおもちゃを持って帰ることは出来なかったと言っていたが、
興奮冷めやらぬ様子には、僕たちもつい心拍数が上がってしまったのである。
その素晴らしい世界を味わってみたいでは無いか。
今日は放課後、ガキ大将のハジメと弱虫の智成と一緒に、
早速白いマスクを挑戦したのである。
しかし当然ながら、野良猫はそんなに沢山彷徨いていない。
その中でも白いマスクをした猫を探すのに随分と時間が掛かってしまって、
僕たちはロクにマスクを見つめることなく、お開きとなってしまったのだ。
ハジメは「また明日」と言っていたが、
僕はその言葉に内心優越感というやつを抱いていた。
僕の家にはフースケがいる。
頭の模様がふたつになってて、灰色と白色のハチワレ猫だ。
フースケの口周りはしっかりと白いマスクで、
それからいつも生臭い匂いを漂わせている。
フースケは子供部屋が大好きだ。
特に、僕のベッドの上が落ち着くようで、
僕が宿題をする素振りを見せると瞬く間にやって来る。
ベッドから起き上がり勉強机の椅子に座ると、
フースケは小さな鈴の音を奏でながら、僕の部屋へやって来た。
フースケは昔から鈴を付けていた訳では無い。
一昨年の台風で脱走してしまったことがあり、
それを機に首輪を付けるようになったのだ。
歩くと鈴がリンと鳴るので、フースケがどこにいるかはすぐ分かる。
僕は振り返って近付くと、毛繕いを始めたフースケをじっと見つめた。
白いマスクはよく見ると、沢山の毛で出来ている。
そこは山のように2つに盛り上がっていて、平仮名で表すならば「ふくふく」といった感じだ。
山から出ているヒゲは、いつも動き回っている。お父さんはよくヒゲを剃っているけれど、猫にとってヒゲはとても大事な部分だとお母さんが言っていた。
フースケと名付けたのはお母さんだった。
お母さんが昔飼っていた猫の名前がフースケだったので、そのままフースケと呼ぶことにしたらしい。
僕たちは、その意見を何も疑問を持たずに受け入れた。
今ではフースケは、フースケ以外何者でも無い。
「フースケ」
僕が名前を呼ぶと、素知らぬ顔で毛繕いを続けているのに
耳だけはこちらを傾ける。
猫は知らんふりが好きなのだ。
僕がフースケの白いマスクに触れかけると、フースケはほんの少しこちらを睨みつけて
「シャッ」と小さく鳴いた。
猫がニヤリと笑うだなんて、とにかく果てしないに違いなかった。
「颯太!ご飯よ!」
階段の下からお母さんの声が聞こえる。
だけど、今諦めてしまっては勿体ない。
僕はもっと長い時間、フースケのマスクを見つめる必要があるのだ。
「颯太!」
反抗虚しく、3回程無視をしていたところで
お母さんは足音を立てながら階段を上り始めた。
「分かった!すぐ行く!」
もう、と小さく呟いて、僕はフースケを再び撫でた。
今度は反抗することなく、フースケはうっとりと目を瞑った。
僕が階段を降りて台所に着いた頃、
脚の高い長テーブルにはすっかり料理が並べられていた。
「まったくもう、早く来ないと冷めるでしょう」
僕は椅子に座ると、違和感を覚えた。
魚じゃない。
今日はお父さんが帰ってくる日なのに、焼いた鯖はどこにも無くて
代わりにナポリタンが大皿に盛られていた。
「なんだか晩御飯を作る気にならなくて」
お母さんが夕食を一皿で済ますなんて、珍しいことだった。
見る限り、心無しか元気も無さそうだ。
「ねえ、今日は鯖の塩焼きだってさっき言って無かった?」
僕の言葉に、お母さんの眉間がピクリと動いたのを見逃さなかった。
「鯖の塩焼きなんて、作る訳ないでしょう」
僕に言ったのか独り言なのか、曖昧な程に小声だった。
僕はナポリタンが好きなので構わないが、
なんだか様子がおかしいお母さんは気になった。
さっきから落ち着きが無いし、ご飯にも手を付けていない。
「だけど今日は」
お父さんが帰ってくる日じゃないか。
僕が言葉にする前に、聞き馴染みのあるインターホンの音が鳴った。
ピンポーン、という音が何度もこだまする。
お母さんは一度立ち上がってインターホンの画面を確認するとため息をついて、
応答することも無く机の方へ戻ってきた。
「颯太、ちょっと出てきて」
不思議だった。
今までわざわざ僕を呼びつけて、来客の対応をさせることなど一度も無かったのだ。
画面を覗くとやっぱりお父さんが立っていた。
お母さんは、お父さんと僕を一番に会わせる為に親切心で言っているのだろうか。
「早く」
お母さんの眉間が、また少し動いた。
苛立っている。
僕は返事もせずに玄関に向かうと、内側から掛けているドアのチェーンを外した。
「ただいま!」
スーツ姿でお土産の袋を持つお父さんは、いつもに増して元気そうだった。
お父さんは僕を見る度に「大きくなったな」と言うが、
お父さんは1ヶ月ぶりに見ても何も変わらない。
違うのは、疲れて元気が無いか否か。それくらいだった。
「久しぶりだね、お父さん」
僕は簡単な挨拶を済ませて食卓に戻るつもりだった。
「…久しぶり?冗談言わないでくれよ」
振り向くとお父さんは寂しそうに笑っていた。
「颯太が欲しがってた物、買ってきたぞ」
片手に提げていた袋を渡されたので中身を見ると、
RPGのゲームだった。
お母さんにねだったことのあるゲームだ。
「なんでこれを?」
僕はお父さんに、そのゲームを欲しいなど言ったことがなかったのだ。
お母さんだって、あの時はゲームを買ってくれるなど言わなかったでは無いか。
僕が知らない間にやりとりをしてくれていたのだろうか。
だけど今日は僕の誕生日でも無ければクリスマスでも無い。
素直に喜ぶよりも先に、違和感が僕を押しつぶした。
お母さんに直接尋ねるより他無いと思い食卓に戻ると、お母さんは居なかった。
「お母さん?」
後ろに立っているお父さんが、罰が悪そうな顔をしている。
「お母さん、さっきまで此処にいたんだけどな」
お父さんはスーツから私服に着替えるために、
台所を抜けてリビングの方へ向かった。
「お母さんは、多分お父さんに会いたく無いんだよ」
不思議と僕は、その言葉をすんなり受け入れた。
先程のお母さんの言動とも合点が入ったからである。
僕は机に座ると、冷め始めたナポリタンに手を伸ばした。
ナポリタンは麺と麺がくっついてしまっている。
お父さんは目に見える場所にいるのに、
何も話したいと思えなかった。
僕はくっついた麺をまとめて摘むと、1人寂しく口に入れた。
お父さんも何も口にはしなかった。
着替え終わると、スーツも放り投げたままそのままお風呂の準備を始めた。
「お父さん、ナポリタンは?」
お父さんはまた罰が悪そうに笑った。
「何言ってんだ、それは颯太の分だよ」
通り過ぎたお父さんから、家とは違う匂いがした。
甘い匂い。
これは先程からお父さんから漂わせていた、罪の匂いなのだろうか。
冷蔵庫が低く唸る音と、リビングの壁に掛かっている時計の音だけが聞こえる。
いつもと同じ家の中なのに、何かが違う。
好きなゲームを手に入れたことも喜べず、僕は伸び切ったナポリタンを食べ続ける他、何も出来なかった。
寂しさのせいなのか、なんだか薄寒い。
大好きなナポリタンも、今日は全然味がしないのだ。
お母さんは部屋に籠ったきり、戻って来る気配は無かった。
静まり返った部屋の中で僕はようやく理解して、
額から冷たい汗が流れ出た。
白いマスクだ。
僕はもうさっきからずっと、他の世界に飛ばされているんだ。
「フースケ!?」
大声で呼んでもフースケは来ない。
フースケはとても気まぐれなのだ。
部屋はそんなに広くないのに、僕の声がこだましたようにも聞こえた。
先程までの違和感は、全部作り物だったのか。
そうなるともう、どれが本物で偽物なのか、
何も信じる術は無い。
ナポリタンは僕の喉元を通って行く。
だけどこれは本当に、今ここにあるのだろうか。
冷蔵庫は、時計は、お父さんは、お母さんは?
僕は堪らず立ち上がると、勉強部屋へ向かって駆け出した。
階段はトントンと軽快な音を立てる。
こんなにも勢いよく上がっているのに、
品良く聞こえるのも不気味だった。
階段を上がるとすぐ、勉強部屋がある。
フースケは居なかった。
「フースケ!?」
遠くから「うるさい!」と怒鳴る声が聞こえた。
寝室に篭ったままの、お母さんの声だった。
僕は自分の力ではどうにも出来ず、
勉強机に突っ伏した。
滝沢の言う最高の世界など存在しなかった。
もしくは滝沢の行った世界とこの世界が別物なのだろうか。
とにかく僕にとって、
白いマスクで向かった先は
ドロドロとしていて、何も楽しく無かった。
唯一の満足はゲームのカセットを貰ったことくらいだ。
現実世界で買ってもらえなかったカセットだけでは
アンバランスに傾いた世界に残るつもりにはなれなかった。
「違う、そうじゃない」
円満な親子、嫌いな晩御飯、買ってもらえないゲームのカセット。
この世界は、裏と表が逆なのだ。
僕が満足していたことは、この世界では欠損している。
逆も然り、僕は随分と呑気に生きていたようだ。
どうすることも出来ないが、立ち止まっているのも落ち着かない。
顔を上げ椅子を半分回転させると、
いつの間にかフースケは欠伸をして寝転がっていた。
鈴の音は聞こえなかった。
だけどもはや、そんなことは少しも気にしてはいなかった。
もう一度フースケに近づくと、口周りをじっくり見つめながら
フースケに話しかけた。
「フースケ」
フースケが本物かどうかは分からなかった。
だけど撫でた時のフワフワした肌触りも、
僕よりほんの少し暖かい体温も、
伝わってくる感覚は本物に違いなかった。
白いマスクの部分をキュッと持ち上げると、
魚を噛み切る為の牙が見える。
僕はこの牙が好きだった。
「また魚やるからさ、元の世界に戻してくれよ」
シャッ!
フースケは口周りを触られたのが気に食わなかったようで、
小さく威嚇をした。
フースケは幾ら怒っても、決して噛みついたりはしない。
猫は僕たちが思うより、随分と大人である。
「颯太!寝てるの??」
その時階段の下から、お母さんの声が聞こえた。
「起きてるよ!」
静かだった家の中に、突然空気が充満したような気がして心拍数が上がった。
その声を合図に慌てて駆け降りると、
お母さんが僕の部屋へ向かって覗き込んでいるところだった。
「どうしたの、偉い慌てて」
「お父さんは?!」
僕はお母さんの眉間を見つめた。
眉間はピクリとも動かなかった。
「帰ってるわよ」
お母さんについて台所に行くと、
お父さんは黙々と鯖の塩焼きを食べているところだった。
「颯太!また大きくなったな」
お父さんは鯖を頬張りながら、小さく手を挙げた。
僕の席には、鯖の塩焼きが置いてある。
お腹から空虚の音が鳴った。
ゲームのカセットは貰えなかった。
代わりにお父さんは、出張先の饅頭を買ってきていた。
冷蔵庫の音も時計の音も聞こえなくなった我が家で、
僕はお父さんに「ありがとう」と呟いた。
♢
始業前の教室は相変わらず騒ついている。
皆白いマスクに希望を持って、今日も話題は持ちきりだ。
「白いマスクなんだけど」
僕はハジメに昨日の話をするつもりだった。
今日も参加する意思がないことは、はっきりと表明する覚悟で学校に来たのだ。
話をしようと思ったが、ふと気が付いて教室を見回した。
「…滝沢は?」
もうすぐ授業のチャイムが鳴ると言うのに、滝沢が居なかった。
「滝沢?知らねえよ、休みじゃねえの?」
それもその筈で、皆滝沢が一日休むことなどなんてことは無かった。
だけど僕は、なんとなく気が付いていた。
「滝沢は来ない」
僕の言葉に、ハジメは「はあ!?」と呟いたが、
それ以上の詮索は無かった。
教室の扉が開く音がする。
「はい、もう授業が始まるわよ!席に戻って!」
先生が教室に入ってきた途端、
生徒は一斉に座り始める。
全員が座り切った教室で、滝沢の席だけが空いていた。
滝沢は、学校に来ない。
もしかするともう、いないかもしれない。
よろしければサポートをお願い致します!頂いたサポートに関しましては活動を続ける為の熱意と向上心に使わせて頂きます!
