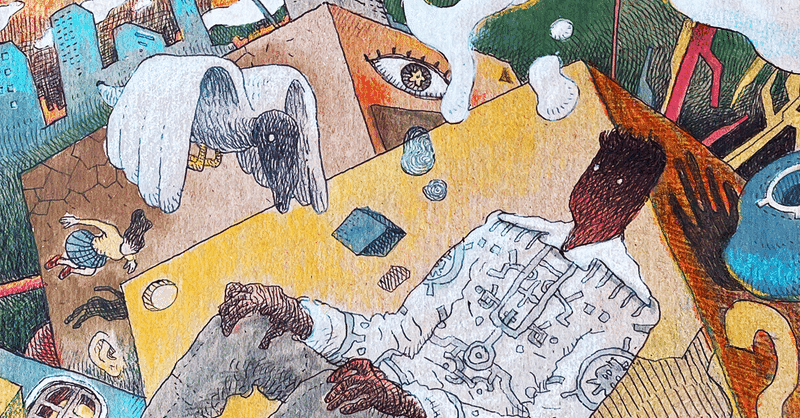
【適応障害休職中】病気が自己洞察の好機を与えてくれる
あなたにとって「病気」とは何ですか?
今日は、
「病気である」という状態が、人生においてどんな意味を持っているのか?
ということを考えてみたい。おそらく、今の私と同じような適応障害の状態で葛藤を抱える人、かつての私のように不妊や女性特有の不定愁訴などで悩む人にとっても、何らかのきっかけになるのではないかと思う。
前回記事では、不妊治療を通して私が経験し感じたことをまとめ、「医師との関係性」という観点から、病気であることと、それが軽快してゆくこととの関連を考えてみた。
今回は、私の人生とは切っても切れなかった(?)「病気」というネガティブな側面を持つものに対して、あえて有意義な意味を見出し、価値を与えてみたいという気持ちで書いてみようと思う。
「病気である」という状態を自覚している人はたぶん、その多くが自分自身の心身を見つめなおし、良くなるように努める。そして体の痛みや苦しみが少し軽快した頃、今度は「自分とは何者なのか?」という問いに向き合っているように見える。むしろ、「向き合わざるを得ない」というのか…ある種❝根源的なニーズ❞と言えるようなものに駆られているようにも見える。
私だけではない、という確信に基づいて、そのプロセスや理由について考えてみたい。今日は、そんな話。
「病気」とは何か?
そもそも、「病気」とは何か?
単なる語義ではなく、「病気であるという状態」を明らかにしようと試みている興味深い説明があったので、少々長いが引用してみたい。
(以下、下記より引用↓ 太字、筆者による)
医学では病気を「体の機能、構造、器官などの断絶、停止、障害」すなわち正常状態からの逸脱と定義することが多いが、「正常」という概念そのものが不確かである。突きつめていくと「異常でないこと」という語義反復の矛盾に陥ってしまう。自然科学的に病気を定義することはむずかしい。(中略)
前段で述べたように、病気一般に妥当する定義をすることはむずかしい。なぜなら、病気とは、まず社会学的、行動学的な概念であるためである。ただ、このような概念の背後には、日常的な活動を妨げるものとして、それを取り除くことが望まれているものの存在が措定されている。 その一つは自然的な実体である。それが存在することによって、日常的な責任が全面的あるいは部分的に免除されたり、道徳的な責任も追及されず、さらには治療をも含めた援助を受けることの正当性が社会的に承認される。つまり、自然的であるということは、病む本人の意志とは無関係であると考えられるため、責任のとりようがなく、また、そのために能力が低下したということであるから、周囲からの援助に加えて、専門的援助が必要とされるのである。こうした専門的援助の基本になるのは、多くの社会では医師である。医師は、こうした自然的な実体を、それぞれの時代において広く承認されている自然的事物の説明原理に沿って明らかにすることによって、実効のあるものにすることができる。具体的にいえば、医師は医学を根拠にして病気の存在を明らかにするわけであるが、普通、医師の思考過程や、その結果として明らかにされる病気は、いずれも直接みることができない場合が多いため、その判定も医師によってなされる。つまり、社会学的な手続として病気が措定されることとなる。
もう一つは個人的な事情である。それが個人を苦しめ、運命にも大きな脅威となる災厄である以上、なぜそのような状態がもたらされたのかという個人的な事情を納得できなければ、それからの解放の手だてはつかめない。とくに近代以前の社会においては、個人的な事情の多くは、非行や不道徳に対する罪や呪(のろ)いや試練であったりする。これらの違いは、文化的背景や個人差によるが、共通していることは、それが回顧的に追求されるということである。そして、現在の症状や苦痛について自らが理解できたときに、それから解放される契機が得られるということである。
一般に古いタイプの医学は、後者すなわち個人的な事情の理解と結び付き、新しいタイプの医学は、前者すなわち自然的な実体の把握と結び付いているが、精神的な病気では、自然的な実体の理解が困難であるため、個人的なものとして回顧的に扱われることが多い。
この引用した部分に、病気であるという状態の「曖昧さ(カオス)」が集約されているように思う。そして、私が個人的な解釈を加えつつ、読み取れることがいくつかあるので、下記にまとめてみる。
☑正常/異常の定義は非常に曖昧である。
→統計学的に言っても、「平均値の人」が全人口のうち、何人いるだろうか…?身長や体重、血圧や血糖値、IQに偏差値…精神疾患に特化すれば、「正常な人」という定義自体がむしろ滑稽に思えてくる。確かに、社会は中央値付近の人に快適であるように設計されているから、グラフの両極に位置する人は、多かれ少なかれ何らかの生き辛さや不便を感じることになるのだろう。
☑病気の時の、「社会的な手続き」と「私の内部」で行う作業は別。
→noteで記事を書いていて、読んでいて感じるのは、病気について語る時はやはり、①公的サポートや受診にかかる費用やスケジュール感といった諸手続や申請と、②個人の内部で行う感情・思考の処理や行動変革のプロセスという2つの視点に分かれやすいということ。
☑医師の診断という社会的な手続きを踏むことより、「病気」の原因が個人に帰されず、社会的なサポートを得る(適切な医療を受けることや、費用は社会保険適用される、休職や復職後の処遇改善)などの正当性が確保されている。
→だから、診断書が必要だし、必要な手順を踏んで手続きを行うことが必要。誤解を恐れずに言えば、それが病気になった当人が行うべき「最低限の責任」なのかもしれない。もっと言えば、このことに配慮出来れば、病気が軽快して社会復帰を望むにあたって、当人がスムーズに目指すべき状態に移行しやすくなる、ということだろうか。
そして、「病気で休む」「働けない」「他者の力をかりる」ということに、なにも罪悪感を抱く必要なはない、ということである。逆説的に言えば、非常に曖昧な「病気であるという状態」を社会的・医学的に捉え、ある意味公的な「保証」を与えるために医師が存在している、と言える。いろいろな意味で、主治医が大切な存在なのだ…
☑病気である当人が、現在の自分自身の状態を直視し、必要があれば過去を参照して整理し、納得感を得ることで、病気である状態から抜け出すきっかけを得られる。
→これは身をもって実感しているところ…自身が「病気である」と自覚している人がnoteで発信を続けているのも、似たような考えからではないかと思う。時間をかけて、「正常ではない」ときの自分のキャパシティーが許す容量で、少しずつ過去を振り返り、表現し、自分自身への理解を深めてゆく。そのなかで、現在の自分自身の状態を新たな目で見られるようになったり、気づきを得たりして、いわゆる「落としどころ」みたいなものを見つけてゆく。そうすることでやっと、文化や生活歴や他者の言葉、習慣や固定概念によってもたらされていた縛りや不自由さに気づき、そこから逃れようとする力と戦略を手に入れることが出来るのだろう。
個人的に、最も大切なのは、自分自身のストーリーとそれを語る言葉を手に入れ、表現し、頑なに自分を縛っていた価値観や思考に「気づける」ことだと思う。このことが私をやっとスタート地点に立たせてくれたのだし、将来同じ轍を踏まないようにするための「正しい武器と戦略」と与えてくれているのだと気づいた。
「病気」が教えてくれること
この記事に、ここまで付き合ってくれた、あなたにとっての「病気」とは、いったいどういう存在だろう?
過去に、深刻な状態にあった人、また、今現在重篤な病状を抱えて闘病中のいる人もいるだろうし、一方で「病気とは無縁!」という人もいるかもしれない。人生のストーリーも、健康状態も千差万別であるし、一概にまとめて「病気とは〇〇である」という断定は不可能で、そもそもそういう目的でこの文章を書いていないということは、ご了解頂きたい。
私自身は現在、「適応障害で休職中」であり、「無月経」を長年患ってきたが、「不妊治療ののちに出産を経験」し、「緊急帝王切開で死の淵も垣間見た」経験がある。青春時代は「肥満気味」で、「メンタル不調」はずっと抱えてきたし、おそらくそれが適応障害につなっているわけだが、「低血圧」すぎて抗うつ剤は服用できないということだった。ちなみに、これも断定はできないけれど、無月経は完解したとは言えず、産後のホルモンバランスはガタガタだし、「PMS」の疑いがあり、もしかしたら「更年期障害」も出始めているかもしれない…
なにも病気であることを自慢したいわけではない。いくつかの不調と病気を抱えてきた人生のなかで、私は今度の休職中に、本当にたくさんの気づきを得て、根本的な部分で少しずつ、これまでの人生には得られなかったような変化を感じはじめているので、そのことをただ書き留めておきたいのである。
罪悪感から解放され、心身の状態を好転させようと務めた十分な時間があり、そのなかで、これまでの人生を言語化するというアウトプット(noteの存在が大きかった)が出来たことで、現在のステータスを冷静に把握することが出来た。そのうえで、私の人生に大きな影を落としてきた(と私が思い込んでいた)「仕事」という領域にフォーカスすることで、私という「全体像」をフェアに観察し、自己理解が進んだと実感している。そのうえで、これまで大切にしてきたことや、これから大切にしていきたいもの、そのバランスや優先順位を十分検討出来ている気がするし、そのために正当な戦略も練れているという納得感もある。
おそらく、こういう実感は、「病気」を抱え、その状態を中立的に見つめられる状態にいる人に共通の感覚ではないかと、そんなことを考えた。
前回は、「病は気から」という話だったけれど。
今回は、「怪我のの功名」ということわざで、テーマ回収してみた。
そんな話。
アイディアを形にするため、書籍代やカフェで作戦を練る資金に充てたいです…
