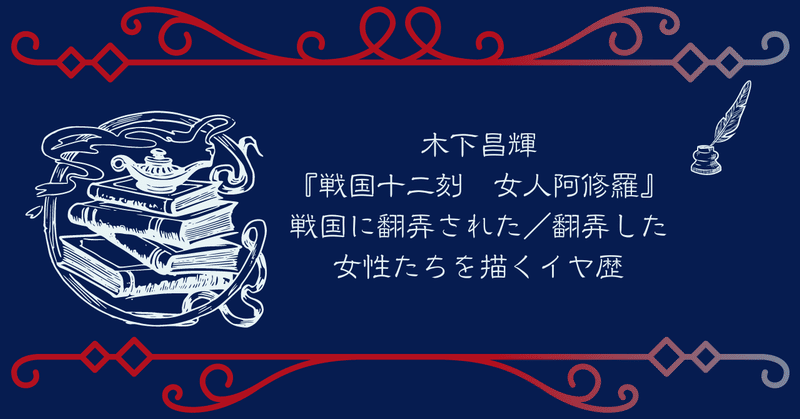
木下昌輝『戦国十二刻 女人阿修羅』 戦国に翻弄された/翻弄した女性たちのイヤ歴
(記事タイトルに誤記がありましたので修正しました)
木下昌輝による『戦国十二刻』シリーズ、久々登場の第三弾であります。今回は副題にあるように、女人を中心にした物語――決定的な瞬間に向け、刻一刻と変化していく状況の中で、それぞれに趣向を凝らしたサスペンスフルな七つの物語が展開します。
合戦の決着や落城、誰かの死など、戦国時代のある決定的な瞬間に向けた十二刻――二十四時間を描くというスタイルで展開してきた『戦国十二刻』シリーズ。これまで『終わりのとき』『はじまりのとき』と、それぞれ副題通りの時を描く二作が刊行されてきましたが、今回は戦国に翻弄された/翻弄した女性たちを主人公とした、些か趣が異なる内容となっています。
臨月を迎えながら家康軍に従軍した阿茶の局の奮闘ぶりを通じて、長久手の戦いで家康が勝利するまでの十二刻を描く「戦腹」
細川ガラシャを救出しようとするある企てと本能寺の変の驚愕の真実の果てに、彼女が炎の中に消えるまでの十二刻を描く「殉妻」
織田軍に包囲され、絶望的な状況となった高遠城で、愛する諏訪勝左衛門に恐ろしい疑念を抱いてしまった花が高遠城を脱出するまでの十二刻を描く「祈刀」
数々の求婚者を袖にして、美僧との情事に溺れる賛姫に対して、思いもよらぬ愛の証を示して吉川元春が婚約を成立させるまでの十二刻を描く「醜愛」
愛する妻・ジュリアを傍らに、悲願である神の国をこの地に作るために島津軍に決戦を挑んだ大友宗麟の軍が耳川の戦いで壊滅するまでの十二刻を描く「聖室」
息子と兄がにらみ合う中に割って入った義姫の行動から、彼女の秘め隠された内面を描きつつ、彼女が伊達家と最上家を和睦させるまでの十二刻を描く「鬼妹」
岐阜城で兄・信雄の軍に包囲され、生母を人質にすることを求められた織田信孝の、幼い頃に生き別れた母への複雑な想いと共に、彼が母を犠牲にして和睦するまでの十二刻を描く「証母」
細川ガラシャや義姫のように後世によく知られるような有名な人物もいれば、諏訪花のようにほとんど伝説上の人物、織田信孝の母のように名前すら残っていない人物まで――その主人公のバラエティはこれまで以上(「殉妻」のもう一人の主人公のように、作中では明かされない有名人がいるのも心憎い)、当然ながら物語のバリエーションも、驚くほどであります。
特に本シリーズは元々ミステリ味が強く、限られた時間の中で事態が進行する中で、秘められた真実、隠された想いが明らかになっていくという趣向がほぼ各話で共通しているのですが――その各話でのどんでん返しには驚かされるばかりです。
そして本書の場合、人の負の感情、それも狂気や妄執というべきレベルのものが描かれるエピソードが少なくなく、その後味はほとんどイヤミス――いや、イヤ歴(そんな言葉はないかと思いますが)と呼びたくなるほどであります。
その中でも強烈に印象に残るのは、やはり「醜愛」でしょう。巷説では疱瘡により醜い容貌となった賛姫を、それでもと強く望んで元春が妻に迎えたという一種の美談が残っていますが、それを本作がどのように描いたか? そもそも元春が彼女に求婚した理由だけで現代人としてはどうかと思わされるのですが、彼女に対する永遠の愛の証として用意したものは――いやはや、もはやただ唖然呆然とするばかりであります。
そのほか、愛し合っていた二人がどうしてこんなことに、とさめざめ泣きたくなる「祈刀」、これまで悪女とも猛女とも描かれてきた義姫を、それとは全く別のベクトルから恐るべき女性として描いた「鬼妹」など、よくもまあここまで――というほかありません。
その一方で、掉尾を飾る「証母」は、読んでいていたたまれなくなるような信孝の回想など、どう考えても悲惨な物語にしかならないところを、最後の最後に明かされる彼の母の真意が、一種のホワイダニットとして機能することで、大いに泣かされる一編となっています。
思えば作者のデビュー作『宇喜多の捨て嫁』は、まさしくイヤ歴であると共に一種の「女人阿修羅」の物語であり、そして同時に「母」の愛を描く物語でもありました。本作はそんな作者の原点を思い起こさせつつも、さらに進歩したところを見せてくれる、そんな一冊であるとも感じます。
必ずしも全てのエピソードで十二刻という趣向がうまく機能しているとは言い難い部分もあります。また、シリーズ恒例の最初と最後を通しての仕掛けも今回はほとんどない(少しだけある)のですが――そうした点を補って余りある、名品揃いの短編集であります。
関連記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
