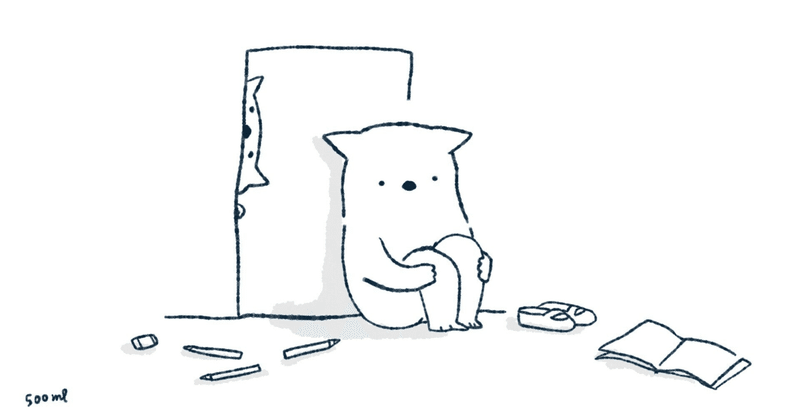
対話する
こう見えても、否、そもそもどう見えているかは定かではないが、私は対話することが苦手である。つまるところ、人と饒舌に話をすることが少々苦手なのである。というよりも、自ら何を話しかけていいのか迷い、話題に困窮し、悩んだ末に面白くないなと勝手に決めつけて黙っていることが多い。初対面の人であれば尚の如く顕著である。人となりも分からないがゆえに、相手が何を考えているかも分からないし、私が唇を切ったことによって話がすぐ途絶えてしまったりしたら、しんとした空気が漂い続ける。その空気感がどうにも居たたまれないので、最初から静けさを選択してしまう。ただ静かな雰囲気が嫌いではない。寧ろ好みである。ただし、ずっと独りは寂しくなる。甚だ自分勝手だ。
でも、そういうことを考えると、明石家さんまさんは仕事の範疇なのかもしれないが、思ったことをどんどん口から言葉を発することができるのは意外にも羨ましく思うときがないわけでもない。逆に、あれだけ喋り続けたら疲れないのかなとさえ勘繰ってしまう。
ふと、中学生のときを回想する。“お菓子を学校で食べていいか”について是非を問う討論会がクラスで開催されたことがある。そのとき、反対派だったか、中立派だったか記憶は曖昧だが、とある人が「兄弟はいますか?」と、賛成派の人に質問した。この突拍子もない質問に私は度肝を抜かれた。一見何の脈絡もない問いに感じるのだが、悲しいかな、その同級生に“凄い”人だなと憧れを抱いた。彼なら、もっと核心をついた質問ができたであろうに、なぜその質問だったのか。私自身は、賛成派にどんなことを質問していいか全く思い浮かばなかったからこそ、逆に、そういう「投げかけ」が私の心に突き刺さって、今の考える原動力の一部にさえなっている気がする。
ところで、原因は不明だが6人のうち1人の割合で妊婦さんは残念ながら流産してしまう。その一人が妻である。その当時、私は声をかけてあげることができなかった。励ますために何を伝えていいのか分からなかった。あれほど傍にいたのに、無力を痛感した。
しかし、5年前から本を読むようになり、自分の中に存在する陰の自分と対話したり、本と(著者と)対話したりする場面が増えた。その流れの中、いい書店、店員さんに巡り合え、2年前から読書会に参加し、全国津々浦々の人と出会い、対話する好機を得た。対話とは“水中でもがく”様であり、その積み重ねの結果、心の中にあった棘がとれて、徐々に丸くなってきた気がする。自分中心に物事を考えるのではなく、相手の気持ちをいい形で汲み取るようなことも徐々にできるようになってきた。勿論、まだまだ未熟であるが…。でも、妻が悩めるときにも傾聴してあげられるようになったし、どういう心持ちでいたらいいかをその当時読んでいた本をもとに対話することができるようになってきた。書物そのものには力はないが、どう読んで対話したかで自ずと感ずるものがあり、力となっている。
今に至っては、それらを経験したせいか、“いのち”に向き合うことにはとりわけ真剣になる。何事にも「答え」があるわけではない。だからこそ、もどかしい、もがく対話こそ欠かせない。
2021.10.22
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
