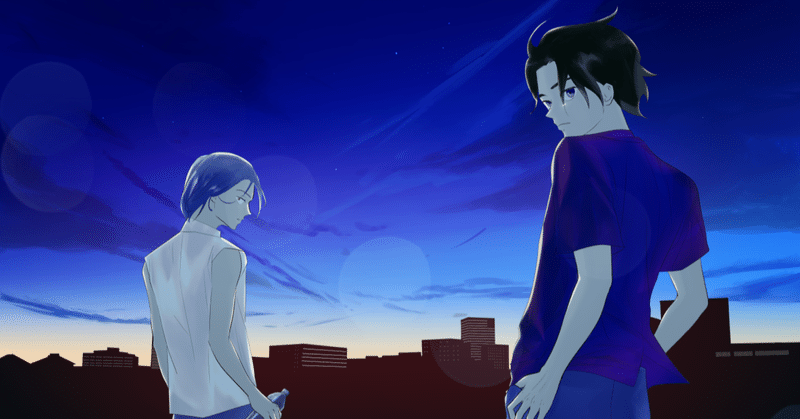
& Love for 【短編小説】
こちらの短編小説「& Love for」は「ナイルの庭」の6年後を舞台にし、その主人公、「晃」の「友人」であった、「翔」を主人公に置いた物語になっています。
運命と夏
夜だというのに、ムシムシとした暑さ。どうにも嫌いな季節、真夏だ。翔は、様々な人間とネオンで賑やかな夜の歌舞伎町をフラフラと歩いていた。汗がじっとりと不愉快だ。0時に勤務を終えて、歩ける距離の自宅に帰る道のり。
すると、路地裏から女の子と男が、揉めている様子が目に入った。そんなこと、この歌舞伎町では日常茶飯事だ。翔は無視を決め込んで、通り過ぎようとした。女の子と、どうやら数人の男が揉めている。
「これは・・・まずいな・・・。」
何故だかはわからないが、翔はついその仲裁に入った。
「ちょっと、止めとけよ。集団で、女の子に絡むとか。」
翔はその男のグループを睨みつけた。
「ふざけんな。そっちが先に絡んで来たんだ。俺たちは悪くねえ。酔っぱらって絡んで来たのは、そっちなんだよ。」
男達から女の子を引き剥がすと、彼女はおぼつかない足取りで、ふらふらと歩き、派手に転んだ。
「大人になれってんだよ、酔ってるんなら余計だろ。」
再び翔が睨みつけると、「うぜーんだよ。」と言いながら、男たちは去っていった。
「君、大丈夫?1人で飲んでたの?相当酔ってない?悪いけど、放置できない。ここに居てもいいけど、暑いから。どっか入る?」
「・・・どっかって?何処?ラブホ?」
「そんなつもりはない。居酒屋かどこかで、とにかく酔いを醒まして。始発で帰ったらいいよ。」
翔は彼女に肩を貸すと、とりあえず入れそうな居酒屋に入った。
「酒はもうだめ。ソフトドリンクにして。俺もそうするから。ウーロン茶でいい?」
「グレープフルーツジュース・・・。」
「何か食べる?」
「いらない。」
「わかった。」
翔は自分のウーロン茶と、グレープフルーツジュース、そして少し空腹を感じ、いきなりシメのお握りをオーダーした。
まじまじと彼女の顔を見つめる。誰かに似ている気がした。まだ少し幼くて、髪型はボブ。健康的に日焼けしている。・・・ああ、あの頃の、彼だ。翔は瞬時にそう自覚した。だから彼女を助けたんだ。
ウーロン茶とグレープフルーツジュースがくると、彼女はグレープフルーツジュースを一気に飲み干した。眠そうだ。少し寝ればいい、そうすれば酔いも覚める。翔は、お握りをゆっくりと食べながら、彼女がうつらうつらする様子を眺めた。やはり似ている・・・。運命か、これは。
2時間程、経ったか。彼女が意識を取り戻した。まだ酔っているようではあるが。20歳は超えているだろうが、自分よりは遥かに若そうだ。
「・・・あ、私。貴方、誰?」
「君が酔っぱらって男どもに絡んでトラブルになってた。」
「貴方が助けてくれたの?良く覚えていないけど。」
「まあ、イジメられている子は、放っておけない性質でね。」
「・・・ありがとう。」
「ダメだよ、あんな時間に、酔って1人でふらふらしてちゃ。女の子なんだから。」
「別にいいの、あたしなんか、どうでも。」
「じゃあ・・・俺とする?」
翔は少し緊張しながら、彼女にそう言った。次のセフレを探していた翔は、丁度いいな、何か似てるし、と深くは考えなかった。
たいそう驚いた顔をしたが、彼女はそれを承諾した。翔は驚いたが、何となく、お会計を済ませて、居酒屋を出た。
正直、ホテルなんてどこでも良かった。歌舞伎町のホテル事情には詳しいけれど、適当に一番近いホテルに入った。
朝、先に目覚めたのは翔だった。全裸の自分の隣で、全裸の彼女が眠っていた。
(やっちまった。・・・可愛い顔してるから、まあいいか。似てるし。)
翔はシャワーを浴びに、浴室へ向かった。ざあざあと音がする水しぶきを浴び、浴室を出ると、彼女が呆然とベッドに座り込んでいた。
「あ、起きた?」
「貴方、誰?どういう状況?」
我に返った彼女は、酷く慌てているように見える。
「覚えてないの?昨日、男共に絡まれているところを助けたんだけど。」
「それでホテルに連れ込んだの?酔ってたから?」
彼女が翔を睨む。
「居酒屋で、話をしたじゃん。なんかどうでもいいとか言うから、俺とするっつったら、君は『いいよ。』って言ったよ。」
「覚えてない・・・。」
「俺はカケル。君は?」
「ホノ。」
「ねえ、ホノさあ・・・俺のセフレにならない?」
「え・・・?」
「いいじゃん、定期的に会おうよ。何か良かった、君とのセックス。」
彼女は考えた風をして・・・。
「いいよ。」
即答した。翔は驚いた。
「でも私、彼氏いるけど?それでもいいの?」
「え、そうなの?じゃあ何で、あんな時間に歌舞伎町なんかふらふらしてたの?彼氏いてセフレ、いいの?」
翔が逆に問う。
「セックスレスなんだ、彼とは。」
「抱いてくれないの?」
「うん。」
「同棲してるのに?してないで?」
「してるよ、同棲。一緒に寝るけど。」
「そんな奴、見限れば?」
「何となく、お母さんに反発して、作った彼氏。別れるのは・・・。」
「じゃあ、俺としようよ。それでいいじゃん。そこの不満解消に、俺を使ってよ。」
「それでいいの?あなたは・・・カケルは。」
「俺、今彼女いないし。セフレもいないし。丁度いいじゃん?」
実際、翔には彼女はいなかったが、何人かセフレがいた。だが今ホノに言わなくてもいい気がした。もちろん、自分から誘ったセフレ等いなかった。誘われて、翔がのった。それだけ。でもとにかく今、ホノを手放してはいけない。
「わかった。シャワー浴びるから、ここ出る前に連絡先、教えて。」
ホノが翔とセフレになることを承諾したのは、翔に、彼氏にはない、あまりにも穢れのない佇まいに惹かれたのが、理由だった。翔となら、気持ちのいいセックスをして、それで完結する関係になれそうな気がしたのだ。
2人は、連絡先を交換し、その日は別れた。彼女は新宿駅の方に向かって歩き、翔は逆方向に歩く。
憂鬱と安息
「ただいま・・・。」
誰も居ないマンションの一室に戻る。同居を始めて2年の、晃とは、生活時間が違いすぎて、すれ違いだ。だいたい、晃が寝る頃翔が帰宅し、起きる頃は彼は仕事に出かけている。だがいつも、翔には必ず晃によって食事が用意されていた。仕事に出かける前に、電子レンジで温めればいいように、晃が作っていくのだ。そしてそれを食べて、晃が居ない内に翔は出勤する。たまに休みが重なると、2人で出かける。出かけると言ってもあまりアウトドアでないので、シーシャを吸いに、家から歩けるお気に入りのシーシャ屋に行く。そのくらいだ。
翔は過去、晃と同じ鉄道社員として勤めていた。朝が苦手なのに、何故か選んでしまった職業で、何となく晃の力を借りながら、何とか乗り切っていた。その頃、晃には「萱」という彼女が居たが、翔にはそれがおままごとのようにしか思えなかった。そんな関係、終わると思っていた。
確かに、その恋愛はあっけなく終わった。晃と萱とはおままごと恋愛で、終わる。そのカンは当たったが、晃はその理由を頑として言わなかった。だが翔は、晃に本当に愛するひとができたのだと、悟ってしまった。どう見てもお付き合いをしている様子はなかったが、晃は萱と別れた日から、少し変わった。瞳はいつも見えないその「愛するひと」を見ているように思えて仕方なかった。翔はどうにもそれが辛かった。晃に本当に強く愛する女性ができるとは、予想もしていなかった。そして翔は晃に対する友情以上の感情を隠せない、そう思ってしまった、だから翔は退社の道を選んだ。自ら晃の前から消えたのだ。そうするしかなかった。あの社員寮での晃との奇妙な生活は維持できなかった。たまに連絡は取っていた。晃は真面目に、鉄道社員としての仕事を続けていた。
しばらく女の子の家を適当にふらふらした後、翔は夜職の道を選んだ。風俗業の門を叩き、いつの間にか指名客も増え、生活には困らない。もう5年以上、そんな生活を送っている。そして翔が1人暮らしにも大分慣れた頃、翔の退職後に昇進試験をパスしていた晃が突然退職した。どういう心境の変化からかはわからない。だが、その後久しぶりに食事をした時、晃の瞳からあのどうにも翔の感じてしまった「愛するひと」の存在はなくなっているように見えた。
退職後、晃は何か勉強を始めたようだった。だが、彼女も作らず、半分ホームレスのような生活を送る晃を見かねて、翔は晃に同居を持ちかけた。貯金を崩して勉学に勤しんでいた晃を、助けたかったのだ。辛いかもしれなかった。事実、翔は晃への友情以上の感情を感じてしまう。だが、今はずっと助けられていた晃を助ける時と思ったのだ。恩返しみたいなものだ。晃は最初、断固としてその提案を受け入れなかった。だが、翔が、泣いた時。
「お前が心配なんだよ、晃。お前は強いから、いつかポッキリ折れそうだ。」
そう言って思わず泣いてしまった時に、初めて翔の手を握った。
「わかった。世話になる。」
晃は、同居を始めてしばらくして、一定の勉強を終えて、カウンセリングセンターに勤めるようになった。もちろん、大学院を出なければ、学歴的にそれをクリアしなくてはならない臨床心理士として働くことはできなかった。だが、晃にできるだけの「心のケア」のお手伝い、をするようになったのだ。翔には、あの、鉄道社員時代の彼から、全く今の晃を想像できない。何かに憑りつかれたように、激務をこなしていた、あの頃の晃とは別人だ。人に寄り添い、人の心に寄り添っている晃の姿など。そしてひたすら勉強を続ける晃。驚くほど穏やかになった彼に、翔は改めて恋をしてしまったと感じた。感覚として、また新たに恋をした、そんな感覚だ。
だが、晃が変わっていないのは、鈍感なところだ。共に鉄道社員として社員寮生活を送っていた頃も、同居生活を送っている今も、全く翔の心には気づかない。良いか悪いのかは、わからないけれど、晃との関係は友人関係から全く発展しない。同居を始めて、何となく以前より晃に近づいた気はするけれど、晃にはそもそも女っ気がなかった。
(まさかこいつ、26歳にしてまだ童貞とかじゃねえよな?)
萱と別れてから、女っ気ひとつない彼。疑ってしまうのも仕方ない。万が一そうなら、もう風俗でも何でも使って童貞など捨ててしまえ、いや、俺が相手になればいいのでは?
(あり得ない。)
翔は苦笑した。晃とセックス?ないない、そもそも童貞だとして、初体験が男など、俺じゃないんだから、と頭を振った。おかしいのは俺、どっちかと言えば晃は正常。何人もセフレが居て、仕事でもセックスを主に生業として、奔放すぎるのは俺。晃のいる世界とはそもそも違いすぎる。晃はとにかく真面目。仕事にも、女にも、真面目。ただ自分を疎かにする悪い癖があるけれど、それ以外はいたって真面目だ。真面目故、風俗など使わないと思うが、まさかまだ童貞ではないのかと、翔は無駄に心配だった。
翔が多くの男女と関係を持ってしまう、持ってしまうようになった理由に、翔自身も気づいていない。それはおそらく、晃への気持ちをセックスで紛らわす為で、だがそれで紛らわせられているかと言えば、全くそうではなかった。行為の度に、虚しくなるだけで、見えない何かが、翔を追い詰めていた。苦しい想いは、晃には理解してもらえない。当然かもしれなかった。理解してもらおうとも、正直思っていないのかもしれない。この、一輪の桜の花が咲いたような、ちっぽけな、でもいずれ壮大になるだろう恋心など、今更口になど出せるものか。
ともかく、「ホノ」という安息を手に入れた翔は、頻繁に彼女に会うようになった。他のセフレよりも、お客さんよりも、「ホノ」が良かった。ホノは優しい。とても心の優しい女の子だった。いい子、だった。翔はこの苦しみが受け入れられたような気がして、ホノに縋った。自分から「セフレにならない?」などと言ったのに、翔の中で、ホノはセフレ以上の存在になってしまった。決して恋はしていない。恋は晃に置いてきた。だが、ホノも翔には必要になってしまったのだ。
真実と後悔
翔とホノの関係は続き、あれから1年程が経過した。関係はあくまで「セフレ」だったが、翔にとって、ここまで関係が長く続いた人は初めてだった。
相変わらず晃は、翔の恋心に気づかない鈍感で、共に生活をしながら、翔は正直疲れていた。もう、9年近くに渡る、長い報われない片想いに疲れてしまったのだ。ホノには、セックスレスな彼氏になんかとは別れてもらって、自分が恋人の座につこうか、そのくらいのことを思っていた。ホノと居ると、心が安らぐ。晃といるより、安らぐのだから。セフレに「浴」という苗字を明かしたのも、ホノが初めてだった。
ある夏の暑い日の夜、翔はホノと落ち合っていた。ホノと初めて会った日、適当に選んだラブホテルだった。安らぎを覚えながら、行為をして、正直気持ちよくてとてもすっきりしたその後、ホノは翔に言った。
「翔、話があるの・・・。私、結婚することになった。だから、もう会えない・・・。」
翔は、心底衝撃を受けた。まさか、結婚するだなんて。だって、俺の方が・・・。ホノのことは、良くわかっていた・・・はずで・・・。もう、会えない?俺じゃなくて、抱いてもくれない彼氏を選ぶのか・・・?
翔は、晃に恋をしながら、ホノを抱いていた自分のことを棚に上げて、勝手な嫉妬をした。そして、自分は結局その存在程度の存在にしかなれないのだなと自分を嘲笑い、そして妙に納得した。
「わかったよ。次、会う時を、最後にしよう・・・。」
打ちひしがれて、翔が家に帰ると、いつものように、物音ひとつしなかった。晃はもう寝ているのだ、明日の仕事の為に。ホノを失ったら、どうしようか。事実失うことはもう決定事項だ。既に失っていると言っても過言ではない。そっと、晃の部屋を開けた。眠る晃を、見つめる。ホノはやはり、あの、出会った頃の晃に、そっくりだった。
次の日起きると、いつも用意してある食事に、メモが添えられていた。
「明日、休みだろ?久しぶりに家で飲まないか?お前の好きな『雨後の月』買っておいた。」
何となく憂鬱な気持ちと、晃と家でゆっくり時間を過ごせる喜びが入り混じった。好きな日本酒を覚えている晃の優しさも、嬉しいが、辛い。
翔は、無心で勤務を終え、つまみになりそうなものを買って、家に帰った。晃が起きていた。
「お帰り、翔。疲れたろ、風呂沸いてるぞ。」
「どうした?」
「明日、休みだから、たまには待っていようかと。」
「あら優しい。」
翔が笑うと、晃も笑った。
「晃は、風呂は?」
「まだ、お前先入れって。」
「待ってなくていいのに!先入れば・・・。」
「どうにも、お前が先な気がして。いいから入れって。」
様子がおかしいな、と思いながら、「じゃあ遠慮なく。」と言って、翔は風呂に入った。風呂はいい。命の洗濯だ。生き返る。汚れた自分が綺麗になった気がする。一通り身体を洗い、浴室を出ると、晃がバスタオルを投げてきた。
「俺も入る。交代。湯冷めすんな。」
「真夏に湯冷めするか。」
晃が浴室に入るのを見送って、翔は摺りガラス越しに、晃を見つめた。ただ見つめた。もうすぐ、10年に渡るこの片思いをしながら、翔は沢山の男女と関係を持ってきた。だが、どうしても、心が惹かれるのは、関係を一切持ったことのない、晃だ。何でだ。どうしてこんな。どうしてこんなにも惹かれる?
見ているのも辛くなって、翔はその場を離れた。自室に戻ると、ベッドに腰かける。濡れた髪をバスタオルでばさばさと拭いた。そして、久しぶりに泣いた。涙が勝手に落ちるだけ、翔はそう自分に言い聞かせた。晃を想って泣いたのは、いつ振りだろう。恐らく、晃に同居を持ちかけた、あの日以来かもしれない。
「翔?」
自室のドアが開く。晃だ。翔は慌ててバスタオルで涙をゴシゴシと拭いた。
「どうした?泣いてるのか?何かあったか?職場で、何かあったのか?」
晃は、翔が身体を売る仕事をしていることを知らない。ホストクラブでホストをしていると認識している。もっと言えば、もう10年近い付き合いだが、翔が男も女も愛せることを知らない。翔は、晃が自分のことなど何も知らないと思っている。どうしても、言えない。言えるわけがなかった。
涙が止まらなかった。晃が隣に座って背中を撫でた。
「大丈夫、落ち着けよ、翔。話したくなかったら、話さなくてもいい。でも、大丈夫だから・・・。」
子供に戻ってしまったような翔に、晃は酷く動揺していた。
(晃は、翔さんを、助けてあげなさい・・・。絶対に、翔さんに、迷惑をかけないように。)
幼いころ、母に言い聞かせられた言葉が、よみがえってくる。翔を、助けなければ・・・。
「翔、たまには一緒に寝るか。」
「????」
「いや、本気だ。」
「一緒に寝て、どうすんの?」
「寝るだけだよ、ほら、横になれって。明日、一緒に飲む約束だろ、ベッド、半分借りるぞ。」
晃に何も他意はない。自分を心配している。恐らく、こうして泣く人を、晃は職場で沢山見ているのだろう。そして、心に寄り添っているのだろう。
「狭いぞ。2人で寝るようにできてないんだ。」
「いいだろ、寝ろ。おやすみ。」
晃が、目を閉じる。翔は黙って天井を見上げた。晃から、規則正しい寝息が聞こえてきたのは、まもなくだった。翔は、どうしても我慢ができなかった。唇に、唇を、一瞬触れさせた。好きだった、晃が。どうしてこんなに恋い焦がれてしまったのか、どうしてもわからなかった。別にタイプの顔ではなかった。可愛いけれど、翔のタイプとは少し違う。翔はここのところ溜まっていた疲れや、ホノとの関係で、あまり眠っていなかった。だが晃が隣にいるだけで、安心して、意識を手放した。その時、晃はそんな翔を見ていた。晃は眠っていなかった。一度ベッドを降りて、自室に戻る。机の一番下の引き出しを開けて、その一番奥から、一枚の写真を取り出す。それをただ見つめる。そして、また翔の眠るベッドに戻り、眠りについた。
翔が起きると、隣に寝ていたはずの晃の姿はなかった。キッチンで音がする。ドアを開けると、晃が朝食を作っていた。
「翔、おはよう。相変わらず、朝が弱い。もうちょっと早く起きられんのか、お前は。」
時計を見ると、10時だ。いや、翔にとっては充分早いのだが。
「晃の感覚がおかしいの、お前は。鉄道会社なんかに、6年勤めた功罪だよ。」
「罪とはなんだ、早起きはいいことばかりだろ!」
「起きたやつは起きろ起きろ。俺は、早起きなどもううんざり。」
「しょうがないやつ・・・。朝飯、食うだろ。」
「食うよ、お前の飯は美味いからな。」
「お世辞は沢山だ、いただきます!」
「いただきます!」
晃はよく食べる。その食べっぷりは、翔が呆気にとられるほどだ。
「・・・美味いな、ぬか漬け。」
翔がぬか漬けを好きだと言ったら、晃は小さなぬか床で野菜を漬け始めた。驚いたのを覚えている。ぬか床なんて、面倒なもの。毎日掻きまわさないと、カビてしまう、ペット並みに世話のかかる代物だ。だが3年間の間、晃はぬか床をダメにしたことはない。
「不味いと言われたら、速攻捨てるぞ。お前の為に漬けてるんだよ、毎日。」
「そりゃ、どーも。」
翔には、どうしてもお袋の味と言う物がない。あまりそういう記憶がないのだ。印象的な、母の味と言う、記憶が。何不自由なく育てられたと思う。3人目でやっと生まれた長男で、姉2人にも、もちろん父母にも、可愛がられ、甘やかされて育った気がする。だが、家族の思い出と言う物が欠如していた。母がぬか床を持っていた記憶はない。そもそも、ぬか床を毎日掻きまわすような人ではなかった。
食事が終わると11時過ぎ。晃がシーシャに行こうと言い出した。シーシャは、同居するようになって、翔が晃に教えた嗜好だ。何だか晃に酷くハマったようで、どうも1人でも行っているらしかった。何が良かったのだろう。煙草を吸わない、口寂しさが紛れるのか、ただドーパミンが放出されて快感なのか、良くわからない。
朝食の片づけをして、適当に家を出て、新宿に行く。ドライヤーが壊れているのを思い出した2人は、電気店で買い物をした。そして、適当にシーシャ屋で、約2時間吸って、家に帰る。17時半だった。
「飲み始める?適当につまみ、作ってある。あんまり変わり映えしないけど。」
テーブルに並べた酒のアテは、もう乾き物などなくても充分だった。晃が出してきた日本酒を、一緒に飲む。昨日言っていた『雨後の月』の他にも、日本酒、ビール、色々用意されていた。
「何だ、俺、誕生日か?」
「自分の誕生日がいつかもわからなくなったのか?」
「いや、誕生日じゃ、ないけど。」
「お前の誕生日は1ヶ月以上先だ。どうした。」
「いや、何か、お前、気合い入ってない?」
「別に、いつもと変わり映えしないと思うけど。」
「そうかな。お、やっぱり卵焼き、美味いな。」
「お前、好きだよな、卵焼き。俺も好きだけど。」
いつもより、晃の酒のペースが速い気がした。350mlの缶ビールを2本空け、日本酒もペースが速い。晃はいつも、翔の介抱をして、あまり飲まないはずなのに、今日はどうした、どうにも飲むな、これは俺は飲まない方がいいのか?翔は一旦、飲むペースを緩めた。そもそもよく考えれば、晃から飲もうだなんて、どうしたのだろう?今日、何の日だっけ?翔は考えても、わからなかった。
案の定、早々に晃は酔い潰れた。こんな姿など、見たことがない。ベッドに寝かせたいけれど、翔は晃を持ち上げられなかった。翔はとりあえず布団をかけようと、晃の自室のベッドの布団を、取りに入った。
綺麗に整えられたベッドから、布団を剥がして、持ち去ろうとした時、ふと、晃の机の上が気になった。
「写真?子供の?・・・俺?」
それは確かに、覚えがある。翔自身が、写っていた。実家で自分の写真を見たことがある、間違いない、恐らく、2歳になったか、なってないかくらいだ。そして、同じくらいの子供が、もう1人写っていた。日付を確認する。
98.08.16
8月16日?今日、8月16日じゃなかったか?その写真をまじまじと見つめる。この子は、誰だろう。仲が良かった友達?2歳にならない子供に、そんなに仲のいい友達がいる?親が撮った?
ふと、写真を裏返す。それを見て、翔はぎょっとして、思わず写真をポトリと落とした。
「1998.8.16 翔 晃」
確かにそう書かれていた。晃?晃、なのか?「ヒカル」とはあまり読まないかもしれないが、珍しい名前ではない。でも、そんなに周りに居るかと言われると、翔は生涯でこの字一文字を名前に持つ友人は、晃しかいなかった。
(どういうことだ?)
そして、もう1枚あった、白い便箋を、手に取る。
「晃は、翔さんを、助けてあげなさい・・・。絶対に、翔さんに、迷惑をかけないように。いつも心に言い聞かせなさい。」
翔は真っ白になった、回転が速いとは言えない頭で、理解をした。そして、家を飛び出した。
昼間はあんなに晴れていたのに、雨が降っていた。ゲリラ豪雨と言うものだろう。雨がバシャバシャと打ち付ける。翔は走った。何処に行くでもなく、ただ走った。無意識に、足は新宿方面に向かっていた。靴の中は雨水が入り込み、びちゃびちゃと不快な音を立て、ただ雨水が滴る程濡れながら走る翔を、誰もがよけた。
辿り着いた、新宿駅東口。構内に入ると、雨が凌げた。翔は座り込んだ。翔は、真実を、知った。晃は知っていたのだ。全て。俺は何不自由なく育てられ、何も知らなかった。
恐らく、晃は、弟に違いなかった。2ヶ月年下の、弟。意味がわからなかったが、母親が違うと結論づけると、筋が通った。恐らく、自分の母が、父と正式な婚姻関係にあった。晃は、父の落とし種だ。どうして、気が付かなかったのか。「カケル」「ヒカル」良く考えれば、似ている名前だった。漢字一文字で「カケル」と「ヒカル」、まるで双子につきそうな名前だ。
「晃」は、恐らく母に、決して自分に迷惑をかけるなと、言い聞かせられて育てられた。晃の母親は、「正妻」の子である翔に、決して迷惑をかけるなと、そう言って晃を育てたのだろう。何となくわかった。晃を見ればわかる。あの時、同居をどうにも拒んだ理由。同居し始めて、ひたすら翔に晃は尽くした。食事を作り、家事のほぼを翔は晃に任せっぱなしだった。神経質な性格なのかとも思ったが、そうではない。掃除も、洗濯も、炊事も、決して翔にやらせなかった。家の事一切、晃がやっていたのだ。週5日、朝から夜まで働く。早く起きて、翔の食事を作って出かけていく。洗濯物も済まされていたし、休日ともなれば、翔が散らかしたものを、綺麗に掃除していたのは晃だった。適当に、朝起きてからでもできた自分が、何故何も感じず、晃にやらせっぱなしだったのか。今更思っても、どうにもならない。
まさか、たまたま同じ会社に居たのではなかった?思えば、あの頃から、翔は晃に頼りっぱなしだった。朝起こすのも晃。一緒に飲みに行くのも晃。酔った自分を社員寮に連れ帰るのも晃。いや・・・それは恐らくたまたまなのだろう。おそらく翔があの写真を撮った日から晃に会ってなかたように、晃も翔に会ってはいないはずだ。ただ、母親から俺のことを聞いていたのだとしたら?進学しなかったのも、俺が原因だとしたら?もう暴走する頭が止まらない。
新月と救済
びしゃびしゃに濡れて、座り込む翔を、見ないふりをして、人が往来する。その時、目の前に足音が止まった。
「翔・・・?どうしたの?」
ホノだった。どうして現れたかも、わからないが、そこに居たのはホノだ。ホノが心配そうにしゃがみ込み、翔の濡れた髪をかき分けた。その姿を見た瞬間、翔は、ホノに抱き付いて、むせび泣いた。
「大丈夫、落ち着いて、翔。話したくなかったら、話さなくてもいい。でも、大丈夫だから・・・。」
しばらくホノの胸で泣いて、翔は一度落ち着きを取り戻した。
「こんなところじゃ暑いから・・・。付いてきて。びしょびしょだね、電車には乗れないかな。」
ホノが手を繋いだ。雨で冷え切った翔の手を、しっかり握って、ホノは歩き出した。
東西自由通路を抜けて、西口に出る。雨は止んだようだ。濡れた地面がキラキラと光っている。だが、空に月の姿はなかった。
「何処まで行くの?」
「もうちょっと。」
西口を出て、7、8分歩いただろうか。目の前は、ヒルトン東京という、ホテルだった。名前くらいは知っていた。ロビーに入る。
「お部屋、空いてるか確認してくるから、ちょっと待ってて。そこ、動かないでよ?」
「うん。」
ホノはフロントに向かう。しばくして、ルームキーを持って、戻ってきた。
「お部屋、空いてた。行こ。全室禁煙だけど、いい?」
「一本吸ってきてもいい?・・・あ、煙草忘れた。」
それは、あんな風に家を飛び出したのだから、当然だ。
「コンビニあるけど?」
「じゃあ吸ってくる。少し待てる?」
「先に部屋行ってる。はい鍵。」
「わかった。」
ホノは、部屋番号の書かれた紙と、カード式のルームキーを翔に手渡した。
翔は煙草とライターを購入すると、喫煙所で煙草を吸った。
晃が突然煙草をやめた後も、翔は吸い続けるどころか、どんどんヘビースモーカーになっていった。ゆっくりと煙草を燻らせ、部屋に向かう。鍵を開けて入ると、ホノはぼーっとベッドに腰かけていた。
「翔、風邪をひくから。お風呂ためておいてから、入って。夏とはいえ、雨は冷えるから。」
「ありがとう、そうする。」
下着まで雨で濡れてしまっている。それを脱ぎ捨て、翔はシャワーを浴びてバスタブに入った。
「温かいな・・・。」
帰宅すれば、必ず風呂に湯がはってあった。晃はいつもそうしていた。
身体が充分温まった翔は、浴室を出た。ホノが心配そうな顔をして翔を見つめた。
「翔、何があったの?そんな雨の中、家から新宿駅まで、傘もささずに来たの?何かあったなら、話して。聴くから。」
「・・・わかった。少し、長くなるけど。」
「いいよ、時間はあるから。」
「俺には、ずっと愛している人がいる。もうこの想いを抱えて、9年以上になる。片思いだよ。」
「告白しなかったの?」
「できなかった。だって、その人は男だから。ホノに『セフレにならない?』と言ったのは、ホノが出会った頃の彼に、少し似ていたから。」
「そう・・・私に・・・。」
「だけど彼は、弟だった。半分血を分けた、弟。俺は全くそれを知らなかった。弟は、俺のことを知っていた。俺だけ、何も知らなかった。弟は、高校を卒業して、おそらくたまたま同じ会社に入社した。だけど弟は、俺の存在に気づいたんだ。」
翔が言葉を選ぶ。ホノは待ってくれた。
「俺の想いは、『恋愛感情』ではなかった。俺は愚かだった。」
話し終えた翔は、項を垂れ床を見つめた。
ホノはしばらく黙り込んだ後、彼の名を呼んだ。
「ねえ、翔。」
「なに、ホノ・・・。」
翔が振り向いたその瞬間、ホノは彼の頬に手を添え、優しくキスをした。
「約束通り、会うのは今日で最後に、しよう・・・。私の話も、聴いてくれる?」
「・・・うん。」
「私の名前は、ホノではない。『ホノカ』」
「どういう綴り?」
「星に、希むに、香りで、星希香。」
「どうして、『ホノ』って、名乗ったの?『ホノカ』で良かったよ?」
「私は母親から来た『香』の字を否定したかった。」
「お母さんと、何かあった?そう言えば、彼氏を作ったのも、お母さんへの反発で作ったって言ってたね。」
「私には、少し年の離れた弟がいる。でもそれは私の父との子ではなかった。B型の母とB型の父からは生まれることのない、AB型だった。母親に密通相手がいたことは、ここ、ヒルトン東京の領収書で悟った。多分、本当に1回きりの相手だったと思う。でも母は妊娠して、弟を産んだ。私はそのことを、必死で父に訴えた。でも父は、わかっているとしか言わなかった。私は、母がそんなことをしながら、良き妻、良き母親でいようとするのが許せなかった。だから、好きでもない知り合いの優しそうな男を彼氏にして、好きな男ができたらさっさと別れるつもりでいた。男に縛られている母親への、当てつけだった。だけど、当の彼氏は、1度した後、セックスレスになった。世の中思い通りにはいかないものね。そんな時、翔と出会った。」
「ごめん、辛い事話させたね。」
翔は星希香の肩を抱き寄せた。
「翔が私を通して誰かを見ているのは、何となくわかっていた。貴方と何回か関係を持った後、私は翔が好きかもしれない、と思った。だから、『セフレ』がいることを彼に告白して、別れを切り出した。でも、彼は私に『セフレ』がいることを知っていた。それでも傍に居て欲しいと言われて、私はそれ以上何も言えなくなってしまった。」
告白と帰還
星希香は話してくれた。彼が、セックスレスになってしまった理由。それは彼女との初めてのセックスで、酷く彼女を傷つけているような感覚に陥ってしまったから。それ以降、怖くて彼女を抱くことができなくなってしまった。別の男と関係を持っていることは、薄々気づいていた。だが、彼女を愛する気持ちで、別れを切り出すことはできなかったのだ。もし別れを彼女の方から切り出されたら、承諾するつもりでいたと。だが、いざその瞬間になると、離れたくないという気持ちが溢れてしまった。そんなズルい自分を許して欲しい、『セフレ』がいようが、傍に居て欲しい。彼は、そう思ってしまったんだと・・・。
「彼は、涙を流しながら、静かにそう訴えた。その彼の表情に、翔のある表情と同じものを感じた。翔がたまに見せる、苦悩と哀しみ、そして慈愛を含んだ表情、あれは翔が本当に『愛している人』を想っていると思った。そう思った時、私は彼をとても愛おしく感じた。翔の話を聴いて、それは本当だったと理解ったの。母が離婚しない理由、父が、裏切りを受けても母を今も愛している理由も少しだけわかった。」
星希香は、一息ついた。
「だから、彼に言ったの。ずっと一緒に居ようって。ずっと。一生一緒に居ようって。」
翔は言葉を失くした。
「今日、ここ、ヒルトン東京に来たのは、そんな母への憎しみと決別するため。」
「うん。」
「私が結婚を決意できたのは、翔のおかげ。翔に出会えたから『人を愛する』ことができた。翔は私を救ってくれた。だからとても感謝している。」
「俺は、ただ自分の勝手にホノを利用しただけだよ。罪深いのは、俺だ。」
「ううん、それは違う。絶対に違う。私たちは、お互いの救いの為に、出会うべくして出会ったと思う。だから今度は、私が翔を救いたい。今日のセックスは、いつもみたいに意識して優しくしなくていい。だから、翔の全てを私に吐き出して欲しい。そして、どうかその人を、弟を、『愛したい気持ち』を諦めないで。愛のカタチは多種多様だって教えてくれたのは貴方よ。だから・・・その気持ちを捨てちゃダメ。」
星希香は、脱衣した。そして優しく翔を抱きしめると、そのままベッドに倒れ込んだ。翔には、星希香がどうしても出会った頃の晃に見える。星希香を抱いているはずなのに、何故か晃に抱かれているような気がした。涙がポトポトとシーツに落ちた。その時。翔は、自分が救われた、とそう確信した。
翔が目を覚ますと、星希香の姿はなかった。ああ、もう会えないんだ。自分を救ってくれた女性には、もう会えない。心が波だった。ふっとベッドサイドを見ると、着替え一式と、ミント色の缶のようなものが、2つと、雑な走り書きが置かれていた。香水のようだ。メモには、こう書かれていた。
『本当は旦那と一緒に使うつもりだったけど、あげる。これで愛する人をギャフンと言わせろ!』
翔は、まじまじとその2つの香水を見た。どうやら、メンズとレディースで、対になっている香水らしい。時刻は9時を過ぎている。きっと晃が心配をしている。家に帰ろう、と翔は思った。そのメモを、持って帰ろうか、悩んだ。だが敢えて、そこにそれを置きっぱなしにした。星希香と会うことは、もうないのだ。これは永久の別れ。もう、自分の人生に引きずってはいけない。ただ、その2つの香水だけは、星希香が自分の救済の為に置いて行ってくれたもの。持ち帰った。
フロントに確認すると、宿泊費の支払いは済まされていた。もちろん、そんなことはわかっていたけれど。
(早く帰りたいけど、家まで歩こうか。)
朝9時を過ぎたばかりなのに、気温は30℃を超えている。太陽がギラギラと攻撃を開始した。だが、今の翔はそれに怯む存在ではなかった。新宿駅を越え、ひたすら自宅を目指す。晃に会いたい。
アパートの近くに来ると、人の姿が見えた。そわそわと動く影。晃だ。その瞳が翔を捉える。
「翔!」
「晃、ごめん。酔いつぶれているうちに、いきなりいなくなるなんて。」
「どうしたんだ、俺、お前に何かしてしまったんじゃないかと・・・もう帰って来ないかと思った。心配した・・・。」
「そんな訳、ないだろ!俺が晃から離れるわけないじゃん。」
翔は晃に抱き付く。ひとしきりじゃれ合って、2人で家に戻った。
「お腹、空いてない?ご飯は?食べる?ごめん、今から準備するけど。」
「うん、食べる。俺も手伝うよ。」
「翔に何ができんの?卵も割れないだろ?とりあえず、冷蔵庫から納豆出しといて。あとは待ってて。ご飯は冷凍ので我慢して。ちゃんと温めるから。」
「スミマセン。」
「どしたの?」
「いや、別に・・・。」
食事をしていて、気づく。
「晃、仕事は?」
「有給取った。」
「ごめん、俺のせいだ。」
自分のせいで、晃の仕事を休ませてしまった。
「違う違う。俺が心配しただけ。気にすんな。お前こそ、今日仕事は?」
「夜出勤。」
「そうか、少し寝たら?」
「うーん、その前に、話が。」
「何、改まって。」
「片付けてからでいい。俺も手伝うよ。ちょっと聞いて。」
「わかった。だが翔は余計な仕事を作るから、そこで待ってて。」
「・・・スミマセン。」
「何をいまさら・・・。」
2人は笑った。
そして、改めて2人は向き合った。
「これ、晃にあげる。」
「・・・香水?何処の?」
「ティファニーの。メンズ。種類少ないんだよな、ティファニーのメンズって。」
「そっちは?」
「ん、同じティファニーの、それと対になってる香水。レディースだな。これはやらんぞ?」
「いや、何で俺がメンズで、お前がレディースなの?そもそも、お前からのプレゼントなんて、初めてだ。」
「お前はどうにも、『少年』から『男性』に変貌した気がするから。お前はどうにも女っ気がなかったが、どうしても、今もお前が童貞を維持しているとは思えん。お前は風俗など使わんだろ。恐らく、誰かと、忘れられない夜を過ごしたのではないか。」
「・・・何で、わかるんだ・・・?翔、お前には何も話していないはず・・・。」
「わかるんだよ、兄だからな。」
約束と決意
晃の瞳が衝撃で見開いた。
「・・・知ってた?のか?ずっと・・・。」
「いや、俺は何も知らなかった。この前お前が酔いつぶれた時、部屋に布団を取りに行って、その時机の上にあったものを見てしまった。」
「あれを、見たのか。ああ、あんな所に置きっぱなしにしていた。まさか見られていないだろうな、とは思っていた。それ以外、お前が急にいなくなった理由が、思いつかなかった。・・・すまない。あれをお前に見せてしまうとは・・・母さんごめんなさい・・・約束守れなかった。」
晃が絶望的な顔をした。翔が続ける。
「だいたいの事情は、想像で補完した。多分間違いない。俺とお前は、腹違いの兄弟だ。それも2ヶ月しか離れていない、禁忌の兄弟、だと思う。全て父が原因だろう。あれだけ一緒に居たのに、俺はお前がシングルマザーに育てられたなど、知らなかった。ぬくぬくと甘やかされて育った俺と違って、お前はとてもしっかりしたやつだった。お母様からの、メモ書きを見たよ。おそらく、お前は決して俺に迷惑をかけたりしないように、俺を助けるように、そう言って育てられたんだろう?お前の中で、自分より俺が優先されるようになっていった、と思う。」
「だいたい、その通りだ・・・。俺は物心ついた頃から、自分には兄がいること、そして決して、いつか出会ったとしても、自分が弟であることは言ってはいけないと、散々言い聞かされてきた。何でも、俺の兄は浴家の長男で、待望の男の子の誕生だった。名前は「翔」。一時期俺は母に酷く反発した。何で、俺なんかが産まれてくることになったのか。そもそも、俺の母がお前の・・・俺たちの父を拒めば、こんなことには・・・。入社した時、あれだけの人数の新入社員がいるし、お前の事を知らなかった。だが、「浴翔」という同期がいることを知って、そしていつの間に俺達は東京駅で職場を共にするようになった。お前の存在を知った時、正直すぐにでも辞職しようと考えた。怖かった。だが距離が近づいて、考えが変わった。俺は兄の役に立つ時が来たんだと、ようやくその時が来たんだと、そう思った。お前が退職した理由は、俺なのではないかと思っていた。俺と距離を置きたかった。もしかしたら気づかれたのかもと思っていたけど、そうではなかったんだな。改めて聞く。何故、退職した?朝起きるのが嫌だったは、理由にならないぞ。」
「話すよ。」
翔は言った。
「お前の中に、どうしてもお前の心に沁みついた女性の存在を感じるようになった。正直、俺はお前と萱ちゃんがずっと続くとは思えなかった。俺にしてみれば、あれは「おままごとの恋愛ごっこ」としか映らなかった。どうにも『少女』を捨てきれない萱ちゃんと、『少年』を捨てきれない晃の恋愛など、長続きするとは思えなかった。だが、お前の中に『女性』が見えるようになった。お前の瞳はいつもその女性を見ていたし、それが辛かった。」
「確かに、お前の言うとおりだよ。俺はある女性と、一晩だけ、過ごした。愛してしまった。だが俺は身を引いた。その人は家庭を持っていたから。俺の出る幕ではなかった。でもどうして、それをお前が辛がるんだ?」
相変わらず、純粋で、鈍感なやつだと、翔は思った。話しておくべきか。これからの為にも。
「俺は、お前が好きだった。兄としてじゃない、俺はお前に恋をしていた。今もだ。ずっと、お前と出会った時から。お前は全然気づいてくれない。もう、9年間以上続いている想いだ。」
晃は驚いた顔をした。本当に驚いたようだった。
「お前・・・女の子と付き合ってただろ?そんな事、信じられるわけが・・・。」
「お前への気持ちを紛らわすためだった。申し訳ない。」
「男とも、付き合ってるの?」
「付き合ってない。事実、今「お付き合いをしている人」は男性でも女性でもいない。ただ、関係は持っている。仕事でも、プライベートでも。全て晃への想いを紛らわす為だ。お前、俺がホストクラブに勤めていると、疑ってないだろう?」
「違うのか?」
「お前に言えなかった。俺は、男に身体を売る仕事をしている。悪くないんだ、その限られた時間だけ、心が繋がれる。お前を忘れられた。辞められなくなった。女の子はその辺に立ってれば寄って来るし、困らなかった。」
晃は思った。翔を、兄を助けたい、そう想いながら、俺は翔を追い詰めていった。またあの疑問に辿り着く。どうして、産まれてきてしまった・・・?翔の想いに応えなければ・・・。
「晃は男を愛さないことは、充分知ってる。だが、想いを忘れることができなかった。そしてお前の兄だったと知って・・・。酷い罪悪感だ。俺は弟を愛していた。どういう状況なんだ。」
翔の混乱は、当然だった。今日の今日まで、弟がいることなど知らず、それは同居している晃で、愛している人だった。
「俺、翔を好きになる。もちろん今も好きだよ。だけどお前の想いに応えたいんだ。だから、許してくれ・・・。俺は翔を必ず愛するから。」
「そんなことは、いいんだ、もう・・・。」
「どうして、、?」
「俺は晃を、弟として、家族として、愛することにした。多分、気持ちは変わらないんだ。だから、それでいいんだよ。だから、俺の側に居てくれ。ずっと。お前が結婚するまででいい。お前に子供ができたら、俺嬉しいだろな。俺の血を分けている子供だ。」
「お前は、結婚を考えたことはないのか?」
「ない。俺には無理だ。俺が結婚できるとは思えない、到底。」
「そうか・・・。」
しばしの沈黙だ。この産まれてからの26年間の膨大な時間と比べれば、今、翔と真実を語った時など一瞬かもしれない。だが、酷く長かった。人生を全て振り返ったような気持ちになった。翔を兄として、晃はひたすら想い続けた。決して弟と名乗ってはいけないと母に禁じられて、ただ想うことしかできなかった。だがようやく出会えて、翔の役に立てるようになったと思った。その喜びも束の間、翔は自分の元を去ってしまった。そして今、翔の自分への想いを知った。鈍感過ぎた。何も翔の役に立っていなかったどころか、翔を苦しめていたのだ。
「とにかく、香水をつけろ。彼女できないぞ。このままでは、俺も困る。」
「だからそもそも、何でお前がレディースなんだ?」
「それは、ある女性と出会って、自分の中に『慈愛』のようなものを見出せるようになった。だから、俺は、レディースの方。」
「それは俺を『慈しみ、愛している』のか?」
「そうだ。」
かつて、晃は、たった1人、本当に愛した女性から、香水をもらったことがあった。「ナイルの庭」という香水。家で、1人で香りを楽しんでいた。たまに、1人で出かける時にもつけた。何となく、爽香さんが共にいるような気がして、心が落ち着いた。そして、最後の一滴まで使い終わって、晃は今度は自分で購入するか、悩んだ。だが、それをしなかった。そろそろ次のステップに踏み出す必要を感じた。その時、退職をするという道を選び取った。自分が、爽香に想われたこと。それで、人を想う仕事に就きたいと思うようになった。鉄道社員でも、叶ったかもしれない。でももっとリアルに、そういう現場に立ってみたいと思ったのだ。
そのうち、爽香の存在が、少しずつ心から抜けて行った。忘れたわけではない。ただもう愛していると言うのとは違うかもしれないと思った。自分の中にいるのではなく、どこか遠くから見守られているような、母がいつもどこかで必ず自分を想っているような、そんな感覚に変化した。
そして、新たに、翔から渡された香水。どうしても、感情の伴なうものしか、自分は受け入れられないのかもしれなかった。萱に「煙草」の香りを感じて、爽香に「ナイルの庭」を感じた。そして、翔にこの香水を感じるようになるのだろう。
満月と残香
そしてまた、次の夏がやってきた。晃はひたすら勉強と経験を積み重ね、心理カウンセラーとして、ますます人の「心」に寄り添うようになった。
翔は、晃への想いを告白しても、何故か「売り専」の仕事を辞めなかった。近いのだと言う。晃の仕事と、自分の仕事は。ただセックスで金を稼ぐだけじゃない。お客さんと話し、コミュニケーションを取り、心に寄り添う様は、晃とは立場と方法が違うにしろ、目指しているものは同じなのかもしれなかった。晃への想いをセックスで紛らわせていた頃と違い、今、翔は仕事が楽しかった。
翔は、副店長になった。きっとこの先、その仕事に関わって生きていくつもりなのは間違いない。そのうちいつか、経営に回ったりするのかもしれないが、きっと何か関わって生きていくのだろう。
珍しく、晃の出勤時に、翔が起きていた。
「晃!香水をつけるの忘れるなよ!彼女できないぞ!」
自分のことを棚に上げ、翔が言う。
不貞腐れながら、晃は香水を手首に散らした。
「行ってきます!」
「行ってらっしゃい、気をつけてな。」
晃が家を出て行ったあと、翔は自分の机の引き出しから、その1対になった香水をつけた。表情は緩み、幸せそうだ。
晃が愛おしい。これからも共に歩みたいのだ。血を分けた「家族」、「弟」として、これからも愛していきたい。強くそう思う。
今日の夜は満月だ。きっとこの晴天が続けば、見ることができる。『雨』の後の月は、空気が綺麗で極めて美しい。
2人が使う、香水。
それは、「TIFFANY&Co.」の「& Love for」.「Him」と「Her」で一対になっており、「Him」を晃、「Her」を翔が使っている。
愛し合う二人を引き合わせる様々な愛のかたちを讃える香水だ。
【後書き】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
