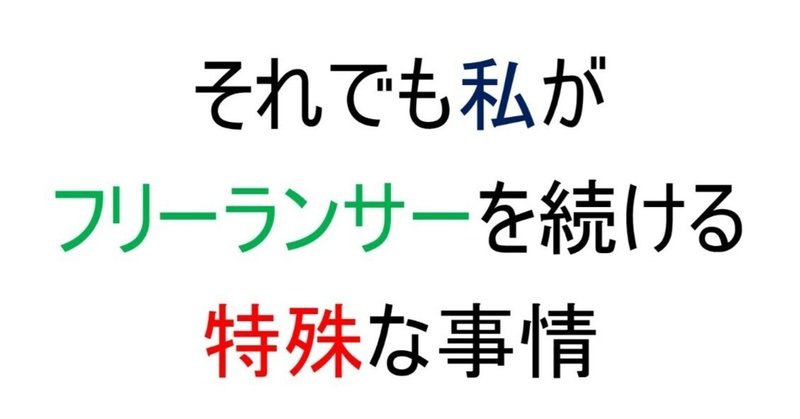
第二章 フリーランサーへの道(3)
遺伝子、確かにもらったよ
とは言うものの、それから数年間、映画に関係する仕事は熊日さんのレビューだけで、基本的には相変わらず実家の“社員”として、経理から雑用までいろいろこなしつつ、隙を突いて映画を観に行くという生活を送っていました。辻先生が、
「公開される映画はとにかく一本でも多く観ておきなさい。」とアドバイスしてくださったので、そのお言葉に従いました。
一方、父は新たな療法を自分で開発、それが実績を上げたこともあり、“弟子”を自認する方々が多数いらっしゃったので、毎月勉強会を開いていました。特に免許が要るものでもなかったので、一応は私も出席して少しは父を手伝えるぐらいにことは習得しようとしたのですが、やはり私にはこういう分野は合わず、最終的には事務関係のサポートに徹することになりました。
そういういきさつもあり、熊日で執筆していることは父には黙っていました。と言っても隠し通そうとしていたわけではありません。父は毎日新聞を読んでいたので、そのうち気づいて小言を言われるだろうと思っていたのです。知れたら知れたで、別にどうってことはない。一応、家の仕事はきちんとやってるし。ところが、私が執筆を始めてから1年以上経っても何も言ってきません。
「とうとうこんなことまで始めて、これはもう望みなしだな。」
と、呆れ半分諦め半分で何も言ってこないのだろうと思っていました。
ところが、ある日突然、意外な形で私のライター仕事のことが父に知れたのです。用事があって電話をかけてきた辻先生が、私と間違えて父にレビューの話をしたことから、最終的に私の仕事の話について説明を受けたらしいのです。ちなみに、辻先生は私の父と同じ高校で1学年上。もしかすると、当時校内で遭遇していたかも知れません。
話を聞いた父は怒るか口を利かなくなるかと覚悟していたのですが、それまでとまったく変わらない態度だったので拍子抜けしました。いや、厳密には衝撃的なことが起こっていました。しばらくして、治療に来ていたお客さんやお弟子さんの何人かから、私が映画のレビューを新聞に書いていることを父が嬉しそうに皆さんに言いふらしていた、というお話を聞くようになったのです。これはまったく予想していなかったリアクションでした。やはり、自分も映画好きだったからでしょう。
そのことについて、父から直接何か言われたことはありませんでしたが、BSで昔の西部劇を見ていた父が、
「この俳優は誰だったっけ?」
などと訊いてきたりするようになりました。
しかし、私が執筆の仕事を始めてからちょうど3年経った2005年の春、父がS状結腸ガンにかかっていることが分かりました。以前から体調が悪かったのをずっとほったらかしていたのですが、我々に説得されてようやく病院に行ったところ、即入院して緊急手術。切り取られた結腸には大きな穴が開いていました。そして、すでにあちこちに転移していました。
「持って半年です。」
映画やドラマでおなじみのあのシーンに、まさか自分が入り込むことになろうとは。どうすればいいか分からないまま父の闘病の世話もこなしながら、極力普段通りの生活を送ろうと務めました。
そんな日々が続いていた7月半ばの日曜日、私はレビューを書くことになっていたアニメ映画『ロボッツ』(2005)を娘と一緒に親子試写会で観た後、病院に寄ったりしていたら結局夜になってしまい、レビューの原稿は翌日書くことにして就寝しました。数時間後の深夜、病院にいた母から、父が息を引き取ったと電話がありました。結局、約3ヶ月半しか持ちませんでした。あと9ヶ月頑張れば、孫娘のランドセル姿が見れたのに…。
それからの2日間、私は憔悴しきっていた母に代わり、実質的な喪主として無数のことをこなしました。あまりの忙しさに悲しむ余裕すらなく、火葬場で職員の人から
「親族が押すという規則だから」
と点火ボタンを押すように言われた時も、正直言って躊躇なく押しました。
何とか葬儀まで終えた翌朝、『ロボッツ』の原稿の締め切りがその日であることを思い出しました。
『ロボッツ』は、ロボットだけが暮らす社会が舞台。中古ロボットを非情にもどんどんスクラップにしようとする大企業の陰謀と戦おうとする主人公の青年ロボットは、貧しい中古ロボットたちが住む町で彼らの面倒を見る博士に協力します。映画を観ながら黒澤明の『赤ひげ』(1965)みたいだと思っていた私は、そこに父を重ね合わせながら集中して一気に書き上げ、締め切りに間に合わせました。それでも、涙は出ませんでした。あまりに忙しく、さらにこの後もやることがあまりに多過ぎて「泣き損ねた」、という表現がピッタリかも知れません。泣き損ねたまま、父の没後のいろいろな手続きなどに忙殺される日々が続きました。
あっという間に9月になり、だいぶ生活が落ち着いてきた頃、『チャーリーとチョコレート工場』(2005)が日本で劇場公開されました。ティム・バートン作品が大好きな妻子も楽しみにしていたので、3人で観に行きました。
(※以下、ネタバレあり)
世界中で大人気のお菓子を作るウィリー・ウォンカ‘(ジョニー・デップ)。秘密のベールに包まれた彼のチョコレート工場の見学の抽選に当たった子供たちとその親が招待されますが、ちょっと困った子供たちは次々にひどい目に遭い…というメインの物語は、バートンらしい毒のあるユーモアと個性的なキャラや音楽がいっぱいで存分に楽しめます。
実はウォンカは、子供の頃にショコラティエになることを決意しますが、歯科医である父親(クリストファー・リー)にチョコレートに関するすべてを禁じられたため家出し、その反動で現在の地位を築き上げた、という過去がありました。
子供たちの中で唯一まともな心優しい少年チャーリー(フレディ・ハイモア)に説得され、ウォンカは久しぶりに父親が営む歯科医院を訪れます。待合室には、ウォンカの輝かしい功績を称える新聞記事の切り抜きの数々が、額縁に入れて飾ってあります。患者を装って診察椅子に座ったウォンカの歯並びを見た父親は、目の前の男が我が息子であると気がつき、父と息子は長年の断絶を乗り越えて抱き合います。
私は、待合室の額縁のシーンで涙があふれ出てきました。自分の意に沿わないものとは言え、ウォンカの父親が自分の息子とその仕事の業績を誇りに思っていたことが分かるそのシーンで、私の父が皆さんに私の新聞での仕事を嬉しそうに話していたということを思い出したのです。私の父も認めてくれていたんだ、と自分に都合よく解釈しました。
心身共に憔悴しきっていたにもかかわらず、何かが降りてきたかのようにスラスラと『ロボッツ』の原稿が書けたのも、父の仕業だったんだろうと思いました。
幼い頃からテレビの洋画劇場を一緒に見ていた時から始まっていたのでしょう。たぶん親父はあの世で、ブツブツ文句を言いながらも、私のこの仕事を誇りに思い、応援してくれていると勝手に思っています。
ただ、最近になって気がついたことがあります。私は父と一緒に映画館で映画を観た記憶がありません。母たちも、そんなことがあったという話はしたことがありません。私がアルコールにあまり強くないので父と二人で酒を飲んだということもありませんでしたが、それよりも一緒に映画館に行ってなかったことの方が、とても心残りです。
(つづく)
<これまでのお話>
持続化給付投げ銭(サポート)、何卒よろしくお願い申し上げます!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
