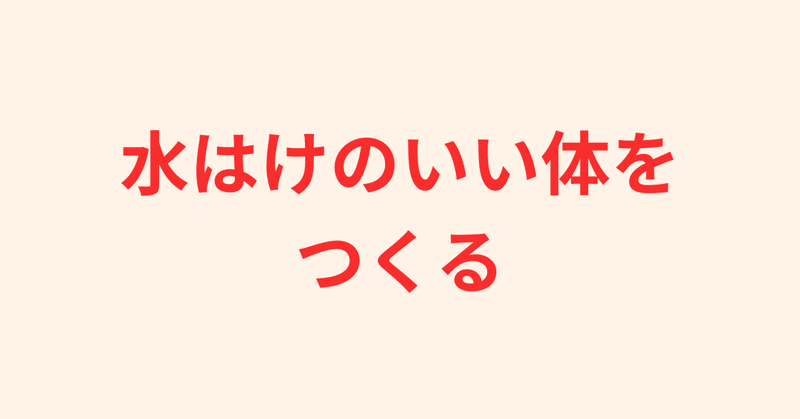
水はけのいい体をつくる
とにかく溜め込みたくない・・・!
「体が重い」 「むくむ」 「やる気が出ない」
水を溜めたバケツみたいに重く鈍い心身。
チャポンと重たいと、なにもかも億劫になったりしますよね。
この「重さ」を取り除き、水はけのよい体で過ごすための方法を
アーユルヴェーダの観点からお伝えします。
水はけのいい体をつくる方法
✔︎生理的衝動を抑えてはならない
出たいものを、閉じ込めない。
アーユルヴェーダの医学書「チャラカ・サンヒター」には、生理的衝動が生じた時これを抑圧してはならない。とあります。
体の自然な欲求=体内のバランスを取るために発せられると考えられるからです。
生理的衝動は13あります。
睡眠、食欲、喉の渇き、排便、排尿、おなら、ゲップ、くしゃみ、あくび、疲れたときのため息、涙、射精、嘔吐
これらの衝動を無理に抑えてしまうことで、体内のバランスが崩れ、とくにヴァータの不調が起こります。
ヴァータは「運ぶ」という動かすエネルギーを司るため、不調になると体内の巡りが停滞しやすくなります。
流れのよい体をつくるには、自然な衝動を抑えてはいけません。
「あ、きた」という時に「はいどうぞ」と促してあげることが重要です。
とにかく、抑えないこと、です。
✔︎カパを鎮めるケア
アーユルヴェーダの基本は「増えすぎたものを減らす」こと。 過剰になっているものを鎮静することで、もとのバランスに戻し自然な体の反応を活発にします。
「水」がたまる重い感じがする時は「カパ」が増えていると考えます。
その特徴は、冷たい・重い・湿り。
これは食べ物だけでなく、場所、運動、人間関係にも当てはまります。
冷蔵庫から出したばかりのおかず、飲み物、寒い部屋、動かないため筋肉が冷える、じめっとした人間関係・・・このようなことがカパの要素を増やします。
そして、真逆のものを取り入ることで鎮静させることができます。
主に温かい・軽い・サラッと消化しやすいもの。
温野菜
根菜でも軽めのにんじんや大根
火を通したおかず
フットワークを軽く
筋肉(特に足)を動かす
前向きな会話をする
太陽にあたる
・・・etc
重いときには軽いもの。冷たさには温かさ。
湿り気にはさっぱりしたもの。
嘘のようで一番効く処方箋です。
まとめ
水はけのいい体をつくるには
生理的衝動を抑えないこと
カパを鎮めること
温かく・軽く・さっぱりしたものを選ぶこと、これは食べ物も、人間関係も。
「反対の性質でバランスさせる」アーユルヴェーダの知恵をとり入れてみてくださいね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
