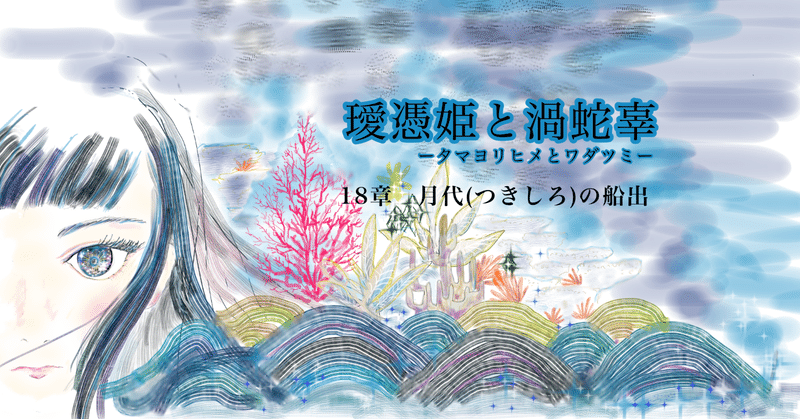
璦憑姫と渦蛇辜 18章「月代の船出」③
波座の様子がいつもと違うと礁玉は感じていた。
口に『波濤』を咥え、鯱はあらん限りの速さで陸から離れていく。咥えられた鉾の柄に掴まった礁玉はその速さに振りきられないように鯱の腹に身を寄せ、水の圧の中を進んだ。
切り落とされたワダツミの腕は固い意志で未だ『波濤』を握っていた。
ワダツミがどの程度の距離なら鉾を呼び戻すことができるのか分からない。だからできるだけ遠くへ離れなければならない。『波濤』がなければ水の獣や水柱を生み出すことができないのは、共に戦場にいた日々から予測がついた。
彼と対峙して最も警戒すべきは、海水を変幻自在に従える力だ。水の量と速さとを自在に操る彼を前に、数も力も知略も通じない。反対にそれを封じればどこかに勝機はあるはずだった。人ならざる者の人ならざる力の化身がその鉾であった。彼の手にそれがあることで戦局は常に彼に有利だ。ならば何をおいても先んじて『波濤』を奪う必要があった。
もちろんこの場合、ワダツミに協力者がいることは勘定に入っていない。この海で最も強いがゆえに孤高である。タマヨリをおいて他に並ぶ者はいない。その娘は断崖の上の林から引き離した。この勝負に入り込むものはいない。
ー追ってきたらどうする?
と礁玉は考えた。
ーその時は刺し違える。………いや、浪と亥去火を信じよう。
しかし礁玉は誰もいるはずのない海中に視線のようなものを感じるのだ。彼女の勘が告げる。
何かがおかしい。波座がもう長いこと浮上していない。いつもなら礁玉の呼吸に合わせて海面へ出るというのに。逃げることに専心しているせいだろうと思ったが、さすがに息が続かない。
ーあがるぞ、波座。
その鼻先を撫でて浮上を促したが、鯱は頑なに云うことを聞かない。そればかりか一層深くへ潜ろうとするのだ。
ーしょうがない。
礁玉は相棒から手を離し、ひとり海面へと向かって泳いだ。
その時、一匹の靭が彼女の正面に泳ぎきて、まっすぐに立ちふさがった。まるで一本の棒のように垂直にその胴体を伸ばし、首だけ不器用に曲げてこちらを睨めつけている。
常の靭ならそのような動きはしない。云い知れぬ不気味さと対峙したままでいると、靭が笑った。
礁玉は海中で短い銛のようなものを構えた。
「醜い傷じゃ」
靭は女の声で云った。
「人の分際で神と交わり、捨てられて牙を剥くなど………なんと身の程知らずな。賽果座の雌犬はあな恐ろしや………」
くくくと靭は笑う。
礁玉がすかさず放った銛は靭の体を刺した。魚は悶えたが声は変わらずつづいた。
「なんと野蛮な。報いを受けるがいい」
脚の下の海中に旋回している波座の影が見えた。
「その鯱はもう妾の術のうちじゃ。ギタギタに食いちぎられて死ぬがいい!」
靭は銛を刺されたまま硬直している。その魚の口から漂い出る澱んだ水のようなものの中に礁玉は不吉な影を見た。
ータマヨリ?
靭の口を借りていたのは乙姫である。不意打ちで死んだ体から、急ぎ意識をたぐり寄せた術師の似姿が映ったのである。
タマヨリと乙姫の顔は文字通り生き写し、輪郭あやふやな海中で見分けようはなかった。
礁玉は海面へ出ると呼吸をし、再び潜った。
迅る心音が危機を知らせる。このまま進めば黄泉下が口を開くだろう。
しかし、海中の波座は不自然な強張りに全身を侵され、聡明だった目は胡乱な濁りを湛えている。助けを求めたくて求められない苦しみだけが、彼女に伝わってくる。
ーあの女だ。なんだってタマの面をしているか知らないが、あの女は魚ならなんでも操るってとこだ。
のたうつように身を捩って旋回する波座のその体から、かつて発していた王者の風格も賢者然とした佇まいも消えていた。
ー大丈夫だ。あたしがなんとかしてやるよ。
礁玉は潜った。
人魚の血を引く彼女のおよそ魚じみた泳ぎは、驚くほどの深さまで潜ることができるのだ。ほとんど光の届かない場所まで潜り、礁玉は術の主ー乙姫の姿を探した。
ー術をかけた女………、あいつが誰だろうと見つけて仕留める。大丈夫だ。戦え、戦え!今も海賊衆は神を相手に戦っている、あたしが怯んでどうする。
ワダツミに協力する者がいるなら摘まなくてはならない。波座が術中ということは『波濤』も奪い返される。沈んでいた靭から銛を引き抜くと礁玉はそれを握りしめた。
しかし乙姫がいるのは遠い肚竭穢土の地である。礁玉に見つけようはない。
背後には波座が迫っていた。
ワダツミと亥去火の消えた断崖に海賊達は取り残こされ、その群れから離れた所で浪は黙って海を見ていた。
よかったのは『波濤』を奪うまでであとは算段が狂った。人外の術を使う者がもう一人いたとは、あれがタマヨリの話に聞いた乙姫という竜女なのだろう。海はワダツミの独壇場………、ではない。礁玉には波座がいる。まるでひとつの命をふたつに分けたように礁玉と波座は繋がっていた。何もかもを共有し、命じなくとも働いた。海の生きとし生けるものの頂点に立つものが彼女の半身なのだ。死にはすまい。
それより向こう見ずにワダツミを追っていった亥去火が気掛かりだ。
「あの馬鹿が………」
背後では海賊達が、動揺と興奮の中でてんでに云いたいことを声高に叫んでいた。
「舟を出せ!」
「そうだ!お頭と亥去火を助けにいくぞ!」
「行くったて海のどこに向かうんだよ!」
「海のどっかにはいるだろう!」
「どっかじゃ分かんねえんだよ、クソが!」
「沖だ!幾つか船団出してさがしゃあ見つかるだろう」
「そんなわけあっか!」
そこに坂道を駆け上ってくるウズの姿があった。カイとフナトと共に王の邸へ行ったはずの彼だった。
「お頭ーーー!」
息を切らし、倒れこまんばかりのウズに気づいた海賊達が道をあけた。その先から浪が駆け寄った。
「お頭は海だ。どうした、ウズ」
「来る………ハアハア」
「数は?」
「ハアハア、王下の水軍100人……ハ、寝返った海賊くずれ20人ばかり」
「分かった。おい誰かこいつに水を飲ませてやれ」
邸から体をかえりみず走ってきたのだろう。真っ赤を通り越して青ざめていくウズは仲間の差し出した水を啜った。
「カイが、出航の用意をしてます。……フナトは多分、捕まったかも………」
「舟の用意はうむ、よい判断だ」
浪は落ちた矢を拾い集め、使えるか確かめた。
「ここに賽果座の兵士が来るぞ、じきにだ」
浪に云われ海賊達はウズが駆け上ってきた道を振り返った。
ガサガサと茂みが揺れた。彼らの中に緊張が走り、得物を握る手に力が入った。
「待って!置いてかないでー」
と聞き覚えのある素っ頓狂な声がする。
「タマ、速いよー。ぎゃー蔓がハトの足を足を絡んで、やめてああー取れないー!」
「なーにやってるんじゃー」
紅い影がひらひらと揺れて道の先からタマヨリとハトが現れた。
「帰れって云ったくせにハアハア……、こんなに人がおって。不粋はみんな同じじゃな」
息を切らせながら、悪態と冗談をまぜこぜにタマヨリは云った。
「なあにみんなお頭のことが気になるのさ」
と浪は返したが、その口舌はどうにも上滑りであった。
「礁姐、どこ?」
とタマヨリが聞く。
「『いさら』がざわざわする、ワダツミの気配が遠くに行った、ねえ、礁姐はどこ?」
タマヨリの目は雨が降ったわけでもないのに、大水を被った林の様子をとらえていた。不安に飲まれそうな顔で浪に詰め寄った。
浪は成り行きを話した。
タマヨリとハトとウズの顔がどんどんと曇っていった。
つられて海賊達も先程までの喧々囂々のやりとりはどこへやら、浮かない顔を見せる者までいる。
「………云いたかねえけど、亥去火はもう戻ってこれねえんじゃ」
海賊のひとりがぽつりと漏らした。
「何云ってんだよ!あの人に限って死ぬなんてありえない!だってワダツミと互角だったんだろう」
息を整えたウズが立ち上がって反論したが、海賊は首を振った。
「互角と云えば互角だったけどよぉ、毒くらっちまってんだぞ。それにひとりで何ができるっていうんだよ」
「ハト嫌よ!亥去火とお頭を探しにいこう!」
ハトの勢いに皆が乗りはじめた時、浪は坂を下り始めた。
道の先から大勢の人間が迫ってくる気配がする。浪の後を追おうとする海賊を彼は手で制した。
「浪殿!」
と王の側近の男が手を挙げた。にこやかなのは口元だけで目にも体にも緊張が漲っているのが分かる。目の前にいるのは泣く子も黙る礁玉一味なのだ。
男が手を挙げたのが合図だったのか、後ろに控える兵士達が一斉に剣を抜いた。
「ああ、まだ話が終わってませんから」
と慌てた様子で側近はいちばん近くの兵士に云った。水軍の兵士長と思われる男は剣を納めさせた。
「で、あの女は?」
と側近が尋ねると浪は小首を傾げてみせた。
「今は海の上ですよ」
「取り逃した!?いや、みすみす逃したわけではないでしょうねぇ」
そんなことすればどうなるか分かっているのか、という口ぶりだった。娘の亜呼弥は今も乳母とともに社にいることをちらつかせている。
「まさか」
「あんた達は今からでも礁玉を追うべきだ!追って生け捕りだろうと屍だろうと、我々の前に差し出さなければ、もう国で生きていく道はないんだぞ!」
「なるほど根無草の我らを脅すにはもってこいの言種だ」
「あんた……初めから王や我々を裏切るつもりだったんだろう……」
「裏切る?」
「そうだ。王や臣下の信頼が厚いのをいいことに………」
「違いますよ。私が仕えるのは礁玉ひとり。最初から最後までね」
「はん!この国でおまえは全てを約束されたいうのに!恩知らずが!食わせものの賊徒め!」
「なんと云われようと、私はお頭が欲しいものを手に入れるために働くのみ」
王族を欺き、礁玉捕縛と偽ってワダツミに向けた罠を仕掛けた。ワダツミの首ひとつが有無を云わさぬ起死回生の一手だった。肚竭穢土は後ろ盾を失い岐勿鹿は袋の鼠となる。
和睦などというまやかしでつけ込まれた王族はこれで消えることになる。
礁玉は肚竭穢土を諦めない。誰にも奪われない国へと彼女は向かうのだ。
「なぜだ!おまえはこれまで我らと賽果座のために尽くした。巫女の婿として我々は受け入れた。なぜあの女なのだ!所詮、賊は賊ということか!」
「知っているでしょう、あの人とっても恐いんです。裏切るなんてとんでもないですから」
本当のことなどこの側近に云ってやる必要はない。
なぜ礁玉なのか?それは浪が人質として生きることを科せられた時まで戻る。
あらゆる才に恵まれた。そこで彼は彼を囲う者達のためにその才を活かすことが求められた。それでいいと思っていた。云われた通りにすれば待遇は格段に良くなった。己はそうやって生きてそうやって死ぬだけだと受け入れていた。
礁玉と亥去火に会わなければ彼は自由というものを問うこともなかっただろう。命知らず彼らの軽い命の向こう側にそれは泰然としてあった。
浪は外洋を渡る舟の仕組みを熟知し、波と風を読むことに長けていた。海渡りの一族であるコトウが見込んだ才だった。
ー私は……礁玉がいなければ迷ってしまうだろう。進むべき方角をいつも燦然と示してくれる、彼女は北の心星だ。
北の心星とは北極星である。海をゆく全ての者はその星を目印に進む。
側近は苛立ちを隠そうともせず顎をしゃくった。
「どうせそんなことだろうと思っておったわ。鼠がうろちょろとこれを盗りにきたのでな!」
側近は胸元から宝珠を取り出して見せた。しかし浪の目を奪ったのは兵士長によって引き立てられ地面に転がったフナトの姿だった。
袋叩きにあったのだろう。顔半分は潰れ変色した頬に血がこびりついていた。
「私の家族に手を出すな!」
常の浪からは想像できない罵声が飛んだ。海賊達は殺気だって、前へと進み出た。
その中からウズが走り出て、勢いのまま兵士長の首筋に蹴りを入れた。そのままフナトを抱え起こそうとする。
「フナト!フナト!」
引き剥がそうとする兵士に向けて石の礫が飛んだ。海賊のひとりが走り寄りフナトを自分達の方へ連れ戻した。
「あちゃー、フナト生きてるかー?ハトだよ、分かる?」
ハトが頬を叩こうとするのを止めてタマヨリが口元に水を垂らした。フナトがうめき声をあげた。
「さあ、怪我したくない奴は帰りなさい。先を急いでいるのでね、逃げるなら見逃してあげますよ」
浪の声に怯む兵士はいない。
「こっちには何人いると思ってるんだ。多勢に無勢だ。よし!礁玉の代わりだ。おまえら全員縛り首にして肚竭穢土に送ってやる」
側近の合図を皮切りに乱戦となった。狭い崖の上では数の優位は意味をなさない。浪が射かければ三人が同時に倒れた。歴戦の海賊達に兵士達は及び腰となった。
「下がれ!一斉に射かけろ!」
兵士長の命令に兵士達は列を組み直し、矢をつがえた。
盾を持たない海賊達は我先に木の影に入ったが、あぶれた者は的のように立ち尽くすことになった。
戦う意思のないタマヨリももちろんその中のひとりとなった。
だが矢が雨のように降り注いだ時、それは大きな水膜に押しとどめられた。
空中に現れた水のかたまりはタマヨリを中心に、海賊達を蓋うように広がり、全ての矢を受け止めている。
「浪、ここはもう終いでええんじゃろ?」
タマヨリが呼びかけると浪は諾なった。
「ワダツミのおる所は分かる。そこに礁姐も亥去火もおるんじゃろ?ならすぐに出よう」
「よし」
浪は側近目掛けて矢を放ったが、タマヨリはそれも水の壁で防いだ。
何が起きているのか分からず、唖然とする側近に近寄るとタマヨリは男の服の中に腕を差し入れた。
「すまねえなぁ、これはおれに預からせてくれ。多分、もう返すことはないが」
ガサガサと服の中から取り出したのは宝珠だった。そうされても側近は、タマヨリの得体の知れなさと芽生えた畏怖の念とで動けずにいる。
タマヨリの後ろに浪が続き、フナトを抱えたハトとウズが続いた。
その後ろから海賊達がゾロゾロとついてくるが、兵士達は手出しができない。
水は姿形を変え、海賊と兵士の間に壁となった。通り抜けることはできるが、よほどの力でなければ矢も刃物も水の中で失速した。
「舟は出せるのか?」
とタマヨリ問われ浪は頷いた。
「ああ、すぐに出航だ」
続く
読んでくれてありがとうございます。
