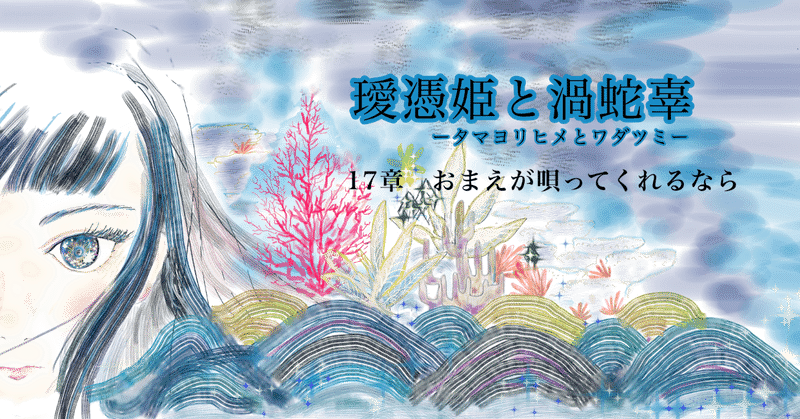
璦憑姫と渦蛇辜 17章「おまえが唄ってくれるなら」①
とこ永遠の国から現へと、海に死せる者はことごとく陸へと押し寄せた。その中にあってタマヨリは一心不乱に舞い歌い続けていた。
声は伸びやかに、律動はゆるやかに黒髪は潮風になびき、たんたんたたんと砂を踏む脚はしなやかに、しかしタマヨリの足元に渦巻く影は夜より黒く海の底よりも昏かった。
持ち主の動きに関わらず影は膨らんでは縮まって、それはあたかもひとつの生き物のようにふるまった。舞姫は聖と邪の汀へ変わっていった。知ってか知らずか湧き出る死者どもは誰もタマヨリの方へは寄ってこないのだ。
「『いさら』は元はといえば剣ではなく貝殻の欠片じゃった」
いつか乙姫の屋敷で、凪女を相手に話したことがあった。機織り機の前に座した凪女の手の中では杼が行き来していた。
「それはもしや瑠璃色の貝殻片ですか」
「そうじゃ。凪は知っとるのか」
「はい、お生まれになった時から握っておいででしたよ」
「えっ、そうなのか」
「乙姫様が何度とり上げようとしても姫様は握り込んでしまって。お可愛らしい手にどうしてそんな力があるものかと思うほど、ぎゅーっとなさって」
当時を思い出して凪女はふふふと笑った。その声も規則正しい機音に織り込まれていく。穏やかなひと時であった。
「赤子ながらにそんな怪力じゃったのか、おれは」
タマヨリは照れ隠しに凪女の足元ににじり寄った。
「いえ、そのご様子も可愛らしいくて、さぞ大切な物だろうと凪女は感服しましたよ」
「ううん。じゃあそれは生まれる前から持っておったのかなぁ。なあ凪、そのう、おれが、おれになる前、ワダツミが云うところの目も鼻もないよく分からん塊だった頃は、見たこと………あるのか」
不意に機音が乱れ、凪女の手から杼がすべり落ちた。
「あらあらまあまあ」
と凪女は動揺を抑えこんで鈴を鳴らすような声を立てた。
タマヨリは落ちた杼を拾って凪女に手渡したがその手は強張っていた。
「私としたことが……。しょうがありませんね」
と済まなさそうに眉根を寄せておどけると、貝殻片の話も生まれる前の話もそこで途切れた。
しかし凪女は覚えていた。海の割れ目から這いずり出てきたあれを。
彼女が目にした『下海』の卑しい生き物の中で、最も忌まわしい姿をしたものが主人にのしかかったのだ。
ー何も見てはいない。
そう思い込むほどそれはおぞましかった。
乙姫は水鏡を通じてその割かれた肉片と契約する。己の巫術に神々と匹敵するような力を与えること、『下海』を支配すること。その代償に胎をかしたのだ。
途方もない難産だった。生まれたのは輝くばかりの女児だったが、乙姫がその胸に娘を抱くことはなかった。
ーそれもやむなし。
と凪女は思った。一方で生まれた赤子はまるで穢れなく見えた。人の姿でかようにか弱く生まれたのは、相応の由があるのだろう。赤子には生まれたわけは分からずとも、長ずればその真意へたどりつく。
握りしめた貝殻片をそのままに、凪女はタマヨリを遠い南の島へと逃したのだった。
それが今、貝殻片から剣へと姿を変え、黄泉の者を従える儀仗へと変わった。
傍目には軽やかに踊るタマヨリだったが、足元に渦巻く影の重さを全身に感じていた。『いさら』にもうひとつの役目があるとすれば、本来の姿を封じる意味があった。正しく使わなければ、それが己に返ってくることを身を持って知った。
ひとつ間違えれば足元の影は主を食い破って、不可視の姿を顕現させるだろう。タマヨリの中ではあちらとこちらで綱引きをするように、別の方へ向かう力が拮抗していた。
手の感覚も脚の感覚もとうになくなっていた。泥のような疲労が全身を巡った。
ー亜呼………
と胸の内で親友に呼びかける。
ーおれの正体は魚の怪物じゃ。でも何を本当にするかは己で決めたらいいんじゃろ。亜呼もそうしたんじゃろ……
眼裏で亜呼の白い手が揺れて、『いさら』をとり落としそうになったタマヨリの手に添えられる。
巫女はタマヨリを支えて舞った。
水に還った巫女の魂は水鏡へ繋がる。だから海へは行かない。海に戻らなかった死者をタマヨリは呼ぶことはできない。
それでも亜呼が力を貸してくれているのを感じた。
人の身で生まれ、人の身で死んでいく。『竜宮』へ行くならそれは叶わないことなのだろう。だがせめて地上にあるうちは人の生を全うしたいと願う。その心内に寄り添うように巫女はそばにいてくれる。
ー仕合わせになってね………
そう云う声が聞こえたような気がした。
『竜宮』へ行く前にもう一度、人の姿のまま兄に会いたい。それは覚悟であり祈りであった。
「………兄ぃさの魂、ここに来い………」
憑かれたように踊るタマヨリの均衡を保っているのは、その最後の希みだった。
死者は戦を止めるだろう。人々は海と黄泉を支配する者を感じるだろう。そして『海境』は開かれるだろう。
そのための底なしの祈念の舞を可能にしているのは兄に会いたいという一心だったのだ。海も浜ももはや狂乱とも呼べる様相へ変わったが、死者の中に兄を見つけるまでは止まぬと思われた。
「波の手………… はこ……や わ………こえて…… 」
ついに声は掠れ、足の指の爪には血が滲んだ。『いさら』の刀身に映り込んだ亜呼の魂がタマヨリの身体に向けて手を伸ばした。
しかし受け止められるはずはなく、タマヨリの上体は傾ぎそのまま脚がもつれた。堪えようとするが『いさら』が手から滑り落ち、それでも声にならない声は海を呼んで、そのまま倒れた。
渦巻く影は正体定らぬものから、次第に魚影へと変わった。それでもタマヨリは起きなかった。倒れ伏しそのまま気を失っている。
死者はそれを避けて進むが、誰ひとり気に留めるものはいない。どれほどの数が呼び出されたのか、彼らの行進は止む気配はなかった。
一方、沖の小島では岐勿鹿は最初こそ先頭に立ち死者どもを蹴散らしていたが、きりがないのが分かると部下に任せて島の高台へと身をひいた。
賽果座は目の前だったがこれが続けば兵士たちは疲弊しきってしまうだろう。これらを差し向けたのが敵国でないのは、臨戦体勢で島を取り囲むも死者に四苦八苦する海賊の様子から察せられた。
己らが攻め込むまさにこの日、誰かが黄泉の軍団を呼び出したの偶然ではないと思われた。誰かがこの戦から手を引かせるため仕組んだことだ。
「ワダツミ殿!ワダツミ殿ー!」
兵士と馬と死者を掻き分け探すがワダツミの姿見当たらない。
「皇子、ワダツミ殿は渚におわしに!」
老体でひっしと馬の背に張り付いていた従者の於緑耳が教える。
「なるほど」
と唸った岐勿鹿が見たのは波の獣に周囲を囲ませたワダツミの姿だった。死者も近づけば獣の鋭い爪で霧散する。
「大海神よ、どうか知恵をお授け下さい!これはいったい誰の仕業なのでしょう!憎き賽果座を前に我らはどうすれば!」
岐勿鹿は波音に負けぬ大声で呼びかけた。彼を一瞥してワダツミは、
「なり損ないの神が浅知恵を働かせただけだ」
と『波濤』でひとなぎすると、周囲の死者どもは水に帰した。現れた一筋の道を彼はワダツミへと駆け寄った。
「老耄どもの機嫌をとったところで『海境』を越えた途端に、いいようにされるのが落ち。あれは分かっておらんのだ。己が力で開かない限り、『真海』の神々は我らに傅くことはない」
岐勿鹿には何の話か分からない。ただ今の事態が神々の駆け引きで起こっているのは察せられた。
「我々はいかなる時も大海神の徒卒です。ご指示あらばいかようにも動きます」
「いや」
とワダツミは突き放した。
「おぬしらはもう足手纏いだ。宝珠を奪うには俺ひとりでこと足りる」
「しかし!」
と叫んだ岐勿鹿をワダツミは上から睥睨した。
「あ………」
と岐勿鹿が口をつぐんだのは受けたことのない蔑視からでも、怖れからでもなかった。
この気まぐれな神の横暴が自国の兵士に及ぶかもしれない。それを直感し云い控えた。
ワダツミは波の獣を束ねるとその背に乗った。
「まず、この馬鹿げた死者の行軍の大元を断つとしよう」
そういうと全てを置き去りに、陸へと向かっていった。
物言わぬ死者の群れは、相変わらず波の彼方から波のように浜へ辿りつき海の衣を纏ったまま進み続けた。
二本の脚は生きていた頃と同じように土を踏んだが、踏まれた土はぐっしょりと濡れるのだ。
もう乾いた砂などどこにもない浜に若い死者が身を起こした。平たい足裏でぺたぺたと歩き始めた。水の体に水の衣、陸を目指して進むのは他の死者同様だった。違うのは列を抜け、倒れ伏したタマヨリの方へその下の影をもろともせずに近寄ってきたことだ。
身なりは漁師風の粗末なものだった。生前そのままに無頓着に結んだ腰ひもが左右ちぐはぐな長さで揺れていた。
「おうおう、やっと見つけた」
とその死者は嬉しそうに笑った。
「タマぁ、こんなところで寝ておったら風邪ひくでな」
とタマヨリのそばにしゃがみ込んでじっとその顔を覗き込んだのは、兄の海彦だった。
「うううん、やはり目がよく見えん。耳だってあんまりよくない。おらの口はちゃんと動いておるんかなぁ。長いこと暗い場所におったでな、いや長いのかも分からんな。おらは数えるのが下手じゃからな。昨日の前の前が何日前かも分からんし、しょうがないよなタマよ。
その代わりかなぁ、おら、鼻が随分ときくようになったでな。いや?鼻というかなんだかもっとよく分からん体ぜーんぶの感じでな、見聞きする代わりに嗅いでおるぞ。死んだら生きとる時と同じちゅうわけにはいかんもんやなぁ。でもな、兄ぃはちゃーんと戻ってきてやったぞ」
死者の声は生者にはぼおおおうよおおとしか聞こえない。波音でしかない。しかし海彦はそんなことはお構いなしに妹に語りかけた。
「おまえが唄ってくれるなら、星のないどれほど暗い海だって、おまえの元に帰れるんだよ」
と、そう云った。
続く
読んでくれてありがとうございます。
