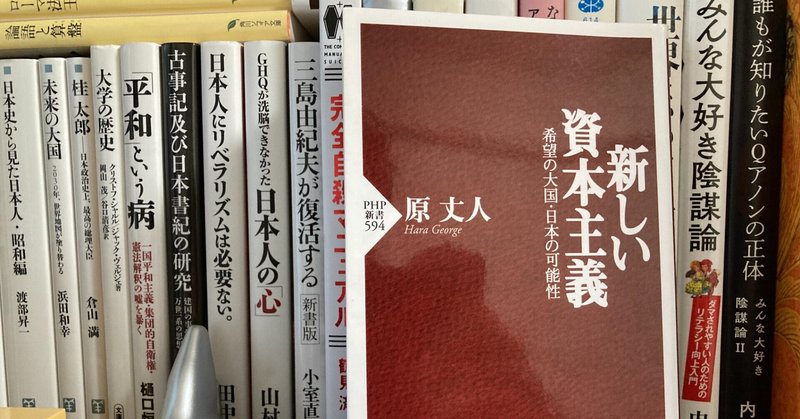
「新しい資本主義」原丈人(著)
「成長と分配の好循環」=「岸田首相の新しい資本主義」
岸田首相が今の日本を「新自由主義に蝕まれている」と述べ「新しい資本主義」の提唱を行っています。
分配を主にしている以上、新しい資本主義は財政出動をしつつ、財政規律を理由に増税をする政権の危険性を持っています。
今回この本を読んだ理由はまさに「新しい資本主義」という岸田総理の言葉から連想された本だったからです。
世界ではリーマンショック以降、資本主義は金融市場の影響を受けすぎて危険な状態になっていると考える人が多数出てきました。
2008年のリーマンショックは1929年の大恐慌と重ねられて、双方に共通する「金融」と「欲望」は資本主義において危険だという考え方が増え、新しい資本主義を模索する研究や意見が今に至るまで出続けています。最近、話題になっている「脱成長」「人新生」もその中の一つです。
本書は2009年に書かれていることから、リーマンショックを意識したと思われる部分が多数見受けられますが、それでも本書が提言している内容は現在の日本にも通じることが多いです。
私はこの本から、日本は議論だけは進むが、現実社会はその進んでいく議論を聞いたふりで変えていく気がないという、政治の固定化した状態を感じました。
・金融資本主義は危険?
岸田総理が「金融所得課税」を模索し、大きな批判を浴びたのは最近のことです。Financial Timesが「岸田ショック」と称した記事を発表したのはまさにショックな出来事でした。
Japan stocks suffer ‘Kishida shock’ as new leader suggests tax rise https://t.co/te4ODMptj3
— Financial Times (@FinancialTimes) October 6, 2021
アベノミクス以降、「数字の上では景気は回復しているが世間一般がそれを感じられない。株式市場だけが実感している」という言説が多く言われるようになったと感じています。
今年の春、日経平均株価がバブル以降初めて30000円に近づいた時、評論家の一部はバブルだと警鐘を鳴らしていました。
このような言葉たちだけを見れば危険だと思うのかもしれませんが、金融資本主義の問題点を著者はそこだけには見ていません。
著者は「利益目当て」で株主となり、会社の方針を自身の利益に誘導しようとする「アクティビスト」を深く憂慮しています。
「アクティビスト」によって会社の方針が混乱する現象は今年だと「東芝」に見られます。
今年の東芝は極めて慌ただしい一年だったように思えます。結果として分社化することになりましたが、それでも不安な人には不安なことでしょう。
著者は金融市場の本来の役割を長期的な会社の発展のための「支援」であるとし、自身の「利潤」を重視することではないと言います。そしてこの株主を中心に考える「株主至上主義」では金融資本主義は再び危険な状態になるかもしれないと言います。
実際、リーマンショック前後に「株主第一主義からの脱却」や「倫理資本主義」などの新しい資本主義の意見は出ていました。
重要なのは経済活動であるが、それは株主の利益を重視するだけでは不十分であるという著者の意見は従来の資本主義観とは差があります。
・日本の代謝を上げる
金融資本主義の危険性を説く著者ですが、それは決して金融市場を無視せよなどという極端な意見ではありません。どちらかと言えば金融市場に参加する人々に倫理観を求めているような気がします。
そのうえで著者は日本人がもっと金融市場に参加することを提案します。さらに日本の都市が国際金融都市になることも提言しています。これは確かに素晴らしいことです。
コロナ以前、政府や東京都は「東京」を国際金金融都市にするという目標のもとで、外資誘致の様々な政策を模索していました。
著者は日本の都市が国際都市へと発展するために、「税金を片っ端から下げていけ」と提案します。
G7で法人税を統一するなどという話がありますが、あれは自国の企業を海外に逃がさないためのルール作りです。
普通の企業であれば、負担する税金の少ない国にいた方が自由に使えるお金が増えますので、税率の低い国に行く傾向があります。すなわち、税率を下げると雇用してくれる企業がやってくるかもしれないのです。
経済活動が活発になるという点でこの提案はいいものだと思います。日本では増税が普通に行われ、財政規律の名のもとに国民は増税されることに抵抗がなくなっています。
著者は過去の日本の名君は、財政が危険な時には「コストカットを行い、市民が富を生み出せるように努めていた」という話を出し、今の日本にもその必要があると言います。
「個人の経済的自由が社会的自由を作る」というのはハイエクの言葉ですが、まさに今の日本に必要なのは経済の代謝を上げるために減税をして、経済活動を活発にすることなのです。
・終わりに
今回は本書の主に経済について部分を中心に書きましたが、他にも著者が国連と協力して発展途上国で行ったビジネスや援助について、日本が次の時代の覇者になるためにどのようなことが必要なのかなど、様々なことについてコンパクトに書かれています。
著者は金融資本主義を批判しますが、それは金融市場に倫理観を求めた「公益資本主義」という考え方で、きっとイーロン・マスク氏などに見るアメリカ流資本主義とは若干違う、興味深いものです。
分配重視の新しい資本主義ではなく、「自由」を大切にした助けある「公益」を重視した資本主義。実現できないことはない理想的な市場の形とも取れます。
ですが、倫理観の押し付けになってはいけません。利益追求は資本主義の基本ですし、倫理重視の政策は社会主義者の常套手段です。
そこは押さえた上で、資本主義の構成員である諸個人がどうあろうと行動するかが大事だと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
