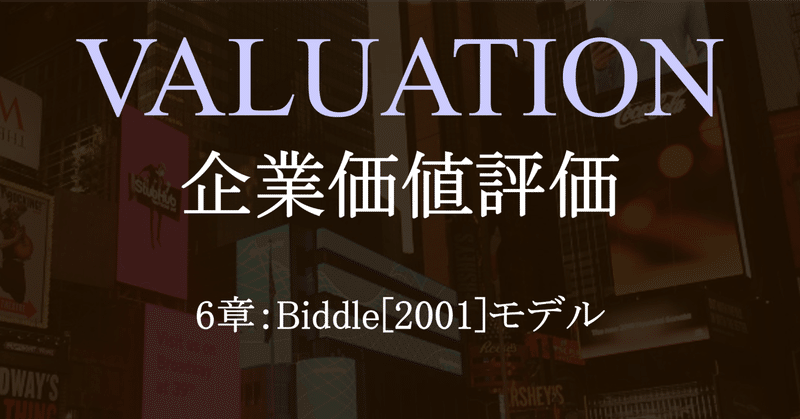
企業価値評価:Biddle[2001]モデル
前回までのOhlson[1995/2001/1999]モデルやFeltham-Ohlson[1995]モデルでは、残余利益の推移に線形の自己回帰モデルが仮定されていた。今回議論するBiddle[2001]モデルでは、企業の投資決定メカニズムを残余利益の減少過程に導入することで、合理的な企業行動によって残余利益の推移が非線形に変化するケースを扱う。前回はこちら。
Biddle[2001]は、投資プロジェクトが株主資本残余利益率$${\dfrac{x_t^a}{b_{t-1}}}$$により決定するとの仮定を残余利益モデルに導入することで、投資プロジェクトが超過収益を生み出す状況(正のNPV活動)におけるモデルを提案した。このモデルでは会計の保守主義を仮定していないため資本測定にバイアスが生じず、会計上の収益率は投資の内部収益率に等しくなる。
金融資産/負債のない企業 ($${b_t=oa_t}$$)において、純設備投資$${I_t}$$は、クリーン・サープラス関係(CSR)下において利益と配当の差として定義される。
$${I_t=oa_t-oa_{t-1}=b_t-b_{t-1}=x_t-d_t}$$
ここで、純設備投資と資産売却の効果を明示的に区別するため、以下の通り$${I_t}$$の符号により次の記号を導入する。
$${I_t^+=I_t \text{if} I_t≥0}$$
$${I_t^-=-I_t \text{if} I_t<0}$$
更に、$${t}$$時点の収益性$${q_t}$$を、期首資産に対する利益率と資本コストのスプレッドとして以下の通り定義する。
$${q_t\equiv\dfrac{x_t^a}{oa_{t-1}}=\dfrac{x_t}{b_{t-1}}-r}$$
Biddle[2001]は残余利益そのものではなく、株主資本残余利益率$${q_t}$$の成長を線形の自己回帰過程によって表現している。
Biddle[2001]モデルの線形情報ダイナミクス(LID):
$${\tilde q_{t+1}=\theta q_t+\tilde ε_{t+1}}$$
ここで$${0<\theta<1}$$は株主資本残余利益率の減衰速度を表すパラメータであり、市場における企業の競争力(顧客、立地、技術、管理スキル等)により決まると考えられるが、これらの要素が来期にも一定程度持続する傾向がある限り、LIDの正の相関関係は妥当であると言える。$${t}$$時点の1単位の純設備投資がもたらすスプレッドの現在価値の総和(投資の限界価値)は、
$${\dfrac{\theta q_t}{1+r}+\dfrac{\theta q_t^2}{(1+r)^2}+\dfrac{\theta q_t^3}{(1+r)^3}+\cdots=\dfrac{\theta}{1+r-\theta}q_t\equiv\Theta q_t}$$
と表せる。
Biddle[2001]モデルでは、投資の限界価値$${\Theta q_t}$$によって純設備投資額を決定する企業を考える。$${\Theta q_t≥0}$$の時に追加の純設備投資により業容拡大する一方、$${\Theta q_t<0}$$の時は資産売却により事業を縮小する時、期首の株主資本と期中の限界価値に依存して決まる純設備投資$${I_t^+}$$と資産売却$${I_t^-}$$は、以下のように表せる。
投資の限界価値と意思決定に関する仮定:
$${I_t^+=π_1 b_{t-1}\Theta q_t \text{if} \Theta q_t≥0}$$
$${I_t^-=-π_2 b_{t-1}\Theta q_t \text{if} \Theta q_t<0}$$
$${π_1>0,π_2>0}$$はそれぞれ、純設備投資と資産売却の機会を表すパラメータである。例えば、資金調達を随時円滑に実施できる企業であれば、投資規模を拡大しやすいと考えられるため、$${\pi_1}$$は相対的に大きくなる。資産売却の場合は、収益性の低い事業の清算を円滑に実施するための経済的、組織的な種々の制約の程度により$${\pi_2}$$の大小が決まる。
なお、上式では純設備投資/資産売却と限界価値の線形関係を仮定したが、より一般的に$${I_t^+=π_1 (b_{t-1}\Theta q_t )^{\kappa}, I_t^-=-π_2 (b_{t-1}\Theta q_t )^{\lambda}, \kappa, \lambda>0}$$と置いても以降の議論に質的影響を与えない。上記の仮定とLIDを用いて、以下の残余利益に対する時系列関係を導出することができる。
企業が純設備投資を行う場合
この時$${t+1}$$期の残余利益は次のように表せる。
$${\tilde x_{t+1}^a=b_t\tilde q _{t+1}=(b_{t-1}+I_t^+ )(\theta q_t+\tilde ε _{t+1})}$$
$${=θx_t^a+π_1 b_{t-1} θΘq_t^2+\tilde e_{t+1}=θx_t^a+\dfrac{π_1 θΘ}{b_{t-1}} {x_t^a}^2+\tilde e_{t+1}}$$
ここで、$${\tilde e_{t+1}=b_t \tilde ε_{t+1}}$$は平均0の擾乱項である。$${b_t>0}$$を所与とした時に$${\tilde x_{t+1}^a}$$の期待値$${E_t[\tilde x _{t+1}^a]}$$を$${x_t^a}$$で微分すると(あるいは$${q_t}$$で微分した場合でも同じことであるが)、
$${\dfrac{\partial E_t[\tilde x_{t+1}^a]}{\partial x_t^a}=θ+\dfrac{2π_1 θΘ}{b_{t-1}} x_t^a=θ\bigg(1+\dfrac{2I_t^+}{b_{t-1}}\bigg)>0}$$
$${\dfrac{\partial^2E_t[\partial x _{t+1}^a]}{\partial {x_t^a}^2}=\dfrac{2π_1 θΘ}{b_{t-1}} >0}$$
となることから、正の純設備投資を行う企業では、1期先の残余利益の期待値$${E_t [\tilde x_{t+1}^a ]}$$は当期の残余利益の増加関数かつ凸関数であり、両者の線形性を仮定したOhlson[1995]モデルとは対照的である。
上記の非線形関係式の通り、株主資本を所与とした時、当期の残余利益が大きい程資本効率(=スプレッド、同じことであるが投資の限界価値)が上昇し、当期スプレッド上昇が当期の純設備投資額増大及び1期先のスプレッド上昇(但し$${θ}$$だけ減衰するが)をもたらす。結果1期先の残余利益成長率が上昇し勾配が大きくなる。つまり、当期残余利益(=当期スプレッド)に関する凸性により、その増加が1期先のスプレッド上昇と純設備投資額増加の二重の効果をもたらす。
ここで、上記の2階の式$${=0⇔π_1=0}$$もしくは$${θ=0}$$すなわち純設備投資がゼロの時、後者の効果が消失し残余利益の時系列モデルは線形となる。また、残余利益を所与とした時、投資機会を表すパラメータ$${π_1}$$によって、純設備投資額ひいては1期先の残余利益が次のような影響を受ける。
$${\dfrac{∂^2 E_t[\tilde x_{t+1}^a ]}{∂x_t^a ∂π_1 }=\dfrac{2θΘ}{b_{t-1}} x_t^a>0}$$
$${\dfrac{\partial^3 E_t [\tilde x_{t+1}^a ]}{\partial {x_t^a}^2 \partial π_1 }=\dfrac{2θΘ}{b_{t-1}} >0}$$
すなわち投資機会の増大により、残余利益の時系列モデルの勾配及び曲率が大きくなる。
企業が資産売却を行う場合
この時$${t+1}$$期の残余利益は次のように表せる。
$${\tilde x_{t+1}^a=b_t \tilde q_{t+1}=(b_{t-1}-I_t^- )(θq_t+\tilde ε_{t+1})}$$
$${=θx_t^a+π_2 b_{t-1} θΘq_t^2+\tilde e_{t+1}=θx_t^a+\dfrac{π_2 θΘ}{b_{t-1}}{x_t^a}^2+\tilde e_{t+1}}$$
$${E_t[\tilde x_{t+1}^a]}$$を$${x_t^a}$$で微分すると、
$${\dfrac{\partial E_t[\tilde x_{t+1}^a ]}{\partial x_t^a}=θ+\dfrac{2π_2 θΘ}{b_{t-1}}x_t^a=θ\bigg(1-\dfrac{2I_t^-}{b_{t-1}}\bigg)}$$
$${\dfrac{\partial^2 E_t[\tilde x_{t+1}^a]}{\partial {x_t^a}^2}=\dfrac{2π_1 θΘ}{b_{t-1}}>0}$$
となる。純設備投資を行う場合、$${t+1}$$期の残余利益は当期スプレッドの二乗に比例して増加していくが、資産売却を行う場合、スプレッドのマイナス幅が非常に大きい、もしくはスプレッドに対し限界的に増える売却額が大きい($${=π_2}$$が大きい)場合、$${2I_t^--b_{t-1}<0}$$となり$${E_t[\tilde x _{t+1}^a ]}$$は$${x_t^a}$$に対し単調減少関数となる。これは、業績不振に陥った企業が大規模な資産売却により業容を縮小し、将来の損失を最小化するケースに相当する。純設備投資の場合と同様、$${π_2=0}$$もしくは$${θ=0}$$すなわち資産売却額がゼロの時、残余利益の時系列モデルは線形となる。ここで、パラメータ$${π_2}$$はスプレッドがマイナスに陥った企業における資産売却の機会の大きさを表す。
$${\dfrac{\partial^2 E_t[\tilde x_{t+1}^a]}{\partial x_t^a \partial π_2}=2θΘq_t<0}$$
$${\dfrac{\partial^3 E_t [\tilde x_{t+1}^a ]}{\partial {x_t^a}^2 \partial π_2}=\dfrac{2θΘ}{b_{t-1}} >0}$$
上式より、資産売却の機会増大に伴い企業が速やかに将来の損失を抑制することが可能となるため、残余利益の時系列モデルの勾配がフラット化し曲率が増大する。
投資の意思決定と残余利益の持続性
このようにBiddle[2001]モデルは、企業による内生的な投資決定のメカニズムを残余利益の減少過程に導入することで、残余利益の推移が単調ではなく、合理的な企業行動によって弾力的に変化し得ることを明らかにした。
企業の営業投資が合理的な判断基準に即していれば、投資の規模は確定した成果に応じて柔軟に変更される。より収益性の高い投資に資金が振り向けられれば企業が獲得する利益は増大し、残余利益も長期に渡り維持され得る。この場合、残余利益のダイナミクスは各期の利益水準に応じ非線形になる。
逆に、$${q_t<0}$$で投資の縮小を選択する企業では、縮小される規模が将来の残余損失の持続性に影響する。投資縮小に制約が伴わず、そのペースが迅速($${\pi_2}$$が十分に大きい)である程、来期の損失が少なくなる。従って$${b_{t-1}-2I_t^-\rightarrow 0}$$の時、投資変更後の持続係数$${\dfrac{\partial E_t[\tilde x_{t+1}^a ]}{\partial x_t^a}=θ\bigg(1-\dfrac{2I_t^-}{b_{t-1}}\bigg)}$$が小さくなり、速やかに損失が解消される。このケースでは営業資産の半分が清算されたとき、翌期の残余損失がゼロとなる。
このBiddle[2001]モデルを日本企業に適用した中條[2003]によれば、日本企業にも非線形ダイナミクスが当てはまる一方、株式の持ち合い構造が重要な影響を与えるようである。残余利益の持続性は、残余損失が生じている局面では他企業の支配が強い企業で相対的に大きくなる。つまり、企業間の取引関係が強い企業ほど低収益の営業投資の清算が遅れるため、残余損失が長く企業に流入する。営業活動の硬直化をもたらす資本構造は、株主に帰属する損失を拡大すると言えよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
