
◆レビュー.《ウケ・ホーヘンダイク監督『みんなのアムステルダム国立美術館へ』》
※本稿は某SNSに2021年5月14日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
ウケ・ホーヘンダイク監督のドキュメンタリー映画『みんなのアムステルダム国立美術館へ』見ましたよ~♪
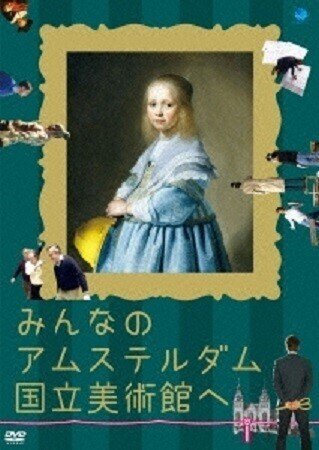
<あらすじ>
2004年、オランダで200年の歴史を持つアムステルダム国立美術館に改修工事の計画が持ち上がった。

アムステルダム国立美術館と言えばオランダの首都にあってレンブラントの『夜警』やフェルメールの『手紙を読む青衣の女』など数々の名作絵画を有するオランダを代表する美術館である。
改修工事の計画に着手したのは2004年の事。計画では2008年を目指して大規模な全面改修を実施する事となったが、美術館の敷地内を貫く公道の設計に対して、自転車王国アムステルダムの"サイクリスト"市民たちが猛反発。「自転車が通りにくい!」という事で設計の改善を訴えてきたのだった。

美術館スタッフと市民たちとの間に話し合いが持たれ、その間、改修工事はストップしてしまった。だが、問題はそれだけに終わらなかったのである。
市民団体からの批判、建築家との衝突、内装家との喧々囂々のやり取りなど、様々な問題が次々に起こり、紆余曲折を経て計画は延長に次ぐ延長を余儀なくされた。
忍耐の限界を迎えた館長は辞任。
新館長体制の元で人事も新たに、もう延々と続くかに思われた問題をようやく片付け、グランドオープンまで漕ぎつけるまでに、なんと10年の歳月を費やしてしまっていた……。
これは、問題に次ぐ問題によって右往左往する美術館スタッフ、そして改修工事スタッフらを10年に渡って取材したドキュメンタリー。
「何故オランダ最大の国立美術館は、10年ものあいだ閉鎖されていたのか?」
全4回にわたって放映されたテレビシリーズを映画化し、モントリオール国際映画祭のドキュメンタリー賞など数々の賞を受賞した名作ドキュメンタリー映画である。
<感想>
……というわけで、先日レビューでご紹介したフレデリック・ワイズマン監督の『ナショナル・ギャラリー 英国の至宝』に引き続いて美術館に関わるドキュメンタリー映画を今回も見てみた。
本作は『ナショナル・ギャラリー』ほどの傑作ではないにしても、「世界的な大美術館の10年に渡る改修計画の紆余曲折」という、専門家でなくとも興味を惹かれそうな題材を扱っていてなかなか楽しめる一作になっている。
ぼくは割とドキュメンタリー作品が好きなのだが、なかなか良いドキュメンタリー映画というものが手に入らなかったのでそれほど数を見れているわけではない。
今回はたまたま、アート系のドキュメンタリー映画が二本手に入ったので続けて見る事ができたが、そのためにいろいろと両作品を比較して見る事が出来たのは良かったかもしれない。
本作と、前回ご紹介した『ナショナル・ギャラリー』は、いい意味で結構スタイルが違っていて、その辺も楽しめる部分ではあった。
前回の『ナショナル・ギャラリー』はかなり客観的な作りになっており、極力作り手の作為を画面には込めず、出来る限り「編集」の効果のみによって作品として成立させるようにしてあったのが何よりもまず大きな特徴であった。
それに対して本作は、『ナショナル・ギャラリー』と比べれば多少の「演出」をかませているというのが印象に残った。やはり、元々テレビ・シリーズとして製作されたという事情もあったのだろうか。
本作ではちゃんと場面に合わせてBGMを使っているし(煽情的ではなく、クラシックによる静かなBGMといった使い方だったが)、物語の半分くらいはアムステルダム国立美術館のスタッフや、改修工事に携わった様々な業者たちへのインタビューによって成り立っている。
また、『ナショナル・ギャラリー』のほうは「あらすじ」さえ書けないほど徹底した客観主義に徹していたが、本作については、上記のように明確に「製作意図」が前面に提示された「ストーリー仕立て」が成立している。
だが、その中に「製作者のメッセージ」が直接伺えるほどの露骨な作為は感じなかった。
「製作者の顔」がちらほらと透けて見えるドキュメンタリーは、ぼくの中では点数が低い。
それが例えば監督がカメラの前に立って、「監督自身も含めたドラマ」として撮っているドキュメンタリーであれば、まだいいだろう。
イヤなのは「ここが泣き所ですよ?ここで感動してくださいね!」といった製作者の作為が露骨な作品だ。ああいう下品なドキュメンタリーを見ると、逆に胸やけを起こしたかのような気分になってしまう。
ドキュメンタリーの取材対象である人の「泣くシーン」をことさらクローズアップして、インタビューで涙を誘うような質問をしたり、人が涙を流している所を待ってましたとばかりにカメラで覗き込み、煽情的なBGMで盛り上げようという演出の下品さも興ざめである。
ぼくがこのごろ日本のテレビ番組制作のドキュメンタリーを見なくなってしまったのも、そういった下品さに嫌気がさしたからなのかもしれない。
本作がその「下品さ」を脱しているのは、あくまでも「10年に渡る改修工事の顛末」というストーリーを追う事を最大の目的として、取材対象の内面にまで影響を及ぼそうとするかのような「演出」を控えめにしているからかもしれない。
◆◆◆
本作がどういう作品化と言えば「アートをモティーフとした作品」というよりか、美術館という公共施設に関わる「建物のドラマ」であるともいえるだろう。
本作を見て最も強く感じるのは、「国立美術館」というものはあくまでも「公共施設」なのだ、という事である。
だから、市民団体から問題を指摘されたら、嫌でも従わなければならない。
本作に出てくる美術館職員や館長などは、市民団体や活動家などからの訴えを忌々しそうに見ており、「民主主義の悪用だ」とか「今回の問題が解決すれば、連中はまた別の問題を持ってくるだろう」等と文句を言っている。
Web上の本作のレビューなどにも美術館職員たちに同情して、「市民団体のわがまま」を非難する意見もちらほらとみられる。

だが、ぼくから見れば市民団体の言う事は意見として真っ当だし、それを言う権利は全力で擁護しなければならない。それが民主主義なのだから、仕方がない。
「市民のわがまま」等というのも、随分な意見だ。彼らからしてみれば、公共施設の変化というのは、自分たちの生活の変化と同義なのである。
何しろ「あらすじ」にも書いた通り、アムステルダム国立美術館はその建物の中央を公道が貫通しており、歩行者と自転車が非常に多く行き来しているのである。
「自転車大国」だというオランダのアムステルダムで、その天下の往来をいち国立美術館が自分たちの構想だけで勝手に変えてしまってもいいという事ではあるまい。
それに、何よりもアムステルダム国立美術館は国家からの予算でその活動費の大部分を賄っているのである。税金を投入している市民らの意見を全く無視していいというわけではない。
公的資金によって運営されている施設として、市民の声は絶対に無視してはならない。
だが、多様な立場のあらゆる市民の要望を聞いていたら、いつまで経っても改修のメドは立たないのである。
それに、「建築物」としての美術館の美しさも考えれば、素人の市民たちの意見を全て受け入れたために最終的に貧相な建物になってしまっては、元も子もない。
無様な恰好の美術館となってしまっては、オランダの美と文化を象徴する国立美術館がヨーロッパ中から笑いものにされてしまう。
「公共施設」として、「公」のものとしての義務として、市民の声は無視できない。だが、自分たちの理想も諦めたくない。
アムステルダム国立美術館のスタッフらは、そういう葛藤によって延々と問題を抱え込んでしまうのである。
あまりにも多く持ち上がる問題に忍耐が限界にきた館長は、改修工事の半ばで辞任してしまう。「人生すべてが美術館だというわけではない」。確かにその通りだ。
しかし、ヨーロッパのキュレーターというのは、さすが本場の美を司るプロだ――と、本作を見ていてつくづく感じさせられた。
やはり美術館職員という職業は、美に奉仕する仕事なのである。
美術館の内装は変える必要があるのか、展示室の壁の色はどうすれば作品の見栄えが良くなるのか、展示ケースはどういったものにすれば見やすくなるのか、展示品の並べ方はどのようにすれば観客の理解が促進するか……本作でアムステルダム国立美術館の職員たちは、改修工事スタッフや外部の建築家、内装家などとそういった事についていちいち喧々囂々と議論しているのである。
なるほど、これではそうそう簡単に計画が進むわけもない。
◆◆◆
日本のわれわれの感覚からしてみれば、改修工事の途中で問題が起こって市民団体らと様々な議論をしなければならないという事態が何度も何度も新聞やニュースで取り上げられれば、これは美術館の仕事に問題があるのだろうという感覚を覚えるかもしれない。
確かに、工事に取り掛かる前の改修計画の段階で、広く市民からの意見を聞き、そして話し合いの場も設けていれば……という事も思わないでもない。市民とのコミュニケーションに失敗したのだろう。これは事前準備の失敗というケースなのかもしれない。
だが、ぼくからしてみれば、このように美術館改築工事が伸びに伸びてしまった原因の一つには、確実に美術館職員が簡単に妥協しなかったという理由があるのではないかとも思うのである。
この工事が延長したのは、役人のごまかしでも手抜きによる問題の発覚でも手抜かりによる中断でもない。
全ては、オランダの「美」の看板を背負った美術館スタッフたちの自負と責任とこだわりの強さから引き起こされた問題の数々だったのではないかという気がするのである。
この映画を見ていて感じるのは、ヨーロッパの国家的美術館を支える職員たちの「プロの仕事」という意識の強さなのである。
「俺の記憶は写真並みだ。施設のヒビのひとつひとつまで完璧に記憶している」と豪語する美術館の施設管理人は、工事によって長年自分の担当していた施設が壊される時「悲しいよ」とつぶやいていた。
本作最大の"癒し系"人物であるアジア館マネージャーは日本の廃寺から阿吽の二体の仁王像を譲り受けた事を、ほほを上気させながら嬉しそうに語っていた。
だが、わざわざ日本にまで赴いて入手した仁王像も、改装工事中はずっと収蔵庫の中に眠らせておかねばならない。
「仏像には敬意を払わなければならない。それをこんな暗闇の中に……」と残念そうにつぶやいていた。

本作では、映画『ナショナル・ギャラリー』では取り上げられていなかった、美術館の作品調達プロセスを見せてくれたというのも、ぼくとしては嬉しい部分であった。
新館長の元、コレクション・マネージャーに昇格したキュレーターのタコは、ヤン・スホーンホーフェンの代表作がサザビーズに出展されているのを知り、館長に説明して落札の許可を得てオークションに電話参加するも、値段が高騰して予算オーバー。
「公的資金を使う美術館としては、払い過ぎは慎まねばならない」と言いながらも、悔しそうに項垂れていた。
様々な問題が持ち上がった事によって、国立美術館を10年間も閉鎖し続けねばならなかったという失態をおかしたとは言え、その裏には自分たちの仕事に妥協を許さない、誇りをもって当たる職員たちのプロ意識が流れていた、と評価したい。
2013年、やっとのことでグランドオープンにこぎつけ、大々的なパフォーマンスでオープニングセレモニーを行うアムステルダム国立美術館の様子は、本作では割と控え目に紹介されていたのも、どこか印象的な作り方だと思った。
この10年間、アムステルダム国立美術館に関わる新聞記事のすべてを切り抜いて廊下の掲示板に張り付けていた美術館の広報部長はこの映画のラスト、オープニングセレモニーを取材した新聞記事を掲示板に張り付けてから、最後にいたずらっぽくカメラに向かってウインクをした。
そして画面は暗転、スタッフロールが流れる。
過ぎ去ってみれば、これもまた全部、いい思い出だっただろう?
――とでも言いたげな表情であった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
