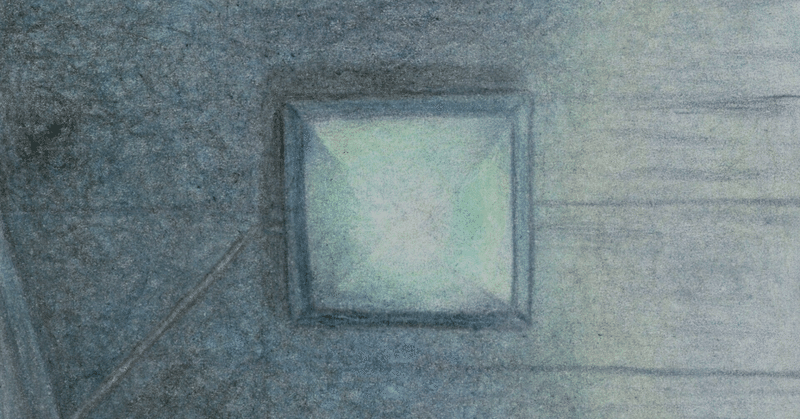
或るありきたりな物書きの夕べ
頭が重かった。
眼球の裏に、ざらざらした粗い砂が詰まっているような頭痛がしていた。
僕という砂時計は寝ている間にひっくり返され、頭に溜まっていく砂の重みで何も考えられなくなっていた。
風邪をひいたのだ、と気づいた。
今朝からほんのすこし、気怠さを感じてはいた。
でもそれは午後になって本格的な不調になっていた。
雨のせいだろうか、などとぼんやり考えながら、その日の執筆作業をなんとか終わらせた。
幸い、今日は休みだったので、外に出なくてはいけない用事もない。
いや、ひとつだけあった。
僕は知人のTさんのメッセージ画面を開き、その日誘われていた鍋パーティへ参加できない旨を伝えた。とても残念だった。
そのあと、心細くなって彼女に何度かメッセージを送ってしまうと、本当に何も考えられなくなった。
もう一文字だって、書くべき価値のあるものは浮かんでこないように思えた。
「だめだ」
僕は無理やり読もうとしていたレイ・ブラッドベリの文庫を片付け、PCと部屋の電源を落とし、ロフトによじ登り、毛布を引っ張り出して、それにくるまった。
ただ寝るためだけの場所になっているロフト。そこには何もなく、僕は独りぼっちだった。
明かりを消した部屋は空洞だった。
しかし、横になってしばらくその空洞を感じていると、僕の意識に浮かんでくるものがあった。
そしてそれは書き留めておかないと、後悔する類のものである気がしてならなかった。
「いや、これは後で見返したら全然大したことないものに決まってる」
僕は自分にそう言い聞かせた。
「今は休まなきゃだめだ」
しかし、そのアイデアの先触れのようなものは消えてくれなかった。
それは、まるで暗闇の中のうさぎみたいに、じっと僕をみつめていた。
「わかったよ」
僕は体を起こした。
頭の重みも一緒についてきた。
僕はシャワーを浴びたり、トイレに行ったりするときのことを思い出していた。
人間、書いてはいけないときほど、書きたいものが浮かんでくるものなのだろうか、などと考えた。
明かりをつけて、ロフトを降り、机に向かって頭の中のものを書き出していった。
「なにか、できそうだ」
ノートの上に羅列された文字列が、僕に何かを語りかけている気がした。
僕はその言葉を、残らず書き留めようとした。
けれどもその言葉たちは、古いラジオから聞こえる音声のように曖昧で歪だった。
「もしかしたら、また何か浮かぶかもしれない」
僕はノートとペンを握って、ロフトに登った。
明かりをつけて、それが訪れるのを待った。
しかしそうして身構えていても、一向にそれは現れる気配がなかった。
「もう寝ようかな。電気を消して、っと。……今なにかすごいアイデアが浮かんだら、書く前に忘れちゃうかもなあ。残念だなあ」
僕は空洞に向かって話しかけていた。
空洞は沈黙をつらぬいた。
あきらめた僕は、潔くまどろみに身をゆだねた。
夢をみた。
ものすごく素晴らしく、ものすごく愉快で、それでいてものすごく悲しい夢を。
目が覚めたとき、僕はすぐさまペンをとった。
「この感動を残しておこう!」
自分の中の狂喜につき動かされるままに、明かりをつけてノートを開いた。
しかしその眩しさのなかに、書くべきものはひとつもみつからなかった。
了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
