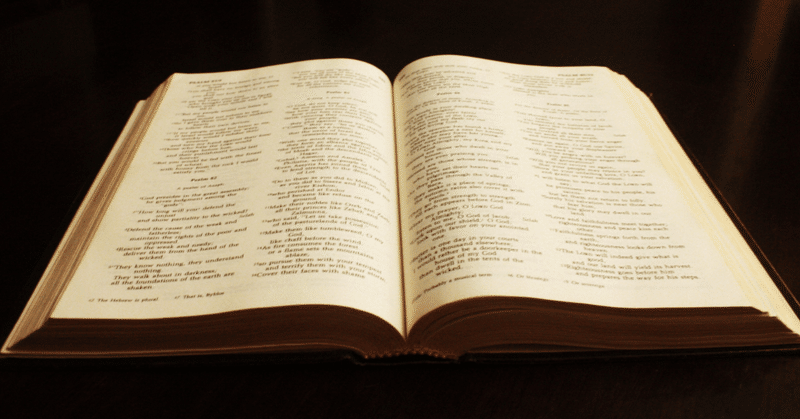
なぜ読者はフィクションと現実を混同するのか
以前、X(通称Twitter)で、『マダムたちのルームシェア』という漫画を見かけました。大変ポジティブなほっこりする内容の漫画です。それを何の気なしに読んでいたとき、大変どうでもいいことが頭をよぎりました。
パジャマパーティーをしてみるマダムたち🌙(1/2) pic.twitter.com/V7Tbd63mzq
— seko koseko (@sekokoseko) May 27, 2022
この漫画では、「栞」さんというマダムが登場します。実は、この「栞」という漢字が人名に使われるようになったのは意外と最近のことで、平成2年(1990年)からなのです。
現在は2024年なので、私たちの世界の中で栞さんという名前の方は、最も年長でも34歳ということになります。このような事実を念頭に入れたとき、上記の漫画に対していくつかの考え方ができます。
①当該の漫画の「栞」さんは、2024年現在34歳のマダムである。
②実は2060年頃が舞台である。
③私たちの現実世界とは異なるパラレルワールドである。というか漫画だし、作品の根幹にかかわることでもないので、そんなくだらないどうでもいいことにこだわるのは無意味で不毛。
①や②の考え方は無理があるように思えます。③のスタンスがおそらくごく一般的なものになるかと思いますが、本来は私自身も③の立場です。このような些細なことで『マダムたちのルームシェア』の品位が落ちることはないでしょう。
しかし私はたまたま、「栞」という漢字について知ってしまっていたため、ふとなんとも言えない違和感が頭をよぎりました。果たして、読者は作品に対して、こんな無粋な指摘をすることが許されるのでしょうか。そもそもフィクションが我々の現実世界の背景と整合性を持つ必要はあるのでしょうか。
虚構の約束
小説にしろ、映画にしろ、漫画にしろ、私たちが一般的に親しむ物語はフィクションと呼ばれる、虚構の語りです。ドキュメンタリーとしてノンフィクションを描き出そうとするものを除いて、程度の度合いはあれ、作り話だといえるでしょう(ドキュメンタリー作品も監督の視点から再構成されていることを考えると、創作の一種と考えられるかもしれませんが、ここでは複雑になってくるから触れません)。
本来フィクションを受容するとき、事実(曖昧な言葉ですが)の部分と虚構の部分を分けて考える必要はないはずです。なぜならフィクションの物語はすべてひっくるめて虚構の話をしているからです。逆に言えば、どんな内容であれ物語を受容する際には、その物語の中の虚構に対する猜疑心を一旦棚上げし、全てを受け入れなくてはいけません。「クモに咬まれたからといってクモ人間になるわけがない!」なんて言うのはルール違反なわけです。
ウンベルト・エーコ(Umberto Eco, 1932-2016)は、このようなルールについて、読者は暗黙のうちにテクスト(あるいは作者)と「虚構の約束」を結んでいる、と述べています。
物語テクストに取り組む基本的な規則は、読者が暗黙のうちに作家と「虚構の約束」を結ぶことですが、コールリッジはこれを「不信の停止」と呼んでいました。
作者は本当のことを語っているというふりをし、読者はそれを本当のことだと思うふりをする、というのが物語を読む際の大前提です。それが許せなければ、その物語を読むことはできません。
しかし時折、読者はフィクションと現実を混同してしまうことがあります。冒頭の私の指摘はまさにその一例です。別に漫画が現実の日本の戸籍法規則に則している必要はありません。
もっと簡単な話にしましょう。たとえば、最近私の大好きな漫画『ゴールデンカムイ』が実写映画化しました。この漫画は日露戦争後の北海道が舞台ですが、アイヌの存在も大きく物語に関わっており、アイヌ文化をカジュアルに啓蒙するのに大きく貢献しています。実際アイヌ文化の専門家が監修に入っており、かなり詳細に取材したことがうかがえます。そのため、作中で出てくるアイヌの食事や文化は、かなり事実に基づいているのではないかと想像されます。
――どのように監修に関わっているのですか。
基本的に私はアイヌ語が専門ですから、アイヌ語の意味とか語形に関して間違っていないかどうかを確認するということと、作中のアイヌ語のセリフを作文すること、アイヌの登場人物の名前を考えることというのがおもな仕事です。その他に文化的な事項に関するアドバイスや、場合によっては話の設定そのものに関わることもあります。話の展開に従って、アイヌ関連の事項に関するチェック一般を行うことが私の役割ですね。
「『ゴールデンカムイ』監修者がおすすめ アイヌ文化を知る厳選12冊」(https://book.asahi.com/jinbun/article/13324324)
だからといって、作品のほかの部分も歴史的「事実」に基づいているのかというとどうでしょうか。例えば『ゴールデンカムイ』の世界では、土方歳三が函館戦争で戦死せず、その後監獄に捕らえられていたため、日露戦争後も存命していた設定となっています。もっというと、(あまりにも当たり前ですが、)日露戦争後の北海道で金塊争奪戦が繰り広げられる、という本筋もまたフィクション上の設定にすぎません。これは多くの読者は当然のように理解していることです。しかし(ほとんどいないかと思いますが、)あまりにもナイーブな、フィクションに不慣れな読者は、土方歳三のような実在した人物も登場するし、札幌や小樽といった現実の北海道の地名で物語は展開するし、実際に歴史的にあった事件をモチーフに漫画を作成したんだ、と思ってしまうかもしれません。このような読者は、漫画と現実の区別もつかない哀れなひとなのでしょうか。
フィクションと現実を混同してしまうひと
一見このような感想を持つのは、(私のように)学術的な訓練を十分に受けていない人であったり、フィクションに疎い読者に限られているように思えます。しかし実は珍しいことではありません。例えば、ウンベルト・エーコはアメリカの大学で行われた特別講義の中で、『薔薇の名前』の読者について、こんなエピソードを披露しています。
(…)最近になって(つまりは小説の出版から約三〇年を経て)、あるドイツ人がわたしに手紙を送ってきました。「キルヒャーの本を置いてあるブエノスアイレスの古書店を見つけたのだけれど、わたしが小説のなかで言及したのともしかして同じ店の同じ本なのではないか」と言うのです。(…)
本物の修道院や本物の手記を探した人たちは、文学の慣習に疎いナイーブな読者(…)なのかもしれません。しかし先ほど話に挙げたドイツ人の読者は、稀覯書を扱う古書店に通う習慣があって、キルヒャーについても知っている様子でしたから、教養も高くて、本や印刷物に詳しい人物に違いありません。つまり教養のレベルにかかわらず、多くの読者はフィクションと現実との区別ができない(あるいはできなくなってしまう)ということです。
和田忠彦・小久保真理江訳、筑摩書房、2017年、84-85頁。
この教養ある(しかし私と同じように分別が足りていないように思える)ドイツ人読者は、『薔薇の名前』について何もかもがノンフィクションであるとまでは考えていないでしょう。つまり、アドソという人物が、実際に中世のイタリアの修道院で起きた大事件を記した羊皮紙が、現代まで残っていて、それを翻訳したのだとまで信じ切っていたわけではないと思います。ただ、フィクションとしてこの物語を構成するとき、作者のエーコが実際に訪れたブエノスアイレスの古書店が存在するのではないか、つまり一種のモデルがあるのではないか、と考えたのではないでしょうか。これはそれほど突飛な考えとは思いません。実際、『薔薇の名前』の次回作である『フーコーの振り子』の執筆において、エーコはパリの街を何度も歩き、風景を観察したという旨の話もしています。現実のパリをモデルに話を構成しているわけです。
この章を書くためにわたしは、幾晩もテープレコーダーを片手に、目にする物事や印象を記録しながら、同じ道のりを繰り返したどってみました。
そういった逸話をふまえると、物事はそう単純ではないことがわかります。以前『HHhH:プラハ、1942年』という特殊な小説について、いろいろな方が書いた感想を読んだことがあります。この小説はまるで著者が小説を書いているときの心情を残したかのような、エッセイ的形態となっています。ナチスドイツという比較的直近の歴史を扱っており、かなり入念な取材を行った様子なども明け透けに書いています。私が読んだ感想の中で、「著者の独白が多い」、「著者による取材記録が(…)」、「著者の主観が(…)」といった文面を数多く目にしました。当たり前ですが、これは小説なので主人公の「私」は著者ご本人ではありません。これはそれなりに難解な小説なため、読者は比較的本を読みなれている人が多いわけですが、それでも多くの方が著者と小説の主人公を混同してしまったのです。
もちろん私自身も、冒頭の例だけでなく、性懲りもなく同じような経験を何度もしています。ボルヘス(Jorge Luis Borges, 1899-1986)の『アレフ』を読んだときがまさにそうで、なんとなく登場人物について本人の実際の交友関係を下敷きにしているのかなと思ってしまいました。実際彼の作品にはそういったものも多いし、主人公の名前も作者と同じ「ボルヘス」だし、多分主人公は著者自身なのだろうと思ったわけです。つまり物語の核の部分は想像力で創り上げられてはいるものの、あとは現実の友人たちへのオマージュのようなものなのでないか、と思い込んだのです。読み終わった後、元ネタを知りたいと思い登場人物名をネットで調べた時、ほとんど架空の人物であったことを知り随分と驚きました。後から考えれば小説なのだから当然のことです。それでもなんだかとても衝撃を受けたことを覚えています。
フィクションの許容限度
このように私たちは簡単にフィクションと現実を混同してしまいます。しかしそれはどうしてでしょうか。
ボルヘスにしろ、エーコにしろ、ビネ(『HHhH:プラハ、1942年』の作者)にしろ、物語世界と私たちがいる現実世界を意図的にリンクさせているように思えます。それによって物語世界へのより深い没入を促す効果があります。物語とは、ひとつの世界を構成することであり、読者をより強く引き込み、その世界に閉じ込める能力が高いものが、魅力的な物語だと言えます。
ここであげた例は技術的に卓越している作者の腕によるものではありますが、物語世界が現実世界をベースにして繰り広げられるという事象は、特別ではありません。むしろ、すべてのフィクション世界は必ず現実世界に依拠しています。というのも、究極的には私たちは現実世界の物差しでしか事象を理解できないからです。
テクストで「水」という言葉が出てきたとき、私たちはそれが「氷」を指しているのではないことを知っています。「東京」と書いてあれば、それは「パリ」ではないことを知っています。「ドアの取っ手」が「花束」を意味しないように、「電車」は「犬」ではありません。このようにあらゆる語りは共通の認識基盤を持っていなければ成立しません。
私たちは物語を読むときに、作者は本当のことを語っているというふりをし、読者はそれを本当のことだと思うふりをするという虚構の約束を結ぶわけですが、この約束によって、ある程度まで、読者は無条件にルール、あるいは世界観を受け入れることができます。
レックス・スタウトの探偵小説の舞台はニューヨークです。このとき読者は、ネロ・ウルフ(…)の存在を受け入れます。ウルフがハドソン川にほど近い西三五番街の、砂岩づくりの家に住んでいるということだって受け入れてしまうものです。それがほんとうにあるかどうか、またスタウトが物語を設定した時代に実在したかどうか、確かめに出かけることもできるでしょうが、普通そんなことはしません。
しかしなんでもかんでも無条件に受け入れられるわけではなく、許容される限度があります。あまりにも現実世界から逸脱した描写は、物語世界への没入を妨げてしまいます。
ですが仮に、ウルフの家があったのが当時も今も実在しない場所だったと認めるとしても、五番街でタクシーを拾ったアーチー・グッドウィンが、アレグザンダープラッツへ連れて行ってくれと運転手に告げたとしたら、それは認めるわけにはいかないでしょう。なぜって(…)アレグザンダープラッツはベルリンにあるのですから。
『アレフ』では、世界の一切を含む「アレフ」という神秘を目撃したことが語られます。ある家の地下室にあるちっぽけな一点に宇宙のすべて、世界の過去、現在、未来が同時に存在しているという凄まじい超常現象が、平易で明快な文章と、リアルな人間関係の描写などから説得力をもって語られます。このような現実には存在しない概念もまた、そのほかの描写を現実感のあるものとすることで、虚構のレベルを読者の許容限度内に収めていると言えます。
冒頭において、私は「名前の表記の問題」がこの許容限度を超えてしまったと感じたのだと思います。現実世界の論理から不自然な飛躍をしたように見えたのです。その意味で言えば、冒頭の疑問、フィクションが我々の現実世界の背景と整合性を持つ必要はあるのかについて、あると答えることができるでしょう。
おわりに
フィクション世界は現実世界に依拠しなくてはいけないため、必然的にフィクションは現実の延長線上にあります。作者はより完成度の高い世界の構築のため、狙ってその境界線をより曖昧にするような技術を駆使しますが、だからといって読者が過剰に没入してしまうことまで作者の責任になってしまうのでしょうか。
思うに読者もまたフィクションの約束事、つまり語られていることは虚構であることについて、よく理解しておく必要があります(日常生活では不要かもしれませんが)。その意味では、冒頭の私の指摘はやはり無粋で不要のものだと思います。例えばシェイクスピアの『冬物語』では、ボヘミアに海があります(現実ではチェコに海はありません)が、そんなことに関わらず、その作品は傑作なのです。多くの観客や読者にとって、許容限度を超えるほどの虚構ではなかったのでしょう。
言ってしまえば、フィクションの記述はすべて「フィクションにすぎないもの」ですが、そうやって切り捨ててしまうのも悲しいものです。なぜなら、フィクションと現実の境界線を確かめてみる行為は、実は多くのひとを惹きつける魅力があるからです。いわゆる「聖地巡礼」をする方が多いことからもわかります。物語世界を現実の物差しではかる行為はいささか偏執的な趣きがありますが、逆に現実世界に物語世界を拡張してみる行為は、我々の生きる少し息苦しい世界を鮮やかに色づかせる手段の一つであり、これもまた物語の持つ魅力かもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
