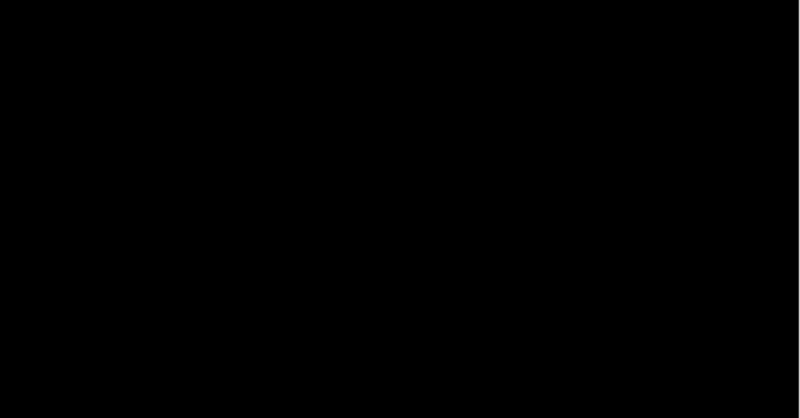
「姫」と祖母の自殺
夫婦喧嘩
元々仲の悪い両親でしたが、私が10歳頃が険悪のピークで、離婚やむなしの大喧嘩を繰り広げていました。
ときには祖母も入れた3人での戦争です。
その怒号は家の何処にいても耳に届きました。
その度、心臓が速く動いて、不安で眩暈がして、頭が痛みました。
ときに姉は両親の喧嘩を止めようとしました。
しかし、焼石に水で、彼女の必死の訴えは届きませんでした。
姉妹弟で一塊になって泣いて過ごしたこともありました。
全員が疲れて、病んでいました。
私が5年生になる頃、冷戦が始まりました。
両親がお互いを無視し、会話がなくなりました。
静かにはなりましたが、常に緊張の糸が家中に張り巡らされていて、息苦しい日々が3ヶ月近く続きました。
私の精神は限界を迎えていました。
神経過敏になっていたのだと思います。
その日、父の咀嚼音が気になって仕方ありませんでした。
無言の食卓。
父は咀嚼するとき口を閉じません。
クチャクチャクチャクチャクチャクチャクチャクチャ
水気のある汚い音が、
目の前で糸を引き咀嚼物が溢れ出そうな開けっ放しの口が、
嫌で、とにかく嫌で、耐えられませんでした。
父に「どうした?」と声をかけられてハッと気がつきました。
無意識に耳を塞ぎ、硬く目を閉じて、俯く自分がいることにです。
私は何でもないと答えました。
「何でもないことないだろう!」
不機嫌そうに父は声を荒げました。
目が熱くなり、声が震えました。
それでも私は何でもないと言い返しました。
父は更に不機嫌になって「言ってみろ!」と怒鳴りました。
それで思わず、言ってしまいました。
「どうして口を閉じて食べないの?」
父は一瞬、面食らった顔をしてから引き攣った笑みを浮かべ、揚げ足を取るように
「口を閉じたまま、どうやって食べ物を口に入れるんだ!? やってみろ!!」
と怒鳴りました。丁寧にジェスチャー付きで。
私はほとんどパニック状態で続けました。
「クチャクチャ音がする……。」
それを聞いた父は、そっぽを向いて力なく言いました。
「もう親子じゃない……。」
この言葉に私は衝撃を覚えました。
怒号を受ける痛みとは違う痛みでした。
もう声が出ません。
「親子じゃない。……お前は音をいっさい立てずに飯が食えるのか!? やってみろ! 出来ないだろ!」
声を荒げ、私を責めます。
論点はそこではないという話なのですが。
母は流石にこの状況はまずいと思ったのか、父に「そんなこと言わないで。」と言いました。
「うるさい! もう親子じゃない……!」
父は拗ねた子どもの様に反発しました。
その態度に母は肩を落とし、ぼそりと溢しました。
「もう出て行こうかな……。」
これに父は激昂して
「じゃあ出ていけ!!!」
と怒号を飛ばしました。
これに弾かれた様に私の身体は跳ね上がり、ダイニングから飛び出し、廊下を挟んだ向かいの和室に逃げ込みました。真っ暗な部屋の最奥に隠れる様に膝を抱えて小さく蹲りました。
心臓の音と両親の怒鳴り合う声が身体中に響き渡り、『どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう』と心の声が無限に渦巻いて、何も考えられませんでした。
そこに姉がやって来て、低い唸る様な声で
「あいつ、何処に行きやがった……。」
と、私を探し始めました。
私は身動きがとれません。
見つかるのが怖くて、目を硬く瞑ることしか出来ません。
そろりそろりと畳を擦る足音が私の前で止まりました。
「お前のせいだ。全部お前のせいだからな。」
そう言い残して、姉は去って行きました。
その後の記憶はありません。
再びの冷戦
再び両親はお互いを無視し始めましたが、
何度か怒鳴り合いの喧嘩もありました。
2階にいても2人の声はくぐもって届きました。
内容は聞こえません。しかし、言い争いしていることは分かります。
その音がザワザワと私の内面を掻き立て不安にさせるのです。
私は堪らず、自室を出て階段の上から階下の様子を伺いました。
父の「実行しろ!」という怒声が繰り返し聞こえました。
おそらく、母の「出て行こうかな……。」にかかった言葉です。
姉が目に涙を浮かべながら、2階に上がって来ました。
私の顔を見て、
「お前のせいだ。」
と憎悪込めて言い放ちました。
私は黙って階下を見つめることしか出来ませんでした。
希死念慮の始まり
私は始めて自殺を考えました。
自室のベランダから飛び降りて、何とか死なないものかと考えて、2時間ほど、ぼんやりベランダに立っていました。
当時、私の自殺のイメージは飛び降り自殺でした。
怪談や噂話で出てくる自殺方法の多くが飛び降りで、印象に残っていたのです。
しかし、自宅の2階からではとても死ねそうにありません。頭から落ちれば、死ねるかもしれません。
『でも、もし死ねなかったら?』
そう思うと手すりから身を乗り出してみたものの、辞めて、勢いを付けてみて、辞めて、結局飛び降りられませんでした。
ここからでは死ねないという結論に至りました。
しかし、もう死ぬしかありません。
自宅より高い場所など学校くらいなものですが、人目が多すぎて、そこで死ぬイメージが湧きません。
では、何処で、どうやって死のう。
毎日、そんな事を考えるようになりました。
食事
私はもう食卓に着けませんでした。
父の前で食事が出来ません。
「お前は音を立てずに食べられるのか?」
と言われるからです。
父のいない時間に食べるしかなく、満足に食べられません。
休日は食事を抜いたり、こっそり食パンを盗み食いして過ごしました。
この頃の記憶は空腹と共に蘇ります。
育ち盛りにはとても堪えました。
家にいる間は、ほとんど自室から出ませんでした。
姉が「部屋に食事を運ぼうか……?」と提案してきましたが、
私は拒否も賛成も出来ず「ありがとう……。」としか答えられませんでした。
お前のせいだと責める一方で食事を与えようとする姉に当惑しました。心遣いへの感謝と申し訳なさと、少しの怒りを感じていました。
私が余計なことを言ってしまったのは事実で、負い目でした。
どんな状況であれ、人の咀嚼音について面と向かって指摘するのはマナー違反だったと反省していました。
しかし、もはや私が父に謝って解決する問題でもありません。
父の怒りの論点は“私が出来ないことで父を非難した”という所にすり替わっているのです。
己がクチャラーという事実を無視して、私が咀嚼音を絶対に立てないかどうかに論点をずらし、何としても攻撃しようという構えなのですから、とても相手に出来ません。
それに、咀嚼音問題が解決したところで両親が不仲な限り、喧嘩が止む訳では当然ないのです。
姉の努力を否定したくはありませんが、彼女が介入したところで無意味なのはとっくに分かっていたことで、それを私に八つ当たりしていただけなのです。
家族を離散させたくない姉の気持ちを分かっているつもりでしたが、もうこの悪環境から脱せるのなら離婚も仕方ないのでは? というのが私の本音でした。
『早く全部、終わって欲しい。』それが私の願いでした。
母からの誘い
咀嚼音指摘問題から半月ほど経った夏休み目前の日曜日、祖母も含めた3人で大喧嘩が勃発しました。
それで、母が出て行くことになりました。
翌朝、目覚めから憂鬱でした。
昨夜の話通りなら今日、母が出て行くからです。
少しばかり私は責任を感じていました。
私が余計なことを言わなければ、母も余計なことを言わなかったのではないかと。
追い出される母を哀れに思い悲しむ反面、
正直、私は母を憎くんでいました。
喧嘩の原因の多くは父にありますが、火種はいつも母にあるように思えました。
毎日狂った様に喧嘩する2人は私にとって同罪でした。
母には経済力がなく、そのうえ世間体を何より気にするので、どんなに酷い事を言われても出て行けないのです。
それを分かっていて攻撃する父は邪悪でしたが、
己の食い扶持とプライドのために子どもの精神的健康を蔑ろにした母を肯定することは出来ません。
母の心の健康のためにも、父とは一度距離を置くべきだったと思います。
小学校に登校すべく、納戸で身支度を整えていると母が来て言いました。
「私と一緒に来ない? 〇〇(私)ちゃんもここには居辛いでしょう。」
私はこの誘いに応えませんでした。
確かにこの家に私の居場所はありません。
だからと言って母と共に生きていけるとは思えませんでした。
無言のままでいると、母は1階に降りて行きました。
祖母の死
外は夏らしい活気のある爽やかな光で満ちていましたが、
ダイニングは今にも窒息しそうなほど暗くて重い空気で充満していました。それでも各々がいつも通り家を出る支度を着々と整えていました。
そこに父が小走りで駆け込んで来ました。
血の気のない顔をしていました。
何事かあったようです。
洗い物をしている母の横に来て
「お袋が死んでる。」
と告げました。
母は驚いて食器を放り出し、父と共に祖母の寝室へ走って行きました。
私と姉は一瞬顔を見合わせて、両親の後を追いました。
私から見えたのは、開け放った戸の向こうに寝そべる祖母の異様に白い手足と、祖母の身体を揺すり何度も声をかける両親の姿でした。
父は
「お前たちは来るな!」
と叫びました。
私達は弾かれたようにリビングへ走りました。
私と姉は息を切らしながら再び顔を見合わせました。
私は震える声で姉に問いかけました。
「これから、どうなるの?」
姉は答えました。
「分からない……。」
それから続けて
「どうしよう、どうしよう……。」
と繰り返し言いました。
「おばあちゃん、自殺かも……。」
自殺
カレンダー裏に書き殴った祖母の遺書が見つかりました。
救急車をすぐに呼んだのですが、電話口で聞いた状態から手遅れと判断されたのか、だいぶゆっくり来ました。
何かの薬品を飲んだ形跡があり、それで心臓が弱まり呼吸が止まったのだと、姉妹は父から説明されました。
最終的に祖母は高齢による突然死とされました。
前日の夜、姉は自室の窓から、祖母が車庫から何か持ち出しているのを目撃したそうです。
それは農薬だったのではないかと、それを飲んで死んでしまったのではないかと、姉は涙を溢しながら家族に話ました。
私は祖母が自殺したことに疑問はありませんでした。
弟が生まれる直前、父がオーバードーズによる自殺未遂で救急搬送されたのを覚えていました。
母も自殺しようとしたことがありました。
姉のピアノの発表会の日程を間違えたというつまらない理由で、父に責められ死のうとしました。
結局、父に説得され思いとどまりました。
そして私も死のうとしていました。
前日の昼、死ねないと分かっていてもベランダにいました。
頭から落ちれば死ねる。
死ねなくても両親は我身を省みるかもしれない。
そう思って手すりに乗っかりました。
しかし、勇気がありませんでした。
中途半端に生き残ることが何より怖かったのです。
当時の私が確実に自力で死ねる方法を知っていれば実践していたでしょう。
それに祖母は性格に難がありました。
白黒思考の瞬間湯沸器で、衝動的な言動が目立ちました。
母をいじめ、父に暴言を吐き、孫が思い通りにならないと知るや冷たくあしらい、度々家の空気を最悪にする禍の様な人でした。
だから、祖母が自殺を選んだことは自然と受けとめられました。
ただ、その一方で私がまず思ったことは
『先を越された。』
でした。
そして、当時の私がどうしても受け入れ難いものがありました。
祖母が死んで、
離婚が有耶無耶になって、
家族がやっと纏まろうとしている、
やっと静かに暮らせる、
好転していると喜び安堵する私が確かにいることです。
大嫌いだったけど、好きでした。
嫌な思い出が多いけれど可愛がってくれた、幼児期の私には大切な人でした。
それなのに、
祖母が死んだことに安堵し、
喜んでしまったのです、
私は。
私が死ななかったから祖母は死んだのです。
私が死ぬべきでした。
私は生涯、幸せにはなれないだろう予感と、
私の死因は自殺で、天寿を全うすることはないだろうという絶対的な確信を得ました。
この確信が思考を歪め、破滅へ導くことになります。
葬儀
1学期はまだ数日残っていましたが、忌引きすることになりました。
通夜の席で父が
「何で死んじまったんだ! お袋!」
と大声を上げたのが、何だかわざとらしくて、空々しくて、思わず彼を凝視しました。
私の視線に気付いた父は、気不味そうにそっぽを向いて逃げました。
海外で仕事をしていた叔父家族が急遽、一時帰国しました。
棺の中の祖母を見て、叔父は泣き崩れ、義叔母と従姉兄弟達も涙を流しました。
その様子を遠目に、父は母と姉私弟を集めて言いました。
「自殺は お袋の恥だから、心臓が弱った末の自然死と言うんだぞ。」
私は、父の恥だと思いました。
しかし、何度も念を押して言うものですから、本当に祖母の恥なのかもと思いました。当時の私には分からないことでした。
祖母の死の真相は口外法度とし、我家の絶対のタブーとなりました。
少なくとも、当時の私の中に絶対に誰にも言ってはいけないことと刻まれました。
10歳の私には重く、生涯抱える蟠りとして残りました。
嘘を吐くことに罪悪感がありました。
真実を知らずに泣く叔父が不憫な気もしましたが、
真相を伝えたところで新たな戦争の火種になるだけと理解していました。
親の死に素直に涙する叔父を火の海に突き落とすようなことは出来ません。
でも、本当は言ってしまいたかった。
貴方の母と兄が私達にどんなことをしてきたか。
この家を壊してしまいたかった。
壊して欲しかった。
何も知らずにいる叔父、叔父の前では大人しい父、
2人に冷めた感情を抱き、大人達への不信感が募りました。
夏休み
葬儀が終わって数日、叔父家族は帰って行きました。
あんなに賑やかだったのに、家にはもう5人だけです。
私は家族を避けていました。
一緒に居るのが嫌でした。
しかし、夏休みで学校がありません。
田舎なので何もありません。
私の居場所は何処にもありませんでした。
昼食の時間になって、母が私を呼びに来ました。
私は、要らないと答えました。
母の顔を見たくありませんでした。
父と食事なんてしたくありません。
何もかもが嫌でした。
母が言いました。
「何だか避けられている気がするんだけど……。」
そりゃ避けてますもの。
「ねえ、ご飯食べようよ。
もう前に進もう。おばあちゃんが悲しむよ。
これからは仲良くしようよ。」
要約するとこんな事を羅列していたと思います。
もう忘れました。
的外れでフワフワしていて、遠回しに自分に非がないような物言いで、腹が立ちました。
加害者が被害者に言うことではありませんでした。
私の気も知らないで、黙って欲しかったです。
しかし、私は寂しい子どもでした。
家族愛に飢えていました。
家族を信じたかった。
拠り所が欲しくて、差し伸べられた手を取ってしまいました。
他に選択肢はありませんでした。
せめてこの時、家を出る選択肢があれば良かったのかもしれません。
久しぶりに家族5人で食卓を囲みました。
私は緊張のなかダイニングの椅子に座り、促されるまま、恐る恐る食事を口に運びました。
味なんて分かりません。ほとんど噛めません。
父は何か言いた気に、不機嫌そうに私の様子を見ていました。
母は「音を立てていいんだよ。音が出るのは普通なの。」と諭す様に言いました。
当時は私に言ったのだと思いましたが、今にして思うと父にも向けた言葉だったのだと思います。
父は黙って食事を始めました。
相変わらず口を閉じず、咀嚼音が無言の食卓に響きました。
私は無知で無力で、目の前の藁に縋ることしかできませんでした。
祖母がいなくなっただけで、他は何も変わっていないのに、きっとこれから良くなると信じてしまった私が愚かでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
