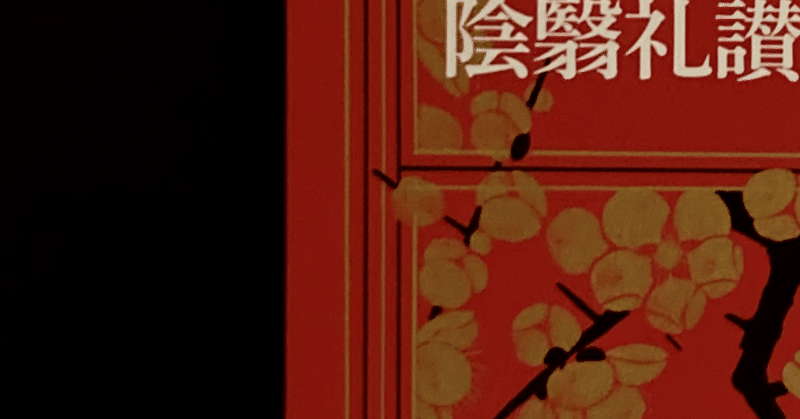
風流は陰の中に
私は以前、noteでこんなことを書いていた。
「変態」を認めたくないがため、私は未だに谷崎潤一郎を読んでいない。そう、興味津々のまま。
大学の教授にいつの間にか変態扱いをされていて、ショックだった故に、長らく谷崎潤一郎を読めなかった、というくだらない話である。
この記事を書いたのは、もう1年以上前だ。その間、私は谷崎潤一郎の作品に一度も手を出していなかったが、自らの「呪い」を解き、ついに読んでみた。

新潮文庫の美しい装丁、魅惑的な漢字の連なり。
ずっと前から気になっていた。陰翳を讃えるとは、どういうことか。
随筆のため、いわゆる変態文学ではないものの、谷崎の文章は、私にはどう読めるのか、少し緊張しながら1ページ目を開く。
銀食器、ダイヤモンド、タイル、陶器…
部屋を、生活を、なんとか明るくしようと、ぴかぴか光るものを用いて光を取り込もうとした西洋。
対して東洋は陰影の存在を認め、暗がりを利用して美しいものを生み出してきた。
東西の生活空間における、光と影の捉え方、美の感じ方の違いを論じた本書。
谷崎は、東洋の陰影を生かした美的感覚に軍配を上げる。谷崎は家を建てた際、和風のインテリアには相当凝ったそうだ。
未だ電灯というものがなかった時代。
蒔絵や漆器などは暗がりに沈みながら時折、蝋燭の火のもとで装飾を瞬かせるからこそ美しいのだと、谷崎は語る。
そんなふうに考えたことはなかったけれど、確かに、と納得してしまった。
蝋燭の炎しか明かりがない生活は、どれほど不便なものだろうかと思う反面、空気のかすかなふるえに瞬く蝋燭の炎の下で見る、蒔絵や漆器の美しさはいかほどだろうか。
さぞ美しいのだろう。
そのことがよく分かる文を引用してみる。少し長いが、これがまた美文なのだ。
つまり金蒔絵は明るい所で一度にぱっとその全体を見るものではなく、暗い所でいろいろの部分がときどき少しずつ底光りするのを見るように出来ているのであって、豪華絢爛な模様の大半を闇に隠してしまっているのが、云い知れぬ余情を催すのである。そして、あのピカピカ光る肌のつやも、暗い所に置いてみると、それがともし火の穂のゆらめきを映し、静かな部屋にもおりおり風のおとずれのあることを教えて、そぞろに人を瞑想に誘い込む。もしあの陰鬱な室内に漆器というものがなかったなら、蝋燭や燈明の醸し出す怪しい光りの夢の世界が、その灯のはためきが打っている夜の脈搏が、どんなに魅力を減殺されることであろう。まことにそれは、畳の上に幾すじもの小川が流れ、池水が湛えられている如く、一つの灯影を此処彼処に捉えて、細く、かそけく、ちらちらと伝えながら、夜そのものに蒔絵をしたような綾を織り出す。
金箔の施された屏風絵や襖絵なども、豪華絢爛、派手、下手をすれば俗悪に見えるが、ほの明るい蝋燭の灯る、暗い部屋にあるからこそ丁度よく、風流なのだろうと想像する。
例えば予期せぬ停電に見舞われた時、例えばアロマキャンドルでもつけてみようと部屋の電気を消した時、暗闇の中に光る懐中電灯なり炎なりが、包み込むような心の落ち着きをもたらすのは、たんに不安をかき消すからだけでなく、電気のなかった時代の生活の感覚を、前世から甦らせるからなのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
