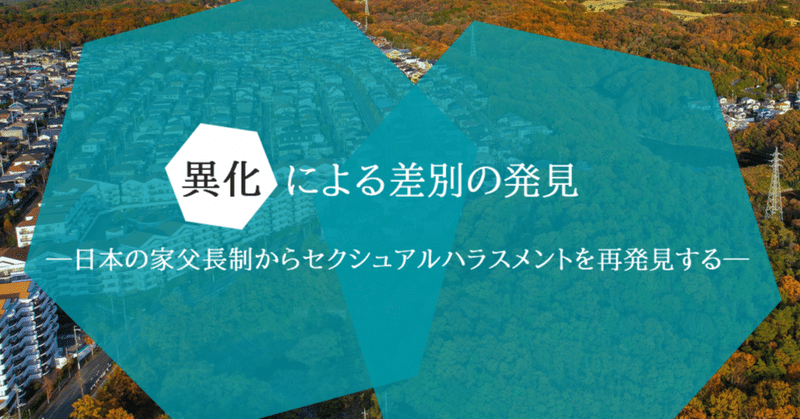
異化による差別の発見―日本の家父長制からセクシュアルハラスメントを再発見する―
1.はじめに
「労働施策総合推進法」の改正(パワハラ防止対策義務化)に伴い、大企業は令和2年6月1日から、中小企業は令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務化された。
私も中小企業に勤める身として、会社の顧問弁護士からハラスメントに関する研修を受けたが、それはあくまでも、制度上における説明に留まっていた。内容は、ハラスメントの定義と、どのような場合にハラスメントと判断されるのか、ハラスメントの類型やハラスメントにおける社内への影響などである。
たしかに、会社としては社員に研修を受講させ、あとは社内制度を改正してしまえば、法が求める要求には応えた形になる。
しかし、果たしてこれで本当にハラスメントが減るのだろうか。
多くの人間は差別をしようと思って、差別的な言動をするのではなく、それを差別的だと考えずに、あるいは、知らないままに発言、行動する。これを、「配慮が足りていない」「知識不足」「人権を軽んじている」「女性蔑視だ」……、と非難することはできるが、では、なぜそうした言動が繰り返し行われるのか。
政治家や事業家や芸能人など、高い社会的地位におり、様々な知識や経験を有している有能な人物であっても、ハラスメント的失言から多くの非難を受けることがあり、そうした現状を認識しているにもかかわらず、何故、ハラスメント的、差別的な言動をしてしまうのだろう。
セクシュアルマイノリティへの侮蔑的な発言や、ヘイトスピーチ、白人至上主義的な活動など、そうした明らかに意図的な差別的言動には一定の理由や要因を見いだすことはできるが、日常における何気ない一言や行動が差別的なものである場合、そこにはどのような理由、要因を見いだすことができるだろう。
ひと口にハラスメントといっても、その種類は多岐に渡るため、今回はセクシュアルハラスメントについて考えて見たいと思う。
そのために、近代日本の家父長制が生まれた背景から、現代の女性の社会進出と私的領域おけるケア労働(家庭の家事、育児、介護などの無償労働)を見ていこうと思う。
今回の試みは、日本社会のジェンダー規範、ジェンダー役割が生まれた背景と、日本の男女の働き方とケア労働への従事から、セクシュアルハラスメントとなる差別を再発見し、悪意がないゆえに厄介な差別的言動を予防する可能性を論考するものである。
その元となる考え方が、タイトルにもなっている<異化>することである。
2.<異化>することによる差別の発見
差別的言動を差別であると認識できない人にとって、その人物の言動を差別的であると指摘したとしても、「そのような意図はなかった」「反応が過剰すぎる」などと、自らが持つ無意識の差別に気がつかないどころか、逆に自らを正当化しようとする。
「労働施策総合推進法」に具体的な罰則規定は存在しない。しかし、2022年5月にピクシブ社に勤めるトランスジェンダーの社員が、男性上司からSOGIハラスメントやセクシュアルハラスメントを受けたとして、約555万円の損害賠償を求めて東京地方裁判所に提訴したように、法的な罰則はなくとも、ハラスメント的行為から訴訟を起こされ、懲罰的な結果を招くことは起こりうる。起訴までいかなくとも、減給や懲戒処分など、会社からの罰則を受ける場合もあるだろう。
意識的、無意識的を問わず、差別意識を持つ人にとって、ハラスメント的言動を控えようとする動機付けは何になるのかといえば、やはり、このような社会的制裁を避けるためだろう。
しかし、懲罰の恐れからハラスメント的言動を予防することでは、根本的な差別意識を取り除くことには繋がらず、かえってそれが行きすぎた結果、バックラッシュが発生し、「言葉狩り」や「言論の自由の侵害」といった言説から反発を生むことになりかねない。
これらを踏まえた上で、綿野恵太(2019)『「差別はいけない」とみんないうけれど。』(平凡社)より、以下を引用し、<異化>することについて、考えて見ようと思う。
アリストテレス以来の西洋の演劇は、登場人物に感情移入させ、怒りや悲しみといった感情を観客に抱かせようとする。ブレヒトは、このような演劇手法を「感情同化」と批判し、観客が登場人物から距離をとって批判的に眺めることを可能にする「異化」を提唱した。……いまではさほどめずらしさを感じない演劇理論を思い浮かべた理由は、「異化」とはまさに差別批判のことだからである。
差別を差別と認識しない(できない)私たちにいかに差別を認めさせるか。これが反差別的な言説や運動が持たざるをえない困難だった。しかし、その困難ゆえに、反差別闘争とは、新しい差別を発見する/発見させるという、すぐれて創造的な行為ともなる。それは、ある意味で、私たちの日常の生活や風景を「異化」させる行為でもある。「異化」とはある出来事から「既知のもの、明白なものを取り去って、それに対する驚きや好奇心をつくりだすこと」だからである。
(※1)
(強調引用者)
ここでは、自らの差別性を認識しない、できない人に、それを理解させる1つの手段として<異化>することを提案している。
差別性は突然自らの内から生まれ出るものではない。必ず、どこかにその源泉があり、それを発見することで、普遍的であると信じていた規範が、そうではないのだと気づき、自らの差別的な価値観や考えを知ることが可能となる。
セクシュアルハラスメントが行われる潜在的な理由を探る上で、日本の家父長制についての研究を元に、日本のジェンダー規範、ジェンダー役割の源泉を知り、女性を私的領域へ閉じ込めてきた背景を見ていく。
3.歴史・制度的観点からみる日本女性のジェンダー役割の形成
世界経済フォーラム(World Economic Forum:WEF)の「ジェンダー・ギャップ指数2021」によれば、日本は156か国中120位、先進国の中では最下位という結果が発表された。これは、日本社会が政治や経済といった公的領域から女性を締め出してきた結果といえる。
古来より、男性優位な社会形成は世界的になされてきた。白人男性至上主義、生物学的決定論、生殖のイデオロギー……、様々な理論で男性の優位性は正当化されてきたが、現代日本のジェンダーを考えるに当たっては、儒教と明治政府の国策から近代の歴史的背景にジェンダー規範の源泉を求め、それが女性にどのように受容され、更にどのように現代まで維持されてきたかを考えていきたい。
3.1.良妻賢母主義と「銃後」安定のための女子教育
「良妻賢母」という言葉の意味をWebの無料事典サイト「kotobank」で調べてみると、ブリタニカ国際大百科事典には、
女子の本来の任務は家を整え,子を産み,子を育てることにあるとする思想に基づいた婦人の理想像を表わした語。つまり,よき妻であり賢い母であることが婦人の理想とされ,したがって教育の目標とされた。(※2)
https://kotobank.jp/word/%E8%89%AF%E5%A6%BB%E8%B3%A2%E6%AF%8D-149966
(2022年07月01日最終アクセス)
と書かれている。現代の感覚から照らし合わせると、時代遅れといえる概念である。
日本を含む東アジアは儒教文化圏とされているが、明治時代の日本では、それが政治的に活用された。というのも、瀬地山角が指摘している通り、良妻賢母は、明治政府が日清戦争の経験を経て、「銃後」の安定には女子教育が必要であると認識したことから、国策として、良妻賢母主義が取り入れられてきたからである。
以下「儒教における女性像」について、瀬地山角(1996)『東アジアの家父長制 ジェンダー比較社会学』(勁草書房)より、引用する。
『列女伝』などにみられるように、古くは夫を諫める存在としても評価されていたが、中国の代表的な女性史家陳東原[1927]によれば明末ごろからはいわゆる「女子無才便是徳」といった考えが広く普及するようになる。無知で男性に盲目的に従属する存在としての女性像はいっそう強くなるのである。(※3)
明治政府は、男女平等とまではいかないまでも、国家統合のためには女子教育が必須と考え、儒教を意図的に読み替えて、『家庭の安定』と『未来の国民を教育する母性観』の構築のために、女子教育を推し進めた。
これは、女性が家を側面から支える者と捉えられるが、あくまでも主体は男性であり、政府は性に基づく役割分業を国策として実施したのである。
このように良妻賢母主義の教育とは、決して単なる封建的な教育ではなく、儒教の徳目を重視しながらも、そのなかに次世代の良質の国民の再生産のために教育する母という形で西欧の女子教育観を取り入れ、さらに国家統合の必要から国家にまで視野の広がった女性を要求するというすぐれて近代的な女子教育なのである。
(※4)
「家」も「良妻賢母」も政治的な意図の元に作られた、近代的な産物であり、決して普遍的でも、伝統ある規範でもないということを、ここでは押さえておきたい。
3.2.「母性」を生み出した日本近代家父長制
日本における近代的な家父長制は、良妻賢母主義を強力な核として、「男性が生産活動、女性が再生産活動」を担うという構図が形成された。
しかし、瀬地山角が指摘している通り、良妻賢母主義の受け手である妻、母は、自分たちが置かれた状況から、これを積極的に受容していった。
日本では夫婦間の情緒的なコミュニケーションがあまり多くなく、女性は子供を産むための存在であるという側面が強かった。
男系の直系線の継承が非常に重視された日本の家族形態もあっては、「女の腹は借り腹」でしかなく、女性は子供を産むための存在であった。……経営体としての「家」がしっかりと存在する一定の層以上では、「嫁して三年子無きは去る」という言葉の示すとおり、女性は子供を産むことで初めて嫁ぎ先のなかで安定した地位を得ることができた。
嫁ぎ先の親との同居が一般的で、夫婦間の愛情も希薄であった時代において、妻・母としての女性が、その孤独を埋める存在として我が子に、感情的な結びつきを求めたのは、当然の結果といえるのかもしれない。
良妻賢母主義の、「子の教育を母が行うべきである」という規範は、そうした女性達にとって受け入れやすいものであった。
大正期に核家族の下、生みの親(母)による育児が強調された時代は、
折しも学歴による労働市場の分断がはっきりしはじめた時期であり、新中間層にとって「我が児の将来」のためにすべきこととは、教育投資であった。……こうして一九二〇年頃、子供の出生率、死亡率がともに低下し、子供は多生多死から少産少死へと移行する。労働力としての子供から愛情の対象、教育投資の対象としての子供が生まれるのである。
(※6)
このようにして、夫婦愛の希薄さと母性愛の圧倒的な強さから、日本の近代的家父長制が誕生した。戦後においても、昭和恐慌のあおりから、政府が厳父に代わって慈母を称揚することで、「家」の保全をはかろうとした(※7)。
こうした母性愛の強調は、戦前から現代まで一貫して、日本社会に強い影響を与えていることは、現代を生きる私たちも実感できるところである。
4.女性の社会進出とケア労働
これは、独身男性の私よりも、子供を持つ共働きの既婚女性の方や、シングルマザー、シングルファザーの方が特に実感されているところだろうが、仕事・家事・育児の三つを同時にこなすことは、非常に困難を極める。
そして日本において、家事と育児は女性の役割とされてきた。前述でみた通り、母性愛の強調から、特に育児は女性が行うべきものという風潮は強く、企業によっては男性の育児休暇を取り入れているところもあるが、その利用率もまだまだ低い。
ここでは女性の雇用率と、社会の家事、育児に関する男女格差についての実態と意識を統計的にみていきたい。そこからみえることは、女性が社会進出を目指すことと、家事と育児の両方をこなすことを求められていることであり、更には、雇用状況や賃金から明らかに男女で格差が生まれていることが分かる。
4.1.女性の雇用労働率と賃金について
厚生労働省の『令和2年版働く女性の実情 「I 令和2年の働く女性の状況」』(※8)をみると、25~65歳以上の女性の労働力率が過去最高を記録している。
もっとも高いのは、未婚者の「25~29歳」までの労働率が93.1%を記録している。有配偶者をみても、平成22年の調査から全体的に上昇傾向にあり、結婚・出産後の雇用継続率、あるいは再雇用率の割合も高まっているのか、有配偶者の20~39歳までの割合をみても、最低値でも70%を僅かに下回るだけである。
ただし、女性雇用者総数に占める割合でみると、正規雇用が45.6%に対して、非正規雇用54.4%となっており、男性雇用者総数に占める割合では、正規雇用が77.9%に対して、非正規雇用は22.1%となっている。
賃金に関しては、令和2年の一般労働者(常用労働者のうち短時間労働者以外の者)の男女格差は、男性を100とした場合、女性は74.3(前年同)となっている。正規雇用に限ると、男性を100とした場合、女性は現金給与額で 75.0(前年 74.4)、非正規雇用に限ると、現金給与額で 78.6(前年 77.9)となっている。
こうしてみると、女性の社会進出自体は進んでいるが、女性の非正規雇用の割合は高く、その上、男女の賃金格差は依然として維持され続けているというのが現状であり、雇用労働における女性軽視な制度的慣行を読み取ることができる。
4.2.女性のケア労働について
令和2年の内閣府男女共同参画局の「令和2年版男女共同参画白書(概要)」(※9)から、女性のケア労働(家庭の家事、育児、介護などの無償労働)にかける時間や意識の変容、育児休暇の取得率を下に、女性のケア労働への従事が、いかに重荷となっているのか見ていきたい。
女性のケア労働は、25~29歳は減少傾向にあるものの、以前として25歳以上の場合、最低でも週平均150分、最大でも300分近くと長時間にわたる。男性の場合は微量に増加傾向にあるが、年齢問わず低水準にあり、週平均50分程度である。
6歳未満の子を持つ夫婦に限ると、共働きの場合は、女性は週平均しておよそ370分、男性はおよそ84分に留まっている。専業主婦の場合、女性は週平均しておよそ565分、男性はおよそ75分となっている。
「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という性別役割分担意識においては、反対する者が男女ともに6割程度と、意識の改善はみられるが、上述のデータからみても、実際の役割の変化は見受けられないどころか、女性のケア労働時間は増加傾向にある。その傾向は、共働き場合の男性の労働時間の長さと、女性の短時間勤務という結果からもうかがえる(それでも、25~29歳の女性の労働時間は増加傾向にある)。
男性のケア労働に従事する時間の短さは、育児に関わる時間からも見受けられる。未就学児のいる夫の育児への参加は、主に仕事がない日に偏っており、分担の割合は妻が7割、夫が3割程度に留まる。また、男性の育児休暇の取得率は低水準にあり、平成30年度の調査では、民間企業で6.16%、国家公務員で12.4%、地方公務員で5.6%となっている。
4.3.男性のケア労働への参加の難しさ
ここまで、女性の雇用率の上昇と男女の賃金格差、また女性のケア労働にかける時間の長さをみてきた。そこから、女性のケア労働の時間を短くすることで、女性の負担を軽減し、更なる社会進出に繋げ、ジェンダーギャップを改善できるのではないかとも考えられ得るが、それも難しい。
同じく「令和2年版男女共同参画白書(概要)」から、諸外国に比べると、日本は男性も女性共にも有償労働時間が長いことが指摘されており、2020年のOECD(経済協力開発機構)の調査では、日本男性は平均452分、日本女性は平均272分となっている。
このような働き方で、男女平等にケア労働に従事しようとしても困難を極め、結果として有償労働時間が男性より短い女性にしわ寄せがいく形になる。
4.4.未だに女性の領域となっている家庭のケア労働
家庭のケア労働(家事、育児、介護など)は、無償の労働として位置づけられ、またそれは、私的領域において女性が担うべきものとされてきた。その意識自体は少しずつ改善の方向へ進んではいるものの、実態はそれに追いついておらず、依然として、女性が多くの時間をケア労働に費やしている。その上で、女性の社会進出が同時に求められることで、女性への負担は増大している。
家庭のケア労働が女性に偏重しているのは、男性の有償労働時間が短縮されず、また男性の育児休暇が社会的に浸透していないことが挙げられる。
これらの事実は、男性が稼得役割を担い、金銭面で家庭を支えているという意識を植え付け、女性よりも尊重されるべきだという無意識を生み出しているのではないだろうか。ケア労働は、生活上欠かせないものであるにも関わらず、その価値が低く見られる傾向にあることは、清水晶子も指摘(※10)している。
女性が公的領域としての社会進出を高める中で、私的領域であるケア労働にも従事し、さらに公的領域内で男女格差が存在することで、女性そのものの価値も低く見られてしまっているのではないか。
本来、稼得役割もケア労働も同じくらい大切であり、家庭を支える上で、どちらも欠かせないものであるにも関わらず、そこに序列がつけられている。
我々は今一度、ケア労働へ意味づけをし直しす必要がある。誰もが子供であった時期はあり、老いて介護を必要とする時期もある。誰もがケアを受けており、ケアに支えられていることを自覚し、ケア労働の重要性を認識しなければならない。
現在、主に女性が担っているそのケア労働を再評価することで、女性の価値を高め、男性の意識を更に変えていく必要がある。
5.性別によるアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)
アンコンシャス・バイアスとは、日本語では「無意識の偏見」を意味し、簡単な例を挙げると「血液型がO型の人は大雑把だ」という思い込みなどである。家庭環境や社会経験やこれまで培われた知識などから、自然と生まれ出るもので、これ自体が悪いというものではない。
しかし、自分がもつアンコンシャス・バイアスに気がつかないでいると、無意識に相手を傷つけたり、差別したりする結果を招きうる。
内閣府男女共同参画局「令和3年度 性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査結果(概要)」(※11)によると、性別役割や思い込みについて、男女ともに5割もの人が、性別役割意識を持っているという結果となった。
特に仕事と家事の分担については、男性の方が性別役割意識が強いことを示している。
ただ、男女ともに「男性は仕事をして家計を支えるべきだ」に対して半数近い人が同意の傾向を示している上に、これもまた男女ともに「育児期間中は女性は重要な仕事を担当すべきではない」に対して30%以上が同意傾向を示している。
前述した通り、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という性別役割分担意識においては、反対する者が男女ともに6割程度存在することを挙げたことを踏まえると、意識的には性別役割分担意識について反対しているが、無意識の内に、性別役割が必要であると思い込んでいることになる。
先のケア労働の女性への負担も、アンコンシャス・バイアスの影響が多少なりとも反映された結果といえるだろう。
6.無意識な差別・セクシュアルハラスメントの発生—まとめにかえて
日本の母性を強調する家父長制は、明治政府の国家統合政策による意図的に強化されたものであった。そしてそれは、嫁ぎ先の親との同居が一般的で、夫婦間の愛情も希薄であった時代において、「子の教育を母が行うべきである」という規範は当時の女性達に受容されやすいものであった。また、戦後においても、昭和恐慌のあおりから、政府が厳父に代わって慈母を強調することで、「家」の保全を図っていった。
現代でも母性は強調され、育児は母親の領域という意識は強い。「育児期間中は女性は重要な仕事を担当すべきではない」という質問に対して、未だに30%もの人が同意していることからも、それが見て取れる。
育児を女性の領域とするということは、女性を家庭(私的領域)へと閉じ込めるものになりかねず、ジェンダー規範、ジェンダー役割の強化へと繋がる。
しかし、男女平等参画を目指す日本において、女性の社会進出を促す必要があった。結果として、女性は社会に進出しながらも、社会における雇用状況は男性よりも不利なものとなり、それは非正規雇用や賃金格差として現れ出る。加えて、元々は正規雇用であった女性が、結婚や育児の関係から時短勤務や非正規雇用になるケースもある。
さらには、有償労働時間が男性よりも短いことから、無償のケア労働が女性へと偏重し、女性の負担が益々増大する結果となった。
こうしたことから、私的領域=女性の領域という構造は維持され続け、特定のジェンダー規範、ジェンダー役割が、あたかも普遍的であるかのような見せかけが、アンコンシャス・バイアスとして男女の中に残存している。
私的領域で行われる家事や育児や介護といったケア労働は、稼得役割に比べると軽視されがちであり、結果としてそれに従事する者も、その労働に見合った評価を受けられない。
つまり、こうしたケア労働に従事する女性を低く評価する一方で、自分たちの稼得役割を高く評価し、女性軽視の傾向が生まれる。
女性の労働状況・賃金格差と、軽視されがちなケア労働を女性に押しつけることで、女性の立場を低く評価するアンコンシャス・バイアスが生まれていると思われる。
これらの要因から、結果として、男性の優位性を利用したセクシュアルハラスメントを生んでしまっていると、本論では結論づける。
今一度、『「差別はいけない」とみんないうけれど。』から、<異化>することについて、引用してみよう。
差別を差別と認識しない(できない)私たちにいかに差別を認めさせるか。これが反差別的な言説や運動が持たざるをえない困難だった。しかし、その困難ゆえに、反差別闘争とは、新しい差別を発見する/発見させるという、すぐれて創造的な行為ともなる。それは、ある意味で、私たちの日常の生活や風景を「異化」させる行為でもある。「異化」とはある出来事から「既知のもの、明白なものを取り去って、それに対する驚きや好奇心をつくりだすこと」だからである。
(※1)
(強調引用者)
今回、私たちは、女性が持つ母性が普遍的でも伝統的でもないことを知った。それでいて、現代でも育児などのケア労働が女性に偏重しつつも、社会進出を果たさなければならず、有償労働と無償労働の二重苦におかれていることを知った。
日本の家父長制を<異化>することによって、私たちは現在女性が置かれている現状の一部分を垣間見ることができ、今まで気がつかなかったアンコンシャス・バイアスを認識することができたはずだ。
しかしながら、本論考には課題がある。
政治的、社会制度的に、何故ここまでケア労働(家庭の家事、育児、介護などの無償労働)が軽視されてきたのか。女性を軽視する男性を心理学的に見た場合に何が分かるか。社会学や民俗学からみた、女性が側面から支える「イエ」の役割とはどのようなものか。こうした視点から見た場合に、また違った結論が導き出されるはずだ。
今回の論考は、日本の家父長制という、一つの窓から見たときの景色を拡張しただけのものであり、社会問題として、まだまだ考える余地は多く残されている。
それは大変な苦労であると同時に、その先に、問題解決の新たな糸口がある可能性という希望もまた存在するのである。
1つの考え、答えを得たからといって満足することなく、これからも多くの知見から、社会の問題解決に向けて考えていけたらと思う。
◆参考文献
※1: 綿野恵太(2019)『「差別はいけない」とみんないうけれど。』平凡社 p.310-311
※2:コトバンク「ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「良妻賢母」の解説」,https://kotobank.jp/word/%E8%89%AF%E5%A6%BB%E8%B3%A2%E6%AF%8D-149966 (2022年07月01日最終アクセス)
※3: 瀬地山角(1996)『東アジアの家父長制 ジェンダー比較社会学』勁草書房 p.129
※4: 瀬地山角(1996)『東アジアの家父長制 ジェンダー比較社会学』p.146
※5: 瀬地山角(1996)『東アジアの家父長制 ジェンダー比較社会学』p.149
※6: 瀬地山角(1996)『東アジアの家父長制 ジェンダー比較社会学』p.151
※7: 瀬地山角(1996)『東アジアの家父長制 ジェンダー比較社会学』p.165
※8: 厚生労働省 令和2年版働く女性の実情「I 令和2年の働く女性の状況」2020年, https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/20-01.pdf (2022年07月01日最終アクセス)
※9: 内閣府男女共同参画局「令和2年版男女共同参画白書(概要)」2020年,
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/gaiyou/pdf/r02_gaiyou.pdf (2022年07月01日最終アクセス)
※10: 清水晶子(2022)『フェミニズムってなんですか?』文藝春秋 p.112
※11: 内閣府男女共同参画局「令和3年度 性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)に関する調査結果(概要)」2021 ,https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/seibetsu_r03/01.pdf(2022年07月01日最終アクセス)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
