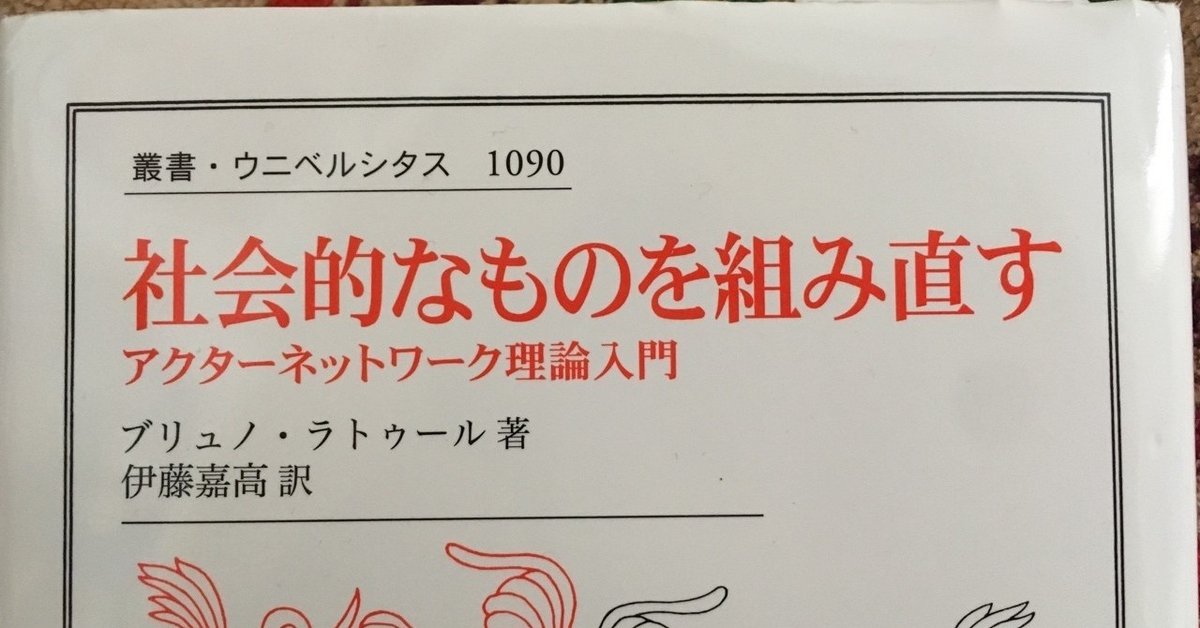
社会的なものを組み直す アクターネットワーク理論入門/ブリュノ・ラトゥール
まず循環がある。
循環があるからつながり、変化が起こり、生成が生じる。
社会があるのではない。社会という固定化された何ものかがあると仮定して、それを探そうとするから見つからない。そうではなく、社会が生成されてくる様に目を向けてみるといい。いや、目を向ける必要がある、その把握しきれないほど天文学的な数の生成の複数性に。
ブリュノ・ラトゥールが本書『社会的なものを組み直す アクターネットワーク理論入門』で伝えてくれることを大まかに示せばそういうことになるだろうか。
むずかしい内容ではあるが、さまざまなところに応用可能な考え方が詰まった本だと思った。
アクターネットワーク理論の射程
たとえば、「訳者あとがき」に、こうあるとおり、その考え方は、経営や組織を考えることにも有効だと思った。
アクターネットワーク理論は、その出自である科学論(科学社会学)の境界を越えて、さまざまな分野の社会学(都市社会学、環境社会学、家族社会学、医療社会学などなど)で幅広く摂取されるに至っている。さらには、経営学、組織論、会計学、地理学、社会心理学など社会科学全般に広がるとともに、哲学(思弁的実在論)や芸術に対しても強い影響を及ぼしている。
あるいは、ここにあげられた学問領域や、学問や研究の領域とビジネス領域との境界を越えての思考が必要となる、これからの持続可能性の問いを展開していくのに、アクターネットワーク理論(以下、ANT)は有効なものだと読みながら、つよく思った。
とはいえ、まあ、難解だ。
おまけに500ページ近くあるからさすがに読み終えるのに12日ほどかかった。でも、とても興味深い内容だった。だから難解さも、膨大な分量も、多少の苦にはなっても、読むのを中断する理由にはならなかった。
面白かった理由は、現実に日々形成されてある、僕らが実際に生きる「社会」というものを、決まりきった形式に押しこめて理解したつもりになるのではなく、きわめて現実的な常識的なものとして理解しようとする学問的姿勢に共感をもったからである。
社会という曖昧かつ現実には存在しないものを無条件に前提としてしまう非現実的な理解の仕方でわかったつもりになるのではなく、現実に存在するものを客観的かつ相対的に理解するためには、慎重かつ丁寧に「現実の循環」をたどることが不可欠であるという、そのANT的姿勢の意義が示されていることが、とても有意義にも思えたからだ。
僕らは、社会のなかにいない
ここで告白しておくと、僕はいわゆる社会学というものを知らない。
これまでラトゥール自身のものを除けば、社会学の本を読んだ記憶はほとんどないからだ。
だから、ラトゥールが「社会的なものの社会学」と呼ぶ19世紀半ばに立ち上がった学問としての社会学がどういうものかを理解していないし、ラトゥールがそれを批判する文章を読むとき、自分自身でその正当性を検証することはできない。ラトゥールの示すANTという新たな社会学方法が従来の社会学をどう乗り越えようとしているかを、ラトゥール自身が説明する以上の意味で理解する術はいまの僕にはない。
その前提に立った上で、ラトゥールのANTに「新しさ」を感じるのは、ラトゥールが社会と自然という二元論の虚構に焦点を当てて、自然がないのと同様に、社会というものもないとするところだ。
これで一安心だ! 私たちは社会の「なかに」いるのではない――自然の「なかに」いないのと同じだ。社会的なものは、私たちの挙動のすべてが埋め込まれている広大な地平面のようなものではない。社会は、偏在しておらず、すべてを把握しておらず、どこにでも姿を現すようなものではなく、私たちの一挙手一投足を見張っておらず、私たちの内に秘めた思いのすべてを聞いてはいない。
"私たちは社会のなかにいるのではない"。
社会なんてものを僕らは見たことがないのに、自分たちが社会のなかにいると信じ込んでいる。人間たちが暮らす場所を、これまた謎めいた「自然」なる場所とは異なるものとして、自然ではないものとしての「社会的なもの」から構成される場所を社会と呼んでいる。
社会とは何かと言われれば社会的なものから構成された場所だとトートロジー的な説明になることを、当の社会学者が発明したことをラトゥールは批判する。
目の前で起こるさまざまな現象を、自然だとか、社会だとか、実態のないブラックボックスを用いて説明してしまうこと、それを学問の対象にしてしまうことにラトゥールは疑問を投げかける。
自然と社会の分離のウソを暴く
科学がその視界から人間的なものを除外することで客観性を主張しようとするのと同様に、社会学は人間的なものに焦点を当てた姿勢を打ち出すためにモノや自然を排除してきた。
『虚構の「近代」』で、ラトゥールは、それを「近代憲法」と呼んでいた。
「近代憲法は、人間と非人間を完全に分離することを善とし、同時にその分離をないものにする」といい、「だからこそ近代人は無敵になれるのである」と書いていた。
「自然は人間の手が作り出したものではないか」とあなたが非難すると、近代人は、自然が超越的であること、科学が自然へのアクセスを可能にする仲介者であること、そこに人間がまったく介入していないことを露骨に示して見せる。そこで「私たちは自由だし、私たちの運命は私たちの手中にあるのではないか」とあなたが言うと、「社会は超越的だし、その法則は常に私たちを乗り越える」と近代人は切り返す。「それではあまりにひどい二枚舌ではないか」とあなたが抗議すると、定義不可能な人間の自由と自然法則を混同したりはしていないと近代人は豪語する。そのくせ、あなたが近代人を信じ、注意を一瞬、他に逸らせたとたんに、何千にものぼる物体を自然から取り出してきては社会集団に移し替える。さらに自然物が持つ確実性を社会集団にも求めてくる。それはあの「達磨さんが転んだ」という子供の遊びのようなものである。
この自然と社会の分離、そして、それを裏では闇取引するかのように互いに流通させる「達磨さんが転んだ」的二枚舌の戦略。
この戦略の上で、従来の社会学者が視界から人間以外のモノを排除し、社会を人間中心に描いてきた考え方にラトゥールは異議を唱える。
モノを舞台に戻す
現実問題、社会は人間だけでは成り立ちようがないし、そのような見方では社会そのものがわからないだろうに、何故そんなことが起こってしまっているのか?とラトゥールは、問い、本書でこう書いている。
「理に適った」社会学者よりも少しでも社会的な紐帯について実在論的でありたいならば、受け入れるべきことがある。それは、どんな行為の進行であれ、その継続性が人と人との結びつきによって成り立つことはまれであり(成り立つのであれば、基礎的な社交スキルでこと足りるものであろう)、モノとモノの結びつきによって成り立つこともまれであり、おそらくは両者がジグザグになって成り立っているということだ。
そう、「達磨さんが転んだ」で鬼が目隠してる背後で行われている自然と社会、いや、正確には非人間(モノ)と人間のあいだの循環に目を向ける必要を説くのだ。
社交スキルのみでは社会は成立しないし、その活動が維持されることはない。モノの役割に目を向ける必要があり、モノと人のあいだで繰り広げられる循環に着目する必要がある。
従来の社会学者が存在のあやふやな概念で説明してきたことを、ちゃんと現場で起こっているモノと人間との協働作業に目を向けて、それをもって説明すること。モノはさまざまな人びとが絡むさまざまな工程のなかを流れていきながら、ほかのさまざまなモノといっしょになりながら、変換され、翻訳され、生成され、構成される。そのモノ自体に、何が起こっていたかを報告されること。
それがANTの姿勢だ。
どんなもの―― 映画、摩天楼、事実、政治集会、通過儀礼、高級婦人服、料理―― の「作成(メイキング)」も、表向きとは十分に違った光景を見せてくれる。舞台裏に導いてくれて、現場の専門家のスキルやこつを見せてくれるだけでなく、どんな既存の存在であっても、時間の次元を加えることで、それまで存在しなかった物事が生まれるとはどういうことなのかを垣間見せてくれる類い稀な場ともなる。さらに重要なのは、次のような現場に導かれるときである。つまり、物事が違った展開を見せるかもしれない、あるいは、少なくとも、まだ失敗の可能性があるという、心を騒がせるような経験や心が躍るような経験がされる現場である―― 最終的にできあがったものに接するときには、それがどんなに美しかったり印象的であったりしても、そこまで深い感情を抱くことはない。
事後の結果だけを見るのではなく、まだ何が起こるのかが確定していない事前
――「変化」の前、「生成」の前、「連関」の前――のプロセス、循環に目を向けるのだ。
従来の社会学者はモノのことは多少気にかけることはあっても、それはすでに出来上がった完成品としてのモノで、生成されるモノ、生成の過程にある未完成のモノの集合には目を向けることがなかった。19世紀なかばという、それこそ、産業革命以降の大量生産がいまの社会そのものをつくりあげていたという未曾有の生成プロセスの変換が行われていた時期に、その学問は生まれ、展開されてきたというのにである。
この従来の社会学が視界の外に投げ出したモノ――モノが生成され、それと同時にその生成の過程において、人びともまた集合を成すということ――を、あらためて、科学的な研究の舞台にあげること。それにより集合体(ラトゥールは「社会」に換えて「集合体」という実在論的な見方を導入する)がなぜ集合し、活動が維持されるのかが理解できるようになる、というのがラトゥールの考えだ。
絵に描いた餅では本当の説明にはならない
このあたりが先に書いたように、ANTが経営学や組織論に有効であろうと思える理由だったりもする。
たとえば、よく企業の成功/失敗を「企業文化」で語ったりするが、それはラトゥールが批判する従来の社会学者のやり方と同じだ。得体の知れない「企業文化」なるものに頼って説明するのは、ラトゥールが何度も本書で例示する相対論以前の科学がありもしないエーテルに頼って理論を組み立てていたのと同様、まったく科学的ではない。説明する目的で、エーテルや企業文化のような説明ツールを作成するのは、説明の道具を説明対象と混同するというトートロジーでしかない。
そうではなく、ちゃんと企業文化なるものの実態を分解して、ちゃんとモノ的なものと人間のあいだで繰り広げられる循環に落とし込むことが必要だ。そうでなければ、どんな組織改革のプランも絵に描いた餅に終わる。
そう。企業文化もまた、エーテルや神の見えざる手と同様、説明にしか使えない、実際には存在しない「絵に描いた餅」なのだ。僕らは「絵に描いた餅」ではなく、本当に実在する「モノとしての餅」を相手にする必要がある。
フラットな地平の上で上下の隔てなく
ただ、モノに着目するといっても、ラトゥールの思考は、唯物論的なものではない。
それは、ラトゥールがモノだけで考えるのではなく、モノと人とが共生的に織りなす循環を思考しているからだ。
このように書くラトゥールの意図を想像してほしい。
ぜひとも、人間をモノとして扱い、少なくとも、ささやかな〈議論を呼ぶ事実〉に授けてもよいぐらいの実現性を与え、できる限り人々を具体化、そう、物象化してほしい!
ラトゥールは、そもそも、モノと人間を分けて考えようとはせず、フラットな地平で、上下の隔てなく、モノと人が共生をしていると思考する。
エーテルや神の見えざる手のような、得体の知れない超越的な存在を探求から排除するANTでは、物事が起こる現場を、上下やウチソトの階層構造がないフラットな関係性のネットワークとして理解しようとする。
たとえば、ラトゥールは大学の講義室を例にして、フラットな関係性として見ることの例をこんな風に示している。
この講義室というローカルな場は、他の場所によって、さまざまなものを介してひとつの場所にされてきた。具体的に見ると、まずは、図面、仕様書、木材、コンクリート、スチール、ニス、塗料などによる、今は無音の媒介によってなされてきた。また、今は舞台から姿を消した数々の労働者や職人の仕事を通じてなされてきた(この労働者や職人は、自分たちがいなくなってからも自分たちの行為をモノに運ばせている)。さらには、気前よく寄附する同窓生を通じてなされており、その行為はブロンズの盾で褒賞されることもある。ローカルなものはローカル化されている。場所は場所化されている。そして、その状態を保つために、ドアの向こう側にいる無数の人びとがこの建物を維持しなければならず、その結果、あなたは学生とともに「建物のなかで」何事もなくいられるのだ。
いま学生を前に講義をしている講師の先生は、単に学生との関係のみにおいて講義しているわけではない。さらに言えば、いま講義室に存在するもののみによって、その講義という実践が成立しているわけではない。講義室を成り立たせている材料それぞれは、それぞれが過去のバラバラの時間にそことは別の場所でつくられ、そこに集められ、さまざまな人びとによって、さまざまな道具を用いて作られた。
講師が講義する内容もそれと同様で、さまざまな時代にさまざまな人びとが検討した結果の集合体だ。
それらは互いに関係しあい、集合体をなしているが、それは上下関係のある階層構造をなしているのではない。いや、階層構造的に見ることでつながりをブラックボックスに入れて見えなくしてしまうことはANTは避ける。
外に、社会はない
ANTが提唱する、フラットな地平において関係性をみるということを、ざっくりと概略するとそのように言える。
講義室のような物理的な存在だけがモノと人間との関係によって組み立てられているのではなく、講義内容である学問もまた同じように具体的なモノと人間の行為の連関を元に組み上げられる。
だから、それは「愛」のようなものでも同様なのだ。いや、同様に見ることではじめて、愛は単なる妄想ではなく現実的な機能となる。
愛でさえも、いや、とりわけ愛は、外からやってくるものとして、つまりは、内なるものを創り出す奇跡的な贈り物として考えることができる。もちろんのことながら、このことは、詩や歌や絵画で取り上げられてきた。天使、ケルビム、キューピット、矢といった、無数の従者たちについては言うまでもない。その客観的存在―― そう、モノ的だ―― も考慮に入れるべきである。愛でさえも、トレーニングルームや司令部、工場の場合と同じように、移送する装置、特別な技法、導管、装具がなければならない。
愛が最初に外にあって、それが僕らを動かすのではない。僕ら自身がさまざまな物的材料や過去のさまざまな詩人や画家たちが描いてきた作品なども素材としつつ、自分とは異なる人との現実的な作業を通じて、愛は現実的に生成される。
僕らの外に、社会的なものや社会そのものがあるわけではない。それはエーテルや神の見えざる手がないのと同じことである。ANTは、物事の循環するさまをフラットな世界において見ることで、社会がないことをわかるようにする方法なのだ。
地形をフラットにしたことで、外部の意味そのものが大きく変わっているのだ。つまり、外部は、もはや社会でできていない――自然でできているのでもない。つかみどころのない主体性と取り扱いようのない構造の両方を捨て去ることで、最終的には、私たちが個人になること、内なるものを得ることを可能にする数多の微細な導管を前面に出せるようになるだろう。
外に社会はない。だから、僕らは社会のなかにいるのではないのだ。
記述によるネットワークの発見
さて、ANTがこのようなフラットな関係性のなかの循環、連関が生成される動きとして、さまざまな集合体が無数に集う場として社会を見るとき、とうぜん、それはひとつの混乱を招く。
そう。果たして、ANTは自分たちが観察や聞き取り調査などを通じて得たとする、それらの循環や連関の生成をどうやって客観的に示すのか?と。
そもそもにおいて、ANTは固定化した循環を描くことを目標にするのではなく、新しく循環や連関が生じてくるさまを描くことを目的としている。
だからこそ、ANTの報告は「上手い報告とは、ネットワークをたどることなのである」とされ、ゆえにアクターネットワーク理論における「ネットワーク」という語自体がすでに固定化された循環を担うそれを指すのではなく、まさに観察や聞き取りの結果をもとに記述する、これまで見つけられていなかった循環や連関を描く報告そのものを指すものなのである。
ネットワークという語は、電話網、高速道路網、下水網などに見られる「ネットワーク」のように、相互連結した点の集まりから成り立っているような外在するものを指してはいない。ネットワークは、あるテーマについて調査後に書かれたテクストの質を示す指標でしかない。ネットワークは、テクストの客観性の程度を表すものであり、つまりは、他のアクターに思いもよらぬことをさせる各々のアクターの力能を表すものである。上手く書かれるテクストによって、書き手が、一連の翻訳として定義される一連の関係を描ける場合に、アクターのネットワークが明るみに出るのだ。
ANTは、"「古い」社会的なものを定義するのに長ければ長けるほど、「新たな」社会的なものが定義できなく"なっていた従来の社会学を更新するものだ。それは新たな社会的なものを発見できるようにするためのアプローチだ。
だから、上手いレポートがいまだ発見されていなかったネットワークを明るみに出すものであるのに対して、
下手なレポートは、そのためだけに書かれておらず、事例に固有に妥当するものではなく、特定の読者に対して特定のアクターの記述を行うものではない。下手なレポートは、標準的であり匿名的であり包括的である。そこでは、何も起こらない。それ以前に社会的なものとして組み立てられたものに関する決まり文句(クリシェ)が繰り返されだけだ。
何が起こったか、どのようにして起こったか。そのネットワークを記述によって明らかにすることが、ANTが目的とすることである。
〈厳然たる事実〉を疑う
ネットワーク=報告が、このような意味で捉えられているからこそ、客観性の意味は変わってくる。
媒介子はついに本名を教えてくれた。「私たちは、集合体を広範囲にわたってまとめ上げて組み立てる存在です。その範囲の広さは、あなたがたが、これまで社会的なものと呼んできたのとまったく同じですが、あなたがたは、規格化された単一の組み立ての型に自らを限定してしまっています。アクター自身に従うことを望むのであれば、私たちにも同じように従わなければなりません」。(中略)法律、科学、宗教、経済、精神、倫理、政治、組織は、すべて、それぞれ独自の存在様態、独自の循環を有しているだろう。多世界論は無理のある仮説かもしれないが、私たち自身の世界における存在の様相の複数性について言えば、既知の事柄である。
先に見た講義室の例のように、関係性のネットワークは記述を続ける気さえあれば、どこまでも広がっていく。その広がりをどの領域に広げていくかで描かれる世界は変わる。描きうる世界が複数あるからといって、それらが事実でないことにはならない。どの事実をどう見たかが異なるだけだ。ANTは、「規格化された単一の組み立ての型に限定すること」を拒む。だから、ANT的視点に立てば〈厳然たる事実〉などはない。あるのは、〈議論を呼ぶ事実〉であり、その事実を発見することがネットワークを明るみに出すANTの目的だ。
そう、ANTは「多世界論」を許容する。すくなくとも「存在の様相の複数性」を。
であるなら、客観的な事実はひとつではない。それらは相対的なものとして存在するはずだ。
であればこそ、だろう。ラトゥールがこう記述するのは。
実証主義――自然主義的なかたちであれ、社会的なかたちであれ、あるいは、反動的なかたちであれ、進歩的なかたちであれ――は、「人間の意識」を忘れて「冷たいデータ」にこだわろうとするから間違っているのではない。実証主義は政治的に間違っているのだ。実証主義は、〈議論を呼ぶ事実〉を、適正な手続きなしに、あまりにも急いで〈厳然たる事実〉に縮減してきた。実証主義は、実在論の2つの課題、つまり、複数性と単一性を混同してきた。実証主義は、諸々の連関を展開させることと、諸々の連関を1つの集合体に集めることの区別を曖昧にしてきた。
繰り返そう。客観性のある事実はただひとつだけ存在するわけではない。それは誰がみても疑いようのない「厳然たる」ものではない。
"何かが「構築された」ということは、それが真実ではないことを意味"すると「近代憲法」に侵された研究者たちは考える傾向があったことをラトゥールは指摘する。
研究者たちは、次のような常識外れの選択をせよという奇妙な考え方をしているようであった。つまり、実在しており構築されていないか、さもなければ、構築された人工的なものであり、仕組まれ発明されたものであり、作り上げられた偽物であるのか、のどちらかを選択しなければならないという考え方だ。
これはラトゥールが人類学的な色の強い著作『近代の〈物神事実〉崇拝について』で問題として提起していたものでもある。ラトゥールはこんなことを書いている。
糾弾が始まるのはアフリカ大陸黒人居住地域沿岸、ギニアのどこかであり、それは、聖母マリアや聖人たちのお守りに覆われたポルトガル人によって行われた。黒人たちが物神を崇拝していると言うのだ。「あなたたちが尊んでいる石や粘土や木で出来たそれらの偶像は、あなたたちの手で作ったのですか。」という最初の質問に答えるようにポルトガル人たちに命じられ、ギニア人たちは躊躇せずに、その通りだと答える。「石や粘土や木で出来たそれらの偶像は、本物のかなのですか。」という2番目の質問に答えるように命じられ、その黒人たちはまったく無邪気に、無論その通りだと答える。そうでなかったなら、彼らはそもそも自分たちの手で偶像を作るようなことはしなかっただろう。
自分たちが木や石で作った像を神と崇めるギニア人を、ポルトガル人たちがそれは偽物の神だと糾弾する。しかし、ANT的な観点でいえば、神がどうやって生じたかが明らかになっている(自分たちで木や石から作った)ギニア人のほうがはるかに客観的だ。神をブラックボックスに入れてその客観性を議論の外に置き、そのことで〈厳然たる事実〉の位置に神を置こうとするポルトガル人の方がよっぽど非論理的である。
研究に政治性を取り戻す
研究において(いや、研究に限らず、いま僕らが)求めるべきは〈厳然たる事実〉ではなく、〈議論を呼ぶ事実〉のほうだ。「研究をするということは、共通世界の材料を集めたり積み上げたりするという意味で、例外なく、政治を行うことである。問題なのは、どのような種類の収集とどのような種類の組み上げが求められているのかを決めることにある」とラトゥールは言っている。
議論を呼ぶからこそ、政治は可能になるのだ。そして、この政治の欠如こそが問題なのである。
だからといって、そうした学問分野は単なる虚構であり、自らの扱っているものをどこからともなく捏造していることにはならない。以上のことが意味するのは、これらの学問分野が、その名が申し分なく示しているように、規律であるということだ。つまり、それぞれの学問分野が、何らかの媒介子を展開させることを選択し、何らかの安定化を好み、したがって、それぞれに十分に教練され完全に定型化された入植者を世界に植えつけてきたということだ。研究者が報告を書くときにどんなことをしていようと、その研究者はすでにこの活動の一端を担っている。このことは、社会科学の欠点ではない。このループから自らを解放したほうがもっとよくなるわけではない。このことが意味するのは、ただ、社会科学が、他のすべての科学と同類であり、エージェンシーを増やし、その一部を安定化ないし規律化するという通常業務に携わっているということだ。この意味で、科学は、公平無私になればなるほど、いっそう深く関与することになり、政治的な意義を有するようになる。
規律もまた循環を促す。だから、学問が規律をつくること自体が問題なのではない。ANTの記述もまた1つの規律の発見なのだから、規律化そのものをANTが批判しようとしているのではないのは明らかだ。
しかし、その規律がすべてに適応できるかといえば、そうではない。規律が適応できるものも、できないものもある。その意味で、研究者は、規律を立てる時点で政治的選択を行なっているのだ。問題なのは、その政治的選択を自覚して、自ら立てた規律が〈厳然たる事実〉などではなく、〈議論を呼ぶ事実〉であり、ちゃんと議論に応じる姿勢をとっているかということである。
私が提案したのは、「自然をめぐる政治」を1つの共通世界の漸進的な組み上げで置き換えることである。さまざまな生態学的危機が迫るなかで、この置き換えは、科学と政治を定義し直し、政治認識論の課題を遂行する唯一の道であるように見えたのである。
と、ラトゥールは書いている。
そう。持続可能性があらゆる学問領域、社会的領域を超えた、何よりの共通の課題である現在において、領域間での議論の可能性は重要なものであるし、誰もが政治的に振る舞う姿勢を示せるかどうかが喫緊の課題だろう。
まさに、そのことを20世紀において社会学がおざなりにしてしまったことこそをラトゥールは問題視している。
19世紀のあいだは、大衆、群衆、産業、都市、帝国、衛生、マスメディアなどあらゆる種類の発明がにわかに立ち現れたので、この驚きの感情が絶え間なく呼び覚まされるのを見るのは簡単なことであった。実におかしなことに、この感覚は、続く20世紀において、数々の悲劇的惨事と技術革新、大量虐殺、生態系の危機のなかでさらに高まるはずだったのに、そうはならなかった。ほかならぬ社会と社会的主体の定義が、いくつかの要素を取り込む一方で、莫大な数の候補子を排除しようとするものであったからである。近代主義が行き渡っているところでは、社会的なものの構成を精査することは、どのような形であれ、非常に困難であった。自然と社会を同時に脇におけば、多くの新たな構成子からなる集合体を組み立てることを本当に難しくなる。ANTはそのことに今一度敏感になろうとしてきたのである。
僕らがこのANTの姿勢に学ぶことは多い。説明すべき事柄をツールとして説明してしまうというトートロジーに陥ることなく、現実にあるもの同士のつながり、循環をたどりながら、その生成、連関のネットワークを記述すること。それは社会学には無縁の僕らにとっても複雑に絡み合った僕らが生きる環境、生態系の持続可能性について考えるという意味においては、非常に参考になる態度だと思った。
難解なれど、参考になることは山ほどある。
P.S. あわせて読みたい
ただ、最後に1つ捕捉するなら、この『社会的なものを組み直す』という本1冊を読んだだけではアクターネットワーク理論について理解するのはむずかしいかもしれない。僕自身も先に『虚構の「近代」』と『近代の〈物神事実〉崇拝について』というANTの方法を具体的に適用して考察した「報告」を先に読んでいたからこそ、ANTが具体的にどんなアウトプットを生むものかをイメージしながら、この本を読むことができて良かったと思う。何故そのようなアウトプットの創出を目指すのか、どうやって行なっているのかがイメージできたからだ。ANTそのものを解説した本書、ANTを適用した具体例が示された本、どちらからでも順番は良いかもしれないが、あわせて読むことをおすすめしたい。
いいなと思ったら応援しよう!


