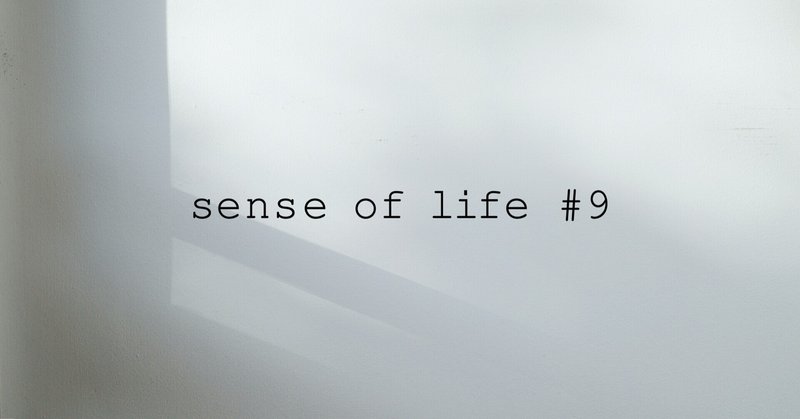
9. 「美しい暮らし」 という罠
美しい暮らし。この言葉にどれだけ翻弄されてきただろう。
衣・食・住を充実させて、いかに日常生活を楽しむか、ということが、一部の界隈で頻繁に語られはじめたのは00年代初頭〜中頃にかけてのことだと思う。
身につける物、部屋に置く物、持ち物、使う物、食べる物といった、生活に関わるものすべての細部にこだわり、妥協せずに、自分なりの心地よさや美しさを追求するという、感度の高い人たちの生き方は、たしかに魅力的だった。
彼らの、既存の価値ではなく、自分の感覚にフォーカスした生活や物選びへの姿勢は、一定の支持を得て多くの追随者を生み、また、そういった価値観をメディアもしきりに提唱し続けたことで、一般の人々の暮らしへの意識は徐々に底上げされていったといえる。そして、今や、日常生活をいかに美しく自分らしい満足のいくものにするかということは、多くの人にとって最大の関心事となっている。
普段使いのうつわや、職人の手仕事によって作られた道具類、朝の時間の過ごし方や、一杯のコーヒーをどのように飲むかが、これほど注目されたことがかつてあっただろうか。もはや、「心地いい暮らし」という文字を見ない日はないほど、ライフスタイル関連市場は巨大だ。
さて、ところで「美しい暮らし」とは何ぞや、ということである。
当然ながら美しさの価値観はさまざまであるが、この文脈における「美しい暮らし」とは、豪奢に飾り立てることではなく、むしろ質素でナチュラル、シンプルながら独自の哲学や美意識を持った暮らし方、もしくは、そういった一貫性のあるスタイルを確立して実践する暮らし、だと言える。賢くて、センスが良いいことが「心地よさ」に繋がるという考えでもある。
具体的には、自然、オーガニック、手仕事、伝統、といったものをベースに、文化的な嗜みと、知的さを加えることが「美しい暮らし」のポイントとなる。
「丁寧なくらし」とか「くらし系」などとされる一連のテイストも、この流れの末端に位置するものと考えてよいだろう。
そうしたライフスタイルの源流は、当初は、大量生産・大量消費、グローバリズムへの反動という面もあり、革新的なものだったはずだが、「心地よく美しい」生活の態度は、ある意味、慎ましく品行方正なものであり、一般に拡がるにつれて前時代的な保守性に着地するという逆説的な結果を生んだのは否めない。が、ともかく、「心地よく美しい」暮らしがもてはやされ、広く浸透したのは確かだ。
その経緯のひとつとしては、時代と親和性が良かった、ということがあるだろう。
経済の低迷が長引く時代、「暮らし」への回帰は、当然の流れでもあった。
やみくもに消費に走るのではなく、何でもない日々の生活の中に小さな喜びや楽しみを見出してゆくという価値観は、当時の若者、とくに、不況の煽りを真正面から食っていたいわゆる氷河期世代の気分にバッチリはまったのである。
氷河期世代のど真ん中である私も、20代の頃は働くことに疲弊していた。希望が持てずに、社会への不信と将来の不安は募れど、自分が何処へ向かうべきかが解らなかった。過去の栄光を引きずるバブル世代の価値観などはまったく理解できなかったが、来るべき未来に対しても悲観的だった。というのも、当時は本格的なデジタル化への過渡期(スマホ登場前夜)で、テクノロジーによって失われゆくものや、もたらされる弊害ばかりに注意が向いていたからだ。
また、ファッション誌やカタログのデザインという仕事についても、支配的な企業に取り込まれて消費を促すことに加担している葛藤が常にあった。
そんな中で、自然や手仕事といった耳障りのよい言葉に惹かれていったのは無理もないだろう。効率や合理性を追求するのではなく、自然との触れあいや、手間と心が注がれたものづくりや、過ぎ去った時代に美しい精神性を見出して、そこに救いや癒しを求めるようになったのは自然なことだ。
混迷する社会に出て身を減らすより、内にこもって、いかに心地よい自分の世界をつくるかということに、あるときから急激に意識が向かいはじめ、かくして私は「美しい暮らし」に向かいはじめたのだった。
自立したセンスのいい暮らしを営む人々に実際に出会ったり、雑誌で目にしたりすると、私は大きな影響を受け、自分も「そっち側」に行きたくて仕方がなくなり、実践できることは積極的に取り入れた。たとえば、アナログな生活道具、自然食品店やファーマーズマーケットで無農薬野菜を買うこと、自然療法の手当、土鍋で玄米を炊くこと、自家製の漬物を作り、ときどき自然派ワインを嗜む、といったように。自然に即した生き方や、美術工芸に関する本を読みあさり、着るものは素材や見えない部分にも気を配って、家の空間を磨き上げ、厳選して買い集めたアンティークや作家もののうつわを、ああでもないこうでもないと並べ替えることに執心した。また、昔の日本人が持っていたような、細やかな気配りと始末のよさを良しとして、そんな立ち振る舞いをする大人たちにも憧れた。
仕事であるデザインについては、活版印刷などのアナログ的手法に傾倒し、過去の素晴らしいものをいかに再現するかに重点を置いた。
そして、いずれは、世間と距離をおいて、野菜やハーブを育て、本を読んだりレコードを聴いたりしながら静かに暮らすことができたら、なんて、寝ぼけた想像をめぐらせていたのである。
果たしてこれが「美しい」かどうかはさておきとして、こういった行為は、一時的な避難場所にはなったのは事実である。
今となってはくだらないと思うが、少なくとも当時の私にとっては、これらは価値を見出すことのできることであり、中に一歩踏み込んでみると豊かな世界が広がっていて、そこにはある種の癒しがあったのは確かだ。
こういったことに没頭することで、私は安心感を得ていたのだろう。実際「暮らし」にフォーカスしはじめてから、一時期、ひどかった不安神経症と抑ウツの症状が一時的に緩和されたので、なおさら傾倒していったということもある。しかし、それは束の間で、時間が経つほどに満たされなさを感じるようになった。
さて、ここで再び、現実としての「美しい暮らし」とは何ぞやと考えてみよう。
メディアはあらゆることを美化するが、そもそも暮らしの本質はサバイバルだ。
生活とは、生存に必要な技術を編み出し、必要に応じて使い分け、蓄積し、向上させてゆく人間の営みで、暮らしとは、その繰り返しの行為である。
あまりに生きる実感が希薄になったため、かつてのサバイバル術を薄味に仕立て直し、疑似体験しているというのが、現代における「美しい暮らし」だ。
つまり、ファンタジーである。現代の「美しい暮らし」は、新たな消費スタイルの一つであり、時間と金銭とを要する一種の娯楽、アクティビティーなのだ。
でも、それを否定するつもりはまったくない。むしろ、享受できるならば楽しい限りだと思っている。しかし、だ。
アクティビティーを楽しむには、それなりの余裕が必要なのである。
たとえば、私のようなグレーゾーン発達障害人に、はっきり言って余裕などはない。通常の家事のオペレーションだけでもてんてこ舞い(#8参照)だし、情緒不安定で、体力にも問題ありだし、世渡り下手ゆえ金銭的にも厳しいものがある。
だいたい発達障害人全般(偏見が入っててごめんなさい)は、真面目で融通がきかず、劣等感が強いものだから、何事にも全力で取り組み、手の抜き加減を知らない。だから、都合よく「美しい暮らし」の上澄みだけをすくい取ってアクティビティーを楽しむなんて、そんな器用な芸当ができるはずもない。信じたことを徹底的に貫く純粋さ(要領の悪さ)あまりに、過剰なこだわりを持って、全身全霊で「美しい暮らし」に挑むのである。
そうして、ストイックなまでの極端な行動を自らに課した結果、自らの首を絞めることになるのが関の山だ。
すると、どうなるかというと、健全な精神がどんどん失われていくのだ。
「美しい暮らし」は楽しみではなく、やがて義務と化す。自ら作り出した信念や価値から外れることを恐れて、不安から行う行為となる。「暮らしは美しくなければいけない」という強迫観念でがんじがらめになる。
それが自己完結的ならばまだしも、そういった努力が認められることへの期待を捨てきれずいると、事態はさらにやっかいになる。本質を求める純粋な心と、「自分のセンスを他人に評価してもらいたい」という承認欲求とで、分裂症的にもがき苦しむのである。
心地よい自分の世界を作ろうとしていたはずなのに、なんという本末転倒。なんというエネルギーの無駄遣い。こうなってくると全ての行いが逆をゆくようになる。自然を求めるあまりに不自然極まりない行動を取り、美しさを追求するがゆえに醜悪になる、というように……。
要するに、私は、遊び方のルールもわからない「ままごと」を大真面目にやって、自家中毒になっていたといえる。
毎度お粗末な話で申し訳ない限りだが、「美しい暮らし」に翻弄された私が通ってきた道筋である。
昨今では、世間一般でも、生活や環境への意識が相当に高くなっているが、そういったライフスタイルへの取り組み方が、良い意味で、以前よりずっと軽くなっているような気がする。深刻さのかけらもないライトな感覚で、当たり前にそれを楽しんでいる若い世代が眩しく見えるのは私だけだろうか。
今は、質のいいオーガニック製品も多く流通しはじめたし、環境に配慮しつつ洒落たものや、グッドデザイン、善良な思想で物づくりをしている会社がたくさんある。もはや、血眼になって探さずとも、簡単に、そこそこ「美しく心地よい」ものが手に入る時代だ。そういったことがグローバル化によってスムーズになったのは皮肉とも言えるが、いい世の中になったものだと思う。
私は今も、手仕事や伝統をリスペクトし、自然に即した暮らしや、経済のシステムに頼らない生き方に憧れを持ってはいるが、自分のやるべきこととはまた別の話だし、自立した賢い生き方はそればかりではなく、もっと多様である。
無理のないリラックスした環境でこそ個々の美しさは発揮される。
絶対的な正解を求めたり、何かの主義に因るのではなく、ライトな感覚で居られる場所を探すことの方が、よほど大切なのだ。
エネルギーは効率的に使うに越したことはなく、エネルギーとは石油ばかりじゃない。ここにきて「スローライフ」は下火になってきたようだ。最近、やたらと「時短」が叫ばれているのは、そういったことに、みんなが気がつきはじめたということじゃないだろうか。
「丁寧」は手段であって目的ではないし、「美しい」は、単なる結果である。
それぞれが淡々と、それぞれの現代版「サバイバル」を続けること。
それが結果として、アップデートされた「美しい暮らし」となるだろう。
晴れて「ままごと」を卒業した私は、この際、大いに文明の利を享受し、経済の恩恵に預かって省エネ快適生活を謳歌してやろうという魂胆でいる今日この頃だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
