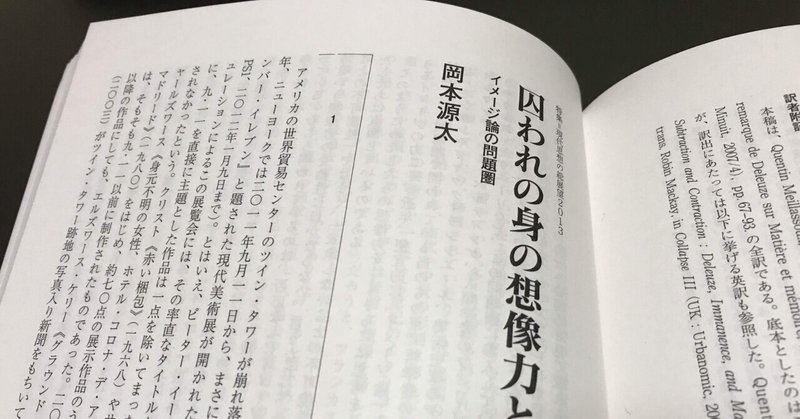
囚われの身の想像力と解放されたアナクロニズム──イメージ論の問題圏(一)
1 アメリカの世界貿易センターのツイン・タワーが崩れ落ちて十年、ニューヨークでは二〇一一年九月一一日から、まさに『セプテンバー・イレブン』と題された現代美術展が開かれた(MoMA PS1、二〇一二年一月九日まで)。とはいえ、ピーター・イーリーのキュレーションによるこの展覧会には、その率直なタイトルとは裏腹に、九・一一を直接に主題とした作品は一点を除いてまったく展示されなかったという。クリスト《赤い梱包》(一九六八)やサラ・チャールズワース《身元不明の女性、ホテル・コロナ・デ・アラゴン、マドリード》(一九八〇)をはじめ、約七十点の展示作品のうち多くは、そもそも九・一一以前に制作されたものであった。二〇〇一年以降の作品にしても、エルズワース・ケリー《グラウンド・ゼロ》(二〇〇三)がツイン・タワー跡地の写真入り新聞をもちいているのみで、そのほかに九・一一のイメージを使用した作品はなく、九・一一を内容にした作品もなかった。
代わりにこの展覧会で提示されていたのは、そうした九・一一と無関係であるはずの作品さえもがいまやわたしたちに九・一一を否応なく想像させてしまうという事態である。長い角材を真っ赤な防水シートで包みロープで縛ったクリストの作品は、爆弾などの危険物ないし被害者の遺体を思わず連想させ、またスペインのホテルから飛び降りる女性の報道写真を転用したチャールズワースの作品は、燃えさかるツイン・タワーから飛び降りた犠牲者たちの姿を想起させずにはいない。『セプテンバー・イレブン』展は、マスメディアを通して全世界に流されつづけてきた九・一一のイメージを敢えて会場から締め出すことによって、逆にわたしたちの想像力がどれほど九・一一のイメージに囚われてしまっているのかを明るみに出す。無関係の過去の作品に九・一一のイメージを重ねるというアナクロニズムを犯してしまうほどまでに、わたしたちの想像力は囚われの身になってしまっているのだ。
この囚われの身の想像力について考えてみよう。『セプテンバー・イレブン』展が、カタストロフィの表象に取り組むものであり、一九八〇年代頃から活発に論じられるようになった歴史と記憶の問題系に連なることは言を俟たない。けれども、たとえばフランスでの『収容所の記憶』展(シュリー館、パリ、二〇〇一年一月一一日〜三月二五日)に際してクロード・ランズマンたちとジョルジュ・ディディ=ユベルマンとのあいだで論争になったような「表象の可能性/不可能性」は(1) 、『セプテンバー・イレブン』展の争点ではない。過去の痛ましい出来事を表象によって認識し理解できるのかどうかという問いは、とりわけアウシュヴィッツをめぐって無数の論争を呼び込んできたが、しかしここではもはや踏み越えられてしまっている。むしろ問われているのは、否応なしにイメージしてしまうという想像力の受動性にほかならない。言うなれば、「表象することの不可能性」ではなく、「表象しないことの不可能性」に、わたしたちは直面しているのである。 このようにわたしたちの想像力を──さらには思考を──呪縛しうるイメージの力こそ、近年、便宜的に「イメージ論」と呼び慣わされている問題圏で問われている当のものだ。哲学者のマリ=ジョゼ・モンザンやジャック・ランシエール、美術史家のディディ=ユベルマンやハンス・ベルティング、人類学者のフィリップ・デスコラやカルロ・セヴェーリなど、この問題圏に参入している論者の出自はさまざまだが、イメージの意味や内容(「なにを語っているのか」)よりも、機能や効果(「なにを行っているのか」)に着目する点で、そこに共通して「イメージの力」への関心を見て取れる。観者への効果、あるいは出来事を引き起こす効力こそが、イメージにとって本質的なものと見なされはじめているのだ。では、このとき「表象することの不可能性」に対してそれでもなお想像すべきだとしてイメージの力を語るとすれば(2)、「表象しないことの不可能性」に対してはどうだろうか。
2 「表象しないことの不可能性」からの脱却は、一見したところ容易いように思えるかもしれない。というのも、しごく単純に想像力がアナクロニズムの誤謬を犯していると指摘すれば済む話のように見えてしまうからだ。無関係の作品に九・一一を重ね合わせるのは誤りだ、というように。しかしながら、そのように想像力の錯誤を指摘して、作品をもとの制作された文脈に差し戻そうとする態度──これを学問的に洗練させたのが歴史主義的な実証主義にほかならない──は、逆説的なことにも、わたしたちをいっそう表象のなかに埋没させてしまうだろう。
仮に、作品の制作当時の状況を再構成し、いわばその「時代の眼」を取り戻すことによって、想像力のアナクロニズムを是正して作品の正しい姿を見いだすことができるのだと考えてみよう。では、その「時代の眼」は、過去の眼差しは、どうすれば獲得できるのだろうか。ただ眼前にある作品を眺めるだけでは、不可能である。まさにその直接の作品経験こそが、囚われの身の想像力に深く浸透されているのだから。
文献学的実証主義の手法を取り入れた美術史学では、作品の直接経験からいったん離れて、作品の制作当時の文献資料へと迂回するという手続きが採用されてきた。かつてピエール・フランカステルが強調したように、そもそも過去のありのままの姿をとどめている芸術作品などない(3)。いかなる時期のどのような作品であっても、多かれ少なかれ変化を被っている。多くは場所を移されており、往々にして欠損していたり、修繕されていたりする。異国のオブジェは展示室のなかへと納められ、古代や中世の彫刻は彩色が剥げおちている。ルネサンスの芸術も、一五、一六世紀のイタリアのフレスコ画も、修正や破損のために、やがては証言と複製を通して間接的にのみ接しうる思い出になってしまうだろうと、フランカステルは危惧してすらいる。とすれば、どのような作品であってもその直接に経験できる姿は過去そのままではありえず、もし過去の姿を見いだそうとするなら、その現在の経験を迂回して、過去の証言や複製といったものに頼る必要がある。作品に接するうえで同時代に書かれたテクストを決定的なものと見なす文献学的実証主義の手続きは、近代的な意味での美術史学が誕生したときに大きな影響力をもっていたという理由だけで美術史学に導入されたのではない。作品からテクストへと迂回することは、作品をもとの過去の文脈に差し戻すために必要不可欠な手続きと見なされたのである。
とはいえ、そのように現在の経験を迂回し、それによって過去の認識を目指すなら、わたしたちはこの眼前の作品をあたかも失われてしまったかのごとく扱うことになる。作品が変化を被っていることを理由にして、作品の経験を過去の認識にとって信頼できないものと見なすことは、いまだ残っている作品を見ず、なおも現前している作品に対して目を閉ざし、現在とは異なる過去の作品の姿を想起するという行為に帰着するのだ。そのとき作品は、残っていようといまいと、想起によって間接的にのみ接近可能であるような、失われた対象になってしまう。作品は、たとえ眼前にあったとしても決定的に失われており、わたしたちにはいかなるイメージも差し出さない。あるいは、わたしたちの眼差しに差し出されるイメージはことごとく偽りのものにすぎないことになってしまう。
これこそ、まさしくミシェル・ド・セルトーが「死の仕事〔travail de la mort〕」と呼んだものにほかならない(4)。セルトーによれば、歴史記述は──少なくともヨーロッパの近代歴史学は──現在残っているものを失われた過去として、つまりいまなお生き残っているものをすでに死に絶えたものとして扱うという。歴史記述は、まずは現在と過去とを引き離し、その過去をさらに複数の時代へと分割し、そうすることで「もはやない」ということばをたゆまず告げていく。過去はもはや現在ではないし、フランス革命以後はもはや革命以前ではないし、ルネサンスはもはや中世ではない。そうして歴史記述は、過去を次々と分割しつつ、その過去をそのつど「もはやない」として葬り去っていく。歴史記述はたえず「死」を与えるのだ。けれども、この「死の仕事」によってこそ、過去は失われた対象として知のうちに保持される。それゆえセルトーは、「死の仕事」はまた同時に「死に抗う仕事〔travail contre la mort〕」でもあると指摘する。ものごとは歴史記述によって過去にされ、それによって永遠に不動のものになる。すでに死んだもののみが、もはや死ぬことがないとでもいうかのように。
近代的な意味での美術史学を打ち立てたとされるヨハン・ヨアヒム・ヴィンケルマンのうちにジョルジュ・ディディ=ユベルマンが読み取ったのも、まさしくこうした思考であった(5)。古代ギリシアの芸術がすでに失われているという事実から出発することによって、ヴィンケルマンはその古代ギリシアの芸術を、ほかのあらゆる芸術が模倣すべき不変の本質、永遠の理想にする。失われた過去の芸術を嘆く『古代美術史』を著した美術史家ヴィンケルマンと、永遠の芸術の本質を希求する『ギリシア美術模倣論』を著した美術批評家ヴィンケルマンは、同じひとりの人間にほかならない。ヴィンケルマンにおいては〈変化〉という自然の時間が〈芸術の本質〉という理念の時間へと転換されるのだと、ディディ=ユベルマンはいう。過去の認識のために現在の経験を犠牲にすることは、作品を失われた対象に変え、まさにそれによって永遠不変の理念の世界に到達しようと望むことなのだ。かくして、想像力のアナクロニズムを排除して作品の現実に寄り添うはずが、むしろ作品の経験から隔絶された過去の表象のなかに飲み込まれてしまうのである。
この問題点をだれよりも鋭敏に感じ取っていたのは、実のところフランカステルかもしれない。フランカステルは、作品が置かれている時代の社会状況を知ることの必要性を強調してやまなかったにもかかわらず、歴史の知識の深まりによっては作品に接することの問題は汲み尽くされないとも指摘している(6)。作品からその同時代のテクストへと迂回し、「時代」に精通し、歴史の知識をどれほど深めようとも、それによっていま眼前にある作品なしで済ますことはできない。作品からテクストへの迂回は、たしかに必要なものであったとしても、それ自体としては美術史そのものの否定を帰結してしまう。現在わたしたちのまえにある作品にではなく、過去のテクスト、そのテクストを残した精神や言語や社会、いわば「時代」のうちに作品の真の姿を求めようとする発想は、すぐさま、作品を「時代」なるもののうちに還元する発想へと横滑りするからだ。作品は「時代」のたんなる反映でしかなくなり、存在しようとしまいとなんの差異ももたらさないことになってしまう。つまり、「時代」のみが存在して、芸術作品などというものはその影にすぎず、結局のところ存在しないに等しいことになってしまうのだ。とすれば、芸術が存在しないのだから、美術史も存在しないことになる。
だからこそフランカステルは、たんにテクストによる過去の認識を目指すだけでなく、そうした過去の認識を現在の経験と突き合わせ、その間隙をたえず埋めていく二重の道程として、美術史学を構想した。フランカステルによれば、作品についての最初の直観、作品の享受は、作品についての歴史的な認識とは隔たりを含んでいるにもかかわらず、それに先駆けるという。つまり、過去の認識は現在の経験のあとを追うというのだ。ここではむしろ、アナクロニズムを犯してしまいうる現在の経験のほうこそが、過去の表象という形姿をまとった想像的なものの圏域に飲み込まれる危険から脱け出させてくれるものと見なされているだろう。
3 そこからあらためて考えてみるなら、想像力が犯すアナクロニズムは、実のところ、過去の作品が現在の眼差しによって誤った(あるいは新たな)意味を付与されるという、そのような単純な事態ではないことがわかる。というのも、作品は「過去」とだけ呼ばれて十全に指し示されうるような単純な一時点へと局在化されてはいないのだから。作品のうちでは複数の連関系が、複数の時間が交錯しており、そのうちいくつかは「過去」と呼ばれるが、いくつかは「現在」と呼ばれるだろう。あるいは「未来」と呼ばれうるものもあるだろう。作品は、過去のみにあるのではない。また眼差しも、「現在」とだけ呼ばれて十全に指し示されうるような単純な一時点へと局在化されてはいない。というのも、眼差しは記憶をもつのだから。見ることは習熟され、修練される。どのように見るのか、そもそもなにを見るのかについて、わたしたちは多かれ少なかれなにがしかを学ばなければならない。そのために眼差しは、別の眼差しを引き継ぐことになり、複数の眼差しとの時間的な関係に巻き込まれていく。眼差しのうちでも、複数の眼差しが、複数の時間が交錯する。そのうちいくつかは「現在」と呼ばれるが、いくつかは「過去」と呼ばれるだろう。あるいは「未来」と呼ばれうるものもあるだろう。眼差しは、現在のみにあるのではない。それゆえ、アナクロニズムのうちで交錯しているのは、事後性ということでしばしば考えられるような「過去の」作品と「現在の」眼差しではない。作品も眼差しも、過去を引き継ぎ、現在にまで残されている。作品のうちのいくつかの時間と、眼差しのうちのいくつかの時間が交錯する。作品と眼差しとの時間関係は、一義的には決定されない。
もう少しゆっくり考えてみよう。芸術作品にとってアナクロニズムには二つの意味があると、ダニエル・アラスはいう(7)。第一に、作品は、それに向けられる眼差しとは異なる時期に生み落とされたにもかかわらず、その差異が忘却されてしまうとき、アナクロニズムが生じる。第二に、作品のなかの複数の要素がそれぞれ別の時代の特徴を示しているとき、そこにアナクロニズムが生じている。
第一のアナクロニズムはまずもって歴史認識の錯誤であり、まさしく無関係の作品に九・一一を投影してしまうときにわたしたちの想像力が犯している当のものだと言える。しかしながら、アラスが強調するように(8)、このアナクロニズムは、想像力の捏造によって生じるというよりも、むしろ作品の可視性の条件が変化しうることに連動して引き起こされており、間違いなく作品それ自体がそのように見えてしまうという経験である。作品は経年劣化をはじめ物理的に変化しうるのであり、さらには場所を移され、映像に写され、時間とともに眼差しとの距離をたえず変えてゆく。場所を移されることで、作品と眼差しのあいだにある媒介や障碍は、つまり光や空気あるいは覆いなどの物体は、決定的に変化する。映像に写されることで、作品が眼差しに差し出すイメージの規模や角度や範囲は、決定的に変化する。だからこそ、アナクロニズムはわたしたちの直接的な経験であって、見えないものを見てしまうことではなく、見ていなかったものを見るようになる(もしくは見ていたものを見ないようになる)ことなのだ。
とすれば、アナクロニズムの誤謬は、かならずしもわたしたちの想像力に全面的な咎があるわけではない。ハル・フォスターもまた、『セプテンバー・イレブン』展に寄せた展評のなかで、この事実に注意を促している(9)。九・一一を否応なしに想像させるためには、クリストのどのような作品でもよかったわけではなく、梱包作品のシリーズでなければならなかった。クリストの《赤い梱包》の形態上の特性こそがまさにアナクロニズムを呼び込んだのであって、わたしたちの想像力が能動的に誤った意味を付与したとは言えないのである。したがって第一のアナクロニズムは、たんなる主観の超越論的機能の暴走というわけではなく、作品が残り、眼差しとは異なる時間を紡いで、眼差しとの距離をたえず変えていくことに関わっている。
ここにこそ、作品自体が複数の時代にまたがっているという第二のアナクロニズムが介入する。作品は制作されたその瞬間にすでに複数の時間にまたがっているために、単一で同一の時間のうちではいかなる眼差しとも出会えないのだ。アンリ・フォシヨンも言うように(10)、作品の形成は一瞬のうちになされるわけではない。作品は突然に閃いては消え去るような瞬間的な存在ではありえず、ある持続をもった一連の過程の結果として生まれ落ちる。作品は別の作品のまえやあとに生まれ落ち、そうした別の作品との時間的な連関を引き継ぐ。いわば、時代に「先んじて」いたり「遅れて」いたりする。それゆえ、いかなる作品であっても、その生誕の瞬間においてさえ、残されたものとして複数の時間にまたがっているだろう。そうした残されたものとしての作品が縺れあって、美術史はかたちづくられていく。ひとつの作品のうちにいくつもの時間が、ひとつの日付のうちにあらゆる傾向がとりあつめられる。フォシヨンが歴史のことを「早すぎること、時宜にかなっていること、そして遅すぎることの葛藤〔un conflit de précocités, d’actualités et de retards〕」(11)と呼ぶのは、そのためである。
したがって、作品の生誕と同じ日付の、同じ時刻の眼差しを取り戻したとしても、作品は残されたものとして生まれ落ちるがゆえに、その瞬間をすでに越え出ている。作品はそれ自体で複数の時間にまたがるのだから、眼差しの時間と作品の時間とが一致する瞬間もなければ、一致していたと見なされうる瞬間もない。眼差しの日付と作品の日付との一致は、なんら理解を保証しない。「過去の」とされる作品について、「過去の」とされる眼差しのほうが「現在の」とされる眼差しよりもよく見えているというわけでは、かならずしもない。作品の生誕と同じ日付をもつ眼差しといえども、作品とは別の時間を紡いできた以上、異なる時間にあり、そのほかの日付をもつ眼差しに比して作品の理解について特権的であるわけではない。ディディ=ユベルマンの言葉を借りるなら、「同時代の者たちは、しばしば、時間的に隔たった者たちよりも良くは理解していない。アナクロニズムはあらゆる同時代性をよぎっている。時間の一致は──ほとんど──存在しない」(12)。「時代」というのはひとつの抽象であり、作品が生み出された時代の人間の眼差しを取り戻したところで、その眼差しはついに作品と一致することはないのである。眼差しが作品と完全に時を同じくすることはできず、その意味でアナクロニズムは避けえない。異なる時代を混淆している作品を見るなら、必然的に異なる時期に属する作品を見ることになる。作品が残りゆくことで引き起こされる眼差しのアナクロニズムは、生誕の瞬間にすでに作品に刻み込まれているアナクロニズムから帰結するものであり、その延長にほかならない。
このような作品と眼差しの二重の生成変化そのものとしてアナクロニズムを考えてみるとき、「表象しないことの不可能性」に囚われた想像力に関していったいなにが問題なのか、より明確になる。問題は、イメージに囚われてしまう想像力の受動性であるとともに、すべてを意味づけてしまう主観の全能性でもある。アナクロニズムとは、まさにこの受動性と全能性との奇妙なアマルガムにほかならない。だが、アナクロニズムはまた、その二重の生成変化のなかで揺れ動くがために、この奇妙なアマルガムが歴史的な所産であり、いわば解体可能な「想像的装置〔dispositifs imaginaires〕」(13)にほかならないということを告げ知らせもする。フォスターは『セプテンバー・イレブン』展について、無関係の作品にまで九・一一を見いだしてしまう事態が、同時多発テロという出来事そのものに起因しているのではなく、むしろこの展覧会のキュレーションによって意図的に構築されていることを指摘している(14)。想像力の受動性と主観の全能性は、この場合、まさしく「美術館」という装置に支えられているのだ。さらに敷衍すれば、想像力を美術館に見立ててしまう隠れた発想こそが、あらゆる作品に意味を付与したり剥奪したりする主観の全能性の幻想を育んでいるだろう。エリー・デューリングも示唆するように(15)、そうした「空想の美術館」の観念がなおも美術館学的無意識に取り憑いており、わたしたちは想像力を美術館のごとく万物を包摂できる普遍的空間として考えてしまう。けれども、意味を付与し剥奪する主観の全能性の発現そのものにほかならないアナクロニズムは、逆に、作品と眼差しのたえざる変転をもあらわにするだろう。「表象しないことの不可能性」は、その所産たるアナクロニズム自体によって歴史化され、わたしたちの想像力をむしろその複数性において理解させてくれる端緒にもなりうるのである。*
*岡本源太「囚われの身の想像力と解放されたアナクロニズム——イメージ論の問題圏」、『現代思想』第41巻第1号、2013年1月、171-177頁
(1) Cf. Wajcman, G., « De la croyance photographique », Les Temps Modernes, no 613, mars-mai 2001, pp. 46-83.(橋本一径訳「写真的信仰について」、『月刊百科』二〇〇六年八月号〜一一月号); Pagnoux, E., « Reporter photographe à Auschwitz », Les Temps Modernes, no 613, mars-mai 2001, pp. 84-108.; Didi-Huberman, G., Images malgré tout, Paris, Minuit, 2003.(橋本一径訳『イメージ、それでもなお』、平凡社)
(2) Didi-Huberman, ibid.
(3) Francastel, P., La réalité figurative, Paris, Gonthier, 1965, p. 159.(西野嘉章抄訳『形象の解読』第一巻、新泉社、二〇〇頁)
(4) Certeau, M. de, L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975, pp. 13-31.(佐藤和生訳『歴史のエクリチュール』、法政大学出版局、五~二三頁)
(5) Didi-Huberman, L’image survivante, Paris, Minuit, 2002, pp. 11-26.(竹内孝弘・水野千依訳『残存するイメージ』、人文書院、一三~二九頁)
(6) Francastel, Études de sociologie de l’art, Paris, Gallimard, 1970, pp. 30-33.
(7) Arasse, D., « La contemporanéité anachronique de l’œuvre d’art », in Peut-on apprendre à voir ?, sous la direction de L. Gervereau, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 1999, p. 285.
(8) Id., Histoires de peintures, Paris, Denoël, 2004, pp. 260-261.
(9) Foster, H., “September 11,” Artforum, January 2012, p. 211.
(10) Focillon, H., Vie des formes, Paris, Ernest Leroux, 1934; Paris, PUF, 1943, p. 83.(阿部成樹訳『かたちの生命』、ちくま学芸文庫、一五八頁)
(11) Ibid., p. 86.(邦訳、一六三頁)
(12) Didi-Huberman, Devant le temps, Paris, Minuit, 2000, p. 15.(小野康男・三小田祥久訳『時間の前で』、法政大学出版局、一〇〜一一頁)
(13) Mondzain, M.-J., L’image peutelle tuer ?, Paris, Bayard, 2002, pp. 26-30.
(14) Foster, art. cit.
(15) During, E., « Comment faire muter une œuvre d’art ? », Art press 2, no 26, 2012, pp. 20-23.
