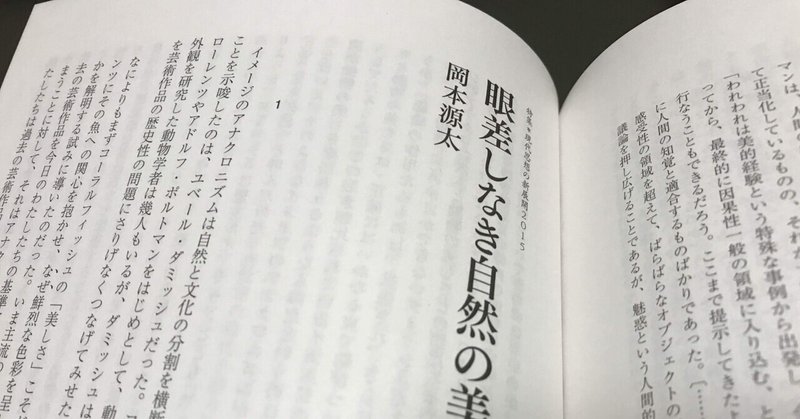
眼差しなき自然の美学に向けて──イメージ論の問題圏(二)
1 イメージのアナクロニズムは自然と文化の分割を横断する。このことを示唆したのは、ユベール・ダミッシュだった。コンラート・ローレンツやアドルフ・ポルトマンをはじめとして、動物の美しい外観を研究した動物学者は幾人もいるが、ダミッシュは彼らの試みを芸術作品の歴史性の問題にさりげなくつなげてみせた。
なによりもまずコーラルフィッシュの「美しさ」こそが、ローレンツにその魚への関心を抱かせ、なぜ鮮烈な色彩を呈しているのかを解明する試みに導いたのだった。いま主流の実証主義は、過去の芸術作品を今日のわたしたちの基準にしたがって判断してしまうことに対して、それはアナクロニズムであると告発する。わたしたちは過去の芸術作品を、その同時代人のものであろう眼と用語によって考察するよう努めるべきというわけだ。だがそうであれば、動物は「美しさ」を指し示すどんな言葉ももっていないにもかかわらず、行動学者がある種の動物の「美しさ」を語り、その美しさを問題にまでしてしまうことに関しては、なんと言うべきだろうか。 (1)
主著『パリスの審判』の註に慎ましやかに書かれたこの指摘の眼目は、もちろん、人間は動物の美しさを語るべきでないなどというような疑義ではない。まさにその逆に、ダミッシュが問題とするのは、わたしたちが人間でない動物の美しさを語りうるのと同様、わたしたちの時代のものではない過去の芸術作品に対して現在から視線を投げかけることができるという事実である。トマス・ネーゲルのごとく人間はけっしてコウモリになれないと言うとしても、人間がたしかに他の動物を理解できるのと同じく、どれほど実証主義歴史学から非難されようと、芸術作品をまえにして引き起こされるアナクロニズムは──すでに別の機会に指摘したように(2)──「時代」「社会」「文化」などといった仮構された全体性から脱け出して、その作品が呈示するイメージの特異性とわたしたちの眼差しの歴史性とを理解し、新しい思考と経験がわたしたちに開かれる端緒となる。ダミッシュ自身の指摘にもとづけば、そもそも芸術というもの自体が、歴史的な実証性など配慮することもなく過去の作品をモデルに新しいイメージをつくり、古いイメージを新しい作品に仕立て、アナクロニズムと言うほかない捩れた歴史を紡いでいる。そのため芸術の呈示するイメージは、生み出された歴史的文脈から意味を与えられるどころか、みずからの歴史的文脈そのものを作り上げ、含み込み、先取りさえしてしまうという(3)。こうしたイメージのありようを、ダミッシュは盟友ルイ・マランとともに、「理論的対象〔objet théorique〕」と呼んだのだった。
とはいえ、そのようなイメージのアナクロニズムが、ちょうど人間が動物の美しさを語りうるようなものだというのは、いったいどうしてだろうか。このとき類比されているイメージのアナクロニズムと動物の美しさは、正確にはいかなる点で結びついているのだろうか。「隠喩の作用たるものは、拡張され、さらには逆転されうる」(4)と指摘したのがほかでもないダミッシュだとすれば、イメージのアナクロニズムと動物の美しさとの類比もまた、逆転され拡張されうるのでなければならないだろう。つまり、イメージが歴史のなかで時間を跨ぎ越していくのと同様に、美とは動物と人間、自然と文化の分割を横断していくものではないのか。
ここでは、一見して思弁的と感じられるかもしれないこの問いの消息を辿って、一つの自然美学への筋道を素描したいと思う。示唆的なことにも、ダミッシュの、そしてマランの学統を継ぐ若き美術史家たち、なかでもベルトラン・プレヴォーとトマ・ゴルセンヌが、近年、まさに動物と人間、自然と文化の分割を横断するような美学を展開しはじめている(5)。それを「イメージの人類学」から「自然の美学」への転回と言い換えることもできるだろう。いったいなぜそのような転回が生じつつあるのか。そこに、ダミッシュの示唆した類比の結節点が──言うなれば人間と自然の結節点が──あるにちがいない。
2 コンセプチュアル・アートの創始者の一人として知られるジョゼフ・コスースは、一九七五年、「人類学者としての芸術家」と題された文章を公表する(6)。かつてコスースは、名高い論考「哲学以後の芸術」(一九六九年)ですべての芸術が概念としてのみ存在すると主張して(7)、《一つにして三つの椅子》(一九六五年)をはじめ、人間のもつ概念そのものを問いに付すような作品を発表していた。けれども、次第にそうした概念を支えている具体的な社会制度・文化言説・政治構造へと関心を移し、フィールドに住み込んだ人類学者のように現代世界を観察して、その観察行為自体を作品化するようになっていく。同時期には、すでにほかにも「人類学化された芸術〔anthropologized art〕」が現代美術の領域にあらわれはじめていた。芸術家が異邦の作品や文物から鼓吹される事例には古来ことかかないにしても、人類学という学術営為の様相を呈した芸術活動は、この頃から現代美術の顕著な動向の一つとなって、今日にまでいたっている。
「イメージ人類学」の呼称で括られる美術史家の試みが登場したのは、それからほどなくしてのことだ(8)。なかでもアメリカのデイヴィッド・フリードバーグ、ドイツのハンス・ベルティング、フランスのジョルジュ・ディディ=ユベルマンの名とともに知られているイメージ人類学の探究は、西洋美術史と民族芸術学との学術制度的な棲み分けを飛び越えながら、人類史全体を貫くイメージの存在を問いに付す。とはいえそれだけのことであれば、なにもオリエンタリズム批判とポストコロニアル批評の時代を潜り抜けるまでもなく、すでにアロイス・リーグルやヴィルヘルム・ヴォリンガーの美術史研究でも試みられていた。一九八〇年代に徐々に姿をとりはじめ、二〇〇〇年代からはっきりとした潮流をなすようになったイメージ人類学に新しいところがあるとすれば、イメージの形態や様式、あるいは意味や内容よりも、イメージの機能や効果にはっきりと問いの焦点を移したことだろう。すなわち、フリードバーグの古典的研究の題を借りれば、「イメージの力」という観点から問いかけたところに新しさがあった。人間が生きては死んでいくなかで、図像や造形をめぐる諸実践はいかなるはたらきをしており、どのような「力」を人々に及ぼしているのだろうか。人々は身体を装い、事物や空間を紋様で飾り、図像に祈りを捧げ、彫像を埋葬し、肖像を身辺におき、画像や図案を取引し、映像を消費する──手法や手順は想像を絶するほど多様だとしても、イメージなしに人間は生きることも死ぬこともない。そこに人類史全体を貫いて作用している「イメージの力」を認めることができるだろう。
しかしながら「イメージの力」への着目は、イメージ人類学にとって尽きせぬ豊饒な成果の源泉であるとともに、一つの罠でもある。現代美術とその批評の「民族誌的転回」を批判的に検討したハル・フォスターにしたがえば、「人類学」とは、学際性を調停できると考えられているがゆえに、芸術的・理論的に曖昧で文化的・政治的に袋小路に突き当たっているわたしたちの現状において選ばれた妥協的言説にほかならない(9)。イメージ人類学に括られる研究の数々に対しても、おおむね似たような方法論的な曖昧さと理論的な雑駁さを指摘できるかもしれない(もっとも、まさにそのような雑食性が実り豊かな考察をもたらしていることも看過すべきでない)。フリードバーグ、ベルティング、ディディ=ユベルマンだけを見ても、分析の手つきから論証の語り口までかけはなれている。全人類史的な「イメージの力」なるものも、相容れないはずの雑多なものを詰め込んだ呪文めいた言葉ではないのだろうか。
ここで示唆的なのは──すでにいちど別の場所で検討したが(10)──『イメージの力』と題された二冊の書物のあいだの奇妙な対照性だ。すなわち、デイヴィッド・フリードバーグの『イメージの力〔The Power of Images〕』と、ルイ・マランの『イメージの力〔Des pouvoirs de l’image〕』である(11)。かたやフリードバーグは、言うなれば歴史家として、イメージに対する観者の反応を歴史上にあとづけ、複数形の「イメージ〔images〕」のなかに単数形の「力〔power〕」を探った。かたやマランは、むしろ哲学者として、イメージを焦点に展開される言葉と思索と行為の駆け引きを理論的にたどり、逆に「イメージ〔image〕」を単数形にして、「力〔pouvoirs〕」のほうを複数形で解した。この一見して瑣末にも思える対照性に、「イメージの力」の呪文を解く鍵がある。
もともとキリスト教における聖像破壊の研究からはじめたというフリードバーグの著作では、古代エジプト美術からモダンアートまで多数のイメージが縦横に取りあげられつつ、いずれもそれらに対する観者の反応が社会心理学的観点から探られている。未開社会から近代社会まで、アフリカ、アメリカ、ヨーロッパ、アジアのいずれにあっても、時代と地域を越えて繰り返しイメージへの同様の心理的反応が──抑圧されることはあれど──引き起こされている。フリードバーグにとって「イメージの力」とは、そのような観者の心理的反応の惹起にほかならない。複数のイメージを貫く唯一の力としての心理作用。とすれば、近年になってフリードバーグが神経学者ヴィットーリオ・ガッレーゼと共同して、認知科学の観点から芸術研究を企図しているのも当然の展開と言える(12)。人類共通の認知構造に、時代も地域も越えて繰り返される反応の根拠が探られる。このとき全人類史的な「イメージの力」は、人類共通の自然本性にもとづく──たとえ実際の反応の度合いはそれぞれの文化や状況によって条件づけられるにせよ──と想定されている。
けれどもマランは、こうしたフリードバーグのいわば心理主義的なイメージ理解に対して疑義を差し挟む。
最近アメリカで出版された著書〔フリードバーグ『イメージの力』〕で試みられているような、諸々のイメージに対する観者の反応の歴史と理論は、諸々のイメージとそれを眼差す者たちとの関係(イメージである身体と眼差しをもつ身体との関係)を特徴づけているヒステリー的な症状を示す関係の両軸のうち、片方にしか、つまり効果という軸、力という軸にしか、位置づけられえない。しかしその軸は、もう片方の軸を通さなければ、効果を惹起するという本性をもつテクストを介さなければ、アプローチできない。イメージの力は、その根底においては、つまりその起源、機能、目的、結末においては、歴史と文化のなかでイメージがとる特殊な布置のうちでのみ、そうした布置の結果と根拠からのみ、導かれ、想定される。パスカルの表現を借りるなら、イメージの本質に関する存在論的定式──力の存在──は全体として、メタ心理学的な仮説に属する理論的虚構でしかないのだ。(13)
マランによる批判の眼目は、観者の反応が、フリードバーグの考えるような心理やその抑圧からだけではなく、まさにイメージによってこそ引き起こされていること、しかもイメージの力はそのイメージが形成する歴史的にして文化的な布置から生じてくるのであって、全歴史と全文化を貫くような唯一普遍の力など理論的虚構にすぎないこと、である。だからこそマランは、フリードバーグと逆に、「力」のほうを複数形で解する。フリードバーグは、心理作用であれ認知構造であれ、人類共通の自然本性を想定し、それがイメージに唯一普遍の力を与えていると見なすが、マランからすれば、イメージのほうが歴史と文化の形成を介してそのつど異なる力を発揮するのだ。
この批判をさらに突き詰めたのが、ベルトラン・プレヴォーである(14)。プレヴォーによれば、フリードバーグの心理主義的前提は、結局のところイメージに力があるのはイメージに力があると思うからだというトートロジーになってしまう。問題の根幹は、見られる客体としてのイメージと見る主体としての観者の関係という想定そのものにあるだろう。
フリードバーグは、イメージを観者との関係、「相互作用」でしか考えないために、イメージそれ自体が関係であることを忘れている。イメージの効力は、観者をすでに捉えて巻き込んでしまっている力関係の場ないし布置がまさにイメージであることを、つねに前提にしている。主体(観者)と客体(イメージ)の分割ないし対立に──哲学的に言えば観念論的な袋小路の対立に──依拠したままでは、図像の効力をうまく問題にできない。(15)
ジョゼフ・コスースが、芸術とは芸術の概念であるという立場に留まりえなかったことは、この意味で示唆的だ。イメージの力の根拠はイメージが力をもつという心理的効果だとするフリードバーグの立論は、たとえその心理をミラーニューロンに置き換えようとも、コンセプチュアル・アートと同じトートロジーにしかなりえない。コスースの芸術活動のモデルが哲学から人類学に変わり、普遍的な概念を支えている個別の具体的な実践に焦点を移していったのに倣って、わたしたちも眼差しの主体において作用する唯一普遍の力とその根拠から多数のイメージを説明するのではなく、逆に、個別のイメージからそのつど異なる多彩な力を把握すべきではないか。マランの系譜に連なるイメージ人類学で「残存するイメージ」とそのアナクロニズムこそが問われているように(16)、時代も地域も越えて反復されてゆくのは、観者の反応である以前に、まずもってイメージのほうだろう。そしてイメージは、プレヴォーの示唆にしたがうなら、観者との関係を取り結ぶよりもまえに、すでに「それ自体が関係である」。
3 ミシェル・セールは、その思想の一つの集大成とも言うべき「大きな物語」四部作のはじまりを告げた著作『人類再生』で、人類史的展望における文化の発生を、人間と動物の関係から考察している(17)。
今日わたしたちは、技術が関わるのは無生物の対象、道具、機械ばかりと思っている。ところが、狩猟、採集、牧畜、農耕は、生物へと特化した鑑定を必要とする。かつて世代から世代へと受け継がれてきた飼い慣らされた動物と一緒の生活は、人類がそうした動物とともに共同の家を構築していたことを想定させる。仕事と日々の混在したこの住居が、多様な文化を生んだのである。そのなかでは、生命はわたしたちの鑑定にしたがい、また逆にわたしたちの技術能力は生命とともに多様化していく。わたしはそうした文化が死ぬまえにその一つのただなかで生きていたから、証言しよう。このような文化は、人間と動物の相互飼育による真の教育をともなっており、さらには哲学者の言う意味での認識の発生を構築したのだ。(18)
セールによれば、哲学者たちは黙して語らないにせよ、家畜化こそ、人類の最初期の所有形態の一つであると同時に、人間の認識の発展をもたらしたものだという。動物は飼い慣らされることで新しい習性を獲得し、人間にしたがうようになり、また人間を理解するようにもなる。同様に人間のほうでも、飼い慣らした動物にあわせて新しい習慣や技能や認識を身につけ、動物を理解できるようになって、動物との共住生活に適応していく。セールが「相互飼い慣らし〔domestication réciproque〕」と名づけるこの過程は、言うなれば、動物の人間化にして人間の動物化という二重の生成変化である。「人間がみずからの特徴を動物たちに受け入れさせようとすれば、そのすべての動物たちの特徴を受け入れることが不可欠だ。〔……〕人間が豚や鶏のもとに入っていくことができてはじめて、豚や鶏は人間のもとに入ってくる」(19)。とすれば、人間が自然状態から文化状態へと移行したのは、パラドクシカルなことにも、人間が動物化したがゆえにだろう。そのためセールは、ラ・フォンテーヌの『寓話』を動物の擬人化と見なすべきでなく、逆に「人間社会のほうが動物集団をつねに取りあげ、模倣する」(20)とさえ示唆するのである。
このとき興味深いのは、相互飼い慣らしの根幹が「誇示〔parade〕」による外観の表出とされていることだ。それをセールは「コスメティック〔cosmétique〕」とも呼んでいる。
誇示を、赤い首筋を振るわせる軍艦鳥の雄のような、交尾へと誘う性的なダンスに単純化しないでほしい〔……〕いや、この求愛の誘惑もまた、呼びかけ、合図、フェイント、臭いなどの構成要素からなっており、その多様な儀礼は、人間の文化にきわめて近接した動物の文化を構築している。だから人間と動物の文化は、農園で、狩猟で、危険な遭遇において、容易に通じ合えるのだ。さらに最終的に模倣は、巧みな置き換えによって、ある一つの種が別の種を「理解」し、その「知」を利用することを、可能にするのではないだろうか。
動物はわたしたちに知らしめてくれる──知は、身体、筋肉、形態、身振り、動きの外観とともに生まれるのだ。誇示はそうした外観を準備する。すなわち、認識のうちには、あらかじめ誇示において準備されていなかったものはなにもない。(21)
この意味で、動物のコスメティック、動物たちの誇示する──しばしばきわめて美しい──外観は、人間の文化と認識の起源にある。動物の外観は往々にして、求愛行動(種の保存)としてか、さもなければ保護色や警告色(個体の保存)としてだけ説明されてしまう。けれども、驚くほど多彩をきわめる動物たちの外観を、同種間の性関係やごく限られた異種間の捕食関係にしか機能していないと考えてしまえるだろうか。セールが重視するように、人類史と自然史の視座からすれば、人間も含めた多種多様な生物たちは、分節言語なしに外観の表出によって、かくも長く広きにわたる諸関係を取り結んできた。人間の文化も、けっして自然と分割されないその渾然とした美学的な場から発生してきたのである。
とすれば、人間と動物はおたがいに、自然と文化の分割を横断するようなイメージを交わし合っているだろう。人間はさまざまな動物の羽、毛、皮、爪、殻、貝などを素材と題材にしてみずからの身体、また周囲の事物や空間を飾るが、それはすでに動物たちがその身をイメージとして誇示しているからとは言えないだろうか。孔雀は尾羽の見事な紋様を誇示し、蛸は巧みに海藻や珊瑚に擬態して隠れ、色鮮やかな熱帯魚は人間に鑑賞されるというように、動物はみずからをイメージとして差し出して、そのつど世界における関係を更新しているように思える。
そうした動物のコスメティックがすでに一つのイメージであることを強調したのは、ほかでもないプレヴォーである。アドルフ・ポルトマンとレイモン・リュイエの洞察を引き継いでプレヴォーは、動物の外観が「非有機的〔anorganique〕」であることを重視する(22)。体表の紋様や色彩は、生体の化学反応によるものであるかぎり無機的とは言えないが、解剖学的構造や内部の新陳代謝から比較的自立しているため有機的とも言い切れない。動物の外観は、身体から(わずかに)離脱している。そこに、個体や種の保存の機能というだけに縛られない、外観の美的潜在性が生じてくる。
動物のコスメティックに可能性の条件を与えているのは、美的潜在性が存在していることにほかならない。形態、眼状斑、色彩、斑点、玉虫色は、物理的なものや有機的なもののたんなる状態として生じるものではない。というのもそこには、そうしたモチーフに一致しないまま発現するものがなにかあるからだ。別の言い方をすれば、そこにはつねにヴァリエーションの余地を有しているなにかがあるのだ。コスメティックは、この種の客観的ではないが完全に実在している確かな美的平面の離脱のなかにある。文字どおり、動物の装いはもはや身体を描かない。むしろ有機的身体を脱身体化して、ヴァーチュアルな身体、ストア派の言う「非物体的なもの」を構成するのだ。(23)
プレヴォーによれば、動物の外観は身体機能に完全に一致しておらず、むしろ脱身体的なイメージを形成するがゆえに、性関係や捕食関係にとどまらない関係を他の動物や人間と取り結ぶことができるという。しかも、パラドクシカルなことにも、このイメージはかならずしも見られることを想定していなかったからこそ、そのつど更新されるような潜在力をもつ。進化論的に見れば、眼の発生よりもまえにすでに生物は多様な外観をもっていた。そのとき眼差す主体は存在しなかったのだから、外観にはいかなる機能もなかっただろう。ただ眼差されることのないイメージだけがあった。それが事後的に眼差しのまえに差し出されるようになったのである。
ディディ=ユベルマンとともにイメージは残存すると言うのであれば、もはや(あるいはいまだ)いかなる眼差しも存在しない世界に残存するイメージなるものは、考えられるだろうか。プレヴォーはまさにこの問いに向かい、観者のいないイメージを問いはじめる(24)。プレヴォーの研究のはじまりは、ディディ=ユベルマンと近しく、アビ・ヴァールブルクの衣鉢を継ぎながらルネサンス期イタリア絵画の身振りを問題にするものだった。かつてフリードバーグを批判したとき、プレヴォーが提案した美術史研究における現象学と人類学の観点のさらなる徹底化にも(25)、ディディ=ユベルマンの影を認められるかもしれない。ところがプレヴォーは、現象学の限界を指摘し(26)、人類学から自然史への踏み越えを語るようになる(27)。イメージには眼差しが必要ないのだとすれば、見るものと見られるもの、あるいは見えるものと見えないものの関係とは別のところに、「イメージの力」を問わねばならない。
ダミッシュの示唆に戻ろう。わたしたちはイメージのアナクロニズムと動物の美の類比を逆転させて、こう問いを投げかけたのだった──イメージが歴史のなかで時間を跨ぎ越していくのと同様に、美とは動物と人間、自然と文化の分割を横断していくものではないのか。いまとなれば、こう言えるだろう──動物と人間の美しいイメージは、錯綜した歴史をみずからつくりあげてしまうイメージのように、いかなる眼差しも存在しない世界にある、と。かくしてイメージへの問いは人類学を踏み越えて、眼差しなき自然の美学へと到達するのである。*
*岡本源太「「眼差しなき自然の美学に向けて──イメージ論の問題圏(二)」、『現代思想』第43巻第1号、2015年1月、143-151頁
(1) Hubert Damisch, Le Jugement de Pâris, éd. revue et augmentée, Paris, Flammarion, 1997 (19921), p. 286 (n. 9).〔ユベール・ダミッシュ『パリスの審判』松岡新一郎ほか訳、ありな書房、一九九八年、三一六頁(註九)〕
(2) 岡本源太「囚われの身の想像力と解放されたアナクロニズム――イメージ論の問題圏」、『現代思想』第四一巻第一号(二〇一三年一月号)、二〇一三年。岡本源太「芸術作品、プロトタイプ、理論的対象」、『であ、しゅとぅるむ』展図録、Review House編集室、二〇一三年。
(3) Damisch, Le Jugement de Pâris, cit., pp. 135-138.〔ダミッシュ、前掲『パリスの審判』、一四四〜一四七頁〕
(4) Hubert Damisch, Skyline, Paris, Le Seuil, p. 8.〔ユベール・ダミッシュ『スカイライン』松岡新一郎訳、青土社、一九九八年、一〇頁〕
(5) Bertrand Prévost, « Cosmique cosmétique. Pour une cosmologie de la parure », Images Re-vues, no 10, 2012.〔ベルトラン・プレヴォー「コスミック・コスメティック」筧菜奈子、島村幸忠訳、『現代思想』本号掲載〕; id., « Les apparences inadressées. Usages de Portmann (doutes sur le spectateur) », in L’adresse. Actes du XVIe colloque du Cicada, textes réunis par Bertrand Rougé, Pau, Presses universitaires de Pau, 2013; id., « Cosmétique animale », Figures de l’art, no 27, 2014; Thomas Golsenne, « L’ornemental : esthétique de la différence », Perspective, 2010-2011, no 1; id., « Généalogie de la parure. Du blason comme modèle sémiotique au tissu comme modèle organique », Civilisations, vol. 59, no 2, 2011.
(6) Joseph Kosuth, “The Artist as Anthropologist” (1975), in Art after Philosophy and After: Collected Writings, 1966-1990, Cambridge, Mass., The MIT Press, 1993 (19911).
(7) Id., “Art after Philosophy” (1969), in Ibid.
(8) Cf. 松原知生「美術史学からイメージ人類学へ」、ヴィクトル・I・ストイキツァ『ピュグマリオン効果』解題、松原知生訳、ありな書房、二〇〇六年、三九三〜四〇八頁。水野千依『キリストの顔』、筑摩選書、二〇一四年、三四三〜三五二頁。
(9) Hal Foster, “The Artist as Ethnographer,” in The Return of the Real, Cambridge, Mass., The MIT Press, 1996, p. 183.〔ハル・フォスター「民族誌家としてのアーティスト」石岡良治、星野太訳、『表象』第五号、表象文化論学会、二〇一一年、一三七頁〕
(10) 岡本源太「イメージの人類学から自然の美学へ――『イメージの力』展に寄せて」、『REAR』第三三号、二〇一四年。考察の必要上、同様の論述がいくらかあることをお断りしておく。
(11) David Freedberg, The Power of Images, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1989; Louis Marin, Des pouvoirs de l’image, Paris, Le Seuil, 1993.
(12) David Freedberg and Vittorio Gallese, “Motion, Emotion and Empathy in Aesthetic Experience,” Trends in Cognitive Science, Vol. 11, No. 5, May 2007, pp. 197-203; id., “Mirror and Canonical Neurons are Crucial Elements in Aesthetic Response,” Trends in Cognitive Science, Vol. 11, No. 10, October 2007, p. 411. なお、フリードバーグとガッレーゼの「神経美学」に対する美学者からの応答としては、フィリッポ・フィミアーニによるものが示唆に富む。Filippo Fimiani, « Simulations incorporées et tropismes empathiques. Notes sur la neuro-esthétique », Images Re-vues, no 6, 2009.
(13) Marin, Des pouvoirs de l’image, cit., p. 15.
(14) Bertrand Prévost, « Pouvoir ou efficacité symbolique des images », L’homme, no 165, 2003.
(15) Ibid., p. 279.
(16) Georges Didi-Huberman, L’image survivante, Paris, Minuit, 2002.〔ジョルジュ・ディディ=ユベルマン『残存するイメージ』竹内孝宏、水野千依訳、人文書院、二〇〇五年〕
(17) Michel Serres, Hominescence, Paris, Le Pommier « Le livre de poche », 2001, pp. 125-190.〔ミシェル・セール『人類再生』米山親能訳、法政大学出版局、二〇〇六年、一二九~二〇三頁〕
(18) Ibid., p. 125.〔同書、一二九頁〕
(19) Ibid., pp. 130-131.〔同書、一三六〜一三七頁〕
(20) Ibid., p. 137.〔同書、一四四頁〕
(21) Ibid., p. 143.〔同書、一五〇頁〕
(22) Prévost, « Cosmique cosmétique. Pour une cosmologie de la parure », cit., pp. 24-28; id., « Cosmétique animale », cit., pp. 162-163.
(23) Id., « Cosmétique animale », cit., p. 161.
(24) Id., « Les apparences inadressées. Usages de Portmann (doutes sur le spectateur) », cit.
(25) Id., « Pouvoir ou efficacité symbolique des images », cit., pp. 280-282.
(26) Id., « Les apparences inadressées. Usages de Portmann (doutes sur le spectateur) », cit., pp. 174-175.
(27) Id., « Cosmique cosmétique. Pour une cosmologie de la parure », cit., p. 28.
