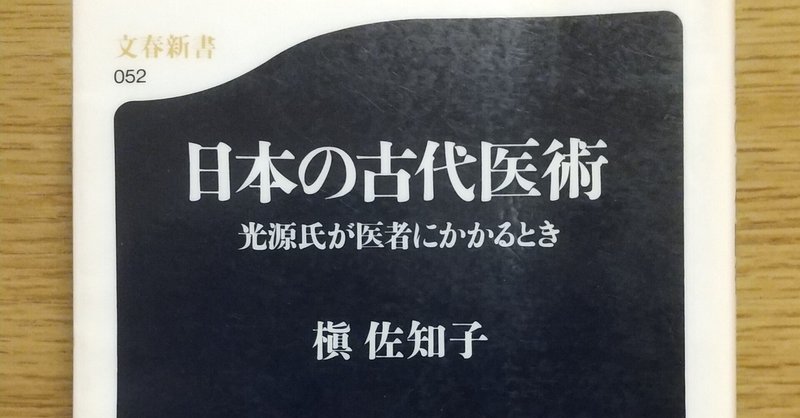
読書と翻訳(前編)
日本最古の医学書「医心方」のことが気になっている。それが縁となって最近、槇佐知子さんのことを知った。槇さんは「医心方」全30巻を翻訳された方なのである。
面白い経歴の人なので軽く紹介したい。槇さんは1933年生まれ、現在も存命で89才になる。静岡に育ち、1953年(20才)に武蔵野美術大学を中退した時点で学歴を終えている。医者でも学者でもない。しかも、瀧井孝作に師事して、小説を少なくとも数作は発表している。この時すでに40代であった。
難解な古語を読解する能力と、古代中国医学についての知識が必須の条件となる、「医心方」の翻訳。槇さんの経歴を見るかぎり、お世辞にも適役とは言えない。しかし、1974年(41才)に安政版の「医心方」を手にした瞬間、槇さんは天命を受け取った。すぐさま解読を始め、38年後の2012年(79才)、全巻の翻訳を達成。984年の成立から1200年、誰にも出来なかった偉業だった。
私は槇さんのことを知るや、江戸時代の学者たちを連想せずにはいられなかった。彼等もまた、槇さんと同じく徹底した独学者で、長い歳月を己の天命に捧げた人々だった。槇さんの「医心方」解読に対する38年に及ぶ献身は、本居宣長が35年かけて「古事記」を解読したのに匹敵する、学問上の事件だった。
さて、これで終わりなら単なる美談なのだが、これから書くことが今日、私が本当に書きたかったことである。
槇さんの著書に「日本の古代医術」があるのを知って読んでみた。題名のとおり、古代日本で行われた医療について分かりやすく紹介した本なのだけれども、槇さんはそのなかで次のように述べられている。
江戸後期の国学者で医師でもあった本居宣長は、私が尊敬する人物の一人である。だが宣長が「平安時代には見るべき医療がなかった」といったために、平安時代は医療の暗黒時代とされて来た。確かに彼が親しんだ『源氏物語』は、もののあわれを第一義とし、加持祈祷を貴び、医薬による治療を“さかしら”と蔑んでいる。やんごとない姫君たちを悩ます“もののけ”は、日本独自の思想と考えられて来た(3頁)
では本居宣長がいうように「当時はみるべき医療がなかった」かといえば、決してそうではない。七〇一年に大宝の律令が制定されたとき、中務省には内薬司、宮内省には典薬寮が設けられた(88頁)
「雨夜の品定め」のくだりで貴公子たちが「風病のためニンニクを食べたので」とデートをキャンセルした女の“さかしら”を笑いものにしている。それはすなわち紫式部の女性観でもある。雅びの一面だけを王朝女流文学が強調したため、「平安時代にはみるべき医療がなかった」という本居宣長の説が世に浸透した。しかし実際には鍼灸・瀉血・罨法、洗滌、さまざまな薬による治療法が、真言密教の呪法や陰陽道と渾然としていたのである(125頁)
読んでいて強烈な不快感に襲われた。理由は単純で、「宣長はそんなことを言っていない」からだ。宣長の著書「紫文要領」の一節を引いてみよう。
問ひて云はく、病といへば加持祈祷をのみして、今はの時迄もひたすら僧法師をのみ頼みて、医療を加へ薬を用ゆる事かつてなし。愚かなる事ならずや。答へて云はく、病といへば物の怪といひ、さならでもひたすら加持祈祷をのみする事、是れ又其の比の風儀人情也。其の比のみにもあらず、今とても又神仏の力をあふぐ事世のつね也。然るを人情風儀を棄てて愚か也と難ずるは、是れ又儒者の理窟にして大きに物語読むには忌む事也。又医薬の沙汰なきを見て、昔は薬をも用ひざりしかと思ふは古へにくらき事也。我国の古へ医薬の事諸書に見え、又此の物語の比とても医薬を用ひたる事はいふにも及ばぬ事也(157-158頁)
【現代語訳】
ある人が次のように質問した。「源氏物語では人が病気になると加持祈祷ばかりする。生と死の瀬戸際になってもまだ、ひたすら僧法師ばかりを頼みの綱にして、医療的な処置を加えたり、薬を投与したりすることが全然ない。馬鹿げたことではないか?」それに対して私は次のように答えた。「病気といえばすぐに物の怪のしわざと言い、そうでなくてもひたすら加持祈祷ばかりをするのは、それが当時の風俗慣習であり人々の病気観であったからだ。当時ばかりではない。現代においてもまた、いざという時は神仏の力を仰ぐのが世の常である。それなのに、そういった風俗慣習や人々の病気観を頭から否定して、馬鹿げたことだと非難するのは、儒学者の行き過ぎた合理主義であって、源氏物語を読むのに大いにさまたげとなることである。また、源氏物語に医薬に関する記述がないことを根拠に、昔は病気になっても薬も与えられなかったのかと思い込むのは、古代について無知にも程がある。古代日本における医学がどういうものであったかは、数多くの文献によって明らかであり、源氏物語の書かれた平安時代においても医薬が用いられたことは言うまでもない」と。
この宣長の言葉は、誰がどのように読んでも、平安時代には医療がなかったかのように誤解している、人々の無知を批判している文章であり、先に引用した槇さんの説明とは真逆である。つまり、槇さんはまともに宣長を読めていない。にもかかわらず、宣長の医療観についての誤った説を、どこかの解説書で聞きかじって、そのまま書き記したものと思われる。
これは非常に危険なことである。槇さんが引用しているのが流行作家の言葉ならまだ良い。引用の正否について検証がしやすいからだ。しかし、相手は宣長という、「書物として入手困難」かつ「文章として読解困難」な、江戸時代の学者の言葉なのである。おそらく槇さんの読者は「そうなのか」と鵜呑みにするだけで、正否を検証しようとは思わないだろう。誤解(デマ)というものは、こうして止めどなく広がって行くのだ。
槇さんの宣長の文章に対する不誠実な態度が、研究対象である「医心方」の文章にも貫かれていないことを祈るしかない。「医心方」の現代語訳に関するかぎり、私たちは槇さん以外に頼るべき人を持たないのだから。
(つづく)
参考文献:
槇佐知子『日本の古代医術ー光源氏が医者にかかるとき』文春新書、1999年
本居宣長『紫文要領』岩波文庫、2010年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
