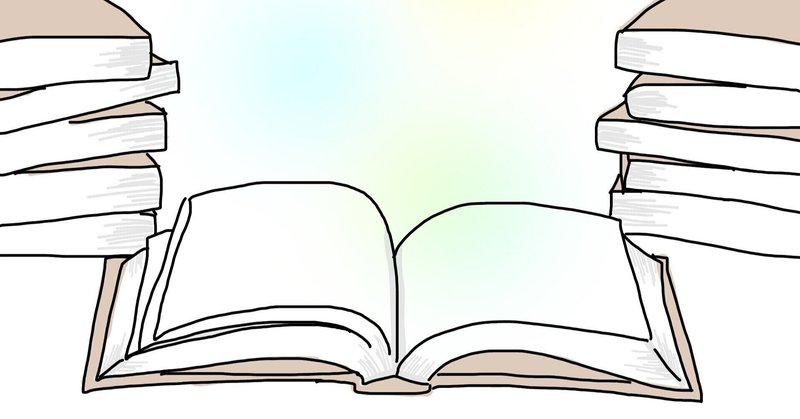
文章の考え方
タイトルにもあるように、今から書くのは、「文章というものをどのように考えているか」についての、個人的な、とりとめもない雑談です。
良い文章を書きたいという方は他をあたってください。私は自分のことを良い文章の書き手とは思っていないからです。とはいえ、何も書かないのは不親切なので一言だけ言えば、良い文章を書きたければ、良い文章を書くと思う人の書くものをよく鑑賞する、そして真似てみる、ということに尽きます。
私の場合、日本語の書き手で最も美しい文章を残したのは、森鴎外、谷崎潤一郎、小林秀雄あたりだと思っていて、最近の書き手ならば内田樹などが上手だと思っています。とりわけ谷崎には「文章読本」という、そのものずばりなタイトルの著作もあるので、谷崎の文章を良いと思う方なら、読んでみることをおすすめします。小林秀雄、内田樹も批評の文体として大変参考になりますが、森鴎外はとても真似られないので鑑賞するだけです。
1.日本語の文章には2つの流れがある
鴎外は真似られない、と言いましたが、これには理由があります。現在のように「話し言葉」と「書き言葉」が限りなく近いものになったのは明治時代のことで、以来、日本語はいわゆる「言文一致」と言われる状態になったのですが、それ以前はどうだったのかというと、スタイル(文体)で分けた時に大きく2つの流れがありました。言文が一致してからも依然として、そのどちらに由来している文章なのかがすぐに分かるほどに、はっきりとしたちがいがあります。
2つの流れ、それは漢文由来の文章と、物語由来の文章です。
鴎外の文章は明らかに漢文に由来しています。鴎外の文章を真似することができないのは、明治人の漢文の素養が現代人とは比べ物にならないほど深かったからです。もちろん、漢文をきちんと習得すれば、鴎外の「筆の運び方」を理解することも出来ましょうが、それは気の遠くなる作業になります。よほど鴎外系統の文章を書きたいと思うのでなければ、おすすめしません。
漢文は、必要最低限の情報で対象を的確に指示する論理的な文章です。反対に物語的な文章は、多くの形容詞を駆使したり、装飾を施したりすることで、なるべく共感を呼ぶように対象を指示する情緒的な文章です。漢文を「分からせるための文章」、物語を「感じ入らせるための文章」と、ざっくり分けては語弊もあるのですが、そういう言い方も出来ます。
2.何のために書くのかを考える
「・・・するための文章」という言い方は、「文章には目的がある」ことを前提にしています。むろん、それはあまりにも当然のことですが、だからこそスタイル(文体)の選択をする必要があるのに、文章の目的に合わせてスタイルを調整しない人が多いことが、私には気にかかります。
たとえば、お固い時事評論をするのに物語風の文体では、絶対に上手く行きません。今私が採用しているのは雑談風の文体ですが、これでも上手く行かないでしょう。時事評論となればやはり、批評の文体を選択するべきです。
批評の目的は、何にもまして分からせることであって、その目的のために多少の情緒が失われても、必要な犠牲と考えなければなりません。ただ、論理だけの文章では無機質すぎて味も素っ気もないので、読者に共感してもらうべく最低限の情緒を、そこはかとなく漂わせる必要もあります。このバランスがなかなかむつかしいのですが、とにかく、文章は書く目的によってスタイルを変えていかなければ、伝わるものも伝わりません。
3.内容があれば書けるものではない
ドストエフスキーは、彼の代表作「罪と罰」を、一人称小説として書き始めたそうです。それが途中で、このままでは書けないと思い直し、今までの原稿をすべて没にして、三人称小説に改めて再出発したと言われています。
内容は変わりません。ラスコーリニコフが哲学的殺人を犯したこと、娼婦ソーニャとの交渉のなかで罪の自覚が芽生えたこと、収容所で独自の信仰が彼に救いをもたらしたこと。そういう大まかな内容の変更はなかったのに、彼は文体の不適切のために書き直した。ここには大きな教訓があります。
文章はたしかに内容を伝えるために書くものです。しかし、内容があれば書けるものでもない。内容を伝えるための工夫が文体です。文体の選択ミスが文章にとって致命傷となることもある、という事実を、書き手はいつも肝に銘じておくべきでしょう。
文体の選択にあたっては、「想定読者」の考え方も重要です。これは内田樹が言っていますが、学術論文を書く時と、出版用の文章を書く時とでは、書き方が全然ちがってくる。学術論文では「周知のように」が呪文のように連発されますが、想定読者が幅広い出版用の文章で「エマニュエル・レヴィナスの絶対的他者とは周知のように」と書いたら、「レヴィナスって誰だよ、絶対的他者って何だよ!」となって、読者は本を放り投げます。読者が見えている書き手の文章は読みやすいですが、見えていない書き手の文章は本当に読みづらいものです。
4.意味ばかりが内容ではない
文章には内容があって、それを伝える工夫が文体だ、という話をしましたが、内容という言葉には、ずいぶん誤解が多いように思います。
小説家の安部公房が以前、NHKのインタビューに答えて、「物事を突き詰めた先には意味があるという考え方が、日本の国語教育の最大の欠陥だと僕は思う」と述べていました。これは文章を読み書きする上でも非常に大事な指摘です。
近年、「分かりやすい」とか「すぐ分かる」とか、枕詞のようにタイトルにくっつけている本が多く、TV番組でも「100分で名著」などが人気を集めているように、分かることが文章を読むゴールであるかのような言い方が、あちこちに見られますが、これはまったくの間違いです。そんなことを言ったら優れた文学作品など、すべてゴール出来るように作られていません。ある種の文章は時に、私たちを「意味の迷宮」に誘います。
文章は何かしらの「内容」を伝えるために書かれますが、その内容は意味でなくたっていい。むしろ、今まで自明の理だと思っていたことが実はそうではなかったことに気づかされたり、意味があるものだと思っていた物事に疑問符を突き付けられたり、答えを明示するのではなくて読者一人一人に答えを考えるよう促したり、そういったものも「内容」に含まれます。
5.分からないから書く
書いてあることの意味が分かることが読者のゴールではない、という話に続けて、書き手すら書いているものを分かっているとは限らない、という話をしてみたいと思います。
たとえば私は今、本居宣長の源氏物語論「紫文要領」を詳しく読むエッセイをnoteに連載していますが、「そういう文章を書けるということは、お前は紫文要領が言いたかったことを分かっているのだな」と問われれば、「いや、まだほとんど分かっていないし、分からないから書いているのだ」と答えます。
まず、書き手の心情から述べれば、分かっていることを述べるほど、苦痛なことはありません。まったく楽しくない。書いていて楽しい文章とは、意味がまだよく分かっていないのだけれど、自身にとって切実な問題であることだけは、はっきりと直観されている対象について書くことです。
もちろん、学術論文や新聞記事などでは、書き手は分かっていることを淡々と分かりやすく書く必要があります。さもなければ読者は読んでいて「この文章は私をどこに連れてゆくのか」と不安になるでしょう。だから、今述べているのは文章一般に当てはまることではありません。私が述べているのは事務連絡的な文章ではなく、書き手にとって「楽しい文章」についてです。
読者はどうなるのだ?いくら書き手が楽しくても、読者が楽しくない文章など、いったい誰が読むのだ?こうした質問が想定されますが、そのために文章は工夫されるのです。小手先の文章技術も工夫の一つではありますが、それよりもっと大事なことがあります。書いている対象と本当に楽しく語り合っているか?・・・これです。読者は敏感に察知します。読者にそこの所を納得させられれば、書き手と読者は自然と楽しみを共有し始めます。嘘らしく聞こえてしまえば、読者はついてゆきません。これは小手先の技術よりも、よっぽど大切なことです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
