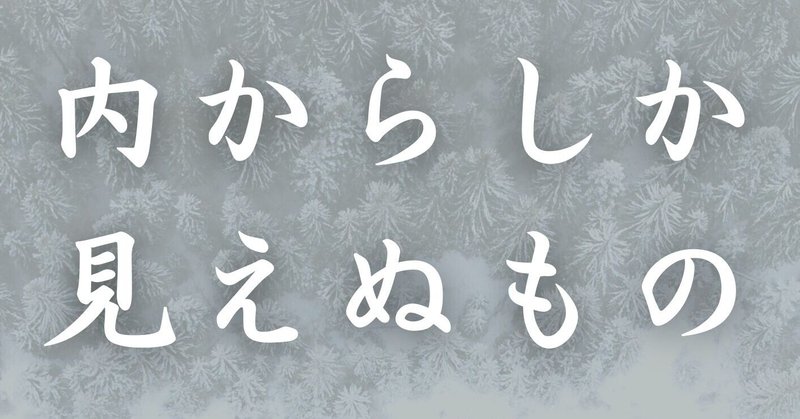
内からしか見えぬもの
今日は雪が降っている。秋をとばしたかのように冬がやって来た。
大学のキャンパスにも中庭にも雪が積もった。
戦火を免れ百年近くの歴史を誇る重厚なレンガ造りの図書館にも、容赦なく雪は積もっていく。普段図書館に足を運ばない学生も、この日ばかりは足を止めて、その姿を眺める。そして皆一様に、いつもなら一瞥もせず通り過ぎるそれを、写真におさめた。
だが、わざわざ雪の降るなか、図書館へ行こうという者はいない。みんな、大学のシンボルの図書館の、いつもと違う雪化粧姿に一度は足を止めるが、寒さに体を震わせ、足早に教室や近所のカフェ、あるいは自宅へとさっさと行ってしまうのだった。
そういった彼らを後目に、私は一人、図書館へ入っていく。
図書館の四階の、並ぶ本棚の間を縫うようにして奥に行ったところにある席が私の “聖域”だ。それはまるで、時の流れからも人の流れからも取り残されたかのようにポツンと一つだけ鎮座している。
図書館の利用者の大抵の用事は三階までで済んでしまうから、四階まで足をのばす物好きなんてほとんどいない。そのため四階には、それも奥の方ともなると、音は本棚の古木や本の紙にすっかり吸収され、独特の静寂が存在している。それが、ここが“聖域”たる所以なのである。
私がこの“聖域”を見つけたのは、大学に入学して半年ほど経った頃であった。世間の喧騒、浮世から離れようと、心地よい空間を求めてふらふらとしていたところ、偶然見つけたのである。それ以来通い続け、そろそろ一年経とうとしていた。
以来、私は、すっかり“聖域”の住人になっていた。騒がしい大学の中、孤高に存在する特別な空間は、まるで幼い頃の秘密基地のように感じられた。
机の上には、先週私が置いていった本はなくなっていた。その代わりに、別の本が置いてあった。いつものことだ。
このような現象が起こるようになったのは、ちょうどこの日のように、雪の日だったから、一年ほど前のことだった。その日、“聖域”に行くと、机の上に見慣れない本が置いてあったのだ。当時、私は、この“聖域”に誰も来ないことをいいことに、読みかけの本を席に置いていくことにしていたのだ。なのに、その日は、私が置きっぱなしにした本はなくなり、代わりに、読んだことのない本がそこに鎮座していた。それは、他人の痕跡――つまり、自分以外の誰かが交換したのだろう。
それを見て、私は、自身だけの、他人を感じさせない空間であったはずの“聖域”が踏みにじられたような気を覚え、その本をぶっきらぼうに手に取った。図書館に返却してしまおうと思ったのである。しかし、わざわざ四階まで来て読書するという奇特な人物が読む本に、存外私は惹きつけられた。同じく“聖域”を見出した、いわば同志は、どのような本を読んでいるのだろうか。私は、その本を開き、読み進めることにした。
――なるほど、“聖域”の住人は、いいセンスをしているようであった。少なくとも私にとっては、置いてあった本は面白かった。
そこで、同じく“聖域”の住人である私は、もう一人の“聖域”の住人に対し対抗意識が湧き上がり、その本を返却すると同時に、私が一番好きな本を借りて、“聖域”に置いていった。それは私なりの一種の返答であり、挑戦状でもあった。
数日後、私が再び“聖域”に来ると、私の置いていった本はなくなっており、代わりに別の本が置いてあった。
あながち私の予想が外れていなかったことを確信し、かくして、“聖域”における奇妙なやり取りが始まったのであった。
もう一人の“聖域”の住人の置いていく本は、私の心に染みるものばかりだった。ある時はワクワクする冒険物語、ある時は眉をひそめる専門的な物語、ある時は背筋が凍る怖い物語、ある時は足の先から頭のてっぺんまで熱くなるような恋愛物語。
そうしていくうちに、私はその人に会いたくなっていった。こんなに面白い本を、どうやってそんなにたくさん知ったのだろうか。どの本が一番好きなのだろうか。他にどのような趣味を持っているのだろうか。“聖域”にたどり着いた経緯はなんなのだろうか。疑問は絶えなかった。
やろうと思えば“聖域”に張り込めば、いつかは会うことができるだろう。しかし、それはなんだか野暮なことのように感じられた。おそらく、その人も、そんなことは望んでいないように思えた。
この場所は、本と対話する場所であり、人と人との会話なんて持ち込んではいけない場所だからだ。“聖域”が“聖域”たる所以は、人の存在を徹底的に廃したところにあるのだ。もし私がもう一人の“聖域”の住人に会おうとしてしまえば、この“聖域”を否定することになる。
ゆえに、“聖域”が“聖域”でありつづけるために、我々はどんなに会いたくとも、暗黙の了解により、“聖域”を介して会ってはいけないのである。
かくして今日も、机に置いていかれた本を私は読む。唯一の、もう一人の“聖域”の住人との繋がりだ。
御多分に漏れず、この本は面白い。そのあまり、体が冷えてぶるりと震えるまで、時間を忘れて本に入り込んでしまっていた。
ふと、窓の外に目を向けた。ここからは、キャンパスの中庭を一望することができる。中庭は誰も立ち入っていないおかげで、誰にも荒されていない、自然のままの雪景色があった。
腰の高さほどの楕円に剪定されたサツキには、うっすらと雪がまぶされ、まるで白い粉を表面に付着させた大福のようだ。その傍には、老齢な赤松が、その枝垂れた枝に、細く雪を積もらせている。
普段から静かではあるが、この日は特に人通りが少なくて、喧騒がなく、ましてや積もった雪が音を吸収するものだから、恐ろしく静寂な空間が俯瞰できた。
――ああ、なんと美しい景色なのだろうか。
しばらくの間、日常世界の非日常的な状態に浸っていたが、寒さが体を震わせ、ふと現実に返った。精神が、景色に奪われていたのが、自分の体に戻る。
私はいつも通り、置いていかれた本を返却すると同時に別の本を借り、机にそれを置いていった。外の果てしなく白い世界に、もう一人の“聖域”の住民への思いを馳せた。
*
数日後、冬に本格的に入り始めてしまった頃、図書館の階段近くの小部屋で、学生による有志の写真展が開かれていることに気が付いた。
私は深く考えずに立ち寄っていた。『四季の図書館』という展覧会のタイトルに、心惹かれたのである。私以上に図書館のことを知っている者はいないという自負があったからだ。
展示は壁沿いにあり、春から始まった。
春の季節。入学の年。鮮やかな青空の下、豊かな花々をつけた桜とともに、図書館がそびえている写真が展示されている。
――聖域の存在、そしてもう一人の“聖域”の住人の存在に気付いた季節だった。
夏の季節。木々の若々しく輝く新緑と、図書館のレンガの落ち着いた色味がお互いを引き立てている写真が展示されている。
――夏休みは、二日おきに図書館に通うことにしていた。夏休み中でも、もう一人の“聖域”の住人とのやり取りはとりおこなわれていた。
秋の季節。黄色や赤色、そのなりかけの色合いの葉が、図書館の鄙びた外壁とマッチしている写真が展示されている。図書館の窓には秋空が映り、それぞれの窓の中に空がそれぞれあるかのようだ。
――読書の秋といわんばかりに、私はいつもの席で本を読んでいた。もう一人の“聖域”の住人も、きっとそうだったであろう。会わずともわかる。
こうして振り返ると、感慨深い。振り返ればこの一年は、顔も知らぬ、もう一人の“聖域”の住人との思い出ばかりだった。
そうして、春夏秋冬、順に見ていって、最後の、冬の展示を見る。
これまでとは違って、一風変わった写真だった。
図書館の建物が写っていないのである。
その代わりに写っているのは、キャンパスの中央に位置する中庭の俯瞰であった。くねった赤松の幹や枝、尖った葉に雪がのっている。老齢な出で立ちも、雪化粧されれば、それはそれで趣がある。その傍には、白い饅頭のように、サツキにも雪がまぶさっている。
「綺麗だけどさ、これ、図書館じゃないだろ」
いつの間にか隣にいたカップルであろう見知らぬ二人組の男の方が、隣の女に言った。
「全然図書館写ってないじゃん。これなら、私が撮った写真の方が綺麗よ」
たしかに一見、この写真は図書館とは関係ない、中庭の雪景色のみ写っているようであった。
だが、私にはわかった――いや、私にしかわからないだろう。
この作品は、私並みに図書館を愛する者しか気づけない、図書館の写真なのである。
私は言い知れぬ、なにか温かいもので心が満たされていくのを感じていた。
なるほど、図書館の建物自体の美しさを知る者は多くとも、その中からからの――それも、あの位置からの景色の美しさを知る者は数少ないものだ。
展示部屋の最後に、写真を撮った学生が受付をしていた。展示されている写真の絵ハガキを売っていた。
春夏秋冬の写真のうち、明らかに冬の写真だけが売れ残っていた。
私は、一年間よく見知った馴染みのある景色の写った絵ハガキを手に取り、買おうと思って受付の人の方を見た。
その人の手には、私が昨日“聖域”に置いていった本があった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
