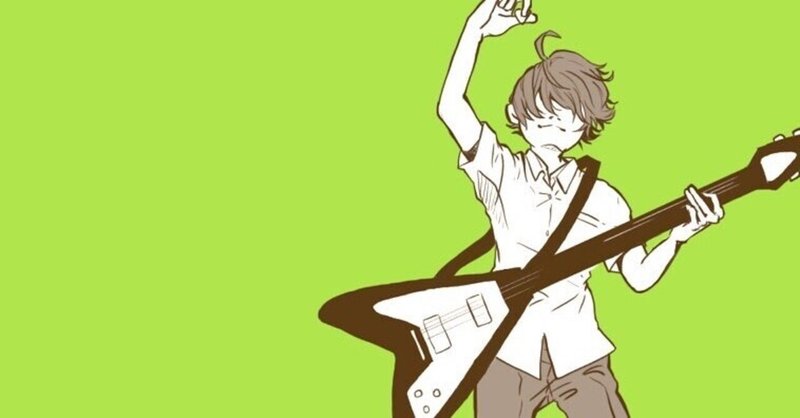
飛べ、飛べ!他の誰でもない自分の目で世界を見つめろ!
「伊藤たかみさんとの対談イベントに参加しない?」
高校1年の冬、誘ってくれたのが現国の先生だったのか友だちだったのかもう覚えていないけれど、その瞬間、ごろりとわたしの人生は転がった。
中学生の頃から美術ひとすじ。課題以外の本は年に1冊も読まない。学校の図書室など入学初日に案内されて以来、1度も足を踏み入れていない。そんなだから、伊藤たかみさんが芥川賞作家だということをそのときはじめて知った。
地元のホールで講演会があり、プログラムのひとつに県内の高校生との座談会が設けられているという。放送部の朗読大会で優勝したのをきっかけに、友だちがステージに上がる高校生のひとりとして呼ばれ、仲の良かったわたしにも声が掛かったらしい。
正直、人前で自分の意見を主張するのは苦手だ。今をときめく作家さんときちんとお話しできる自信もない。だけど、そんな方と同じ舞台に立ってことばを交わす機会なんて、めったにない。観客ならお金を払えばなれるけど、出演するのは頑張ってどうにかなるものではない。舞いこんできたキップを、使わない手はない。
当日までに、各自、伊藤さんの著書を読んで質問を考えてくることになった。はじめて図書室の扉を自主的にくぐり、いくつか借りた。中でも、とりこになったのが『ぎぶそん』(ポプラ文庫ピュアフル)だ。
舞台は昭和の終わり。ロックとギターが好きな中学2年生のガクは文化祭のライブに向けて、元野球部のマロとおさななじみのリリイに声を掛けバンドを結成する。だけど、憧れのガンズ・アンド・ローゼズの超難易度の曲を演奏するためには、もっとギターのうまいメンバーが必要。中学一といわれるかけるの家に押しかけ誘うのだが、彼には短気な一面が。からかわれるとキレるのに、似たようないたずらに怒らない日もあって、わからないから友だちも離れていく。かけるがバンドに入ることで、メンバーの仲もぎくしゃく、音もバラバラ。彼らがどう仲間と向き合い、演奏をまとめていくのか、ドキドキしながら無我夢中で読んだ。
一直線なガクが巻き起こす甘酸っぱく爽やかな風に吹かれ、一読でこの物語が好きになってしまった。音楽にのめりこむ熱さだけではなく、先があずき色のシューズってださいなーとか、デパート1階の「モンモン」はたこ焼き以外ぜんぶまずいなーとか。思春期にゆるんとのっかってくる世界の重みも手に取るように伝わってくる。
絶対、この作品について聞くんだと、質問が浮かんでくるまでページをいったりきたり。心が震える場所を耳を澄ませて確かめた。
事前の打ち合わせで、県内から集まった高校生たちと質問を共有することになった。作品のテーマに踏み込み、自分の悩みと結びつけて発表するみんなを見ていたら、自分の質問がだんだん取るに足らなく思えてきた。やっぱりわたしには考えをことばにするなんて向いてないかも。心なしかまわりがぐんと大人びて見えて小さくなっていると、仕切っていた先生がわたしの名前を呼んだ。
『ぎぶそん』は、ガクとリリイの視点が交互に進む。ガクと一緒に熱くなるのも楽しいが、リリイの繊細な感情の揺れに心を重ねるのもいい。男子といるのを変だと言われたり、かけるに恋するサトミに嫉妬されたり、女子特有のややこしい関係に巻き込まれてうんざり。一方で、自転車を改造したり、不謹慎なゲームで遊んだりして楽しむ男子たちと混ざりきることもできない。微妙な距離感がとてもリアルに描かれている。
徐々にガクを好きだと自覚していく過程もいじらしい。おさななじみだから、同じバンドのメンバーだから、素直になれなくて。バンドエイドの内側に好きな人の名前を書いて交換するシーンはじれったくて、つい自分ごとのように応援してしまった。
「どうして中学生の女の子の気持ちがわかるのか聞いてみたいです」
おずおずと考えてきた質問を口にする。
主人公たちと2年しか離れていないわたしですら忘れていた感覚が、この作品にはぎゅっと詰まっていて、1行たどるたびにぱんとはじけてあふれだす。どうやったらこんなふうに書けるのか。
「いいね!都村さん、トップバッターでいこう」
仕切っていた先生が突き抜けるように明るく答えて、微笑みかけてくれた。
え、いいんだ。
ふっと肩の力が抜けた。どんな驚きも不思議も感動も発見も、本を通して受け取ったものはぜんぶあなたのものよ。たったひとことだったけれど、そう認めてもらえたような気がして自信がわいた。今日は国語のテストじゃない。ぜんぶ、正解なんだ。
ライトに照らされたステージは、反対側に座る伊藤さんの顔より薄暗い客席の方がよく見えた。話した内容を筆記している人が真ん中に座っていて、手元がプロジェクターに映されている。しゃべったそばから消えるいつもの放課後とは違うのだと、みるみる連なっていく文字を眺めながら気を引き締める。
座談会の趣旨説明が終わると早速、わたしにマイクが回ってくる。深く息を吸って、用意してきた質問を意識してゆっくりと音にする。言い終わると伊藤さんがマイクを手に取った。
「なぜか女の子の気持ちが昔からわかるんですよね」
なんでもないことのようにさらりとおっしゃった。あまりにも軽やかな返答に、女の子の気持ちは女の子にしかわからないと決めつけていたのがくだらないことに思えた。
それから伊藤さんは生い立ちから丁寧に語ってくださった。聞きながら、なんて不思議な空間なんだろうと思う。本を読んでいるときは、紙とインクとわたし。だけど、こうやってことばをたぐり寄せていけば、ちゃんと人とつながっているのだ。勝手に物語が生成されるはずもないのだけど、本の向こうに人がいるという実感がじわじわと肌にしみていくのを感じていた。
3年生になって、わたしには美術の世界で食っていく才能もお金もないことを悟った。代わりになるものをあてがわなければいけない。少しでも興味のわく道はどれだろう。大学のパンフレットを前に、好きを拾い集めて浮かんだもののひとつが、『ぎぶそん』と伊藤さんとの対談の思い出だった。もっとわかりやすく役に立ちそうな学問はある。だけど、わたしにとって、学んだ先に確かに人とつながっている実感が持てるのは小説しかなかった。
文学部に進学して、たくさんの物語を知った。大人になっても自分の意見を言うのは相変わらず苦手だ。だけど、本を通して生まれた思いや考えならなぜか思いっきり語ることができる。それはきっと、あのとき先生がどんな質問も認めてくれたから、そして伊藤さんがまっすぐに答えてくれたから。だからこうして今も、本の感想を発信し続けている。
読みたい本は年々増え、つぎつぎ新しいものに手をつけてしまうけれど、『ぎぶそん』はなんども読み返す。
かけるが住んでいるさやま団地は、昼間から酒を飲んだ大人が歩いていて、”ガラが悪い”といわれる地域。かけるのおじいちゃんもおとうさんも酒飲みで、かけるは家事をこなしながら、母親が出ていったあとの家を支えている。”ぎぶそん”ことギブソン社の”フライングV”は、外の世界へ飛び立つためのよすが。でも、同時にどこかあきらめてもいる。
「でもおれは、さやま団地の子やからな。高校かっていけるかどうかわからんし、大学はまずムリ。中学卒業したら、だれも相手にせえへん。高校いったやつらは、その高校同士で仲ようなるしな」(p.47)
そんなかけるにマロやリリイは「さやま団地やしなあ」「問題児なんやろ」とつぶやく。誰かが引いた線に沿って距離を取って、誰かがつくったフィルター越しに見てしまう。
わたしは、かけるやマロやリリイに似ていると思う。「女の子の気持ちは女の子にしかわからない」と決めつけたり、「わたしは自分の意見を言うのが苦手だ」と自分の殻を破ることをあきらめたり。
だけど、ガクはそんな境界線を軽々と飛び越え、相手の心に突っ込んでいく。
さやま団地に住んでない人に気持ちは分からない、と心を閉ざすかけるにガクはこう言ってみせる。
「ガクやったら、おれのこと助けられるんか」
「成功するかどうかはわからんけど、助けようとはするやろ」
「なんでそんなんするんよ」
「なんでって……おまえ、頭どっか打ったんちゃうのん。友だちやったらふつう、そうするやん。みんなそうしてるやろが」(P.110)
彼にとって、友だちは友だち。好きなものは好き。住んでいる場所とか環境とか関係ない。わからないと決めつけずに、まわりに振り回されずに、自分の心で考えて、できるかぎり相手の思いに近づこうとする。そういう彼の身軽さがまわりを惹きつけ、伝播する。
そこに住んでっから、どうせいつか、みんなとバラバラになるなんてだれが決めたんじゃ(p.224)
門があるわけでもないやろ。出るのもはいるのも好きにできるやんけ。地続きやねんぞ(p.224)
本を開くたび、ガクはわたしの手を引いて、境界線やらフィルターやら限界やらを、まとめて一緒に飛び越えてくれる。他の誰でもない自分の目で世界を見つめる大切さを教えてくれる。
はじめて本の向こうへ連れられていったあの日から、この本は変わらず飛べ、飛べとわたしを先導する。大事なだれかの思いのもとへ、夢の先へ。これからも、きっと。
◉伊藤たかみ『ぎぶそん』(ポプラ文庫ピュアフル)
頂いたサポートは書籍代に充てさせていただき、今後の発信で還元いたします。
