
<モキュメンタリーの隆盛とJホラーのリアリティについて>
文=近藤亮太
関連キーワード:
ホラー映画、ホラー小説、フェイクドキュメンタリー
いま、日本のホラー映画界に熱い炎が燃えあがろうとしている。2021年から第一回が開催されている「日本ホラー映画大賞」。KADOKAWA主催で行われているこの映画祭では、全国から応募されたホラー自主映画が審査され、大賞受賞者には長編ホラー映画デビューが約束されている。審査委員長を務めるのは、映画『呪怨』で一世を風靡した清水崇その人だ。かつて、定型にハマった心霊表現を打破すべく生まれた映画『リング』『回路』『呪怨』などといった作品も、もはや「Jホラー」という使い古された定型となってしまった。いま、ホラーの神々は、新たにそれを塗り替える若い血を求めている。
この日本ホラー映画大賞において、近藤亮太監督は、第一回から自主映画を応募して受賞を果たし、第二回では見事大賞を勝ち取った。近藤監督が大賞を受賞した作品は、『ミッシングチャイルドビデオテープ』。とある男児の失踪の際に撮影されたビデオ映像にまつわるホラー映画だ。いま、日本の新しいホラー表現の最前線にいる近藤監督に、いわゆる「Jホラー」と呼ばれる表現や、架空の出来事をドキュメンタリー形式で表現する「モキュメンタリー」の「いま」を聞いた
「モキュメンタリー」「フェイクドキュメンタリー」はどのように社会に受け止められてきたのか?
「モキュメンタリー」あるいは「フェイク・ドキュメンタリー」は、主に映画の世界で使われていた言葉だったと思う。
『食人族』まで遡っても良いが、おそらくいちばんわかりやすいのは『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』だろう。
メディアミックスの手法を取り入れ、映画のみでなく、インターネット上でも情報を補完することで、観客の現実世界に、映画の側が侵食するような仕掛けを施す。
実際に俳優陣にカメラを持たせて、本当に森の中でキャンプをさせながら一日ごとのシナリオを都度渡す、というスタイルは、それまでのホラー映画におけるリアリティの刷新をもたらした。

以降、厳密な定義はそれほどされず(唯一白石晃士監督のみがPOV、フェイク・ドキュメンタリー、ファウンド・フッテージを厳密に用いている)、大まかに言えば「ホントっぽいやつ」がフェイク・ドキュメンタリー=モキュメンタリーとされている。

昨今、このフェイク・ドキュメンタリーが主にホラー分野で大変な賑わいを見せている。それも、映画に限らず、書籍、テレビ、YouTubeと幅広い。 映像ではテレビ東京の大森時生プロデューサーによる一連の作品が挙げられる。『Aマッソのがんばれ奥様ッソ!』『このテープ持ってないですか?』『SIX HACK』『祓除』など。テレビだからこその、一般的なバラエティ番組のフォーマットを逆手に取って、秀逸な恐怖を連発している。 あるいはYouTubeでは寺内康太郎、皆口大地らによる、そのものずばり『フェイクドキュメンタリーQ』が公開されている。自ら「フェイクドキュメンタリー」を謳っておくことで自由度を確保したうえで、現実の裂け目のような多種多様なエピソードを発表している。

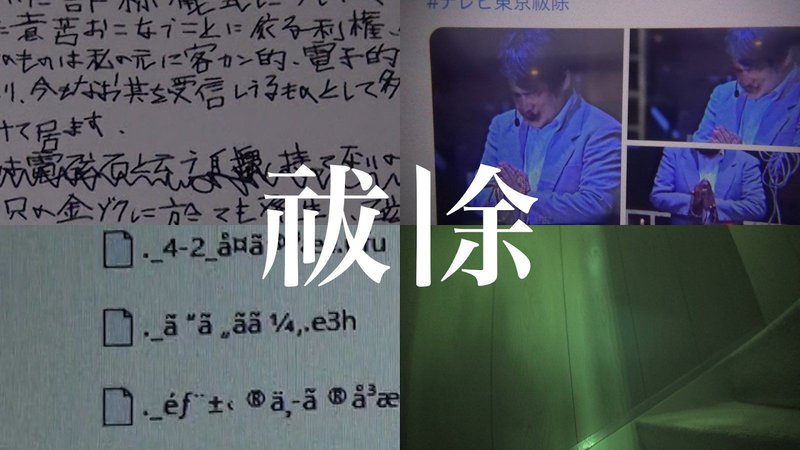
文章における「ファウンド・ドキュメント」
小説分野に目を向けると、比較的前から一定の素地は出来上がっており、代表的な作品としては小野不由美『残穢』からはじまり、三津田信三による『怪談のテープ起こし』や『幽霊屋敷』シリーズ等の諸作。
そして、同人電子書籍にも関わらず各界に衝撃を与えた阿澄思惟『忌録: document X』があって、以降、インターネット発の書き手として、梨『かわいそ笑』、芦花公園『ほねがらみ』、そして極めつけの『近畿地方のある場所について』と、ここにきて一大ジャンルとして発展した感がある。


小説に関していえば、上記の作品は原則としてすべて「発見された資料」「ネット上でかつてあったテキスト」「日記」といったテキストで構成されているいわば「ファウンド・ドキュメント」(朝宮運河氏の提唱)として構成されている点である程度共通している。
ホラー映画の世界では、一つの手法としては完全に定着していたものの、「劇映画」として公開される性質上、どうしても純然たるフェイク・ドキュメンタリーの体裁は取りづらい難点があった。
POV手法を取り入れたホラー自体は多いが、あくまで「劇中の登場人物が回しているカメラの映像」という程度であり、「本当かもしれない」部分は比較的重要視されていなかった感がある。
ところが、昨今の書籍を中心とした「ファウンド・ドキュメント」形式の作品群は、それ自体はどう考えても「作り物」であるにも関わらず、多くの読者にリアリティを伴う恐怖を与えている。
それはなぜなのだろうか。
一つには、どの作品も、「どこかで本当に起きた気がする」ような事件がモチーフになっていたり、何かしら現実との接続を感じるようなモチーフを用いている点が考えられる。
それは、たとえば実際の失踪事件を想起させるものであったり、実在する心霊スポットであったり、そういうモチーフが取り入れられることにより、記憶の片隅にある現実の事象と接続する。それが怖さにリアリティをもたらす。
また、記録メディアの多様化から、インターネットの普及。もっと言えば、インターネットの中でも「オールドインターネット」的な文化が一定数アーカイブされたことも、こうした作品群の隆盛の一つの要因として挙げられると思う。
メディア(情報媒体)がメディア(霊媒)となるとき、そこに「魔」が降りる
筆者は1988年生まれで、ちょうど中学校に上がるかどうかのタイミングで家にインターネットがやってきた世代である。
まだ光回線はなく、ISDNやらADSLといった回線がようやく一般家庭でも使われるようになった時期だった。
たかだか15秒ほどの動画(しかもSDサイズのさらに半分くらいの画質)を見るのに何分もかけていた時代である。
故に、当時のインターネット上のコンテンツは、動画よりは主に「テキスト」がメイン(わずかに「写真」が使われる程度)だった。
「テキストサイト」と呼ばれる、面白い文章で企画をやった経緯を記したり、日常のちょっとした会話を日記形式で書いてみたり。
あるいは映画のレビューを毎週膨大な量まとめて書いたり。
「オモコロ」なんかはまだ現役だが、基本的には文章を書くことで一定の読者を獲得するのは、かつてよりはかなり難しい時代である。
当時テキストサイトでやっていた「面白いこと」は、今では全部YouTubeで動画でやっている。
僕が中高生の頃に熱心に読んでいたサイトはほとんどすべてが閉鎖されてしまった。
「ちみどろあんこくちたい」「風は風雲は雲」「VULTURE`S HEAVEN(ばるへぶ)」......今どきの大学生なんかは何言ってるんだかさっぱりわからないだろうけど。
そのほとんどが更新が停止したりいつの間にか消えてしまった。


昔のインターネットは、主に個人サイトや掲示板、せいぜい2ちゃんねるくらいだった。少しあとになってブログが流行ったが、これもややハードルの高かった「個人サイト」の開設を簡易化したもので、大きな意味でインターネット上の交流は、まだまだ狭い世界だった。
喩えるなら、みんなそれぞれの家に行ったり来たりしつつ、誰か知らない人と話したかったら、適当に飲み屋に行って知らん人とその場限りの話をしているような。
それが、今は、SNSが乱立したことで、なんだかとにかくだだっ広いフリースペースの中で交流しているような世界になった。みんな相手の顔を見たり見なかったり、聞いてるふりをしたり聞かなかったふりをして気を使って生きている。
別にどちらがいいって話ではないけれど。
そうした時代の変遷の中で、更新が完全に止まり、「ネット廃墟」のようになったサイトも無数に生まれた。あるいは記憶の中にしかない個人の記録も。
そして、僕が思うに、そこに魔が宿る余地がある。
フルHDや4Kの映像が当たり前の時代には「VHS」の持つゆらぎや物質性、古さは異物として恐怖表現の手法たりうる。そこには「リアリティ」が宿るからである。
SNSで消費される日常の文章未満の文章たちが当たり前の時代では、個人が手間暇かけて書いて誰に読まれるでもなかったテキストサイトやブログの文章には、個人の肉声に近い感触があり、どこか不気味である。
90年代から始まった「Jホラー」と呼ばれる作品群は、ファウンド・フッテージ形式の『邪願霊』と、実話怪談フォーマットの『ほんとにあった怖い話』を始祖としている通り、「本当らしさ」=「リアリティ」こそが核にあった。
日常に根ざしたシークエンスや設定(映画の撮影所のバックステージものや、呪いのVHSテープの都市伝説など)、そしてリアリティのある心霊表現さえあれば、「ほんとにあった」話を元にしているていがなくても成立することも発見されていった。(『女優霊』『リング』『降霊』『呪怨』など)
つまり、僕なりの考え方で言えば、Jホラーとは、幽霊表現の「見せ方」の刷新ではなく、「リアリティ」に関する表現の刷新だったのだと思う。
だから、昨今のテレビ・YouTube、書籍を中心とした「フェイク・ドキュメント」あるいは「フェイク・ドキュメンタリー」の流行は、今一度リアリティの刷新を図っている点こそが重要なのではないかと考えている。
例えば「フェイクドキュメンタリーQ」の「ラスト・カウントダウン」では、一昔前の記録媒体にあった独特の質感。チープであったり得体のしれなさであったり不明瞭だったりといった、得体のしれなさを醸し出す映像が取り上げられている。
フェイクドキュメンタリーQ『ラスト・カウントダウン - Last Countdown』
https://youtu.be/W6ky-QgNiiM
ガラケーで撮られた荒い画質の短い映像(当時は何十分も連続で高画質の動画は撮れなかった)、素人が作ったVHS、8ミリフィルム映画、およそ聞いたことのない業者が作ったヒーリングDVD、深夜放送のテレビ......。
あるいは、スーパーファミコンとか初代のプレイステーションとか、まだそこまでお金をかけずに作れた時代の、玉石混交なゲームでも似たような感触があった。
ちょっと際どい言い方をすれば「事故る」(狂気の作り手の作品に触れる)可能性を秘めていた。その感覚である。
有名なゲーム「手紙」や、メモリーカードの「身」の話なんか、まさにこういう「事故る」感覚がもたらす怖さなのではないか。


映画では、残念ながらこの「事故る」感覚は早々表現できない。
すでにパッケージングされて劇場でかかっている時点で、誰の目も通らずに出てきたていにはできないからである。
近いものだと『レイク・マンゴー』は限りなく事故っぽい。でもやっぱりまぁある程度映画でもある。
配信映画では、『コリアタウン殺人事件』のような試みもできるが、劇場公開映画では難しい。


故に、今のところホラー映画では、まだフェイク・ドキュメント作品が書籍でもたらしたような「リアリティの刷新」に近い表現は、まだ発見されきっていない。
比較的新しい例では『呪詛』になるが、リアリティという点でいうと疑問がある。面白いホラー映画ではあるが、ここで考える意味でのリアリティの刷新はなく、あくまで既存のPOVホラーの想像力の範疇なのではないか。
『呪詛』が話題になった要因は寧ろ、「フェイク・ドキュメント」系の作品によくみられる「自己責任系怪談」的なオチを、映像作品の中でやった(それもNetflix配信作品で)という点に集約されると思う。
ただ、話がまた少しズレるが、昨今流行りのモキュメンタリー作品の問題として、この「自己責任系」の手法を多用しすぎている節がある。
「実はこの話を通してあなたを呪おうとしていました」というお話は、古くは童謡「さっちゃん」の話だとか、「メリーさん」の話のバリエーションで、それをいかに読者側に体感させるかが腕の見せ所になる。
もちろんそれでもなお効果をあげていて怖いからこそ、『かわいそ笑』にしろ『近畿地方』にしろ評価されているわけだけど、多分そろそろお客さん側も慣れてくる頃である。
個別で見ると、「自己責任系」と雑にくくってよい程同じことをしているわけではない。
勝手に加害者側に加担させられていることがわかっていく仕掛けであったり、それまで視えなかったものが視えるようになる(気がする)暗示であったり、現実と地続きであることが示されたり。まぁ様々である。
(ちなみに映画でも既に日本で安里麻里監督『ゴメンナサイ』がほぼ『呪詛』と同様の仕掛けをしておりこちらの方が早かったりもする)

しかし、徐々に慣れてくるのも事実である。
モキュメンタリーと「自己責任」は非常に相性がいい。
無関係な文章の羅列のようで、実は一定の意味があった、というストーリーテリング上の構造から、「これらは意図をもって読者に提示されている」と開示するラストは自然な流れとして作りやすいし、ホラー的な恐怖や謎解きの面白さ、さらに「考察系」的な面白さも付与できる。
他人事のような気持ちで読んでいたら、リアリティのある記述から、どんどん現実世界と作品世界の境界線が曖昧になって、最後には受け手側が巻き込まれる。受け手は欠落した情報のあちこちから恐怖を喚起され、考察を促されることで徐々に恐怖を増幅させていく。ほとんどそこまでセットのジャンル構造といっていい。
そんな中、逃げ場のない恐怖を提示するなら「自己責任」的なラストが一番決まりやすい。
しかしまぁ、今はまだ全然いいけど、今後のこととして経年劣化の可能性はあると思う。
で、曲がりなりにもホラー映画監督の端くれとして、こうした「自己責任」的な語りではなく、同時にモキュメンタリーホラーの持つリアリティや「事故」感、そういう恐怖演出をこそ考えたいと思っている。
感覚的なレベルで、一番それに近い表現をやった直近の例は、ホラーじゃないけど『aftersun/アフターサン』だったのではないか?という気がしてい
る。

この映画では「記録と記憶の間にいる魔」が描かれている、という感触があった。
物語として観客に「記憶」を植え付け、「記録」を通して思い出させる。
これをホラー映画としてやれないだろうか?
と、そんなことを今は考えている。
特に結論はない。
僕は本当に怖い映像表現をいつもずっと探している。
そのヒント探しの、この文章はひとつなんだと思ってほしい。
2024.01.23 近藤亮太
近藤亮太
1988年6月28日生まれ。
2017年、映画美学校フィクションコース高等科修了。
2018年、『霊的ボリシェヴィキ』(高橋洋監督)助監督として参加。
2020年、『呪怨呪いの家』(三宅唱監督/Netflix)助監督として参加。
2021年、KADOKAWA主催「日本ホラー映画大賞」で、
監督作『その音がきこえたら』がMOVIE WALKER PRESS賞を受賞。
2022年、「ミッシング・チャイルド・ビデオテープ」が
KADOKAWA主催「第2回日本ホラー映画大賞」で大賞受賞。
2025年商業デビュー作となる「ミッシング・チャイルド・ビデオテープ」が公開予定。
企画・編集・サムネイル作成=比嘉光太郎
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
