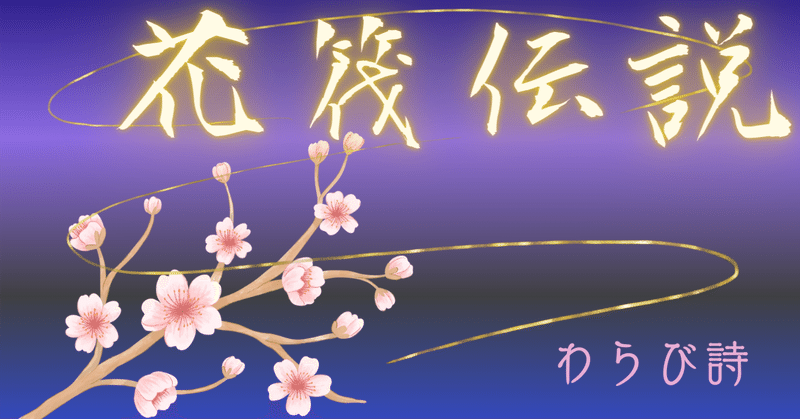
【掌編小説】花筏伝説
細い川に寄り添うように、蕾のままの桜が一本立っている。それ以外に見えるのは、どこまでも続くかのような若菜色の草原と代わり映えのしない暗い空。
空はいつでも紺碧に染まっている。時々乳白色の霞が空の端に浮かぶものの、明かりを感じるのはそれだけ。光の粒さえ見せること無く、太陽は去ってしまう。
桜は、この世にいるのは自分一人だけだと思っていた。
そんなある日のこと、桜の前に金色に輝く神々しい龍が降り立った。立派な髭が夜風になびいている。鋭い牙と爪は夏雲のように白く、瞳はエメラルドのようだ。
龍は威厳のある凛とした声で尋ねた。
――これは見事な桜だ。お主、名はなんと言う?
桜がざわめいた。話をするのは数百年ぶりだったので、咄嗟に言葉が出てこなかった。が、龍は急かすこと無く言葉を待った。桜は動揺しながらも、なんとか言葉を紡いだ。
――わ、私に名はありません。あなたのお名前は?
――余にも名はない。ただの龍だ。
――では私もただの桜です。
龍は声を押し殺して笑った。笑っているだけなのにとてつもない迫力がある。桜は声を震わせながら、ずっと知りたかったことを聞いた。
――まだこの世界に生き物はいるのですか?
――いるとも。だが、ここには来られぬ。
――それは、何故でしょうか。
――皆、下界にいるからだ。
――ですが、昔は鳥たちがよく遊びに来てくれたのですよ。
――お主は知らないのだな。この空に浮く島は、上へ上へと向かっておる。もう、鳥でも来られぬほどの高さだ。それに、風まかせに世界中の空を移動し続けているのだ。余でさえ、この島を見つけたのは数百年ぶりのことだ。
桜は、そうだったのですね、と沈んだ様子で呟いた。
独りぼっちの桜を憐れんだ龍は、不思議な力で黄金の鱗を一片取り、桜の花に乗せた。
――これがあれば、お主の居場所が分かる。無くさないように持っておれ。
花を三分咲きにした桜は、お礼に花びらを一片差し出した。龍は自分の鱗が無くなった所に桜の花びらをつけた。その輝きの前では、一片の花びらなど光に掻き消されてしまう。しかし、龍は満足気に頷いた。
――土産話を持って来よう。しばし待て。
桜がお礼を言うよりも早く、龍は飛び立ち宵闇の彼方へ消えて行った。力強い一筋の光は、何日も何日も残っていた。それを見た桜は、胸に迫る何かに気付いたが、その正体は分からなかった。
それからどれくらい経ったのか。あの光の筋は、ずいぶん前に空の中にとけてしまった。桜は乳白色の霞や暗い川面に映る星を見ては、繰り返し黄金の龍を想った。
――今日こそ来てくれるだろうか。
もう忘れられてしまったかもしれないと思い始めた時、龍が姿を見せた。あの日と同じように、深い藍色の空に光を散らしながら飛ぶ姿は、全ての願いを叶える流れ星のようだった。
――約束通り、土産話を持って来たぞ。
桜は五分咲きの花を更に開き、龍の言葉を待った。
――雪山に住んでいる小人の話をしよう。その小人は雪に畝を立てるのだ。
――雪に? 何かを育てているのですか?
龍はゆっくり頷いた。
――雪の結晶を育てている。小人が育てた雪の結晶はとけること無く、雪で出来た宝石として、世界中で愛されているのだ。
――まあ、それはとても綺麗なのでしょうね。見てみたい。
――見に行けば良いではないか。
桜はあまりにも驚いて言葉が見つからなかった。島から出るなど、考えたことも無い。
お互い言葉を交わさないまま時が流れた。龍は座って休んでいたが、やはり桜を置いて飛び立った。
次は、もっと面白い土産話を持って来よう、と言葉を残して。
龍が飛び去ったあと、桜はもう一度考えてみた。
――ここから出る? 木の私が、どうやって?
独りぼっちで考えても、答えは出なかった。そして何日かそれとも何週間かが過ぎ、また龍が現れた。
――今日の話は面白いぞ。浮かぶ古城に住む、三面鏡の話だ。
――三面鏡? それは生きているのですか?
――生きているとも。三面鏡は新しい主をずっと待ち続けている。しかし、城へと伸びるはしごが壊れたまま直されていないのだ。
――まぁ。どなたか直せる方はいないのですか?
――そうだな。お主が適任だと思うぞ。その立派な枝を伸ばせば、たくさんの人が古城に足を運べるようになるだろう。
桜はまた黙ってしまった。龍は猫のように丸くなり、少しすると寝息をたて始めた。
――私がはしごに……。
浮かぶ古城にはしごを架ける自分を想像し胸がときめいた。けれども、ここから出る方法は思い付かない。
それからも龍はたくさんの土産話を持って来た。炎で出来た花、石から生まれた動物、海底にかかる虹。
この島を目指して何度も飛び立つ、かつての友である鳥たちの話も聞いた。
桜は、日に日にこの島を出たいと思うようになった。しかし、根を張ったこの体をどう動かせと言うのだろう。花は開いて行くけれど、どうにも出来ない根が桜を縛っていた。
毎日のように紺碧の空を見上げ考えたが、やはり答えは出ない。
――まだここに居るか?
また訪れた龍は、地面に降り立つやいなや、体を丸め少し荒い息を吐いた。そんなことは今まで一度も無かった。いつだって威厳があり、堂々としていたというのに……。
――体調が悪いのですか?
――あぁ。余に残された時間はごく僅かだ。眠くて眠くて仕方がない。
――それは……。
――最後にもう一度聞くが、ここから出ないのか?
――私は……ここから出られないのです。
――そんなはずは無い。余は不可能なことは言わない。
――……。
いくら龍と言えど、大木を引き抜き、そのまま新しい土地に植えるなど出来るはずが無い。
――私の為の場所は、下界には残っていないでしょう。私は下界から離れ過ぎた。鳥たちもいずれ私のことを忘れます。私はこのまま、目的地も無い空の旅を続けるのです。
星降る夜、あれは龍の光の粒かしら、と待ち焦がれた日々。久しく開かなかった花を咲かせた、黄金の輝きを持つ龍。
その輝きが今失われようとしている。弱々しい龍の姿を見ていると、どうしようもない不安が込み上げて来た。
龍は黄土色の絵の具を塗ったような姿になりつつあった。初めて逢った日に渡した一片の花びらが、風に煽られ龍の体から離れていく。ひらひらと舞って、川面に落ちた。
下流へ流されて行くそれを見て、桜は全ての花を散らした。
――もう、独りでは生きていけません。ここから連れ去ってください!
――その言葉をずっと待っていた、桜よ!
カッと目を見開いた龍の体が、金色の花吹雪に変わった。……花吹雪では無い。鱗だ。黄金に輝く龍の鱗と、桜の花びらが川を伝ってぐんぐん進んで行く。島の終わりに差し掛かっても、その勢いは止まらない。
世界の端っこで、光り輝く滝が流れた。それを見たのは鳥たちだけ。
金色の中に幾筋もの桜色の光が流れている。光のしぶきを浴びながら鳥たちが叫んだ。
――桜様、やっとお会いできましたね!
鳥たちは溢れんばかりの喜びを歌い、この世の全ての生き物を目覚めさせた。
世界中の川に花びらと鱗で出来た花筏が流れていく。
――どうだ? 下界も良いものだろう。
――えぇ、とても美しく暖かいのですね。
――……わせだな。
――え?
龍の押し殺した笑い声を聞いたのは桜だけだった。
花筏を見た人々は言った。
「これは、竜神様の鱗では無いか!」
「では、この花びらが片思いのお相手『さくら』様か?」
「バカ! それには気づかぬふりをするって話しただろう! ご友人だ、ご友人!」
「と、とにかく掬え! 一片残らず掬って埋めるんだ! 急げ!」
掬われた花びらと鱗は、人々によってあちこちに埋められ、やがて可愛らしい小さな芽を出した。
それから数十年後、立派に成長した桜の木は金色の花を咲かせた。桜は世界中の人々に親しまれ、春の風物詩となった花筏には、様々な伝説が生まれた。
ある村では、竜神を偲んだ桜の涙が花筏になる、と伝えられた。
ある町では、花筏に乗って桜の精が竜神に会いに行く、と伝えられた。
真実は動物たちだけが知っている。
――今年も幸せそうでなによりだなぁ。
また今年も、穏やかに緩やかに……花筏は流れていく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
