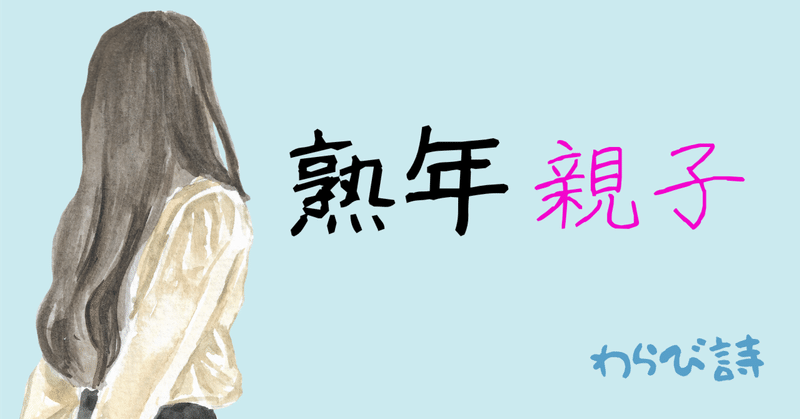
【掌編小説】熟年親子
子どもの頃から、私は父が嫌いだ。
歩幅が広くて一緒に歩くのが大変だった。手を繋いで歩くと私だけ小走りになるし、手を繋がないで歩くと見失ってしまう。
気遣いの出来ない父はいつもの呆れ顔で、私を見つけるなり
「ちゃんとついて来なきゃダメだろ」
などと的外れな注意をする。
もっとゆっくり歩いてくれたら、はぐれたりしないのに。なんて、何度思ったことだろう。
幼い頃に母が死に、男手一つで育ててくれた恩はもちろん感じている。けれど、好き嫌いの感情は頭で決められるものではない。
心が勝手に嫌いだと叫ぶのだ。好きになれるものならなっている。むしろ、好きになりたい。薄情な娘にはなりたくない。でも、無理だった。
心の中にいる黒い自分は、良い娘になりたかった私を嘲笑う。
――良い子ぶったって無駄。嫌いでしょう? だってあんな事を言われたんだから。
もう一人の自分が、何度も何度もあの言葉をリフレインさせる。
そう。とてもひどい事を言ったのだ、父は。
父は今も昔も靴屋で働いている。
あの日、父は店で嫌なことでもあったのか、お酒を呑んだ。強くもないのにどんどん缶を空け、瓶を空け、狭い居間のちゃぶ台に突っ伏して寝てしまった。古い扇風機の音に混じった父の声が、むにゃむにゃ唸っていた。
小学校に上がったばかりの健気な私は、父の背中に自分が使っていた犬柄のタオルケットをかけた。そんないじらしい私に寝ぼけた父は言った。家族間で一番と言っても良いくらいの禁句を言ったのだ!
「息子だったら良かったなぁ」
幼い私は傷ついて、枕に顔を押し付けて泣いた。
私はいらないんだ。お父さんは男の子が欲しかったんだ、と辛い現実を突きつけられた。
どこからか聞こえた犬の遠吠えだけが、私の心を慰めてくれた。
けれども私は父に縋りついた。たった二人の家族だ。父に見捨てられたら生きていけないと知っていたから、縋るしかなかった。
写真でしか知らない母の真似をして伸ばしていた長い髪を切り、ズボンをはき、クラスの目立つ男子の真似をした。どちらかと言えば母親似の私は、ロングヘアの自分に母の面影を探そうとしていたのだが、そんな気持ちは宇宙の彼方に消えた。
必死で男の子になろうと努力した。息子にならなければ父に捨てられる! と心配して。あの頃は人生で一番がむしゃらに生きた時期だった。今思えば、下品なことを言えば良いと勘違いしていたような気がするが。
父はそんな私を怪訝な顔で見た。
「最近どうしたんだ? 変な物でも食ったか?」
フフッと鼻で嘲笑われて、ぶわっと頭に血が上った。
「だってお父さんが『息子が良かった』って言ったんじゃん!」
つい叫んでしまった。
父は自分の発言を覚えていなかった上に、そんなこと言ってない、と否定した。それも堂々と。私は何も言い返せず、恥ずかしくなってまた部屋に籠り泣いた。慰めてくれたのは、やっぱり犬の遠吠えだけ。
結局髪は伸ばし直した。母親似の私にショートは似合わなかったし。
あの一連の出来事が、父を嫌うようになった原因だ。
中学生になる頃には、冷めきってしまった熟年夫婦のようになっていた。熟年親子だ。熟年は父だけだけど。
会話は必要最低限、学校行事も必要最低限しか来ないのが当たり前になった。来るのは三者面談くらいだ。
三者面談で、初めて父を見た先生や友達は
「ミステリアスだね」
と言った。
服に無頓着な父はどこへ行くにも黒ばかり着ていたから、そんな感想が出たのだろう。どこがミステリアス? と問い詰めたい。確かに何を考えているか、娘の私にも全く分からないが、ミステリアスなんて言葉が似合わないことは分かる。不気味なだけだ。
黒ばかり着て、死神にでもなりたいのだろうか。
そんな私たちの関係は互いを空気のように思いながら続いた。
私の髪が母のように腰まで伸びても、制服が新しくなっても、彼氏が家に遊びに来ても、父は無関心だった。
結局、父の本心はあの一言に集約されているのだろう。
私が男だったらもっと仲良く……――恋人を紹介したり、一緒にゲームをしたり、そんな普通のことが出来たんだろうか。
なんてウジウジしている暇はない!
私はついに、あの無神経な父とオサラバすることを決めたのだから。
大学を卒業する私は、家を出る為必死で就活をした。なるべく遠いところ。でも友達とも会える程度の距離で見つけた就職先は、何の因果か父と同じ靴を取り扱う会社だった。
既に借りた新しい我が家は、実家から電車で三時間。しかも乗り換えること四回! 不便過ぎて帰る気にならないし、父も来る気にならないだろう。でも都心までは一本で行けるのだ。我ながら素晴らしい場所に就職が決まったと思う。
卒業式を終えた私は、実家に帰ることなくアパートに帰る。
人生、最良の日!
晴れ着を身にまとい、踊るようにホームを歩く。こんなに晴れやかな卒業式は、生まれて初めてだ。
乗り慣れない路線の電車がキラキラと輝いて見える。
窓を流れる桜並木が、これから始まる自由な生活を祝福しているかのよう。
私はスキップをなんとか堪えながら、改札を出た。でも家が近づくにつれ、やっぱり我慢できずスキップをしてしまった。綺麗に巻いた髪が弾むように揺れる。
我が家に着く頃には、スキップどころか駆け足になっていた。そのまま勢いよくドアを開けると、蝶番が短い悲鳴を上げた。
「たっだいまー!……あれ?」
ドアについたポストに古びた茶封筒が入っている。
大分年季が入っていた。タイムカプセルから出したようなそれには、柔らかい筆跡で私の名前が書いてあった。
切手も消印も無い封筒。直接このポストに入れたのだろう。
反射的に父の顔が浮かび、自分の口角が下がるのを感じた。折角の晴れ晴れとした気持ちが父のせいで台無しだ。清々しかった春の空気も、部屋に入ったとたんどんよりと埃っぽく感じる。
封筒は置いといて、一先ず袴を脱ぎ丁寧に畳んだ。レンタルだから、汚れないようにしなければならないし。
来週から始まる新人研修の予習や準備をし、長風呂につかり、夜食のカップ麺を食べながらテレビを見た。
再度封筒に触れたのは日付が変わり、空が白むころになってからだった。
「下らない内容だったら捨ててやろ」
でも手紙は父からではなく、母からだった。字を見た時点で気づけば良かった。角張った父の字とは対照的な、小川のように優しい線が古びた紙に並んでいる。
意外な事に父は、母が託した手紙を二十年近く大事に保管していたのだ。
未開封だったし、内容を知らずにポストに入れたのだろう。知っていたら絶対に渡さなかったはずだ。
だって、一人前になった私への言葉以外に、父の秘密が書かれていたから。
娘は可愛いけど、いつか家を出て行くんだ。息子だったらずっと一緒に暮らせたかもしれないのに。
こんな幸が薄いオヤジが学校に行ったら、からかわれるかもしれないよね。カツラと帽子とメガネを付ければ俺だってバレない? むしろ悪い虫に舐められないように、黒い服着た方が良いかな。
――と、変装姿を見た母が大笑いしたエピソードなどが書かれていたけど、その全てが別の誰か、知らない人のようで、上手く想像できなかった。
『あの人は大切なものを洋服箪笥の一番下に入れるくせがあります。きっと今頃、一番下の抽斗は二人の思い出でいっぱいになっているはずです』
そんな訳ないじゃん。
でも、もしかしたら……と期待がむくむく湧きあがったのも事実だった。
今日は暇だし、一眠りしたら運動がてら散歩に行きたくなった。
散歩したら、電車に乗って景色を楽しみたくなった。
電車に乗ったら、馴染みの肉屋のコロッケが食べたくなった。
コロッケを食べ歩きしたら、休憩したくなった。
休憩するなら、実家が一番気を使わなくて良い。今なら丁度、父も仕事に行っていないし。
ついでに、あの手紙の真相でも調べてみるか。暇潰しに。
なんて、言い訳をしつつあっという間に帰省した。四回の乗り換えの煩わしさより、真実が気になってしまう。
ほとんど入ったことが無い父の部屋には、たくさんの靴箱が積んであった。靴好きだとは思っていたが、ここまでか……と若干引いた。
靴の山の隣に大きくて頑丈な木の箪笥がある。
私はその一番下に手をかけた。滲む手汗は、きっと歩いたからだ。
「……。へぇ~」
低学年の時プレゼントした画用紙で作った靴、父の似顔絵から始まり、盗撮のような大学の入学式の写真まであった。
「ずっと来てたんかーい。…………」
全く素直じゃ無いんだから。行事に来たいなら来たいって言えば良かったのに。素直に言ってくれたらピースの一つや二つ……したかどうかは分からないけど、もうちょっとマシな写真にはなっただろうに。
「ストーカーみたいじゃん」
と突っ込みながら抽斗を閉めた。
さて、いつバラしてやろうかな。初めて出来た母との隠し事にわくわくする。
とりあえず今日はこのまま帰ろう。
そう思った時、玄関口に父の革靴が置いてあるのが目に入った。会わなかったけど、きっと昨日の卒業式で履いたのだろう。
私は靴箱の引き戸を開けて、靴磨きセットを取った。幼い頃父に教わった磨き方でその革靴を磨く。
少しも手間取ることなく終えられたのは、毎年父の誕生日に靴を磨いていたからだ。
父は気づいて無いだろうけど、私なりの誕生日プレゼントのつもりだった。
息子が欲しかったと言われても、空気のような存在になっても靴磨きをやめなかったのは、父が同じことをしてくれたから。
水たまりで付けた汚れも、自転車のスタンドで付けた傷も、魔法でも使ったかのように、気づいたら無くなっていた。
学生時代使っていたローファーは一度も磨いて無いけど、いつもピカピカだったし、成人式と卒業式で履いた草履は、サンタさんからのプレゼントのように部屋に置いてあった。その横に置かれていた封筒の中身を使って、振袖と袴をレンタルしたのだ。
結局のところ、私は父を嫌いになりきれなかった。もう一人の黒い自分も所詮は自分でしかない。黒い自分も心の底から父を嫌いにはならなかった。この上ないほど恥ずかしい事実だけど、好きの裏返しだったのだろう。だって、好き嫌いの感情は頭で決められるものではないのだから。
靴磨きを終えた私は、全てを元の位置に戻し新しい家に帰った。その日の夜遅く、
「家、来たの?」
と、父から電話がきて動悸がした。
「な、なんで気づいたの?」
「分かるよ。靴磨いただろ。同業者として言うけど、外側ばっかり念入りで内側がおろそかになる癖あるから直した方が良いぞ」
「……」
今までもずっと気づかれていたのだ。気づかれてないと思っていただけに、恥ずかしくて悔しくて今すぐ電話を切りたくなった。そもそもお礼の一つも言えないのか? これだからこのオヤジは……などと心の中で悪態をつく。
父はそんな事よりも、母の手紙の内容に関心があるようだった。
「何て書いてあった?」
「…………」
「もしもし?」
私だってやられてばかりじゃない。今の私には最強の切り札がある。お母さん、ありがとう。ありがたく使わせて貰います。
「一番下の抽斗のこと教えてくれたよ」
今度はお父さんが黙る番だった。
私は良い気分になって不敵な笑い声を漏らしながら電話を切った。
「さーて、寝よ寝よ」
初めての社会人生活がもうすぐ始まる。お父さんをぎゃふんと言わせられたし、幸先が良いぞ。
「素敵な人いるかなぁ」
出来れば、婿養子になってくれる人が良いな。なんて考えながら、気持ちよく眠りについた。
どこからか聞こえた犬の遠吠えは、悔しがっている誰かさんを慰めているのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
