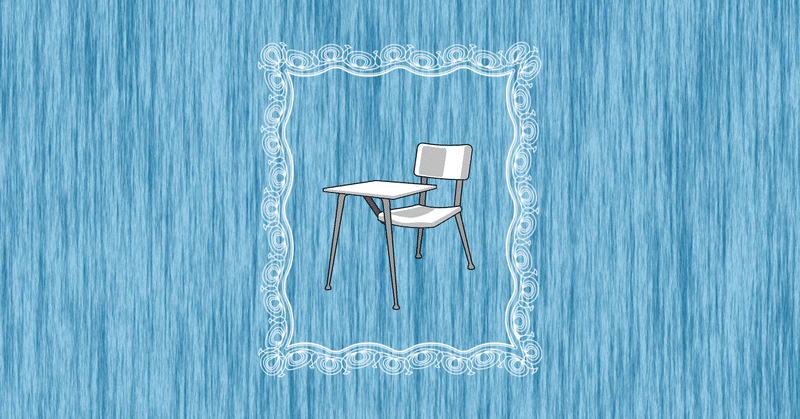
Son alibi
小学校のころ、僕たちの教室には机がひとつ多かった。
学年のどの教室にもその机があった。その机があることで、グループ分けをすると2人のグループが18、3人のグループが12、4人のグループが9、6人のグループが6個できた。
僕たちはそのころ、約数とか素因数分解なんて全く知らなかったけれど、その机があると便利だなと思っていた。実際の人数は、ひとり余ったり足りなかったりでどこかの班に合流するのだけれど、僕たちはいつもその机に座るはずだった子は普段はいなくても仲間だと思っていた。
小学校に入って間もないある日、校長先生が集会で言った。
「みなさんと同じ日にこの山谷小に入学した子がいます。病気で入学式に出られませんでした。先生たちは考えました。その子にも、一緒に学校に来ている仲間だと思ってほしいし、どのクラスの子にもそう思ってほしい。だから教室にはいつも、机がひとつ多いのです。先生たちはみなさんに、その机に座る子と仲間になって欲しいと思っています。友達になってくれるかな?」
みんな、ちょっと胸をどきどきさせながら「はーい」と言ったような気がする。
机の持ち主は女の子で、名前は「さえきみか」さんと言った。僕たちの学年には、だからさえきさんの名前を知らない人はいなかった。机はあったけれど、さすがに名簿に載るのは1クラスだけだったので、学年が上がるごとに、「今年はさえきさん2組だったね」「3組だったね」と言い合った。でも、やっぱりどのクラスにもさえきさんの机はあって、さえきさんはいるのだった。すべてのクラスに机を置いたのは、全員に当事者意識を持ってほしいという学校側の思惑があったからだと、後から親に聞いた。
郊外の公立の学校で、よけいな机はそうたくさんはなかったから、さえきさんの机は捨てられる寸前のような机が多かった。ガタガタしたり、傷があったりもしたけれど、掃除の時や給食のときにはみんなはいつも、その机をきれいに拭いたり、ていねいに扱った。杜撰な扱いをしたりわざと汚したりするような子はいなかった。
さえきさんは、街外れの大きな病院に入院していた。僕たちは時折、さえきさんに手紙を書いて先生から病院に届けてもらったりした。
卒業式では、お母さんが涙ながらに、みんなと卒業できて嬉しい、先生方と学校に本当に感謝していると挨拶した。先生と保護者のほとんどが泣いていた。
僕の進学した中学校は、近隣の小学校から生徒が集まるので、同じ小学校の子は少数派になった。さえきさんも、僕のほうの中学校だった。
中学校は、さすがに小学校の時のような配慮はしてくれなくなって、さえきさんの机は無くなってしまった。僕の小学校の保護者が問い合わせたら、学校に来ることができる状態になったら対応しますという返事だったそうだ。僕たちは、彼女の容体については何もわからなかった。ただ、山谷小では近年まれに見るくらいいじめがなかったけれど、中学に入るとそんなことは全然なくて、同じ小学校だった友達がいじめに悩むようになった。
さえきさんのことはすぐに噂になった。
「山谷小では35人クラスなのに机が36個あって、それは死んだ女の子の机だったんだって。机を撤去すると”出る”からそのままにするしかなかったんだって」といった怪談にされたりするのを聞くのは胸が痛んだ。最初はみんな否定していたけれど、否定するとまた何か尾ひれを付けて言われたりするので、そのうちみんな黙ってしまった。かばいたくても、僕たちがさえきさんのことを何も知らないのは事実だった。
中学生活は忙しくて、僕たちは次第にさえきさんのことを思い出さなくなった。クラス名簿に1名女子が多いことも、そのうちだれも何も言わなくなって、部活や受験に没頭するうち、僕たちは中学を卒業した。中学校で、さえきさんのお母さんの姿を見かけることはなかった。
さえきさんのことを思い出したのは、高校に入ってからだ。
高校の僕の教室には、小学校以来久しぶりに、机がひとつ多かったのだ。
ぼくは進学校ではない「そこそこ」の共学の学校に進んだ。兄が「まあまあ」の学校だったので、両親は僕が「そこそこ」でも入学しただけで満足のようで、助かった。
学校側からは、いつになるかはわからないけれど海外留学の子が帰ってくるので、机だけ置いているのだという説明があった。
当然、生徒たちは中学の時のような怪談まがいの噂をしたけれど、試験や模試や行事などで怒涛のように高校生活は流れた。
夏休み明けに登校すると「あの席」に女の子が座っていた。
本当に海外留学から帰ってきたのかな、と思った。誰かに言おうと思ったが、口にする前に誰もそのことを指摘しないことにも気づいた。
何かがおかしい。
彼女はそこにいるのに、でもクラスの誰一人話題にしないのは変だった。実際、ちらちらみている生徒もいなければ、話しかけもしないし、故意に無視しているような様子でもない。当然、教師も何も言わないままで、気を付けて聞いていたが点呼でも名前を呼ばれている様子がなかった。
これは、ひょっとするとあれだろうか。
いくら僕が鈍くても、僕だけが「見えている」可能性が否定できない。ただ「見えているのかいないのか」と、誰かに確認することもためらわれた。
三日ほど観察したが、やはり毎日彼女はそこにいた。席についた彼女はいつも黒板や教師やそれでなければ窓から遠くを見ていて、目が合うことはなかった。
ある日、小野くんちょっと、と担任から声をかけられた。
僕は「そこそこ」の学校で「そこそこ」真面目なので、提出物も単位も成績も「そこそこ」で教師に目をかけられたり目をつけられたりする生徒ではない。担任は、四十代くらいの女性教師で尾崎という名前だった。
「きみ、気づいてるよね」
ひとり残された教室でいきなり、尾崎先生は言った。
「気づいてる、って、何を、ですか」
僕は少し警戒してそう言った。
尾崎先生は、窓際の彼女の席を指さした。ちょっと予想はしていたけれど、僕は思わずごくりと唾をのんだ。彼女は「下校」したのか、席にはいない。
「いつから見えてる?」
さらに尾崎先生は言った。
「見えて、って。先生も見えるんですか」
「質問しているのは私です」
尾崎先生は冷静に言った。
「とにかく、見えているのか、いないのか、聞いているの」
「見えて、ます」
素直に、僕は答えた。
「そう。それなら、これから私がする話を聞いてくれないかな。そして納得出来たら、協力して欲しいことがあるんだけど」
「はあ」
話が見えずに、僕は尾崎先生が手で示した席に腰かけた。先生もその前に座る。二者面談のように向き合う形になった。
「小野くんは、山谷小出身だよね」
はい、と頷くと「佐伯美加さんを知ってる?」と、聞かれた。
「はい。知ってます。クラスにさえきさんの机がありました」
「うん。佐伯美加は、私の姉の子なの」
「そうだったんですか!」
僕は意外な接点に驚いた。
「あの席にいるのは、美加」
尾崎先生は少しためらいがちに、でもこの話の流れから恐らくそうなのだろうと思っていたことを言った。
「私の姉——つまり美加の母親だけど、小学校を卒業した時点では、もう美加は動くことはできなくて、進学は諦めた。小学校では子供たちと先生の協力で、まるで美加が学校に通っていたかのように良くしてもらったけど、これ以上は無理は言えない、と」
尾崎先生は、まるで同僚に話すように、僕に話した。
「だから中学に美加の居場所はなかったんだけど、そのころちょうど、美加の入院している大学病院で、メタバースの研究をしている教授が、美加の意識をメタに誘導する研究に協力してくれないか、と言ってきて」
腑に落ちない顔をしていたのだろう、はっとしたように尾崎先生はふと、相好を崩した。
「あ。ごめんなさいね。話が突飛すぎたよね。その教授は、美加のように身体が動かせない、意思を伝えられない人の脳に直接機器をつないで、アバターの姿で会話をする研究をしていたの。小野くんは『アバター』っていう映画、観たことある?」
何回か観たことがあります、と言うと、先生は頷いた。とてもからかっているとは思えない、真剣な表情だった。
「あんなふうにね、VRみたいな装置を付けるの。最先端と言えば聞こえはいいけど、言ってみれば人体実験。だけど姉は、もういろんなことに絶望していて、娘と話ができる可能性があるならと飛びついてしまった」
僕はなんと言えばいいかわからず、相槌すら打てずに黙っていた。
「世間にはとても公表できないけれど、とにかく美加と姉は、少しずつ会話ができるようになったの。姉は狂喜乱舞よ。もうずっとメタバースに入り浸って戻ってこない」
そう言って、尾崎先生はふと彼女の席に視線を飛ばし、そしてまた、僕に戻した。
「姉もVR機器を装着したまま、半分植物状態のようになってしまってる。昔で言うネットゲーム廃人みたい、と言ったらいいのかな。そんなことしてる間に姉の夫、つまり美加の父親は、外に女の人を作って出て行ってしまってね」
ひどいですね、と思わず口がすべった。
「ねえ。そうよね。酷い話。だから姉にとっては美加だけが心の支えなの。私と姉の両親は既に亡くなっているし、私もそんな親子を見ているのはとても辛くて」
尾崎先生の目が潤み、かすかに声が震えた。
「そんなとき、思いついたの。私の勤めている高校の、私のクラスになら、美加の席を作ってあげられるかもしれない、って。小学校の頃のようには行かないけど、校長や理事長に掛け合って、机を置くだけならってなんとか認めてもらって。生徒たちには嘘の理由を教えてしまって申し訳なかったけど、そうやって現実に美加を存在させることで、姉をこっちの世界に引き戻せたらと、思ったの。姉はあの頃、PTAなんかにも参加してて活き活きしていたから」
そこまで言って、ついに尾崎先生はポケットからハンカチを出した。意外なことにイルカのキャラクターのついたやたら可愛らしいハンカチだった。
「ごめんなさいね。それで、ええと、どこまで話したかな。そう、そうやってこのクラスに机を置いて。でも三日前、あの席に女の子が座っているのに気が付いた。まさか、と思った。誰か女子が悪ふざけでもしてるのかなと思ったりした。私自身、困惑していたところだった」
ようやく、僕のところに話が戻ってきたようで、僕は少し大きくうなずいた。
「小野くんが、ときどき美加の席をちらちら見ていることに気づいて。調査票確認したら山谷小で。それで、思い切って声をかけてみた。正直、すごく勇気が必要だった。でも、そうなんだね。本当に、見えているんだ――」
僕は、僕と同じように女の子が見えている人がいて安心した反面、やはり動揺もしていた。
「ということは、じゃあ、佐伯さんはもう――」
尾崎先生は、少しぼんやりとした顔を僕に向け、ハッとしたように首を振った。
「いえ。いえいえ、まだそうと決まったわけじゃないの。小野くんにこんな話、迷惑だったと思うけど、でも、小野くんは、あの子が小学校にいたことを知ってるじゃない?」
僕も少し、ぼんやりしてしまった。
あれは「いる」と言える状態だったのだろうか。
でも、「いる」といえば確かに「いた」。名簿に名前もあったし、席もあった。児童たちも、無邪気に「佐伯さん」をクラスの一員だと思っていた。
「はあ、まあ、いた――いました、ね」
僕は曖昧に言った。尾崎先生は頷いた。
「何度か試してみたんだけど、美加と話はできないの。そこに座っているのはわかるんだけど、コンタクトは取れない」
「僕もそうです。目があったことがないし」
「うん。でもきっと、小野くんのことは、美加、知ってると思うんだ。あの子、学校に入ったのが嬉しくて嬉しくて、毎日ベッドの上でランドセルを背負ってた。だんだんに身体が動かなくなっていって、それもできなくなっていったけど、毎年名簿が配られると、嬉しそうに友達の名前を繰り返し読んで、学年全員の名前を空で言えるほどだった。ビデオメッセージでクラスの紹介もしてくれていたでしょう。だから、小野くんのことは、きっと覚えていると思う」
「そう、ですか」
僕の方は、佐伯さんの顔は知らなかった。
今回、あの席に座っている佐伯さんのことも、僕は正直、凝視はできない。顔をまじまじと良く見たことはなかった。
「小野くんがこのクラスにいたことは偶然だったけど、もしかしたら美加も、知ってる子がいるから来てくれたのかもしれない。だから、だからね、無理は言えないんだけど、美加と話をしてみてくれないかな」
「ええっ」
さすがに驚いた。
尾崎先生の話からすると、彼女はいわゆる「霊魂」とか「生霊」などと言われる種類のものなのだと思う。そんな存在と、コンタクトを取ったことは今までかつてない。
「あれ?小野くんは、そういうの見える人じゃないの?」
違いますよ、と僕は両手を胸の前で振った。
「僕には無理ですよ。そんなに簡単に。先生も話せないのに」
僕は怖気ついていた。さすがに嫌だ。怖い。
「そう――そうか、ごめん。そうだよね」
尾崎先生は、ごめんね、無理言って。今の話は忘れてね、と言った。
「まあでも、美加のことは、そこにいることを許してあげて欲しい。私も、とにかく姉を現実世界に戻せるように、頑張ってみるから」
僕は、ただ頷いた。何といえばいいかわからなかった。
それから数日後、相変わらず佐伯さんは登校時間になると姿を現し、下校時間になると姿を消した。どうしても気になってしまって、よくそちらの方をみるようになり、僕は勇気を出して彼女の顔を良く見てみた。なかなか可愛らしい顔立ちをしていて、その辺を歩いていたら声をかけられるようなスレンダーな体つきをしていた。彼女はみんなが笑う時は笑い、体育にも参加していた。
「小野。お前最近よく、あの机のほうみてるよな」
昼休みに、クラスで一番仲のいい風間に言われた時は少しどきりとした。
「なんかあんの?気になんの?」
「そうかな。まあ、いつまで空いてるのかなって気にはなってるけど」
僕はそう言ってはぐらかした。
「確かに、いつになったら海外から帰って来るんだろうな」
風間はそう言ってパンに齧りついた。弁当を食べた後のおやつだ。
そうだよな、と言ってまたそっちをちらりと見たとき、彼女と目があった。初めてだった。思わず固まってしまった。
「ん?どうした」
風間に言われ、何でもないとごまかしたが、今、明らかに佐伯さんはこっちを見ていたと思う。
その時から、彼女と目が合う回数が増えた。
不思議なことに、普通に女子と目が合ったようにドキッとしたし、どうにも恥ずかしい感じがした。彼女のほうも表情が和らいでいき、そのうち、目が合ってにっこり笑うようになった。
そうなると、目が離せない。
僕は彼女が気になって仕方が無くなってしまった。
そんなある日の放課後、忘れ物をして誰もいなくなった教室に戻った。彼女は下校時刻になるとすぐいなくなるので、僕は誰かがそこにいるとは少しも思わずに、教室のドアを開けた。
彼女はいた。
席に座っていたのではなく、窓から外を見ていた。僕が教室のドアを開けたときに、振り向いた。まるで本当にそこにいるように、自然な感じだった。
「あ、まだ、帰らなかったんだ」
普通にクラスメートに話しかけるように、つい、そんなことを口走っていた。
「うん。小野くんは?忘れ物?」
初めて聞いた彼女の声は、涼やかできれいだった。とても自然に、とても普通に、彼女は昔からの幼馴染のように僕に話しかけた。
「あ。うん。宿題」
そう言って、机の中を探した。プリントはすぐに見つかって、僕はまた窓の方を見た。彼女は、窓から外を見ていた。僕はためらったけれど、これは千載一遇のチャンスなのかもしれない、と思った。
「あの」
すると、彼女はさらりとした髪を振って振り向いた。シャンプーのCMみたいだった。
「少し、話してもいいかな」
そういうと、彼女はにっこり微笑んで頷いた。浜辺美波みたいだ。
「うん。私も、小野くんと話してみたかった」
そう言って、自分の席に戻ると、椅子をひいて、隣の机の椅子もひいて、僕と彼女は向かい合って座った。微妙な距離。フルーツバスケットのように近くはないけれど、遠くもない。本当に実際にそこにいるかのように、彼女は実体をもってそこにいた。
「びっくりしてる?」
佐伯さんは僕の顔をからかうように見た。
「うん、さすがに。話してみたいって言ったけど、実際なんて言ったらいいかわからない」
「だよね」
彼女はそう言って、屈んで靴下を直した。
「私のこと、おばちゃんから聞いたでしょ」
顔を上げると、彼女はいきなりそういった。
「なんでも知ってるんだ」
そういうと、彼女はまた、微笑んだ。
「ねえ、私、どんなふうに見えてるの」
「どんなって――」
女優さんに似ていて可愛いなんて、うまいことは言えなかった。
「ふ、普通。すごく普通に見える。ほんとにそこにいるみたいだ」
「鏡に映らないの、私」
ごく当たり前のことを話すように彼女は言った。
「だから自分がどんなふうに見えてるか、わからない」
「あ。それなら」
僕は美術部で、絵には少しだけなら自信があった。
「ちょっと待ってて」
そういうと、ロッカーからいつも置いてあるスケッチブックを持ってきた。
「え。なになに。描いてくれるの?」
「あんまり上手くないけど」
そう言いながら、僕は彼女の絵を描いた。ほんの少し、美化した。
「えー、すごい!私、こんな風に見えるの?絵、上手だね、小野くん」
彼女は感激したように声を弾ませた。白黒のスケッチだったけど、色を載せたらもっとよくなる、と思ってもう一度彼女を見ると、なんとなく彼女には色がなかった。不思議だった。普通に見えるのに、着色しようと思うと何色にしていいかわからない。
とりあえず、出来上がったスケッチを彼女に向けて差し出した。
「うわぁ。嬉しい!嬉しいよ、小野くん」
彼女はスケッチブックを手に取ることはなく、のぞき込んではしゃいだ声をだした。
「たぶん、私の念力だな。今のこの姿、きっとこの世界のアバターだもん。ほんとの私は、立ち上がって歩いたことないから、脚もこんなに細くて、身体のあちこち、ちょっと形が変わっちゃったところもあるんだ。こんな風に見えて欲しい、っていう願いが、叶ったんだな」
そう言って、彼女は笑った。
絵を喜んでもらえて嬉しかった僕の顔が、少しこわばったと思う。
「あ。ごめん。でも同情なんてしないで。16年間、お母さんが一緒にいてくれたし、小学校はちゃんとみんなと通って、卒業した。私の自慢なんだ。メタでは沢山、本を読んだよ。ドラマとか映画とか、アニメも動画もいっぱい観た」
僕は、何と言っていいかわからなくて、言葉に詰まった。
「あのね。小野くん。私、キンプリの高橋くんが好きなの。小野くん、ちょっと似てるかも」
「マジ?そんなこと、一回も言われたことない」
「自信持っていいよ、小野くん。かっこいいよ」
面と向かってそんなこと、普通の女子は言わないな、と思わず苦笑した。きっと、浜辺美波に寄せて似顔絵を描いたお礼なのだろう。
「今の私、きっと狭間の世界にいるんだと思う」
「はざまの世界?」
「うん。この世でもあの世でもないところ。でも私、ひとつだけ気がかりがあってね。お母さんを、こんなにお世話になったお母さんを、残していかなきゃならないじゃない?」
そう言って、彼女は笑ったのだが、声がちょっと震えていた。
「だから私、学校に元気に通っているアリバイを作りたかったの」
「アリバイ?」
「うん。アリバイ。知ってる?」
「事件の犯人が、犯行現場にいなかったことを証明するってことでしょ」
「お母さん、私と話せるようになってからは、ずっと私といっしょにいたがって。でもそれは、私の脳にも、お母さんの脳にも、かなりの負荷がかかってしまうんだって。でもこの前メタにいる時、ついにお母さんがね、もう現実には戻らないって。脳に負担がかかって死ぬなら本望って。それで私、お母さんに学校に行けることになった、って嘘ついちゃって。メタの中で学校に行けることになったんだ、って。それで、教授に頼んで、学校に行くと設定した時間はお母さん側のスイッチを切ってもらうようにしたんだ」
僕はすっかり呆けたようになって彼女の話を聞いていたと思う。
「でもそしたら、どうなったと思う?私、本当に学校に来れちゃったの。おばちゃんが机を用意してくれたからだと思うんだけど。最初はびっくりしちゃって、茫然としてたんだけど、誰にも見えてないみたいだし、わーい学校通っちゃえ!って。この姿ならすごく自由に身体が動くし、本当に楽しかった!体育も初めてやったよ。友達には私は見えないけど、でも一緒にいるだけで、嬉しくて。小学校の時は、みんなは良くしてくれたけど、本当には学校に行けなかったじゃない?今私の姿が見えないことなんてたいしたことじゃない、って思った。しかも、小野くんがいたし。小野くん、私のこと見えてくれないかなって思ってたら、本当に見えてくれたし」
流ちょうに言葉を紡いでいた佐伯さんが、ふと、言葉を止めた。
「だけど、たぶん、たぶんだけど」
そう言って、そっと、はにかむように佐伯さんは僕を見た。
「私がこんな風に学校に来てる、ってことは、私、だいぶ、肉体から離れてしまってるのかもしれないない。メタにいると、脳が別の場所にいるようなものだから、痛みを感じないの。痛みも苦しみもない。でも感覚がないのは、私にはとっても幸せなの。でもそうやってずっと感覚をマヒさせた状態にしておくと、どうしても身体の機能が低下したり、脳が委縮したりしてくる副作用があるって。だからきっと、私、ゆるやかにあっちの世界に逝こうとしてるのかな、って思うんだ」
「佐伯さん……」
僕は初めて、彼女の名前を呼んだ。
「わ!今、私のこと、呼んでくれた?」
佐伯さんは嬉しそうに満面の笑顔になった。
「面と向かって友達に名前を呼ばれたの、初めて!」
僕は面と向かって佐伯さんにそんなことを言われて、そんな気はまるでなかったのに、なぜか涙が出てしまった。
「え。ちょっと、小野くん。泣かないで。私、嬉しいんだよ。嬉しい時は、笑おう。私、誰かが笑ってるの見るのが大好き。お笑いも、だから大好きなんだよ。小野くん、オードリーの若林にも似てるよ」
「いやそれ、ドラマの話でしょ。高橋海斗に似てるのはあれの喋り方だけってこと?」
涙を親指で振り切り思わず苦笑いすると、佐伯さんは喜んだ。
「小野くんも『だが、情熱はある』観てたの?嬉しい~!」
目の前の佐伯さんは、本当にクラスにいる女子のひとりのように自然だった。
『だが、情熱はある』というテレビドラマは親のサブスクで観た。何者かになろうともがくふたりの主人公は現役の芸人さんで、彼らの高校時代の話が面白かった。主役の1人がオードリーの若林を演じる高橋海斗で、顔は全然似てないのに喋り方が似ていた。最初は違和感しかなかったのに、気づいたら夢中で観ていたのだった。自分もまた、何者かになりたくて悩んでいたからかもしれない。
「あのね。だから、ちょっと重い話につき合わせちゃって悪いんだけど、わたしのアリバイの証人になって欲しいんだ。佐伯美加は、ちゃんと学校に居ましたよ、ってお母さんに言って欲しい」
佐伯さんの言葉に、ハッとして顔を上げる。
「佐伯さんの、お母さんに?」
「うん。こんなこと頼めるの、まさに!文字通り!きみしかいない!」
そう言って佐伯さんはコナンくんみたいに僕を指さした。
「でもこれって、アリバイって言わないんじゃないかな。犯罪とか、悪いことしてるときに使う言葉でしょう。きみは全然、悪いことしてないじゃないか」
そういうと、ふっと佐伯さんの顔が陰った。
「アリバイって、ラテン語でalibiって言うの。他の場所にっていう意味なんだって」
「他の、場所に」
「うん。だから、間違ってないでしょ。私、本当に別の場所にいたんだもん。でも悪いことっていえば、悪いことしてる。お母さんに嘘ついてる」
「でも・・・」
「仕方ない?そうかも。そうでもしないとお母さん、悲しいことをしちゃいそう。だから、私どうしても、学校にいる証拠をお母さんに見せたかったんだ。ねえ、これ。この似顔絵。絶対、喜ぶと思うし、信じてくれると思う。だからお願い。小野くん。協力して!」
そう言って彼女は、胸の前で拝むような仕草をした。
「もちろん――でも――お母さん信じるかな」
「どんな細い糸でもいいの。お母さんをこっちの世界につなぎ留めたい。私は、お母さんが大好きだから、お母さんが一緒に行きたいって願っても、それは違うと思ってるの。お母さんはきっと、まだ、やれることがある。若いの。お母さん。綺麗なの。私に似て」
そう言って、茶目っ気たっぷりにほほ笑んだ彼女は、本当にきれいだった。
佐伯さんは、普通に下校する時みたいに帰りたい、と僕に言った。
いつも気がついたら消えていたような気がしていたけれど、毎日そうして帰っているという。
小野くんはそこにいてね。私は帰ります。また明日ね、じゃあね!そう言って、彼女は教室を出て行った。彼女の明るい爽やかさは、まるで夏の日に青空を見上げたみたいに眩しかった。
僕はその足で、職員室に向かった。そして尾崎先生を探して、スケッチブックを見せた。尾崎先生はスケッチブックを抱きしめて泣いた。
「話、できたんだね、小野くん」
「ええ、まあ、たまたま」
尾崎先生は、何度もありがとうとお礼を言った。
「お母さんに、これを見せて話して欲しいって頼まれたんですが」
そういうと、尾崎先生は今度は違う柄のイルカのハンカチを目に当てながら、頷いた。明日行ける?と聞かれたので承知した。
翌日、僕は学校帰りに尾崎先生とバスで街はずれの大学病院に向かった。
初めて本物の佐伯さんに会えるのかと思ったが、やはり佐伯さんは隔離されていて会えないという。外界の菌やウイルスに極端に弱いらしい。
バスに揺られながら、尾崎先生とぽつりぽつりと話をした。
「ずっとなんですか。病気がわかってから、ずっと」
「うん。難病なんだって。原因もよくわからないんだって」
尾崎先生は、短く言った。詳しく話してくれる気はなさそうだった。
「ね。美加、どんな子だった?」
先生がつとめて明るく尋ねた。
「どんな――ちょっと話しただけですけど、すごく明るくて、元気でした。キンプリが好きだって言ってました。ドラマを観てたって言ってました。体育をしたのが嬉しかったって――」
うん、と頷いて尾崎先生は涙を堪えるように口をギュッと結んだ。でも、意に反してなのだろう、涙が溢れた。
先生は今日も違う柄のイルカのハンカチを出して、目元を拭った。
病院に到着すると、佐伯さんのお母さんが談話室まで来てくれた。子供の頃に見かけたときより、ずっと痩せてやつれて、疲れて見えた。
尾崎先生と一緒に、それまであった出来事を包み隠さず話し、スケッチブックを渡したら、お母さんはそれを見つめた。ひたすらに、火がついて燃えるんじゃないかと思うほど、スケッチされたその目を、眉を、鼻を、口元を、輪郭を、何かを追跡するように見つめた。
信じるも信じないも私次第よねと、しばらくして顔を上げたお母さんはとても静かに言った。あなた達ふたりが、嘘を言ってるのだとしても構わない。これは美加。この笑顔は美加です。
佐伯さんのお母さんは、そう言って愛おしそうにそっとスケッチブックを抱きしめた。
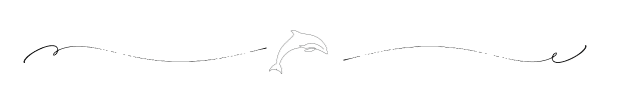
歳月は人を待たない。
僕は大人になった。
彼女と出会って、僕は本気で画家を目指して美大を出た。
個展を開けるようになったのも、やっぱり佐伯さんがいたからだと思う。
ギャラリーの真ん中には、学校の机が置いてある。そこに立てかけてあるのはあのスケッチブックだ。まさか誰も、そこにいない人のスケッチをしたとは思わない、生き生きとした彼女の笑顔がある。
タイトルは――『Son alibi』。
個展を開いたときはいつも、楚々とした美しい老婦人が、その前に佇んでいる。
Ryéさんとコメント欄でお話していたら飛び出した企画。alibi=アリバイというモチーフで創作を投稿し合いましょう!という魅力的かつチャレンジングな企画です。
Ryéさんといえば、フランス語、英語など語学をめぐる記事を、旅や映画、ドラマや原書を通じて上質で洗練されたエッセイを届けて下さる達人です。いつも思いがけない知見をいただき、過去の何かを思い出す――。こんなエッセイは普通、洒落た雑誌でしか読めません。もし飛行機の中の雑誌にあったりしたら、食いついて読むだろうと思います。行き先の旅が面白くなること必須、次に行ってみたい旅にも思いを馳せられます。「ラグジュアリー」「プレシャス」というのが私のRyéさんの記事の印象です。ラグジュアリーとプレシャスくらい英語で書くべきですね、私。笑
私は日頃あまり洋書や翻訳を読まないし、海外ドラマもあまり観ません。Ryéさんに巡り合ってから、新鮮な世界に驚いてばかりです。自分の語学力や知識のなさに絶望しながら、年の功で早々に諦めて時間を無駄にはせずに日本語のエッセイを中心に拝読しています。美しく無駄のない日本語。翻訳もとても心地が良いのです。そして楽しい。ぜひみなさんにもこの面白さを味わっていただきたいと思います。
私はミステリが苦手で、今回のアリバイをめぐる物語は、私にはとても難しかったです。まさにチャレンジ、なのでした。結局、夏向けのホラーなのかミステリーなのかオカルトなのか・・・の不思議なお話になってしまいました。自分で書いていて、なんでイルカなのかなと思っていたのですが、よく考えると結構深かった。ちょっとびっくりしました。
1万字超えとなりましたが、お楽しみいただけましたら、幸いです。
Ryéさんの作品はこちら!↓
