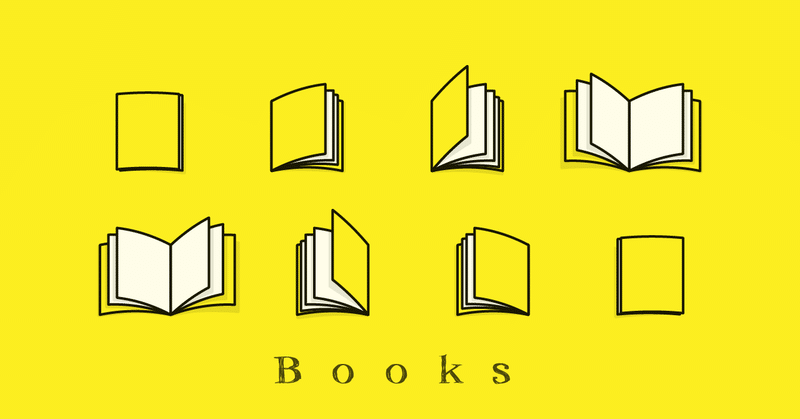
2022年11月 読書記録 青空文庫、ゴーギャンと祖母など
11月に読んだ青空文庫は、三作。落語の口述筆記と江戸時代の浮世草子の現代語訳です。文豪の小説の合間に、こうした毛色が違う作品も読んでいきたいです。
三遊亭圓朝『真景累ヶ淵』『牡丹灯籠』
息抜きにショートショート的なものを読みたくなって圓朝の落語を選んだら、どちらも中編小説ぐらいのボリュームでした…。
三遊亭圓朝は、幕末〜明治に活躍した落語家です。多くの新作落語を創作し、落語中興の祖として知られます。
『真景累ヶ淵』には歌丸師匠のCDがありましたが、何と七枚組。CDの解説を見ると、後半の仇討ち部分は省略しているようなので、全編だと十枚を超えそうです(普段は、抜粋版が語られるようです)。先祖の因果で子孫が次々に不幸になっていく様が語られるのですが、超常現象による怪談というよりは、人の心の闇が織りなす喜悲劇という感じ。江戸時代を舞台にしたモダンホラーにも思えました。
『牡丹灯籠』はホラーor怪談要素とミステリーがうまくミックスされていました。落語の演目と知らずに読んだら、戦後に書かれた時代小説かな? と思ったはず。残念ながら、圓朝の話術を体験することはできませんが(時代的に録音が残っていないので)、創作落語の作り手としてだけでも、文学史に残る方だと感じました。
井原西鶴『本朝二十不幸』抜粋 宮本百合子訳
井原西鶴は、江戸時代初期に活躍した浮世草子の作者です。
翻訳の宮本百合子は、昭和期の小説家。個人的に、彼女の初期小説が大好きなのですが、『道標』という小説の中に、百合子がソ連に洗脳されていく様が描かれていて(本人の描写なので、洗脳されているという認識が全くないのが恐ろしい)。現代の価値観で昔の人を判断したくはないですが、これ以降の作品はちょっと読めないなと感じています(プロレタリア文学が嫌いなのではなく、洗脳された人が書いたものに価値を感じられないだけです)。
さて、どんな経緯で百合子が西鶴の浮世草子を翻訳したのか謎ですが、非常に面白かったです。西鶴は中学の授業で読んだ気がするのですが、こんなに面白かったっけ。親不孝以前に、こういう親娘って今もいるよな…と思わされました。宮本百合子自身、母親との関係に苦しんだ人なので、案外、親不孝娘に共感しながら訳したのかも。
青空文庫で読める西鶴作品はこれしかなさそうですが、どこかで原書を見つけて読んでみたいです。
青空文庫以外では、海外小説を二作読みました。
マリオ・バルガス=リョサ『楽園への道』
リョサは1936年生まれのペルーの小説家で、2010年にノーベル文学賞を獲っています。この作品は、画家のゴーギャンと彼の祖母であるフローラ・トリスタンの生涯を交互に描く伝記風の小説です。
ゴーギャンといえば、小説好きにとってはモームの『月と六ペンス』の印象が強すぎて(村上春樹さんも短編小説「どこであれそれが見つかりそうな場所で」でモームの小説を踏まえた表現をなさっています)。モームの本では中産階級に属するフランス人がある日、突然思い立って、絵を描き始めるという感じなんですね。
ある日突然思い立つという部分は、リョサの小説でも同じです。三十過ぎるまで絵を描いたこともなく、株式仲買人の職を失って初めて、画家になる決意を固めるのです。一方で、ゴーギャンは「普通のフランス人」というわけではなく、祖父の故郷であるペルーで育ち、一時は船員をしていた等、当時の中産階級の価値観からはみ出た背景を持つ人だったことがわかりました。この小説を読んだ後では、ゴーギャンのような型破りな人が、一時的ではあっても、パリで勤め人をしていたことの方が不思議に思えます。株式仲買人だった時は、情熱とエゴをどう抑えつけていたのか…。
ゴーギャンと同様に情熱に取り憑かれた人として描かれるのが、母方の祖母であるフローラ・トリスタンです。ゴーギャンとは違い、彼女はその情熱を「世界を良くすること」に向けます。社会主義者ーーといっても、1840年代の話なので、空想的社会主義ということになるのかな。暴力を否定し、男による女の支配を否定し、労働者の団結を訴える…思想家・活動家として彼女がどのように位置付けられているのかわかりませんが、日本の伊藤野枝のように、語ったことや書いたことではなく、彼女自身の生き方が後世に影響を与えた女性の一人だったように思えました。
チャールズ・ディケンズ『大いなる遺産』
ディケンズは英国ヴィクトリア朝期の作家。アニメ化もされている『クリスマス・キャロル』が有名ですよね。『大いなる遺産』は、完成作としては最後から二つ目の小説で、『デイヴィッド・コパフィールド』や『荒涼館』などと並んで、ディケンズの傑作と見なされています。何度も映画化、ドラマ化されており、1998年版はイーサン・ホークとグウィネス・パルトロー主演、クリス・クーパーとデニーロが脇を固めるという豪華な配役です。映画サイトの評価は並ですが、主演の二人は小説の雰囲気にぴったり。というか、読み終えた後も主人公・ピップのイメージが定まっていなかったのですが、この配役を見て、イーサンの神経質なナイーブさ、傷つき、迷いながらも進んでいこうとする姿が浮かんできて、とても腑に落ちました。ディケンズ自身、現代に生まれていたら作家ではなく、映画監督になっただろうと感じるほど映像的な描写がうまい人なので、彼の小説も映画との相性が良いのでしょうね。
また、作品との向き合い方としては、最近「洗脳された親に育てられた子ども」について考えることが多いせいか、この小説も何かに取り憑かれた親に育てられた子ども、子どもを自分の歪んだ執着心の道具とする親(善意からの執着であっても)を描いた作品として読むことができました。
二十世紀には、ディケンズといえば、誇張しすぎor戯画的すぎるキャラクター作りが批判されていましたが、インターネットにより人々の本音が見えやすくなった現代では、むしろ、人間の本質を見抜いていた作家ではないか? と感じました。文学史的には、ディケンズのこの性格描写が一方ではドストエフスキー、別の面ではプルーストに受け継がれていくのが、よくわかりました。
読んでくださってありがとうございます。コメントや感想をいただけると嬉しいです。
