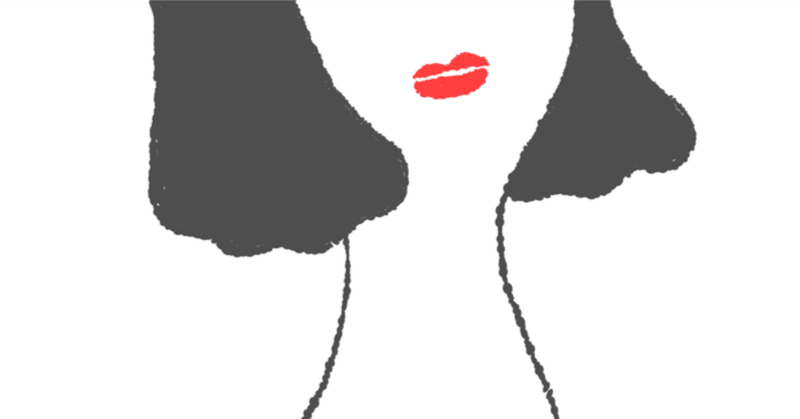
中年ラブ・ストーリー(中編)
目の前に置かれたおでんの盛り合わせを見て、思わず「わぁ」と声を漏らした私は、よくできた反応をしたようだ。克也さんが満面の笑みでそんな私を見ている。
「おでんを呑み屋で食べるなんて久しぶり」
私は自分の小皿に、少しくすんだ色のからしを乗せながら言った。
「家で食べるのも好きだけどね、ひとりでおでんなんて、あんまりやらないでしょ?あつこさんだって」
「まあね、コンビニで済ませてしまうわね。ひとり分のおでんなら」
「そうそう」
克也さんはそう言いながら、私の選んだ冷や酒を注いでくれた。私たちはおでんとお酒を前に、いつの間にか砕けた話し方になっていた。
「おでん、好きなのを好きなだけ食べて。僕はもう全種類食べてるから」
「あら、常連なのね」
「そうでも無いけど」
私は、それじゃ遠慮なく、と言って大根や卵なんかを取っていく。徐々に客で埋まっていく店内は、賑やかであっても、落ち着いた雰囲気を保っていて過ごしやすい。
「あつこさんにはあまり気を遣わなくて、気楽でいいんだよなあ」
「あら、どうして?」
大根に箸を入れると、ふわっと湯気が立った。
「そもそも、パン教室にくるような女性は優しそうだとは思っていたけど、その中でも一際親しみがあったよ」
「あら。だからどうしてよ」
焦らさないで教えなさいよ、と思いながら、若い頃よりそんな話にさして興味もなかった。
「人気女芸人のいい所取りしたような顔してるよな、あつこさんて」
「え、私?そうなの?」
変な例えをする人だ。一応、人気とは付いたが、女芸人の集団を足して割ったような顔と言われて喜ぶとでも思ったのだろうか。
「親しみやすさがあるという意味だよ」
「ふーん」
しばしの沈黙は、おでんを味わうためだとでも言うように、私はやたらと「うーん、美味しい」を連発しながら箸を動かした。
「もうこの歳になるとなんというか、落ち着きのある女性に惹かれるんだよ。懐が深そうな人というか。色んなことで動じなさそうな人」
克也さんはさっきから食べもしないで日本酒ばかり飲んで、少し饒舌になっていた。
「ねえ、何か食べた方がいいんじゃない?変に酔っ払うわよ?」
私のお節介な忠告にそうだね、と言って克也さんははんぺんフライをオーダーした。
「そういえば。私たちが参加したあのパン教室って、一応、男女に出会いの場を提供するっていうコンセプトだったじゃない?もちろん私もそれを知っていたし、そういうつもりで参加したんだけど……」
私はあの不思議なパン教室を思い出していた。
とにかく雑なパン教室だった。既に発酵まで終わっているパンの生地を男女のグループでおしゃべりしながら形を作ったり飾りをつけたりした。
パンを焼いている間に一対一のトークタイムがあり、その後焼けたパンを手にもう一度話したい人の元へ行ってアピールする。
部屋の中は焼きたてのパンの匂いが立ち込めていてなんともいい感じ。自作の不格好なパンを手にしたエプロンを巻いた男女。その全員がいい人に見える。
その中で、今の話を聞く限り私が一番いい人そうに見えたということだろうか。
あの日は克也さんの方から私に近づいてきて、互いの連絡先を交換した。初対面の人との連絡先交換なんていつ振りだっただろう。少しはどきどきしたのだった。見た目はタイプなわけではなかったけれど、特に嫌な印象も与えてこない男性から声をかけられたのは嬉しかった。
「あのパン教室で本当にデートする相手が見つかると思わなかったな」
「え」
克也さんが低い声を出した。
「そんなに乗り気じゃなかったの?あのとき」
「うん、まあ。そんなにがっついていなかったというか。ご縁があればラッキーくらいなものだと思ってたから。克也さんは違うの?」
克也さんは少し黙っていた。私、何か気に障ることを言ったかしら?
「いや、今はどうなのかなと思ってね」
克也さんはまっすぐ前を見つめたまま言った。
「ああ、ここ2回のデートのこと?楽しいよ。誘って貰って良かったと思ってます。うん。なんか良い男友達ができたって感じ」
「そっか」
克也さんは自分の顎を何度か撫でている。
「克也さんはあれよね、前回のデートで言ってたけど、クリスマスに一緒に過ごせる人を探してるって。なんかロマンチックなこと、言ってたもんね」
私がこう言うと、克也さんは小さく返事をしたかしないか。聞こえないような何かを呟いて、私の方を見た。目はとろんとしている。その目が、やけにじっとりとまとわりつくように私を見ていた。
なつに電話をかけたのは翌日、月曜の昼休みだった。予め予定を聞いて、約束の12時15分ぴったりにコールを鳴らした。それをワンコール目で出てくれるなつには心から感謝している。それくらい、話したい用件だった。
「なつ、悪いわね。変な時間に」
「いいのいいの、どうなった?付き合ったの?あなたたち」
私はいきなり肝心な所を聞かれて黙った。
「ちょっと待って。まずは話させて。私たち、呑み屋にいったのよね、昨日は」
「ふんふん」
「そして、出会いのパン教室の話だったり、お互いの印象を話したりしたわ」
「でしょうね」
「そして、どうやらその時点で、だいぶ酔ってしまったのよ。克也さんは」
「え。あつこは?」
「私?私は全然。だって、飲み始めて30分くらいの話よ」
私は克也さんのとろんとした目を思い出した。
「克也さん、日本酒はいつもあまり呑まないみたい。私に合わせて無理したのね」
「えー、なにそれ。緊張してたのかな?彼なりに」
どうだろ、と言いながらそれは少しはあるかもしれないと思った。なんでも自分で決めてしまうように見えたけど、いい所を見せようとして焦っていたのかもしれない。私相手に?「ふふふ」
「へ?なに?」
「ああ、ごめん。思い出し笑い」
「なにそれ。で、あつこはさ、自分の気持ちを確かめるって言ってたじゃない、あれ、どうなったの」
「ああ、それが……」
私は店を出たあとのことを思い出していた。結局酔いすぎてしまった克也さんとは一件目の呑み屋を出たところで解散することになったのだ。
まだ夜の7時、渋谷の街はこれからというところだった。少し辺鄙な場所にあったとはいえ人通りもあった。なにせ渋谷なのだから。それなのに、それなのに。
「抱かれちゃったわよ」
「は……はあ?酔った勢いで?」
「そう。公衆の面前でね」
突然覆いかぶさってきた克也さんのコートの匂いを思い出した。
「……っくりしたぁ!抱かれたって言わないでしょそれ。ハグじゃんか、ハグ!」
「そうよ。でも抱かれてるじゃない。堂々と」
は~びっくりした、と安堵しているなつの後ろでチャイムが鳴ったようだった。
「えーうそ、宅急便かな、どうしよ」
「あ、いいよ切るよ。また連絡する」
私は電話を切った。本当はその後の続きがあったのだ。だけど思いのほか興奮していたなつへの報告はこのくらいがちょうどいいと思った。
私はこの続きを誰に話そうかと考えて、三原さんにメッセージを送った。
(後編へつづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
