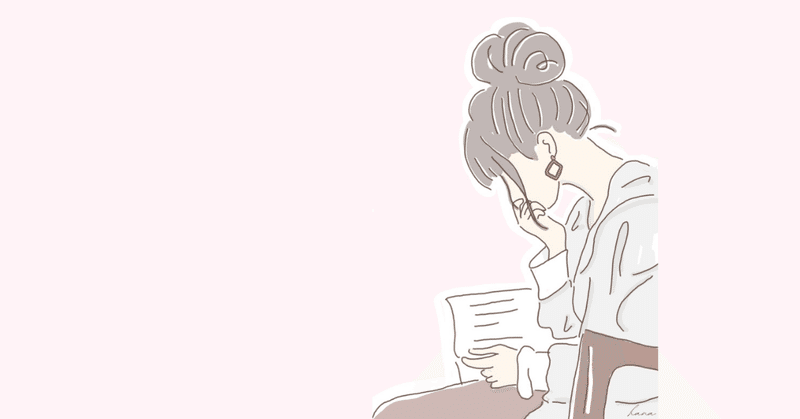
あたまの中の栞 - 葉月/長月 -
どこからか、美味しそうな香りが漂ってきた。グゥとお腹が鳴る。
じとっとした季節もいつの間にか通り越して、少し肌寒い季節がやってきた。私は暑い8月が好きで、お祭り拍子が聞こえてくるとどうしようもなくドキドキしてしまう。
イカを焼く香ばしい匂い、色とりどりに流れゆくスーパーボウル、海へと逃げるタイミングを逃したたい焼きたち。彼らは皆、私に夢を見せてくれる。
でもコロナによってイベントが悉く中止になり、夏休みも例年に比べると凡庸な過ごし方になった。
家でひたすら簿記の勉強をして、時々小説を書く。たまに友人たちが家へ遊びにきて、思い思いの言葉を吐き出して帰っていく。これはこれで愛おしい時間だ。でも、何かが足りない。
ここしばらく毎日小説を投稿していたので、8月と9月に読んだ本たちを振り返る機会がなかった。定期的に外へ吐き出していかないといかんせんわたしの記憶力では、物語を留めておくこと叶わない。
ということで風前の灯となった記憶力を頼りに、改めて2ヶ月分の読書振り返りをしていこうと思います。もう気がつけば10月とは。
1. 騎士団殺し:村上春樹
顕れるイデア編/遷ろうメタファー編という二部制から成り立っている。村上ワールド全開といったところで、日常世界と不思議な世界が入り乱れている。今回は、主人公が住んでいる家で発見された絵画を巡って、「思考の旅」をする形だ。
正直に言うと、このお話わたし自身はあまり物語の世界観に没入できなかった。理由はなぜかと言われると、難しい。
主人公の葛藤やキーパーソンとなる女の子の揺れゆく心情などよく覗き見ることができたのだが、どうも他の村上作品に比べるとわたし自身が登場人物たちの思考に同調できなかったと言う部分が大きいと思う。
『1Q84』を初めて読んだ時の衝撃は忘れられない。当時かなり話題になっていたこともあって、ふと手にしたがその圧倒的な世界観に魅せられた。
それを期待していると、少し肩透かしを食らう。今回の主人公がどこか仙人みたいな暮らしをしていたことも起因しているかも。いつかまた読み返したら違う感想を持つのだろうか。
面白いから旅行をしているわけではない、というのが私にとっての正しい答えだった。(新潮社 p.317)
2. この本を盗む者は:深緑野分
奇想天外な物語の世界。なかなか好き嫌いが分かれそうだが、わたし自身は本作品を楽しく読んだ。
本を盗まれそうになると、主人公によって犯人が見つかるまで本で実現した世界に閉じ込められる、という筋書き。マジックレアリズム(現実と空想が入り混じった世界)やハードボイルドなど本のジャンルに沿った世界が展開される。
どこか森見登美彦さんの『四畳半神話大系』シリーズに似通っているところがあるのかもしれない。これは書籍で読むよりも、実際にアニメ化した方がよりその良さが際立つかもしれないな。
以前同著者の『ベルリンは晴れているか』という作品を読んだのだが、今回の作品を読んでみて全く印象が変わった。(こんなエンターテイメント的な作品も書かれるなんて!)
『ベルリンは晴れているか』はどちらかというとかなり硬めの文章で、第二次世界大戦時代を描いたものだからなかなか読み終わるのに苦労した。どちらかというと、よく考えながら読み進めなければならない作品。それがガラッと趣向が変わった。
どうやらこの世界は眠って終わるものではないらしい。(角川 p.128)
↓『ベルリンは晴れているか』の読後感想
3. とわの庭:小川糸
小川糸さんの作品は、エッセイのように言葉がキラキラしていて、一方で中盤につれてギュッと心が掴まれたようになることが多い。これは誤解を恐れずにいうと、爽やかな日の光が差し込む道を気持ちよく歩いていると時折冷たい雨が降ってくるような感じ。
最初に何気なく図書館で『サーカスの夜に』という作品を手にして読んでから、他の作品も読んでみたいと思い『ツバキ文具店』と『キラキラ共和国』を手にした。なぜか映画化もされた『食堂かたつむり』は未読である。いつか読みたい。
本作品は序盤母娘の愛が丁寧に丁寧に描かれていて、ああなんかほっこりするなあなんて思っていたのに、途中から急に不穏な雲が登場するのだ。苦しい、うまく息ができなくなる。でもどうなるのか知りたい、そんなふうに思ってページを捲った。
最終的にはこの今の生活を前向きに生きる鍵のようなものを教えてもらったような気がする。
愛っていうのは、人やものに対して、報いられなくてもつくしたいと思ったり、自分の手もとにおきたいと思ったりする、温かい感情。(新潮社 p.12)
4. 星のように離れて雨のように散った:島本理生
今年読んだ中でも一、二を争うくらい私の感性にぴったり合った作品だった。出版されたのが最近で、早速主人公を取り巻く環境はコロナ後の世界となっている。
読み進めていくうちに、一つひとつの言葉がしっとりと頭の中に吸い込まれていく感じ。きっとみんな自分のことを大切にしたいと思っていて、それと同じくらい周りの人のことも気にかけていたい。
自分の中に芽生えた違和感みたいなものは最初見過ごしがちだけど、時間が経つにつれて存在感が増していくのよね。
もちろん読んだ人にとって感じ方は違うと思うけれど、素直にわたしはどこか救われたような気がした。宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』、久しぶりに本棚から出して読んでみよう。
いつも大事な言葉ほどいったん飲み込んでしまう。(文藝春秋 p.34)
↓読後感想
5. 形容詞を使わない大人の文章表現力:石黒圭
文章を書くうえでより洗練した形で書くにはどうしたらいいのかなーと最近わかりやすく思い悩んでいて、その延長線上で手に取った本。「かわいい」、「すばらしい」、「いろいろ」、「さまざま」など割と日常生活している上で使う場面が多いけど、具体的なイメージに欠ける部分があるのでこれからは使い方を気をつけよう。
6. 滅びの前のシャングリラ:凪良ゆう
本屋大賞に選ばれた『流浪の月』。物語の展開に魅せられて、貪るように文章を読んだ。最後まで読み終わった時、なんとも言えない読後感が胸の中にストンと残る。普通とはちょっと違うかもしれないけど、訪れるのは心の平穏。
今回の作品でも読み終わった時に訪れたのは、なんとも言えない心の安らぎだった。設定的にはもうあと数日で世界がなくなってしまうかもしれないという状況なのに、描かれた登場人物は確かに人として生まれた上での最大の幸福を手に入れていたのではないかと思った。
真っ向から立ち向かわないと決意すれば、日々はやや楽に過ぎていく。(中央公論新社 p.13)
↓読後感想
7. ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人:東野圭吾
相変わらずこの人の作品は観客を魅了する。国民的アニメに擬えてしまうあたりも、わかりやすさに起因している。とにかくさまざまな登場人物が出てきても、混同しにくいのはさすがだ。
ちなみに作中に出てきた国民的アニメは辻村深月さんの『凍りのくじら』にも登場している。以前私が執筆した短編小説の中にも登場している。こんなふうに何かを例える上で引用されるものはそれだけ示唆性に溢れているし、わかりやすいということだろう。(海外でいうところの旧約聖書のような…?)
文章を読み終わった後で思うことは、ほんのボタンの掛け違いによって人生どう転ぶかわからないということ。最後に読み終わった時の爽快感。この著者の引き出しの多さと言ったら。コロナについても扱っていて、物語全体の流れが巧みだった。
今回登場したマジシャン探偵には、ぜひこの後も登場して欲しい。
8. 名も無き世界のエンドロール:行成薫
在りし日の学生時代をいまだに引きずっているのか、私は割と青春時代の延長線みたいな話が結構好きだ。
その前提を頭に置いたうえで図書館にて本を手にとる。この本は、つい最近映画化もされた作品。映画のエンドロールって、余韻と一抹のさみしさが募る。確か原田マハさんの『キネマの神様』だっただろうか、映画はエンドロールも含めて話が完結するんだといった下り(詳しいセリフは忘れた)があって、おおなるほどと思って以来映画館では最後まで残るようにしている。
出演者がずらりと並び、映画を制作する上で関わった人たちが切れることなく流れていく。映画にあった曲が流れてきて、同時に映画の1コマ1コマが頭の中でリフレインされる。これは確かになくてはならない時間だった。
小説の中に出てくるのは、同じような境遇の中で生きてきた3人。だからこそお互いが抱える気持ちも共有できて。彼らはお互いが足りない部分を補いながら生きていた。読み終わった時、なんと表現したら良いかわからなくなる。
無性に、学生時代に戻りたくなった。ちなみに作中では、私が『クリィムソーダの記憶』の中に出した映画も出てきて、数奇な運命のようなものを感じてしまった。
安心しているんだ。自分が確かに生きているって気づいて、安心している。だけど、それがカッコ悪いから不愉快なフリをしているだけだろ。(集英社 p.7)
9. カラフル:森絵都
確か私が学生の時に一度読んだことがある気がする。どちらかというと大人向けというよりは思春期に悩む子どもたちが読者対象なのかな。メルヘンチックな要素もありつつ、今回読んでみると割と内容が深く暗いなと思った。
森絵都さんの『みかづき』は私がこれまで読んだ中でもとても好きな本の一つなのだけど、『カラフル』はどちらかというと私が親になった時に子どもに読んで欲しいと思う作品だった。
この地上ではだれもがたれかをちょっとずつ誤解したり、されたりしながら生きているのかもしれない。(講談社 p.188)
***
少しずつ季節が冬へと移行していく。願わくば、今の季節がずっと続けばいいのに。4つの季節の中で、最も香りたつ時期。あたりから美味しそうな匂いや花の艶やかな香りがしてくる。芸術の秋、食欲の秋、スポーツの秋。外でゆったり本を読んで、穏やかな日々を過ごしていこう。
■ 今回ご紹介した作品一覧
末筆ながら、応援いただけますと嬉しいです。いただいたご支援に関しましては、新たな本や映画を見たり次の旅の準備に備えるために使いたいと思います。
