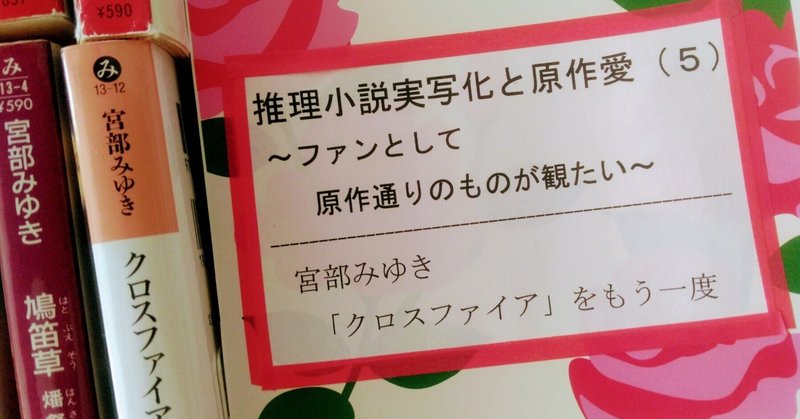
『十角館の殺人』実写化でもう止まらない!推理小説の映像化に湧き立つ(個人的な)期待と不安(5)
つづきです。
前回はこちら。
『十角館の殺人』実写化でもう止まらない!推理小説の映像化に湧き立つ(個人的な)期待と不安(4)|涼原永美 (note.com)
綾辻行人による傑作ミステリー「十角館の殺人」の実写ドラマが3月に配信されるというニュースを聞いて以来、推理小説の映像化についてザワついてどうしようもない思いを、あれこれ綴ります(もはや『十角館~』と関係のない話になっていますが、自分のなかでは繋がっているのでタイトル続行します)。
今回は「好き過ぎて、ぜひ再映像化してほしい宮部みゆき『クロスファイア』」です(作家名や俳優名は敬称略にさせていただきます)。
※原作小説と映画の内容に触れています。完全なネタバレではありませんが、気になる方はご注意ください。
(1)いちばん好きな主人公であり、映像化されて最もがっかりした作品
数ある宮部みゆき作品のなかで「いちばん好きな小説は」と聞かれたら、一晩でも悩んでしまいそうだが、「いちばん印象的な主人公は」と聞かれれば即答できる。
「クロスファイア」(光文社文庫プレミアム上・下巻)の青木淳子だ。
そして、映像化された宮部みゆき作品のなかで、「いちばんがっかりしたのは」と聞かれたら、大変申し訳ないのだけどこの映画版になってしまう。
映画「クロスファイア」(監督・金子修介/2000年/日本)。
理由ははっきりしていて、「いちばん観たかった場面がすっぽりカットされている」のと、ついでに「主人公の恋愛の相手が原作とは別の人になっている」という点。原作ファンとしては、あり得ない改変・・・と言わざるを得ない。
もちろんこの映画をおもしろく観た人もいるだろうから、あくまで個人的な感想です。
「クロスファイア」は、念力放火能力(パイロキネシス)という超能力を持った主人公・青木淳子の孤独な闘いと痛切な恋愛を描いた物語だ。刊行は1998年だが、初読から25年経ってもなお、青木淳子が私の心から離れない。そして映画の公開からも23年ほど経っているが、「あのクライマックスを映像として観てみたかった・・・」という思いが消えないのだ(張り切って初日に観に行った私です)。
無念が大きいのは、「好きな推理小説の映像化」に期待し過ぎる自分のせいだとわかってはいるが、今でも「どうして話を変えちゃったんだよう・・・」と思い続けている(しつこい)。
さて、「どうしても観てみたかったクライマックス」とはどんなもので、淳子が「誰と恋愛するはずが、誰に変更されていたのか」を語るには、当たり前だが「クロスファイア」がどんな話なのかを書かなければならない。
(2)何のために自分は生まれてきたのかーー能力者の孤独が刺さる
※以下、原作の小説と映画の内容に触れています。
――とにかく小説に感動し過ぎた。これに尽きる。
未読の方のためにざっくり説明すると、「クロスファイア」は生まれながらにして念力放火能力(パイロキネシス)の持ち主である青木淳子が、法の目をかいくぐる「悪人」「凶悪な犯罪者」を次々と処刑(!)していく・・・という物語だ。ターゲットがどんどん炎上するシーンは、文章だけでもかなりの戦慄を伴うかもしれない。
と、これだけ書くとマーベル的なダークヒーローのように聞こえるが、まったく違う。
淳子は生身の人間で、その能力以外はごく普通の女性だ。善良な人達が傷つくのを黙って見ていられないし、未来の被害者を減らすためにも、後悔も謝罪もない凶悪犯罪者を葬りたい・・・という気持ちから行動するのだが、次第にその断罪が「正義」なのかわからなくなり、自分自身が傷ついていく――そういう物語なのである。
実在の事件を想起させる凶悪犯罪、被害者の悲しみや怒り、自らも怪我を負う淳子の死闘・・・とサスペンスミステリーとしての読みどころたっぷりなのだが、底辺に流れ続けるのは淳子の圧倒的な孤独だ。彼女はつねに生きる意味を探している。
「だけど、わたしは装填した銃なのよ」と、淳子は繰り返した。「装填した銃を持っていたなら、誰だっていつかは撃ってみたくなる」
(中略)
「だけど、撃つときは、正しい方向に向かって撃ちたい。誰かの役に立つ方向に向かって」
――とこれは、「クロスファイア」の前段階のエピソードである「燔祭(はんさい)」という短編からの引用だ。「燔祭」は、「鳩笛草」(講談社文庫)という短編集に収録されているのだが、クロスファイアの物語はこの短編から始まっているので、興味のある方はぜひこの順番で読むことをお勧めしたい。
読んで常に感じていたのは、「望まずして手に入れた大きな力は、決して人を幸せにしない」ということだ(これは、凡人の若者だった自分をずいぶん励ましてくれた)。
なんのために生まれてきたのか――本質的にはそれが淳子の苦しみのすべてだ。何になりたいか、どんな風に生きたいかを(最終的に叶わなかったとしても)自分で選べるのは尊いことなのだと、そんな作者のメッセージも感じる。そのくらい淳子の苦しみが大きい。
そうして読み進め、上下巻の下巻に入った頃、淳子は「ガーディアン」という謎めいた組織から「仲間にならないか」と誘いを受けることになる。淳子のしたことをすべて知り、監視する組織がいたのだ。怖い。
(3)切なく美しい、一瞬の恋の煌めきが主人公を癒す・・・のだけど
ガーディアン。これが運命の分かれ道であり、淳子の痛切な恋愛の始まりだった。
淳子はここで、木戸浩一という異能者仲間と出会い、人生で初めて本気の恋愛をすることになる。いや、正確にいうならば「燔祭」で出会った被害者家族、多田一樹という男性にほのかな想いを寄せていたのだが、多田は淳子が力を使うことを止めようとして、2人の関係は終わってしまう(多田一樹は『クロスファイア』で警察側のキーパーソンとして再登場する)。
「あなたはいい人よ」(中略)「だけどね、これだけは覚えておいて。わたし――わたしはね、一緒に人殺しで手を汚すことができるまでは、けっして、けっして、誰にも心を許さないわ」
――とこれは、2人が深い関係になる前に淳子が木戸浩一に言った言葉だが、これは淳子の紛れもない本心だろう。
異能者じゃなくても、自分の最も深い部分に秘密や暗さを抱えていたら、そこに優しく触れてくれる相手とでなければ信頼関係は結べない。
ただ結局淳子は、「一緒に人殺しで手を汚す」前に浩一に惹かれてしまう。
それは、浩一がおもしろおかしく語った中学時代の「デートの失敗談」(これが後々・・・戦慄に繋がる)や、終始ふざけているような言動の端々から、絶対的な寂しさを感じ取ったからだ。
ふざけたふりをしてはいるけれど、彼の孤独を、彼の不安を、彼の寂しい渇きを、淳子は理解することができる。それは彼女の内側に、長い間、なだめられることもごまかされることも知らず、ひたすら積もることだけを強いられてきたものと、そっくり同じだから。
ここからの展開がもう、ロマンティックでたまらない。一気にラブストーリーだ。この日はクリスマス・イブの前日。2人がいたカフェにはハート型の燭台があり、その形に添ってたくさんのキャンドルが灯せるようになっているのだが(結婚式でよく見るやつ)、淳子が「見て」と言うと、キャンドルがすべて灯っている(もちろん淳子がつけた)。
これがただの恋愛小説なら、甘すぎる陳腐な場面に思えたかもしれない。
ーーが、生きるか死ぬかの日々をおくる人間が、本当に生まれて初めて理解者を得た、その瞬間の煌めきだから、どんなに甘く美しくてもいいと思ってしまう。
そんなわけで淳子は「大切な人がいる」という、普通の人間としての幸せを嚙みしめることになるのだが、物語としてはここから怒涛のクライマックスが始まる。
「彼氏と永遠に仲良く暮らしました」とはいかない。淳子にも罪があるからだ。
(4)映画版で恋する相手は被害者家族の多田一樹、原作ファンには「?」な展開・・・
――とここまで書いて、映画版はどうだったのかを話しておくと、この木戸浩一は、映画ではまったく違う雑な扱いになってしまっている。
凶悪犯罪者を闇に葬るという「ガーディアン」の一員であり、彼が異能者であることは変わらないのだが、「ガーディアン」の組織としての在り方も映画では掘り下げられることなく、浩一は淳子と恋に落ちることもなく、なんとなく中途半端な敵役として終わってしまうのだ。
――あれ? あれ? と映画を観ている途中からイヤな予感はしていた。
原作では、この「ガーディアン」との関わりと、木戸浩一との恋愛関係が最終的に淳子に「ある終焉」をもたらすことになるのだが、映画ではそこが中途半端なので、淳子に訪れるラストもかなりの力技。これでもかといわんばかりの炎の迫力だけが印象に残って終わってしまう(個人の感想です)。
では映画のなかで誰が恋愛の相手になるのかというと、前述した被害者家族の多田一樹だ。
深い関係にはならないものの、想いを寄せ合うシーンには温もりを感じる炎が効果的に使われ、美しいシーンに仕上がっている。原作にこだわりのない観客には2人の関係が好ましく映ったかもしれないが・・・原作ファンとしては頭にハテナしか浮かばない。
――そして、問題のクライマックスである。
(5)原作は「救済」と「罰」が同時に与えられる衝撃のクライマックス
原作では、いろいろあって2人(木戸浩一と淳子)は河口湖へ行くのだが、そこで淳子がある事実に気付いたことから事件が起こる。
極力ネタバレしたくないので具体的には書かないが、この展開が淳子にとって「あまりに可哀想」と思うか、「これでよかった」と思うかは、読み手によって分かれるところだろう。
もしかしたら大半が前者かもしれない――が、私は後者だ。
このクライマックスは淳子にとって魂の救済のように、私には思えた。
物語というものは基本的に「救済」を描くものだと思う。なんでもいい。いきなりだが「スター・ウォーズ」でも「ハリー・ポッター」でも「鬼滅の刃」でも「水戸黄門」でも、どんな物語でもそれぞれの救済を描いている。それがどんな形なのかが、作者の腕の見せどころだ。
だから「クロスファイア」にとって、淳子にとっての救済は何かと考えると、ひとつは木戸浩一との関係だと思う。
そして、異能者の孤独を共有できた浩一との恋愛は淳子にとって救いであると同時に・・・重ねてきた罪に対する罰でもある。
そして救済はもうひとつ。
「〝装填された銃〟としての人生からの解放」だ。
そう、この物語はクライマックスで、主人公に対する救済と罰が同時に与えられるのだ。それだから心を打つし、この展開しかない・・・と思えてしまう。勝手ながら、作者が最も心を込めて書いたのはこの場面ではないかと感じるのだ。
――だから、だから。
湖畔で起こるこのシーンは、映像でぜひ観てみたかった。
もちろん湖でなくてもいい。美しい自然風景と寒さは必要だと思うけど。それと星空も。
原作ではとても静かなトーンの文章で書かれたこの場面は、そのまま映像化すれば、白い息と星の瞬きがキービジュアルになったのではないだろうか。
(6)遊園地がド派手に炎上した映画版ラストも、迫力はあるけれど・・・
ちなみに映画では、クライマックスはなぜか遊園地で、最終的には炎を用いたバトルアクションの様相を呈していた。
原作では、ガーディアンとして「(悪人に対する処刑の)痕跡を残さないことがいちばん肝心」と言っていた木戸浩一が、映画では遊園地で簡単にチンピラを殺したり、原作で淳子が「自分と同じ殺人者にしたくない」と心を砕いていた同じ能力者の少女カオリちゃんが可哀想な扱いを受けていたりと、かなりの別ものになってしまっていた。
当時のVFXを駆使したであろう炎の表現は迫力があるし、作者が執筆にあたり意識したと語っているアメリカ映画「炎の少女チャーリー」を、「クロスファイア」の映画班も意識したのかもしれないが、とはいえ視覚効果はあくまで原作の物語を活かすために使ってほしかったと私は思う。
「燔祭」から始まる「クロスファイア」上下巻の物語を2時間にまとめるのは難しい。けれど原作を読み解けば、このクライマックスを削っていいとは思えないし、ここを起点に逆算し、原作前半から中盤のエピソードを削ることはできたと思う。たとえば警察内部での捜査の進捗や、淳子がひとりで行動する場面は削ってもそれほど無理はないはず・・・と勝手に「こうすればできたはず」を想像してしまう。
(7)映画版に生かされなかったもう一つの無念は「刑事の時間軸」
じつはもうひとつ、ここも変えてほしくなかった・・・という原作ファンとしての無念がある。
場面というより全体の構成なのだが、原作では青木淳子を追う女刑事・石津ちか子と相棒の牧原刑事が淳子と対面するのは、かなりの終盤なのだ(ものすごく重要な場面)。
警察内部では、幾人もの人間が「焼き払われた」事件に関して超能力者の存在が浮上するにはするが、現実的な犯人として認めることができない。だが、石津・牧原両刑事がほぼ個人的な信念で淳子の足跡をたどり、ついに彼女のいる場所へたどりつく・・・。
これが原作では重要な横軸になっていて、この展開がサスペンスミステリーとしての魅力をがぜん盛り上げているのである。
――どういうことかというと、読者はそもそも神の視点で青木淳子という異能者が実在することを知っているから「謎」がないのだが、警察内部としては「謎」なので、丹念にこれを追う刑事の時間軸があって初めて、「犯人をどう追い詰めるのか」というミステリー、推理小説としての形が浮かび上がるのだ。
石津・牧原両刑事が淳子と対面するのは、じつに、もうこれしかないという絶妙なタイミング。本当にこういった宮部みゆきのストーリーテリングの巧みさには感動する。
この強烈な場面も映像で見てみたかった。
――なのだが、映画ではなぜか淳子が、話の途中で自ら警察に足を運び、石津刑事らに自分の能力を披露してしまっている。
最後の最後まで謎の存在だからゾクゾクするのに・・・。たぶん映画では、ミステリー要素はほぼ排除されたのだろう。残念だ。
(ちなみに映画では石津刑事を桃井かおりが演じていて、イメージがぴったりだった。それだけにもっと石津刑事に活躍してほしかった。あれから再読の際は桃井かおりのイメージで読んでいる)
(8)孤独を描いたから胸を打つ・・・静かに収束する原作ラストの魅力
さて、こんなにおもしろい原作なのだから、いつかまた映像化してほしい。
「燔祭」から始まってほぼ原作通りにやるとしたら、2時間では難しいから、連続4~5回のドラマがぴったりかもしれない。いや映画で2時間半くらいかけてくれないだろうか――原作ファンとして、そんな願いを抱いている。
そういえば、前回「宮部みゆきの小説には宝石がある」と書いたのだが、「クロスファイア」で私が感じた宝石は、いうまでもなく青木淳子に与えられた救済の形だ。この、異能者である主人公に本気の愛を味わわせたことが宝石だと思う。
青木淳子がいつまでも私の心から離れないのは、これが絶対的な孤独を描いた物語だからだ。
けれど異能者でなくても、人は誰でも孤独だ。それを癒そうと誰かを愛して、望まぬ結果になったとしても、誰もその必死さを笑うことなんてできない。
原作ではクライマックスの後、関係者それぞれの顛末や思いが描かれ、物語が静かに収束していく。
あくまで捜査資料である写真――青木淳子と木戸浩一が2人並んだ写真――を見ながら、石津刑事が仲間と
「似合いの二人でしたな」
「ええ、幸せそうに見えますね」
と話すシーンは、映像化でも使ってほしい・・・と思った。
余韻がなんとも言えない。
さて、今日はこのへんで。
――長年どうしようもなく抱いてきた、この小説と映画化に対する思いを、notoのおかげで書き残すことができた。notoさん、ありがとうございます。
つづきます。
次回は、島田荘司原作の映画「星籠(せいろ)の海」について書きます。
御手洗潔の映画に足りなかったパズルのピース~『十角館の殺人』実写化のタイミングに寄せて~|涼原永美 (note.com)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

